■ 001 容積率の限度(法52条1項)
「指定容積率」と「道路幅員による容積率」の値の小さい方が,その敷地の容積率となる。
(1)指定容積率
用途地域ごとに法52条第1項1号~5号に定められているが,それぞれの敷地については都市計画で定められる数値による。
(2)道路幅員による容積率(法52条1項)
前面道路(*1)幅員が12m未満である場合は,前面道路幅員に4/10又は6/10(*2)の数値を乗じたものが道路幅員による容積率となる。前面道路が幅員12m以上である場合は,「指定容積率」を限度とする。
*1 : 法52条第2項
前面道路が2以上あるときは,その幅員の最大のものとする(以下第12項において同じ)。
計画道路に面する敷地の場合(法52条10項)
都市計画において定められた計画道路に面する敷地がある場合,特定行政庁が交通上,安全上,防火及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物は,その計画道路を前面道路とみなす。この場合においては,当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は,敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
*2 :
4/10の区域 :
第1種・第2種低層住居専用地域,第1種・第2種中高層住居専用地域, 第1種・第2種住居地域,準住居地域,特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域
6/10の区域 :
近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域,工業専用地域,用途地域指定の無い区域
■ 002 容積率の加重平均(法52条第7項)
建築物の敷地が2以上の地域又は区域に渡る場合の算定例 (2006H)
容積率の加重平均 = 292% となる
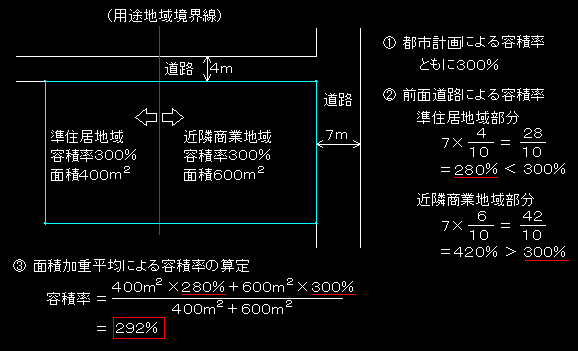
(敷地図)
■ 003 容積率の緩和
住居系用途地域において壁面線の指定がある場合(法第52条第12項) (2007W)
第一種低層住居専用地域から準住居地域までの住居系用途地域内または特定行政庁が指定する区域内で,前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合,または条例で壁面の位置の制限がある場合は,壁面線等を越えない建築物については,前面道路の境界線が当該壁面線等にあるものとみなして,容積率を算定することができる。ただし,前面道路の幅員(m)に6/10を乗じた数値以下でなければならない。なお,当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は,敷地面積に算入することはできない(法第52条第13項)。
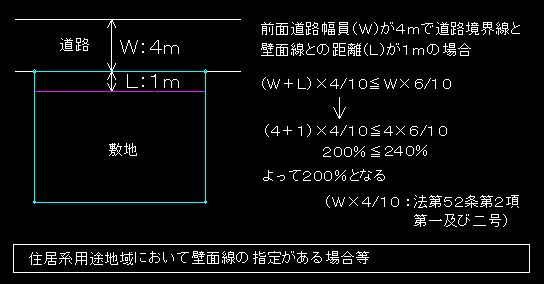
(敷地図)
都市計画道路の特例による緩和(法第52条第10項)
都市計画で定められた道路(都市計画道路)は,法42条第1項第四号(2年以内にその事業が執行される予定のもの(事業決定計画道路)により,特定行政庁が指定したものでなければ,法に規定する「道路」にはならない。しかし,この指定がなされていない都市計画道路であっても,特定行政庁が,交通上,安全上,防火上および衛生上支障がないと認めて許可した建築物にあっては,当該道路を前面道路とみなして容積率が適用される。この場合は,同項の規定により敷地内の都市計画道路の部分は容積率を算定するにあたっての敷地面積には算入されない。これは,計画道路であっても実質的に道路として取り扱うことから当然の規定と思われる。
敷地と空地の規模により容積率制限を緩和する制度(法第52条第8項)
平成14年の建基法の改正により,容積率制限を迅速に緩和する制度が導入されている。第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域もしくは準工業地域または商業地域内にある住宅で,その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上のものに限る。)を有し,かつ,その敷地が政令で定める規模以上のものについては,用途地域に関する都市計画で定める容積率の1.5倍を限度として,その容積率を緩和することができる。
特定行政庁による許可等による容積率(法第52条第14項)
緩和機械室の占める割合が大きい建築物や,敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上および衛生上支障がないと認めて,建築審査会の同意を得て許可したものは,その許可の範囲内で容積率の制限が緩和される。
※ 容積率の緩和特例について (マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項関係)
耐震性不足の老朽マンションの建替え等を促進するため,マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)(以下「改正マンション建替え法」という。)が平成26年6月25日に公布,同年12月24日に施行されました。
改正マンション建替え法第105条では,同法第102条第1項に基づく認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで,一定の敷地面積を有し,市街地の環境の整備改善に資するものについて,特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できることとしています。
また,令和3年6月に行ったマンション建替法に係る総合設計制度許可準則の策定状況調査の状況が以下のようにとりまとめられています。
1.調査時点 令和3年4月1日
2.調査方法 国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
3.調査項目
・マンション建替法第105条第1項に係る総合設計制度許可準則の策定状況等
・許可に関する相談実績
・同準則の内容
・同準則に公開しているホームページのURL
4.調査結果
○ 各特定行政庁の許可基準
各特定行政庁HP上で公開されています。
(省略)
※ 改正 大規模庇等の積卸しスぺースの建築面積(/容積率/床面積)算定
以下を参照してください。 改正されています。
左 INDEX の「建ぺい率と建築面積」 → 「倉庫等の大規模庇等に係る建ぺい率算定上の建築面積の算定方法の合理化 (令和5年4月1日施行) 大規模庇に係る建築基準法施行令の見直しについて」
■ 004 容積率と前面道路の幅員との関係(法52条2項本文)
複数又は幅員が途中で異なる「前面道路」をめぐる問題 (2002K)
道路幅員による容積率の算定で,前面道路が2以上あるときは,その幅員の最大のもの」と規定されている。したがって,幅員の異なる二つの道路にはさまれた敷地で,どちらの道路にも接する場合は,この規定から広いほうの道路を前面道路とすればよい。
例1
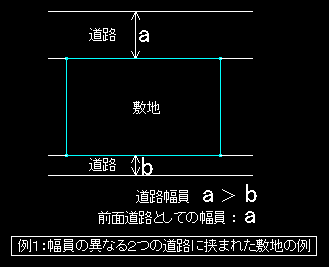
(敷地図)
しかし,2道路に接しているが幅員の大きい道路に接している長さが短い場合(例2),また,前面道路は一つでも途中で幅員が変化してる場合(例3)や道路幅員がV字状の場合(例4)など,「前面道路の幅員のうち最大の幅員」を特定するのに困難なケースも多い。一般的には2m以上接していれば前面道路とみなし,その幅員を適用しているが,計画にあたっては,事前に特定行政庁と相談しておく必要がある。 (2002K)
例2
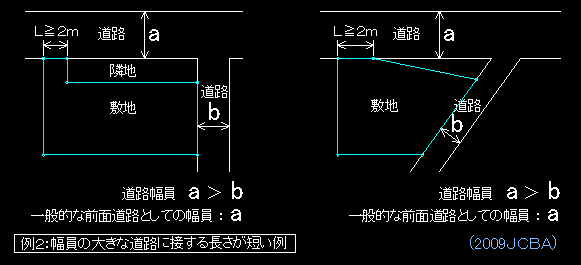
(敷地図)
前面道路は一つでも途中で幅員が変化してる場合及び道路幅員がV字状の場合 (2002K)
例3,4
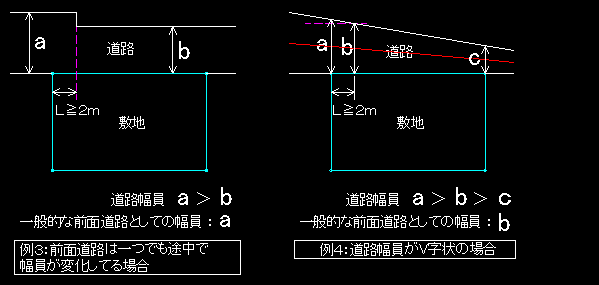
(敷地図)
例5,6 :その他のケース (2009JCBA)
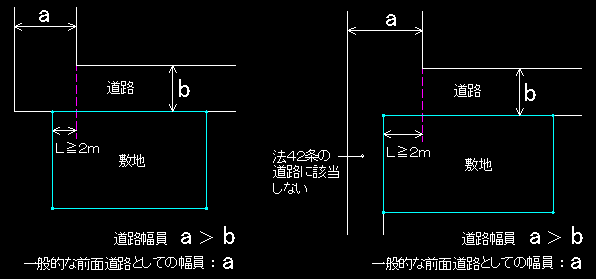
(敷地図)
■ 005 道路幅員による容積率制限の緩和(法52条第9項,令135条の17)
容積率の制限は,都市計画で指定された法定容積率か,12m未満の道路に接している場合の道路容積率のいずれか厳しい方の制限を受ける。この道路容積率制限をそのまま適用すると,広い道路に接する敷地ともっぱら狭い道路にしか接しない敷地には極端な容積率の変化が生じるため,政令により特定道路(≧15m)から一定の距離(L)による緩和がなされ,連続的にゆるやかな容積率の変化となるようになっている。
特定道路接続による容積率の緩和
道路幅員による容積率制限の緩和(法52条第9項,令135条の17)前面道路の幅員が6m以上であり,かつ,当該前画道路に沿って幅員15m以上の道路(特定道路)からの延長が70m以内である敷地については,前面道路幅員に政令に定める数値を加えて道路容積率の制限を算定できる。
緩和要件をまとめると以下のとおりである。
1.敷地の前面道路の幅員が6m以上
2.「1.」の前面道路は特定道路(幅員15m以上の道路)に接続
3.敷地は特定道路から70m以内
例 : 準住居地域の敷地Aにおける前面道路幅員による容積率制限
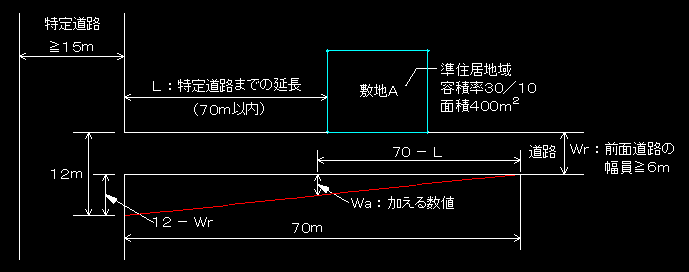
(敷地図)
Wa=(12-Wr)×(70-L) /70
Wa : 加算する数値(法52条9項の政令で定める数値)(単位m)
Wr : 前面道路の幅員(単位m)
L : 特定道路から建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位m)
前面道路幅の算定 = Wr+Wa
よって,敷地Aの前面道路幅員による容積率制限は (Wr+Wa)×4/10 (又は6/10) となる
特定道路からの距離(L)の測り方_道路が水平でない場合
道路が水平でない場合の距離(L)は水平距離とする。
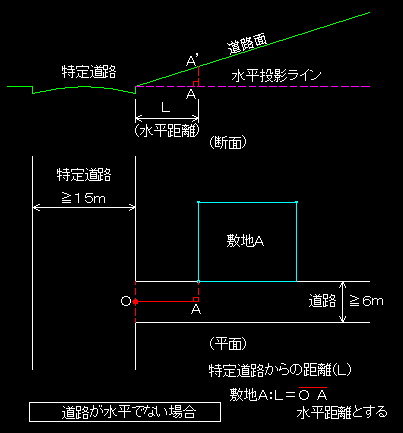
(敷地図)
Lの起点「O」のとり方 (2002K/2006H)
(敷地図)
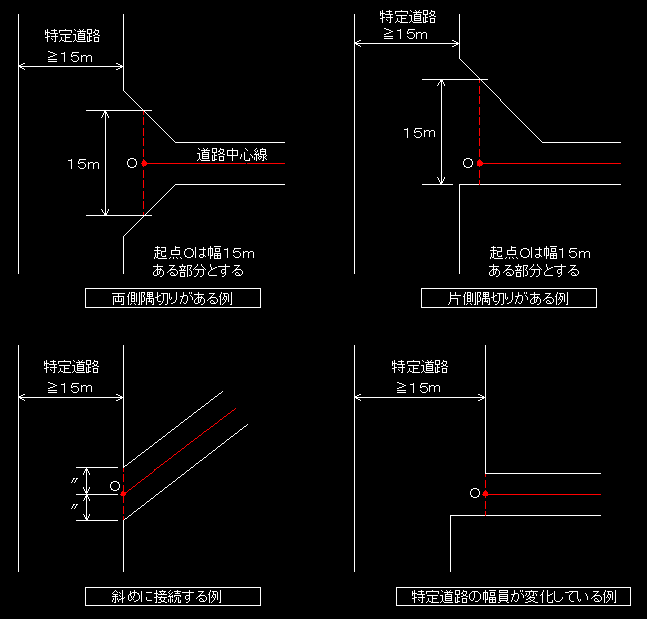
特定道路からの距離(L)の測り方_道路が水平の場合の各例 (2002K/2006H)
(敷地図)
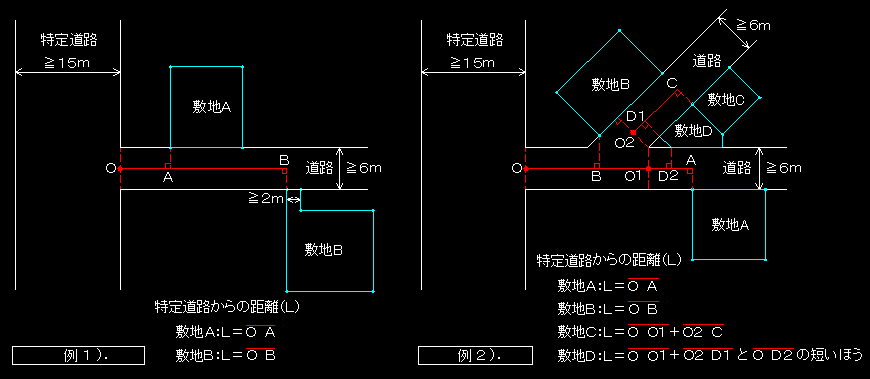
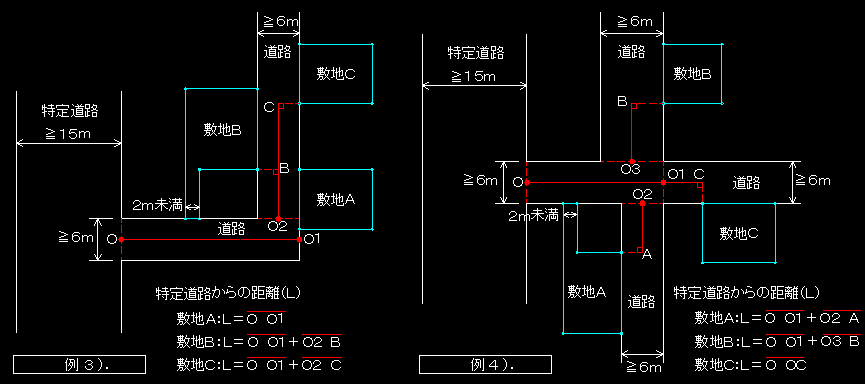
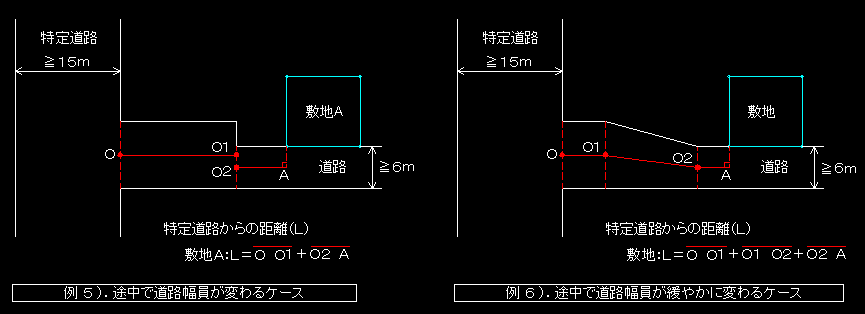
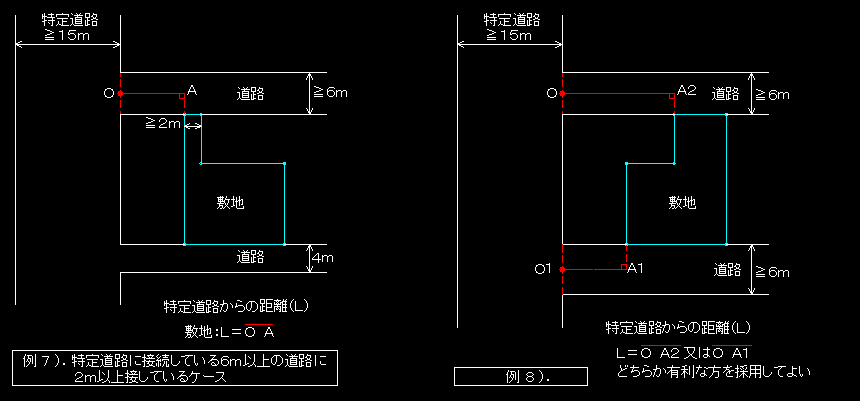
適用対象外の例
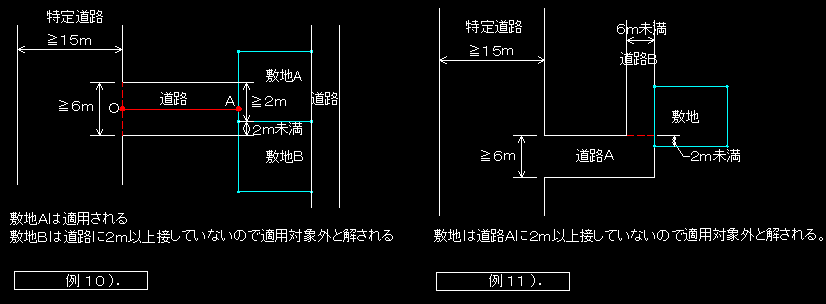
(敷地図)
適用対象外の例及び都市計画道路として15m以上に拡幅の予定がある場合 (2002K)
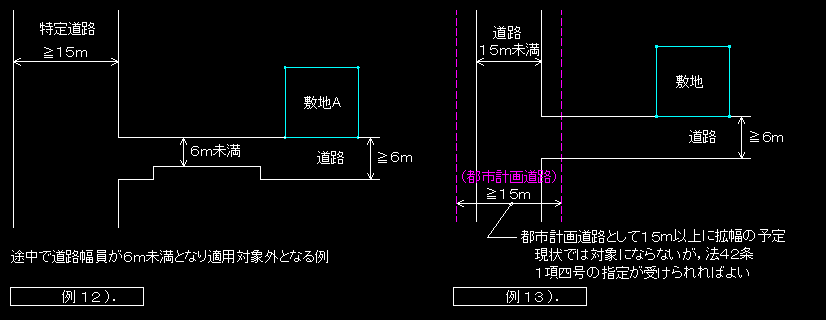
(敷地図)
■ 006 不算入となる容積率の緩和
駐車場等の容積率の緩和(令2条第1項第4号,令2条第3項) (2006H)
駐車場又は自転車置場がある場合の緩和
自動車車庫(誘導車路,操車場所,乗降場を含む),自転車駐輪場で,これらの用途に利用する床面積が延べ面積の1/5までは容積率の延べ面積から除外できる。
駐車場等の例 (A案,B案の場合)
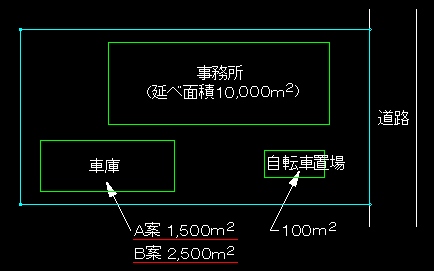
(敷地図)
駐車場等除外許容面積=駐車場等を含めた床面積の合計/5
この場合に,容積率いっぱいの建築物を計画したとすると,容積率に加算されていない駐車場等の許容面積は許容延べ面積/4として計算できる。
A案の場合
(10,000+1,500+100)/5=2,320 となり,車庫及び自転車置場の面積(1,600㎡)が2,320㎡以下なので,車庫及び自転車置場面積はすべて容積率算定の延べ面積から除外できる。よって,容積対象延べ面積は10,000㎡。
B案の場合
(10,000+2,500+100)/5=2,520 となり,車庫及び自転車置場の面積(2,600㎡)が2,520㎡を超えるので,容積対象延べ面積は10,000+(2,500+100-2,520) =10,080㎡となる。
他の方法による計算
元々の「車庫+自転車置場」の限度は10,000/4=2,500 となり,延べ面積合計は10,000+2,500=12,500㎡ となる。
B案の「車庫+自転車置場」の面積は2,600㎡で,限度の2,500㎡を超えるため,延べ面積合計の1/5は (10,000+2,500+100)/5 =2,520㎡ となり,容積対象延べ面積は10,000+(2,500+100-2,520) =10,080㎡ となる。
住居の地下室の容積率の緩和(法52条第3,4項)
はじめに
住宅等の地階の居室について (2007W)
地階の居室の設置条件が規定されました(法29条、令22条の2)。
原則的には居室は地階には設置できなかったのですが、衛生上必要な技術的基準に適合すれば可能ということで、 大きく分けて次の2点をクリアーすれば設置可能です。1つは「防水」、もう1つは「防湿」。詳細は建設省告示 (平成12年5月31日 第1430号)をご覧下さい。これらは基本的に仕様規定となってます。
● 法29条 【地階における住宅等の居室】
建築基準法29条では原則は地階の居室は禁止されているが,居室の前面にからぼりを設け,また衛生上支障がない場合は地下の居室も可能になります。
衛生上支障がないとは,採光の確保,換気の確保,火気仕様の制限,非難経路の確保,結露対策,排水措置等の検討が必要という意味合いです。
● 建築基準法施行令22条の2 【地階における住宅等の居室の技術的基準】
(省略)
● 平成12年5月31日第1430号〔告示〕
地階における住宅等の居室に設ける開口部及び防水層の設置方法を定める件
概要
・ からぼりの奥行き1m以上,かつ深さ(埋まっている部分)の4/10以上であること
・ からぼりの長さ2m以上かつ深さ以上であること・ その他衛生上支障がないことの細部の規定があります
【 住宅の地下室の容積率不算入 】 (法52条第3,4項) (2006H)
建築物の住宅の「地階」(*1)で,その「天井高さが地盤面(*2)から1m以下」(*3)にある「住宅の用途に供する部分」(*4)の床面積については,住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として延べ面積を不算入とする。
*1 地階(令第1条第2号)
床が地盤面下にある階で,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
*2 地盤面(法第52条第4項)建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(その接する位置の高低差が3mを超える場合は,その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面)とする。
法文上地階といわれるのは,床が地盤面下にある階で床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものである。
この規定での地階の判定は,地盤の高低差が3mを超える場合でも,建物全体として周囲の地面に接する位置の平均により行う。
なお,床面積は各階ごとに算定するものであることから,法第52条第4項に規定する地盤面は,建築物の当該階の部分ごとに算定することも考えられる。
*3 天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものとは(法第52条第3項)
(地盤面については,法52条5項により,地方公共団体の条例で,令135条の15の基準に従い,土地の状況等により区域を限って,別途定めている場合もあるので注意。)
不算入の対象となる地下室は,天井が地盤面からの高さ1m以内にあるものである。この地盤面とは,建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい,その接する位置の高低差が3mを超える場合は,その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう(法第52条第4項)。
不算入の対象となる地下室及び天井面が地盤面から1m以下の傾斜地の場合の考え方 (2007W)
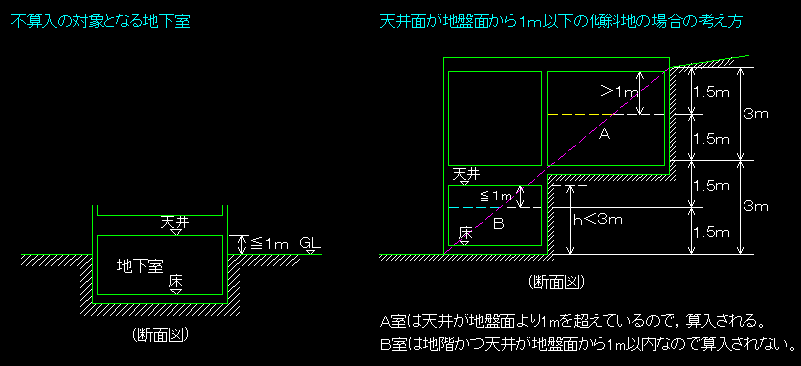
複数の地盤面が設定される場合 (2007W)
法第52条第3項の規定による天井と地盤面の関係につては,一室ごとの平均天井高さにより定まる高さと地盤面の関係となるが,同条第4条の規定により一室内に複数の地盤面が設定される場合は,当該室は低い地盤面(下図の地盤面2)から天井までの高さが1m以内でなければ緩和の対象部分とはならない。
天井面が異なる場合の考え方(法52条第3項の取扱い)
法52条第4項(及び5項)の複数の地盤面(・・・高低差3m以内ごとの・・・)が設定されるている場合
取扱い方
h1,h2は共に≦1mなので非居室,廊下等は緩和対象となる。居室は,h3≦1mであっても,h4>1mなので緩和対象外となる。
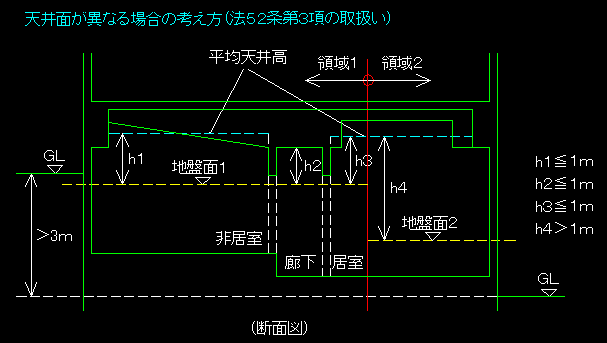
注意).上図の地盤面は,以下の地階の算定方法の場合の床面から地盤面までの高さの取扱いとは異なるので注意
当該階における最も高い位置にある床面から,建築物の当該階の部分が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面(その接する位置の高低差が3mを超える場合においても,その高低差の平均の高さにおける水平面とする)までの高さとする。
*4 住宅の用途に供する部分とは(法第52条第3項) (2006H)
住宅,又は住宅及び住宅以外の用途に供する複合の建築物で,次に掲げるものとする。
a).住宅
b).兼用住宅,併用住宅,長屋又は共同住宅の住戸の用に供する部分
c).住宅及び住宅以外の用途に供する複合の建築物の共用部分で,住戸の利用のために専ら供する管理人室,トランクルーム,機械室,電気室その他これらに類する建築物又は建築物の部分
注意).令第2条第1項第4号に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設は,住宅の用途に供する部分には該当しないが,令2条第3項の1/5の緩和の対象とはなる。
解説)
住宅及び住宅以外の用途に供する複合の達築物について
住宅部分とそれ以外の部分とは壁,床又は建具等により形態上明確に区分される必要がある。
延べ面積に不算入の住宅の用途に供する部分について
法第52条第3項の規定により,容積率の算定の基礎となる延べ面積における住宅の用途に供する部分に,共同住宅の共用廊下,階段,エントランスホール等は算入できない。
【 住宅の地下室の床面積算定例 】 (法第52条第3項)
(1)戸建て住宅の場合 (2002K)
住宅の用途とみなされる部分
・ 住宅の用途には,住宅の居室,物置,浴室,便所,廊下,階段が入る。車庫,駐輪場等は入らない(駐車及び停留共)。
・ 店舗,事務所等を持つ住宅では,店舗等の部分は対象とならない。
・ 地下部分が住宅用途以外なら,算入される。
下図の算定例
除外床面積 : 240㎡×1/3=80㎡
よって,容積率算定の対象となる床面積は,1階80㎡+2階80㎡=160㎡ となり,地階80㎡は除外面積となる。
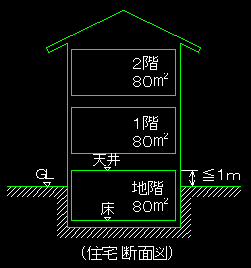
参考
住宅の地下車庫の棟別の取扱について (2008横浜市pdfより)
上層の住宅と地下車庫は,構造上一体でない場合,各々別の建築物として取り扱う。
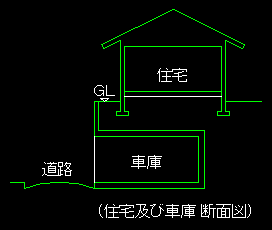
(2)店舗併用住宅の場合 (2006H)
下図の算定例
延床面積75+75+35=185㎡
住宅用途の部分20+35+35=90㎡
したがって,地階の住宅用途の部分は90×1/3=30㎡まで不算入。
よって,地階住宅20㎡は除外面積となり,容積率算定の対象となる床面積は,55+75+35=165㎡ となる。
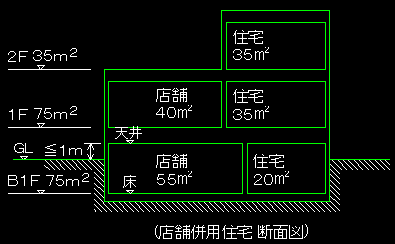
(3)共同住宅,長屋の場合
共同住宅,長屋も緩和の対象となる。
① 住宅用途とみなされる部分(共同住宅の共用廊下等を除く。)
・ 各住戸の専用部分(各戸専用の物置を含む。)
・ エントランスホール・ 屋内階段,廊下,エレベーター(住宅の用途の部分のみに属するもの)
・ 管理人室
・ 住宅用の設備機械室
・ 集会室(居住者のみに使用されるもの)
・ 共同住宅用トランクルーム
② 住宅用途とみなされない部分
・ 併設されるスポーツクラブ
・ 居住者以外の利用する会議室・ 倉庫・白動.申車庫等
注意).寮,寄宿舎,ウィークリーマンションは一般的には共同住宅とは扱われない。
例 共同住宅のトランクルーム (1995K)
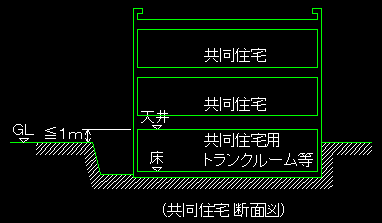
自動車車庫の緩和と併せて適用されるとき (2006H)
下図の算定例
住宅の用途の部分20+50+50=120㎡,延床面積50+50+50=150㎡
よって車庫面積のうち150×1/5=30㎡までは不算入
地階の住宅部分のうち120×1/3=40㎡までは不算入
よって,地階住宅20㎡及び車庫30㎡とも除外面積となり,容積率算定の対象となる床面積は50+50=100㎡ となる。
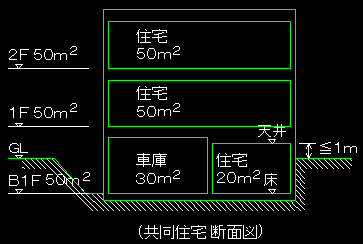
車庫(又は自転車置場等)は,令2条第3項の1/5の緩和の対象となり,法52条第3項の1/3の対象ではない。従って1/5を超えた場合は,超えた部分の床面積を容積率算定用延べ面積に算入しなければならない。
※ 住宅の小屋裏物置等の関連取り扱いについては,「建築基準法及び関連法解説」の以下を参照してください。
地盤面・階・建築物の高さ・天井の高さ (別ウィンドウで表示)
■ 005 小屋裏物置(天井裏,床下収納)などの階(数)の取り扱い
床面積 (別ウィンドウで表示)
■ 006 その他の床面積の算定について
小屋裏物置等の考え方 (1995K)
※ 容積率制限・建ぺい率制限の合理化等について (解説が飛び々で順不同になっています,ご容赦願います。)
近年、防災意識の高まりによる防災施設の設置やバリアフリー化のためのエレべーターの設置、高齢者等の良質な住まいのための空間の確保に向けた対応として、建築物に設ける備蓄倉庫部分やエレべーターの昇降路の部分、地階の老人ホーム等の用途に供する部分など、一定の範囲における床面積について容積率の制限が緩和されてきました。
平成30年には、共同住宅から老人ホーム等への用途の変更をしやすくし、既存建築ストックの利活用の促進を図るとして、老人ホーム等における共用の廊下等の部分の床面積についても容積率の制限が緩和されています。
また、市街地において、延焼防止性能の高い建築物(別のウィンドウで表示)への建替え等を促進するため、令和元年6月には建ぺい率制限の緩和も行われています。
老人ホーム等の用途に供する地階の部分の容積率不算入について (改正法) (Webサイトより)
改正法
容積率制限の合理化
公布 :平成26年6月4日 施行日 :1年以内の予定
(以下参考(抜粋))
事務連絡
平成26年7月4日
都道府県民生主管部(局)/市町村民生主管部(局) 御中
厚生労働省老健局高齢者支援課
・
・(略)
・
現行の建築基準法では,住宅について,その床面積の合計の3分の1を限度として,住宅の地下室の床面積を容積率に不算入とする特例が設けられているところです。
本特例について,今般の建築基準法の改正により,その対象が「老人ホーム,福祉ホームその他これらに類する用途に供する建築物」にも拡充されることとなりました(建築基準法第52条第3項)。 これにより,例えば,既存建物の建替えに際して容積率制限がネックとなって居室面積の拡大が困難であったケースについて,地上部分に計画していた老人ホーム等を構成する機械室等を地下部分に配置することで,地上部分の居室面積の拡大が図られるなど,設計上の工夫等により対応が可能となる場合も考えられます。
・
・(略)
・
(以下条文抜粋)
【容積率】
第五十二条建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。) は,次の各号に掲げる・・・・(略)・・・・以 下でなければならない。
一 ~ 六(略)
2(略)
3 第一項(ただし書を除く。),前項,・・・・(略)・・・・に規 定するものについては,建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第六項にお いて同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には,建築物の地階でその天井が地盤面 からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム,福祉ホームその他こ れらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)の用途に供す る部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は,算入しないものとする。
4・5(略)
6 第一項,第二項,次項,第十二項及び第十四項,第五十七条の二第三項第二号, 第五十七条の三第二項,第五十九条第一項及び第三項,第五十九条の二第一項,第 六十条第一項,第六十条の二第一項及び第四項,第六十八条の三第一項,第六十八 条の四,第六十八条の五,第六十八条の五の二,第六十八条の五の三第一項,第六 十八条の五の四(第一号ロを除く。),第六十八条の五の五第一項第一号ロ,第六十 八条の八,第六十八条の九第一項,第八十六条第三項及び第四項,第八十六条の二 第二項及び第三項,第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には,政令で定める昇降機の昇降路の 部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は,算 入しないものとする。
7~15(略)
※ 平成30年には、老人ホーム等における共用の廊下等の部分の床面積についても容積率の制限が緩和されています。 (建築基準法52条3項・6項)
老人ホーム等における共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積については、共同住宅と同様に容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。 算定対象外です。
※ 建築物の用途を問わず,老人ホーム等の共用の廊下に設置する宅配ボックス等も同様に算定対象外(各階の床面積の合計に1/100を乗じて得た面積を限度として)です。
※ 既存不適格建築物において増改築が認められる範囲に,老人ホーム等の共用の廊下等の部分及び宅配ボックス設置部分も算定対象外(令137条の8関係)です。
昇降機の昇降路の取扱いの詳細については以下を参照してください。
エレベーターの昇降路(シャフト)の容積率不算入について (改正法) (同じウィンドウで移動)
共同住宅の共用の廊下・階段の容積率不算入(法52条第6項)
共同住宅の容積率緩和
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分(以下「共用廊下等の部分」という)の床面積については,居住者が住戸に通行するために用いることであることから,容積算定上その延べ面積には算入せず,除外することができる。
なお,容積不算入の対象となる共同住宅は,共用の廊下又は階段の用に供する部分を有する全ての共同住宅であり,分譲であるか賃貸であるか問わないものである。
共用廊下等の部分に含むもの(延べ面積に不算入)
ア. エントランスホール,エレベーターホール(非常用の昇降機の乗降ロビー及び特別避難階段の付室を含む。)
イ. エントランスホール又はエレベーターホールと一体的に利用するメールコーナー
ウ. アルコーブ,突き当たりの廊下
エ. 床面積に算入されるピロティの通路部分で,他の用途と明確に区画されている部分
オ. 階段に代わる共用の傾斜路の部分
カ. 共同住宅の屋上へ通ずる廊下又は階段
キ. 共同住宅に付属する自動車車庫,倉庫等へ通ずる廊下又は階段
ク. 事務所,店舗等と共同住宅の複合する用途の建築物で共用の室(機械室,電気室等)へ通ずる廊下又は階段(複合建築物の容積不算入対象の算定は次項の「共同住宅の共用部分にかかわる複合建築物の容積不算」を参照)
共用廊下等の部分に含まないもの(延べ面積に算入)
・ エレベーターシャフトの部分,収納スペース,ロビー等の居住,執務,作業,集会,娯楽又は物品の保管若しくは格納その他屋内的用途に供する部分
(発生交通量等を増加させ,公共施設への負荷を増大させるおそれがあるため)
・ 昇降機機械室用階段その他特殊の用途に用いる階段の部分
(居住者が住戸に通行するために一般的に用いないため)
なお,共同住宅には寮,下宿,寄宿舎,ウィークリーマンションは一般的には含まない。共同住宅の住戸で,事務所等を兼ねる兼用住宅については,発生交通量等を増加させ,公共施設への負荷を増大させるおそれがあるため,容積不算入の対象となる同住宅の住戸に該当しない。
例 共用の廊下・階段等の部分 (2009JCBAより)
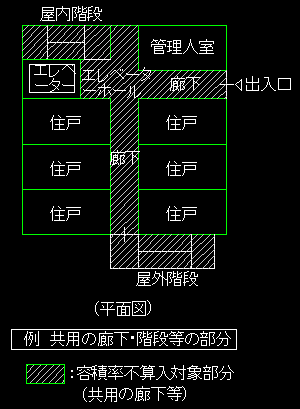
参考).都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成9年6月13日住街発第73号)
共同住宅の共用部分等に係る複合建築物の容積率不算入
容積率不算入の対象
● 専ら共同住宅の利用のために供されている共用の廊下又は階段の用に供する部分(以下「共用廊下等の部分」という。)は容積率不算入の対象とする。例えば,一定の階の専用部分の全てが共同住宅の用途に供されている場合には,その階の共用廊下等の部分は容積率不算入の対象となる。
● 住宅と非住宅の両方に供されている共用廊下等の部分については,その床面積の合計に,以下の下図の割合を乗じて按分した面積を容積率不算入の対象とする。
容積率算入
● 専ら非住宅の利用のために供されている共用廊下等の部分は,容積率不算入の対象とならない。
例 複合建築物における階段部分の計算例 (2009JCBAより)
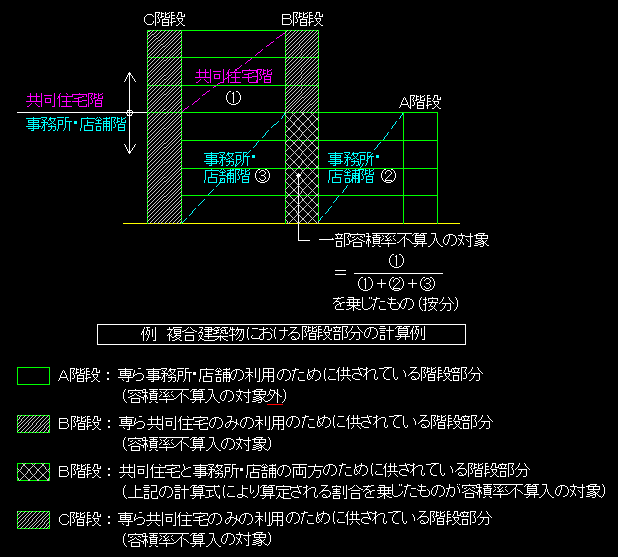
以下,Webサイト「共同住宅の共用廊下の容積不算入 Q&A」より (建設省住宅局市街地建築課) (Webサイトより)
(参考)
・ 共同住宅の「吹きさらし廊下の幅2mを超える部分」の容積率不算入について
質問1.従来より,吹きさらしの廊下については,幅2mを超える部分は「床面積」に算入することとされていたが,この制限は無くなったものと解してよいか。
回答1.「床面積の算定方法について」(昭和61年4月30日付け建設省住指発第115号)において,吹きさらしの廊下については,幅2mまでの部分を床面積に算入しないこととされているが,これは建築基準法施行命第2条第1項第3号に規定する「床面積」の算定方法を示したものである。
今般の共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置は,令第2条第1項第3号に規定する「床面積」に算入される共用廊下等であっても,建築基準法第52条第1項等に規定する「延べ面積」の算定上は不算入とするものであり,「吹きさらし廊下の幅2mを超える部分」については,従来どおり「床面積」には算入されるが,容積率算定上の「延べ面積」には算入されないこととなる。(従って,例えば,防火地域における延べ面積等,他の制限における延べ面積には算入される。)
・ その他
質問2.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置と自動車車庫等に供する部分及び住宅の地階の部分に係る容積率の不算入措置との適用関係如何。
回答2.自動車車庫等の用途に供する部分の容積率の不算入措置は,建築基準法施行令第2条第1項第4号の規定に基づき,容積率を算定する場合において,当該建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度に,自動車車庫等の用途に供する部分の床面積を不算入とするものであり,これは「延べ面積」の定義であることから,まず当該措置を適用する。
次に,住宅の地階の部分に係る容積率の不算入措置は,建築基準法第52条第2項の規定に基づき,住宅の地階部分を容積率の算定上,延べ面積に不算入とするものであるが,対象となる住宅の用途に供する地階の部分の床面積は,住宅の用途に供する部分の床面積の3分の1を限度とする。
この場合,当該不算入措置の対象部分を特定するためには,共用廊下等の床面積を含む住宅の用途に供する部分の床面積を適用する。このため,同条第4項において,同条第2項は適用対象とされていない。
今般の共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置は,こうした措置を講じた上で,共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を容積率の算定上,延べ面積に不算入とするものである。
質問3.高層住居誘導地区の区域内における共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置の適用はどうなるのか。
回答3.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置は,全ての共同住宅の共用廊下等について適用されるものである。従って,高層住居誘導地区の区域の内外にかかわらず適用される。
なお,当該地区内の建築物に係る容積率を算定するため,住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合を算出する場合にあっては,建築基準法第52条第2項及び第4項において,同条第1項第5号は除くこととされていることから,この場合の延べ面積には,住宅の用途に供する地階の部分の床面積及び共同住宅の共用廊下等の部分の床面積も含まれることとなる。
質問4.地区計画において容積率の最高限度が定められている場合,共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置は適用されるのか。
回答4.地区計画における容積率の算定については,建築基準法に基づき市町村が定める条例において,算定方法も含めて定めるものである。
質問5.「共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分」について,規模の上限はないのか。
回答5.共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置の対象となる共用の廊下又は階段の用に供する部分について,規模の上限は設けられていない。ただし,設計図書等において,共用廊下,階段と名称が付けられていても,建築物の構造上,区画された部分については,共用の廊下又は階段には該当しないものとする。
質問6.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積卒の不算入措置の対象に,「寄宿舎,下宿」,「老人ホーム」は含まれるのか。
回答6.共用廊下等の部分に係る容積率の不算人措置の対象は,「共同住宅」とされており,建築計画や機能が共同住宅と異なり,建築基準法において,別の用途とされている「寄宿舎,下宿」及び「老人ホーム」は,当該措置の対象とはならないものである。
質問7.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積卒の不算入措置は,必ず適用しなければならないのか。容積率に余裕があることから,当該措置を適用しないという選択はあり得るのか。
回答7.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置は,選択的な特例措置ではなく,建築基準法第52条第1項等における「延べ面積」の算定方法を定めたものであり,同条第4項において,「建築物の延べ面積には,共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は,算入しないものとする。」とされていることから,必ず不算入とされる。
質問8.共同住宅において,住戸以外の部分(地下駐車場,トランクルーム,集会室など)や屋上へ通ずる廊下及び階段は,共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置の対象となるのか。
回答8.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置の適用に当たって,共同住宅の各部分へ通ずる廊下及び階段がその適用対象に含まれるかどうかについては,当該部分が,住宅の部分を構成するものか,あるいは住宅とは独立の用途を構成するものかによるものである。
この観点から,個々の具体の事例における当該不算入措置の適用の可否について判断する必要がある。
質問9.共用廊下から各戸の玄関へ至るアプローチ部分は,共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置の対象となるのか。当該部分に門扉を付けて共用廊下と区画した場合はどうか。また,空調屋外機置場部分等はどうか。
回答9.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置の適用に当たっては,各部分が共用廊下等に該当するかどうかは,具体の設計により判断することとなる。この際,建築物の構造上,共用廊下等と区画されたものについては,当該不算入措置の対象としない。なお,門扉等については,この観点から,個々の具体の事例について判断する必要がある。
また,空調屋外機置場部分等については,特定の用途に専ら供されるものとして区画されている場合には,廊下としての機能を果たさないものであるため,今般の不算入措置の適用対象には含まれないものである。
質問10.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置の適用を受けた建築物については,用途変更は不可能となるのか。
回答10.共同住宅の共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置は,当該建築物の用途が共同住宅に該当する場合に限り,容積率の算定において,共用廊下等の部分の床面積を不算人とするものである。従って,当該建築物の全部又は一部について,住宅以外の用途に変更された場合には,当該用途変更に係る共用廊下等の部分の床面積は容積率に算入されることとなる。
この上で,容積率制限に抵触せず,また,用途規制等の規定に適合するものであれば,用途変更は可能である。
エレベーターの昇降路(シャフト)の容積率不算入について (改正法) (Webサイトより)
(関連法/令他: 法第52条第6項,令第2条第1項第3号,法第92条,昭和61年4月30日住指発115号)
法第52条第6項の容積率不算入の部分として「政令で定める昇降機の昇降路の部分」という規定が追加され,全ての用途の建築物における全ての階について不算入と改正されました。
公布 :平成26年6月4日 施行日 :平成26年7月1日
(尚7月1日の改正に伴い,確認申請等の法定様式についても変更されました。)
以下 Q & A です。(140829_Webサイトより要約抜粋)
(基本的事項)
Q1.政令では何を定めるのか。
A1.政令では,「エレベーター」と規定のため,エスカレーターや小荷物専用昇降機など,建築基準法に基づく「エレベーター」に該当しないものは容積率不算入の対象となりません。
Q2.昇降機のうちエスカレーターや小荷物専用昇降機が容積率不算入の対象とならないのはなぜか。
A2.今回の改正は,エレベーターは,バリアフリーの観点から設置等を促進する必要がある一方で,同時に使用される床面積はかご数分に限られ,エレベタの昇降路の部分全体を容算率不算入としても,インフラに与える影響が軽微であると考えられるためです。 エスカレーターは,エレベーターとは異なり,各部分を同時に利用するものであるため,容積率規制の趣旨をまえ,容率不算入の対象とはしていません。
また,小荷物専用昇降機は,バリアフリーの観点から設置等を促進する必要があるとは考えられないため,容積率不算入の対象とはしていません。
Q3.エレベーターの昇降路の部分の容積率不算入の対象となる建築物の用途は何か。例えば,戸建住宅のホームエレベーターなども対象となるのか。
A3.建物用途は限定していません。
Q4.容積率不算入の対象部分は壁芯で算定するのか内法で算定するのか。
A4.基本的に壁芯で計測することとなり,昭和61年住指発第115号のとおり,具体的な中心線の設定は各種構造方法により異なります。
Q5.昇降路内は最下階も含めて容積率不算入と考えてよいか。
A5.これまで算入することとされていた停止階分のすべてが不算入となります。
Q6.PH(ペントハウス)階等に設置されるエレベーターの機械室は,昇降路の部分と考えて,容積率不算入となるか。
A6.機械室については,「昇降路の部分」には該当しないため,容積率不算入の対象とはなりません。なお,機械室を設けずに昇降路内に駆動装置等を設置するいわゆる「マシンルームレスエレベーター」の昇降路の部分は容積率不算入となります。
Q7.昇降機の昇降路の部分は,床面積,建築面積及び建ぺい率の算定からも除外されるのか。
A7.床面積,建築面積及び建ぺい率の算定からは除外されません。
Q8.工場,物流施設,倉庫等に設置される生産・搬送設備等である昇降機や,機械式駐車場,機械式駐輪場,立体自動倉庫等の保管設備等である昇降機は,容積率不算入の対象となるのか。
A8.建築基準法上の「エレベーター」に該当しない設備の設置部分については,容積率不算入の対象とはなりません。
Q9.特殊な構造のエレベタのうち「オープンタイプエレベーター」,「段差解消機」及び「いす式階段昇降機」は,容積率不算入の対象となるのか。
A9.オープンタイプエレベーターは,昇降路の囲い等はないものの,昇降路の部分が他の目的に使用されることがないため,容積率不算入の対象となります。 段差解消機は,昇降路の囲い等により,昇降路の部分が他の目的に使用されることがない場合は,容積率不算入の対象となります。なお,かごの部分が折りたたみ式又は着脱式の段差解消機等で通常昇降路の部分を階段として利用する場合には,容積率不算入の対象とはなりません。
いす式階段昇降機は,通常,昇降路の囲い等がなく,いす部分も折りたたみが可能であり,昇降路の部分が他の目的に使用されることが考えられるため,容積率不算入の対象とはなりません。
Q10.ダブルデッキエレベーターや斜行エレベーターも,昇降路の部分全体が容積率不算入の対象と考えて良いか。
A10.これまで算入することとされていた停止階分のすべてが不算入となります。
(手続き関係)
Q11.改正法の施行前に確認申請する場合,エレベーターの容積率不算入を前提とした計画はどのような扱いになるか。また,改正法施行前に,施行後の新様式を使って確認申請を認めることは可能か。
A11.エレベーターの容積率不算入を前提とした計画を確認申請する場合,改正法施行後に確認済証が交付されるものについては,改正法の適用を受けることになります。 ただし,申請様式は,確認申請時点で施行されているものを使用してください。この際,エレベーターの容積率不算入に係る部分については,申請書の「その他必要な事項」欄や「備考」欄に,必要事項を記載してください。
Q12.改正法の施行前に着工し,工事中である建築物について,改正法の施行後に,エレベーターの容積率不算入を反映して増床した計画に変更しようとする場合,計画変更の確認申請を行った上で,変更後の計画に基づく工事を行うこととして良いか。それとも,着工時点の法律が適用されると考えて,いったん改正法施行前の建築計画に基づく工事を完了させた後,あらためて,新規の確認申請(増築に係る内容)を行う必要があるのか。
A12.計画変更の確認申請により対応することが可能です。
(既存不適格)
Q13.令第137条の8について容積率の既存不適格建築物にエレベーターを増築する場合,どのような設置方法であれば遡及適用が緩和されるのか。
A13.容積率の既存不適格建築物にエレベーターのみを増築する場合のほか,共同住宅においてエレベーターに付随して共用の廊下等を増築する場合等についても,遡及適用が緩和されます。なお,機械室は容積率不算入の対象とならないため,令第137条の8の対象となるのは,機械室を有しないエレベーターを増築する場合を想定しています。
Q14.エレベーター前の乗降ロビーは引き続き容積率に算入するのか。
A14.共同住宅の共用の廊下等である場合を除き,乗降ロビーは引き続き容積率に算入されます。
Q15.容積率に関する既存不適格建築物にエレベーターを増築する場合には,構造関係規定も遡及適用されないのか。
A15.構造関係規定が遡及適用されないためには,令第137条の2の規定を満たす増築である必要があります。
防災施設を有する建築物等の容積率算定 (改正法 令第2条第1項第四号へ(新)・第3項第六号(新),建築基準法施行規則別記第二号様式関係) (2023W)
防災施設等の容積率算定
防災施設の設置などへの対応として、建築物に下表A欄の部分を設ける場合、敷地内の建築物の各階の床面積の合計に、それぞれ表B欄の割合を乗じて得た面積を限度として、当該部分の床面積は、容積率算定における延べ面積に算入されません。