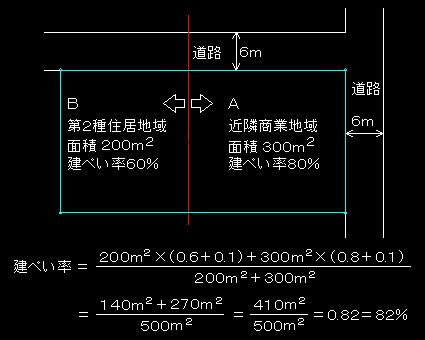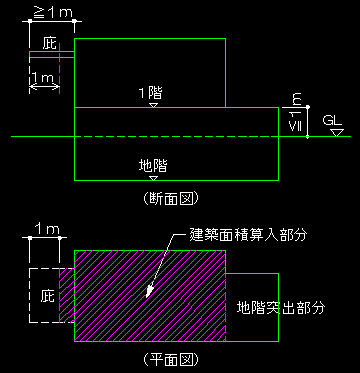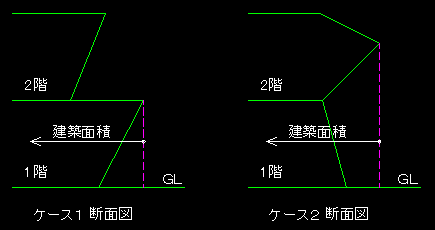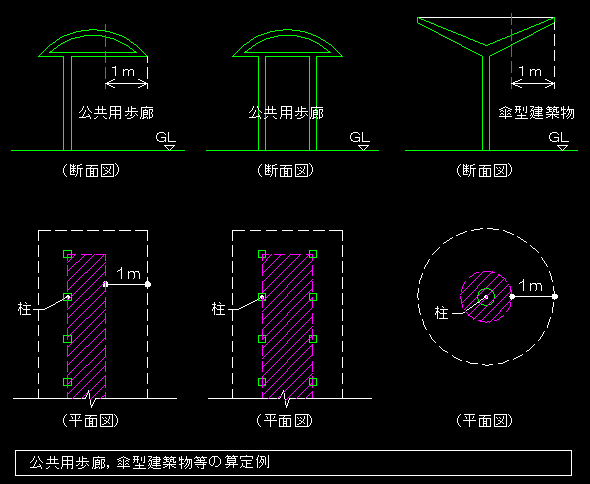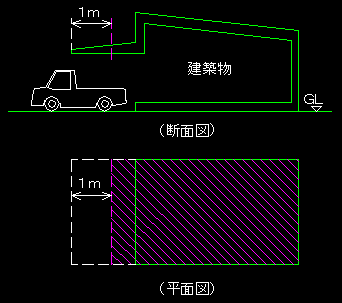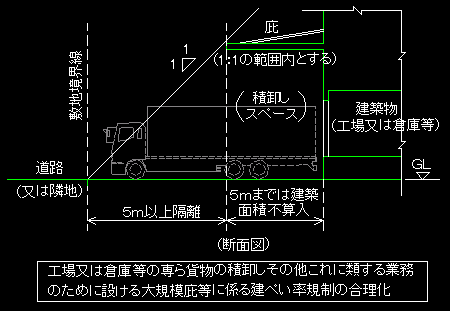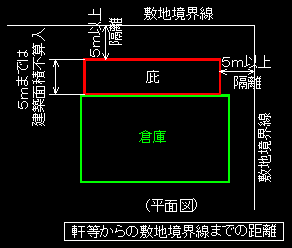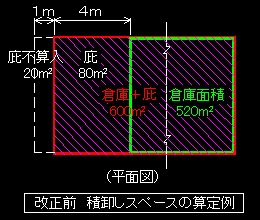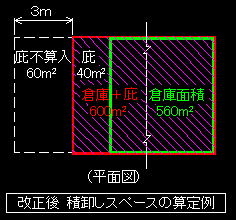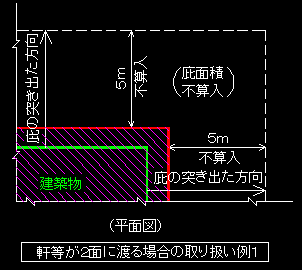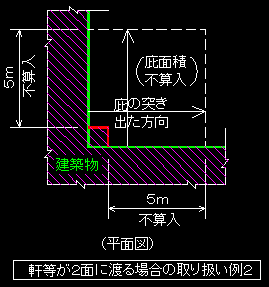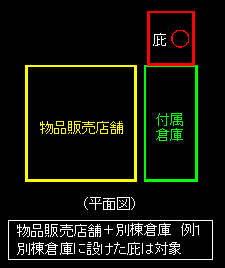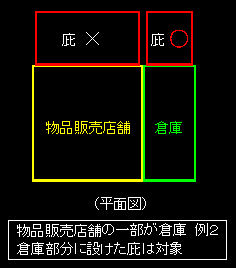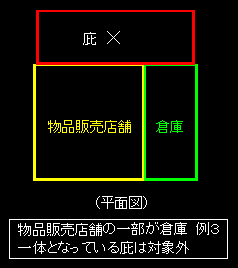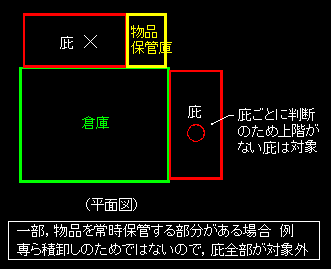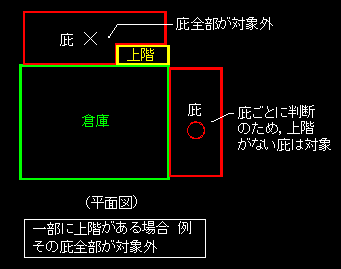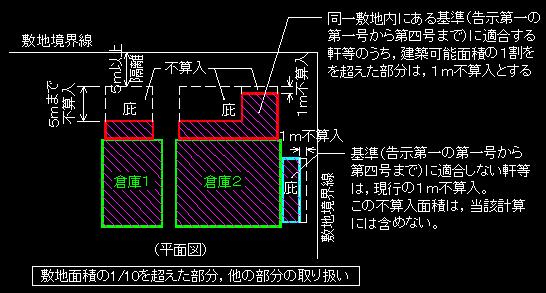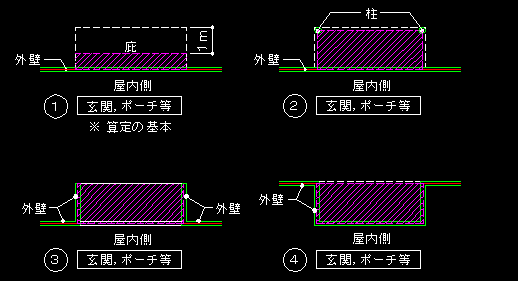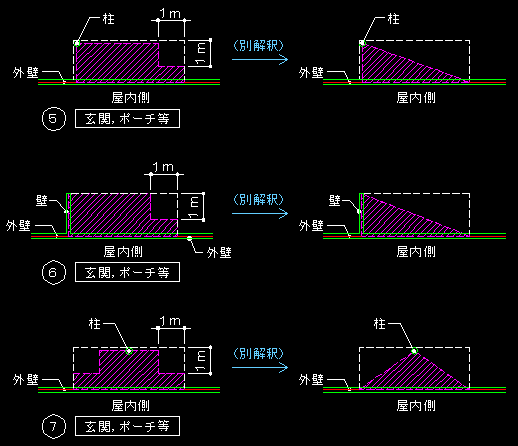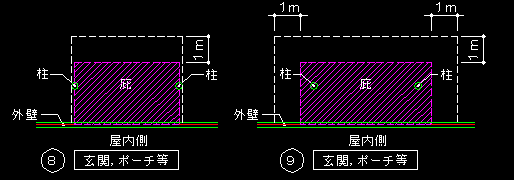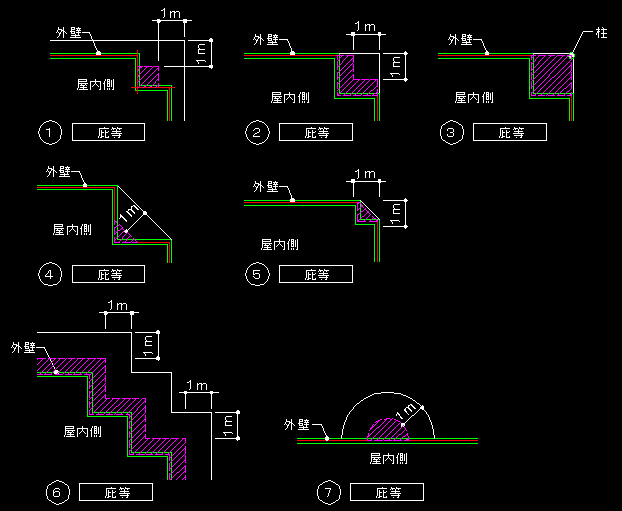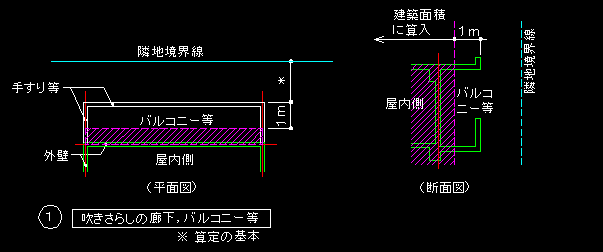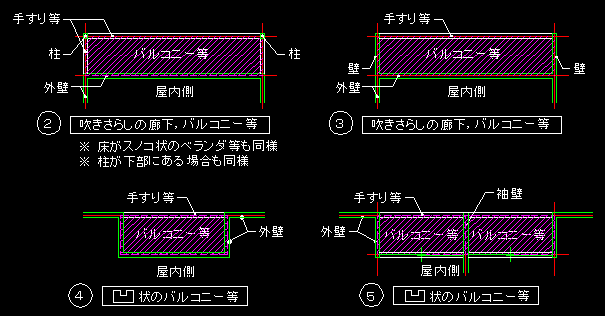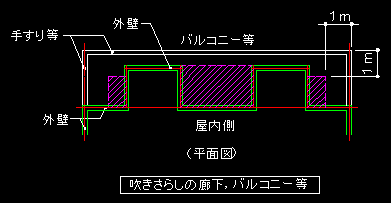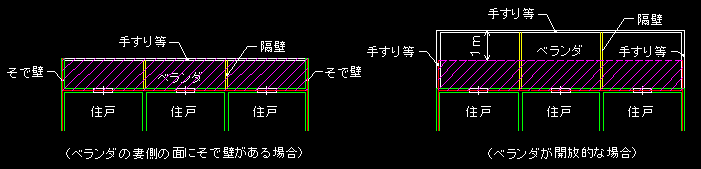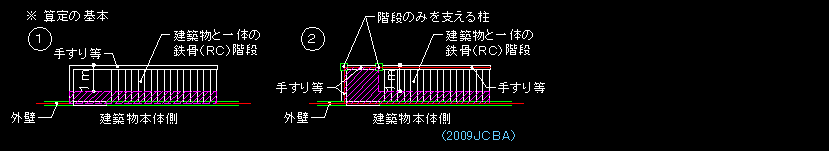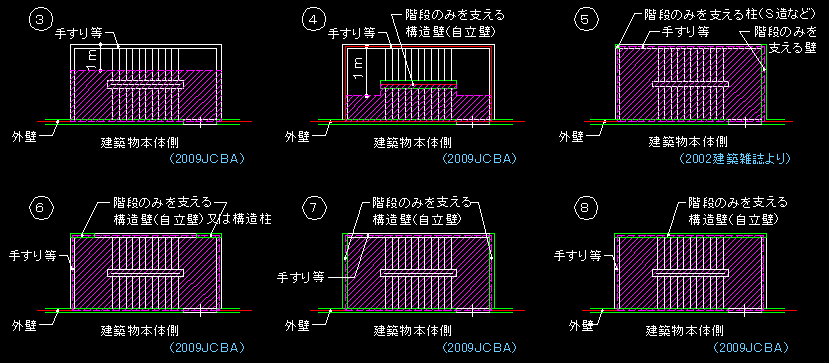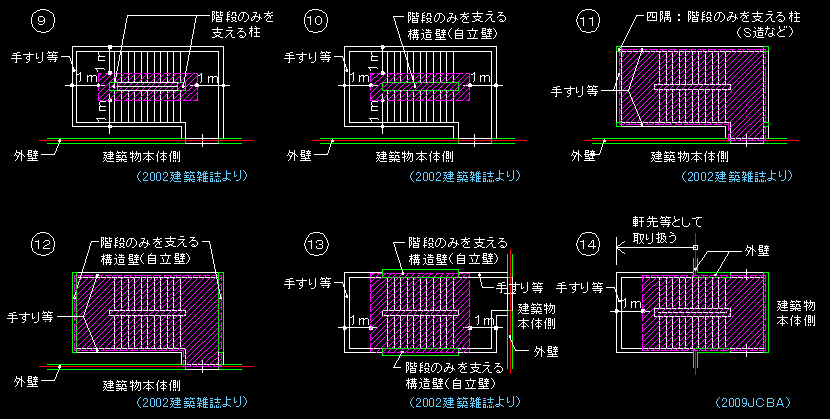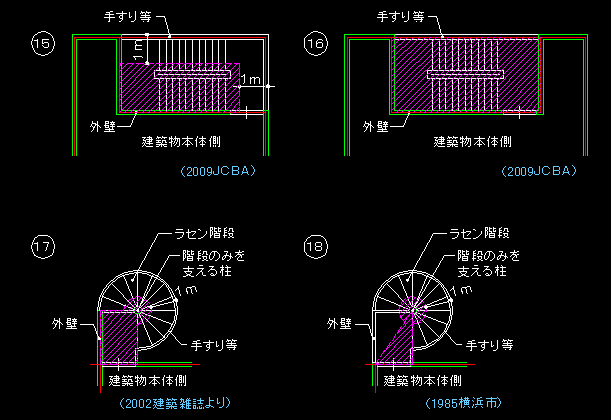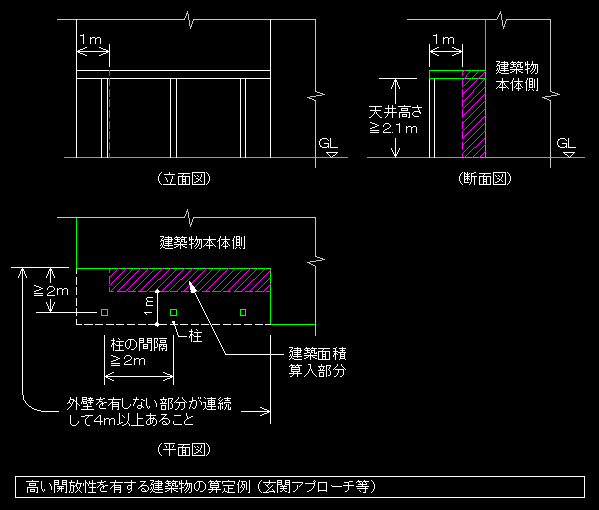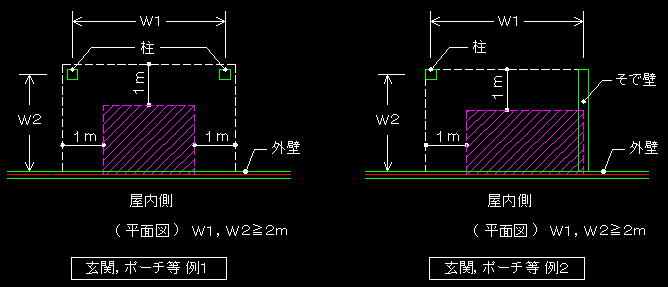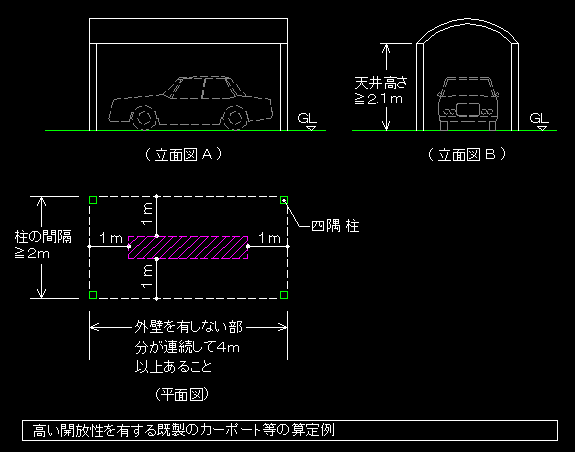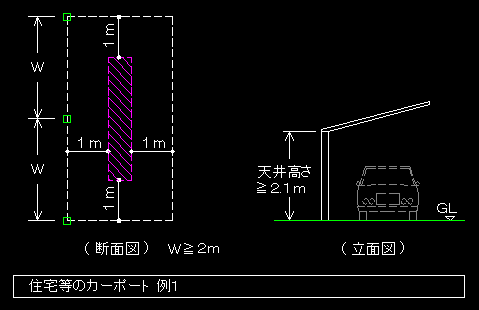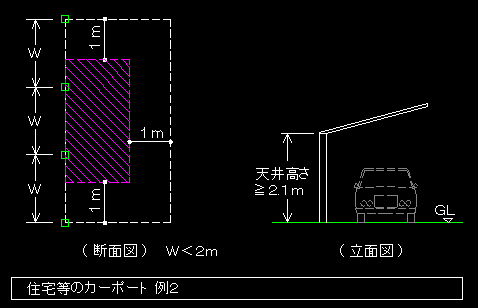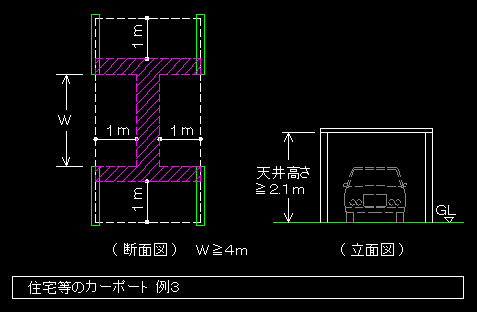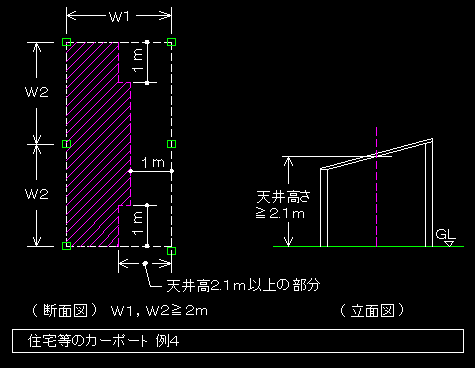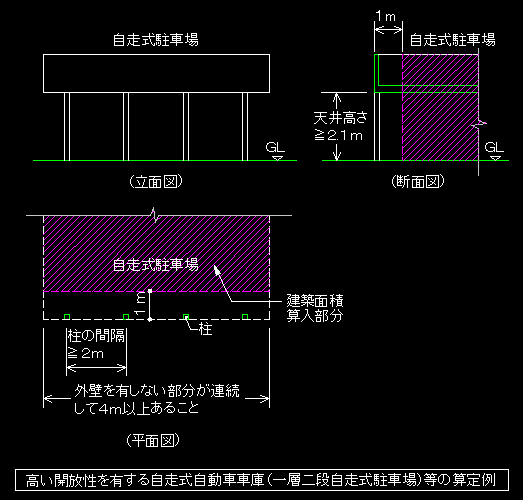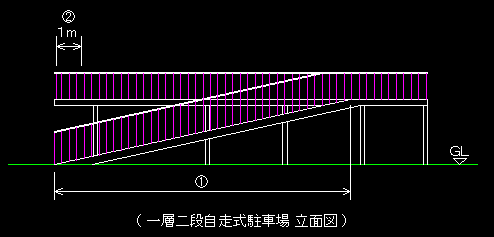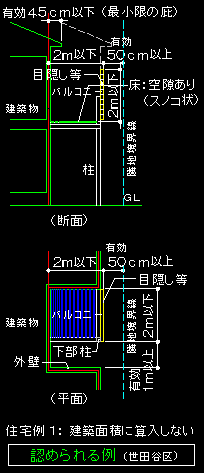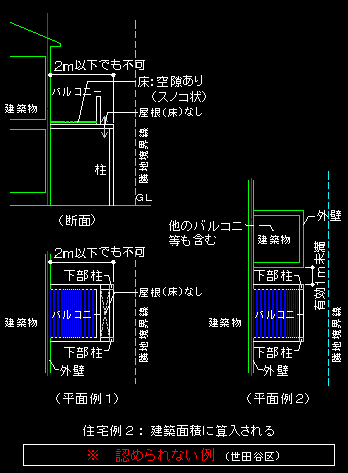「建築基準法及び関連法解説」
全ページ
→
遠山英雄都市建築設計事務所 - HOMEへ
__________________________________________________
建ぺい率と建築面積
「 目 次
」
■ 001 建ぺい率の緩和について(法第53条関係)
角地の場合/耐火建築物を建てる場合/角地でかつ耐火建築物を建てる場合/建ぺい率の制限がない場合もある
延焼防止性能の高い建築物等の建蔽率制限の緩和 (令和元年6月) (2023W)
■ 002 建ぺい率の加重平均(法第53条第2項)
角敷地で建ぺい率値の異なる二つの用途地域にまたがる場合
■ 003 建築面積算定の基本(法第53条,令第2条第1項第二号)
庇及び地階が地盤面上に出ている建築物の算定例
外壁面が垂直でない建築物の建築面積の算定
■ 004 建築面積算定例(令第2条第1項第二号)
公共用歩廊,傘型建築物等の算定例
荷さばきスぺースの算定例
倉庫等の大規模庇等に係る建ぺい率算定上の建築面積の算定方法の合理化 (令和5年4月1日施行) 大規模庇に係る建築基準法施行令の見直しについて
改正 大規模庇等の積卸しスぺースの建築面積(/容積率/床面積)算定
軒等からの敷地境界線までの距離
庇の奥行を5m確保したい場合の倉庫の建築面積の例
改正前 施行令
改正後 施行令
「告示143号」
軒等が2面にわたる場合の考え方
用途による緩和適用の制限
例1
. 庇の一部を常時保管するために利用(物品保管庫等)する場合には,その全部で緩和の対象から外れてしまう例
例2
. 庇の一部に上階がある場合には,その全部で緩和の対象から外れてしまう例
敷地面積の1/10を超えた部分,他の部分の取り扱い / 確認申請書3面の【10.
建築面積】記載欄について
玄関,ポーチ等の算定例
庇等の算定例
吹きさらしの廊下,バルコニー等の算定例1
吹きさらしのバルコニー等の算定例2
階数が2以上のベランダの算定例
屋外階段の算定例
■ 005 高い開放性を有する建築物の建築面積の緩和例 (令2条1項二号,告示第1437号)
高い開放性を有する建築物の算定例
(玄関アプローチ等)
高い開放性を有する玄関,ポーチ等 例1,2
高い開放性を有する既製のカーポート等
高い開放性を有する住宅等のカーポート例1~4
高い開放性を有する一層二段自走式駐車場の算定例
(告示第1437号/3年6月10日建設省住指発第210号/法第84条の2/平成4年の法改正等)
■ 006 スノコ状のバルコニーは建築面積算定の対象となるか (雑則関係
法第92条,令第2条第1項第2号)
近年のスノコ状バルコニーの取り扱いについて
一戸建ての住宅等 (東京都,神奈川県の取り扱い例)
参考1).許可なしで増築できるのは何㎡まで
参考2).民法234条の「建物を築造するには,境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」
について
■
001 建ぺい率の緩和について(法第53条第3~第8関係
(条文省略))
角地の場合/耐火建築物を建てる場合/角地でかつ耐火建築物を建てる場合/建ぺい率の制限がない場合もある
延焼防止性能の高い建築物等の建蔽率制限の緩和 (令和元年6月) (2023W)
以下の①から③のいずれかに該当する建築物では10%(=1/10)を、①と②の両方(角地かつ耐火建築物)または①と③の両方(角地かつ耐火建築物、準耐火建築物を建てる場合)に該当する建築物では20%(10%+10%=2/10)を、都市計画等による建蔽率の限度に加算することになっています。
また、④に該当する建築物には建蔽率の制限がなく、建蔽率の規定は適用されません。敷地面積に対して100%建物を建てられます。
① 街区の角(角地)にある敷地またはこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物 (+10%)
② 防火地域(都市計画等による建蔽率の限度が8/10である地域(※)を除く。)内にある耐火建築物またはこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物 (+10%)
(※.建蔽率の限度が8/10である地域外とは,近隣商業地域や商業地域以外,または第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,準工業地域の内,指定建蔽率80%の地域以外)
③ 準防火地域内にある耐火建築物、準耐火建築物またはこれらと同等以の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物 (+10%)
④ 防火地域(都市計画等による建蔽率の限度が8/10である地域(※)に限る。)内にある耐火建築物またはこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物
建蔽率の規定は適用されず、敷地面積に対して100%建物を建てられます。
(※.建蔽率原則80%の商業系の用途地域である商業地域あるいは近隣商業地域)
角地による建蔽率制限の緩和について
街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するもののうちにある建築物については、都市計画等によリ定められる建蔽率の限度に10%(=1/10)加算することができます。この指定は特定行政庁が行うため建設地によりその内容が異なります。
●東京都の場合(東京都建築基準法施行細則)
(建蔽率の緩和)
第21条
(以下,省略します)
■ 002 建ぺい率の加重平均(法第53条第2項)
角敷地で建ぺい率値の異なる二つの用途地域にまたがる場合の建ぺい率値の算定例
この場合,第2種住居地域も角敷地の一部であるため緩和の対象となり,建ぺい率値は82%となる。
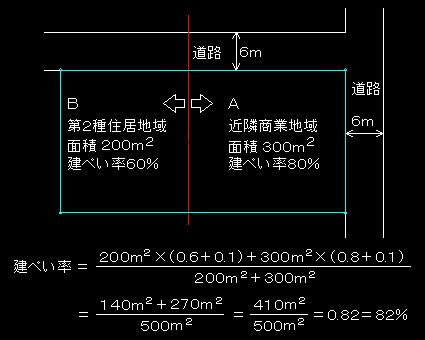
(敷地図)
■ 003 建築面積算定の基本(法第53条,令第2条第1項第二号)
 :建築面積に算入される部分
:建築面積に算入される部分
庇及び地階が地盤面上に出ている建築物の算定
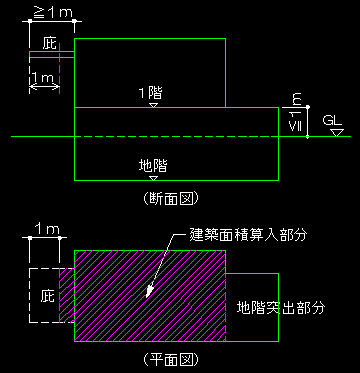
外壁面が垂直でない建築物の建築面積の算定
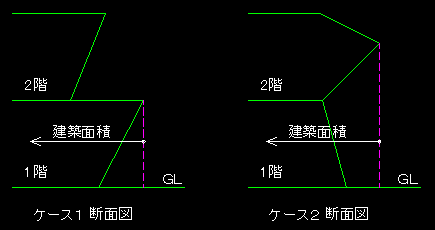
■ 004 建築面積算定例(令第2条第1項第二号)
 :以下,建築面積に算入される部分
:以下,建築面積に算入される部分
公共用歩廊,傘型建築物等の算定例 (1995K)
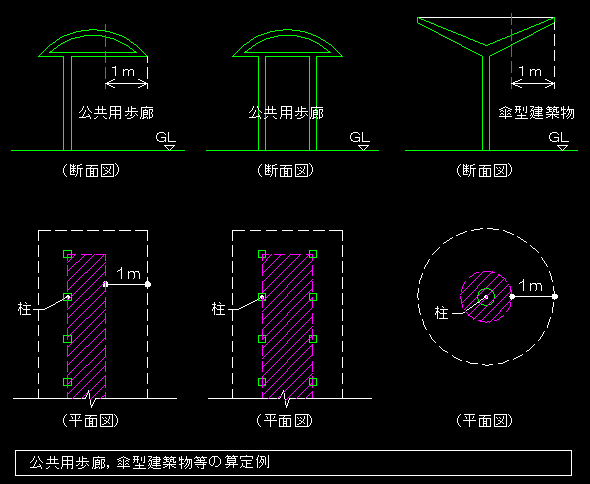
荷さばきスぺースの算定例 (1995K)
ひさしの下を荷さばきスぺースに使用する場合には建築面積に算入されるが,明確な区画がないときには先端から1m引いた部分で算入する。
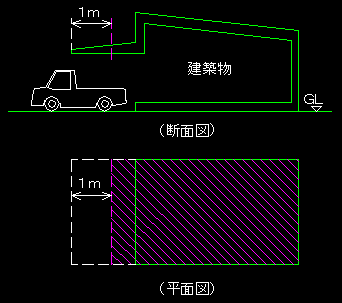
倉庫等の大規模庇等に係る建ぺい率算定上の建築面積の算定方法の合理化 (令和5年4月1日施行) 大規模庇に係る建築基準法施行令の見直しについて
改正 大規模庇等の積卸しスぺースの建築面積(/容積率/床面積)算定
背景
物流業界では,大規模な軒(庇)などの不合理な建ぺい率算定取り扱いの状況の改善を目指し,「雨天時でも荷さばきが可能な大型の庇は荷役作業の生産性向上や,災害時の一時的な蔵置場として重要な役割を果たす」と言ったメリットをかかげ,建築基準法の緩和を長年要望してきました。
法改正によって
倉庫の新設を行う場合,確保できる倉庫面積(庫内面積)が大きくなります。ただ,「安全上,防火上及び衛生上支障がない軒等を定める告示」により,いくつかの要件が定められています。
また,今回の改正は建ぺい率だけではなく,容積率,床面積も同様の規制緩和が適用されます。
|
倉庫等の大規模庇等に係る建ぺい率算定上の建築面積の算定方法の合理化 大規模庇等の積卸しスペースの取り扱い |
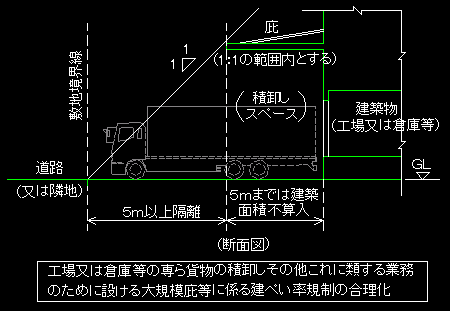 |
倉庫の庇の建築面積で緩和措置がなされました。
不算入範囲を1mから5mへ拡大されました。
建築物の用途と軒等について
工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等であること。
以下,国土交通省 告示143号
要約
「当該軒等の端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地を確保するなど,安全上,防火上,衛生上の要件を満たすこと」という一定の要件を満たさなければならないとされており,「一定の要件」は以下のように定められている。
・ 庇端は敷地境界線から5m以上離隔
・ 敷地境界線を基準点として,庇の高さに応じた離隔距離(1:1)を確保し,この範囲内とする
以下,告示143原文抜粋
二 軒等の全部の各部分の高さは、当該部分から当該軒等が突き出た方向の敷地境界線までの水平距離に相当する距離以下とすること。
・ 庇部分は不燃材料とする
・ 庇上部に上階を設けないこと(※非常用進入口,室外機置場等は可)
・ 不算入となる庇の合計面積は,当該敷地の建築可能面積(敷地面積×当該敷地の建ぺい率)の1割以下とする
|
軒等からの敷地境界線までの距離
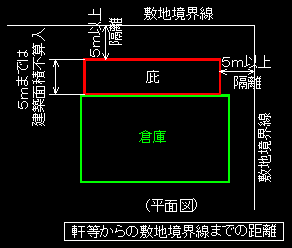
庇の奥行を5m確保したい場合の倉庫の建築面積の例
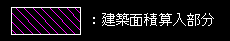
「敷地面積:1,000㎡ 建ぺい率60%」の場所に平屋の倉庫を新設する場合
(庇の最大不算入面積は,建ぺい率の最高限度が定められている場合においては,敷地面積に当該最高限度を乗じて得た面積に十分の一を乗じて得た面積以下とする)
|
| 改正前 |
改正後 |
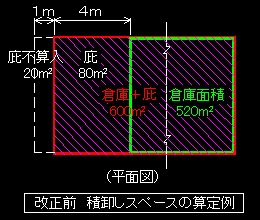 |
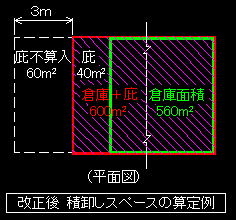 |
庇の奥行を
5m確保したい場合の倉庫面積 (告示より)
例 : 「敷地面積:1,000㎡ 建ぺい率60%」の場所に平屋の倉庫を新設する場合
( 建築面積 ≦ 600㎡ ・ 庇の施工面積 100㎡
)
庇の最大不算入面積 600㎡ × 0.1
= 60㎡以下
庇の算入面積は 100㎡ - 60㎡ = 40㎡ となり
倉庫面積560㎡ + 庇面積40㎡ = 600㎡ となる
最終的な倉庫面積は,560㎡となります。
|
改正前 施行令
令2条1項二号
建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒,ひさし,はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては,その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし,国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については,その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は,当該建築物の建築面積に算入しない。
改正後 施行令
令2条1項二号
建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒,ひさし,はね出し縁その他これらに類するもの(以下この号において「軒等」という。)で当該中心線か
ら水平距離1m以上突き出たもの(建築物の建率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り,工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等でその端と敷地境界線との間の
敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上,防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「特例軒等」という。
)のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離1m以上5m未満のものであるものを除く。)がある場合にお
いては,その端から水平距離1m後退した線(建築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り,特例軒等のうち当該中心線から水平距離5m以上突き出たものにあっては,その端から水平距離5m以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線)
)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし,国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については,当該建築物又はその部分の端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は,当該建築物の建築面積に算入しない。
「告示143号」
第一 令第2条第1項第二号に規定する安全上,防火上及び衛生上支障がない軒等は,次の各号に掲げる基準に適合する軒等の全部又はその一部とする。
一 軒等の全部の端からその突き出た方向の敷地境界線までの水平距離のうち最小のものが5m以上であること。
二 軒等の全部の各部分の高さは,当該部分から当該軒等が突き出た方向の敷地境界線までの水平距離に相当する距離以下とすること。
三 軒等の全部が不燃材料で造られていること。
四 軒等の全部の上部に上階を設けないこと。ただし,令第126条の6の非常用の進入口に係る部分及び空気調和設備の室外機その他これらに類するものを設ける部分については,この限りでない。
五 第一号から第四号に掲げる基準に適合する軒等の全部又はその一部について,次のイ又はロに掲げる軒等の区分に応じ,それぞれ当該イ又はロに定める面積の合計は,敷地面積(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十三条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては,敷地面積に当該最高限度を乗じて得た面積)に十分の一を乗じて得た面積以下とすること。
イ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から突き出た距離が水平距離1m以上5m未満の軒等 その端と当該中心線の間の部分の水平投影面積
ロ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離5m以上突き出た軒等 その端とその端から第二に定める距離後退した線の間の部分の水平投影面積
第二 令第2条第1項第二号に規定する軒等の端からの後退距離は,水平距離五メートルとする。
告示143号 留意 緩和を受ける為の条件
・ 用途と軒等
工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等であること
・
軒等
軒,ひさし,はね出し縁等
軒等が2面にわたる場合の考え方
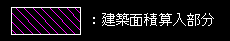
| 例 1 |
例 2 |
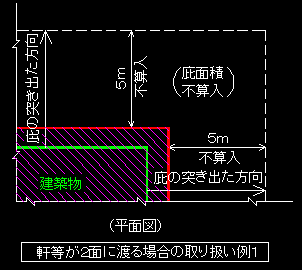
|
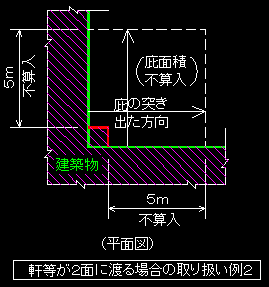
|
用途による緩和適用の制限
例).物品販売業を営む店舗の一部が倉庫の場合
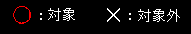
例1 . 庇の一部を常時保管するために利用(物品保管庫等)する場合には,その全部で緩和の対象から外れてしまう例
例2 . 庇の一部に上階がある場合には,その全部で緩和の対象から外れてしまう例
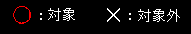
|
例 1
|
例 2 |
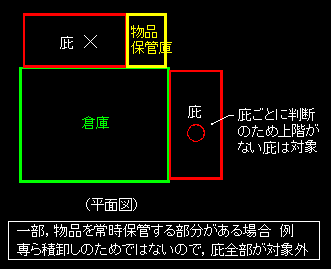
|
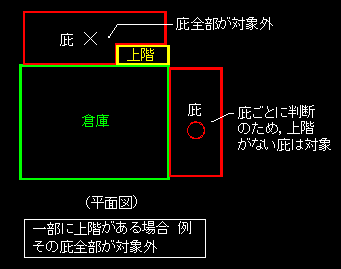
|
敷地面積の1/10を超えた部分,他の部分の取り扱い / 確認申請書3面の【10.
建築面積】記載欄について
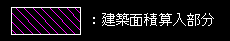
注意1).
あくまでも今回の緩和の対象は,『建ぺい率の計算』に係る部分のみで,緩和は,『建ぺい率の計算』しか除かれないということ。
他の建築基準法の建築面積に係る計算では,通常通り1mの緩和で計算をしなければならない。
建築面積が登場する,令114条3項(小屋裏の隔壁)は今回の計算方法を適用しない。
|
注意2).
※
建築面積は,今回の緩和を適用する場合と,通常の場合と,2つ計算をする必要があります。
確認申請書3面の【10.
建築面積】ので記載欄について
【10. 建築面積】 (申請部分)
(申請以外の部分) (合計 )
【イ. 建築物全体】 ( a )
( ) ( A )
【ロ. 建蔽率の算定の基礎となる建築面積】
( a )
( ) ( A )
【ハ. 建蔽率】 %
イ.欄の
a ,A
には通常の建築面積を記載。
ロ.欄の
a ,A
にはイ.欄の建築面積をそのまま転記。
(※倉庫等の「特例軒等」を設ける場合は別算定の面積を記入。)
ハ.欄にはイ.
ロ.の建築面積を敷地面積で除した数値を記入。
(※倉庫等の「特例軒等」を設ける場合は別算定の面積を記入。)
(「特例軒等」とは施行令第2条第1項第2号に既定する軒等のこと。)
参考).旧3面の【10.
建築面積】
【10. 建築面積】
【イ. 建築面積】
【ロ. 建ぺい率】
【ハ. 建蔽率】
|
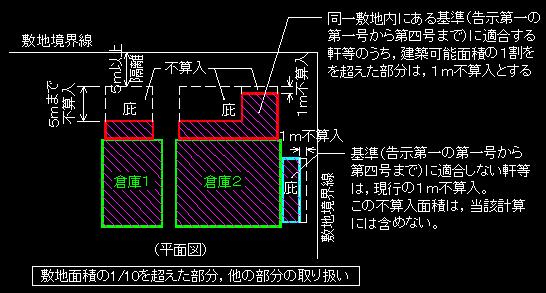
|
庇下の部分の容積対象外床面積の取り扱いについて
庇下の部分は車庫と同じ扱いになるので,庇の面積は,延べ床面積の1/5を上限に容積率の算定面積(延べ床面積)から除外されることになります。但し,庇下であってもプラットホームなど車両が駐車できないスペースについては,車庫とみなされないので,その部分の庇の面積は除外の対象にならないので留意。
駐車場/駐輪場の取り扱いは以下となっています。
駐車場や駐輪場は,該当部分を含めた全体の延床面積に対して1/5の範囲内なら,容積率の算入対象外です。1/5を超えた場合,該当部分のみ,算入対象として計算します。
玄関,ポーチ等の算定例 (2002K)
(平面図)
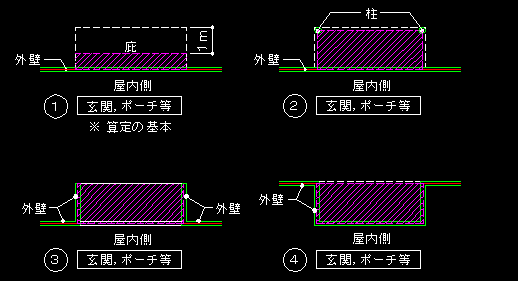
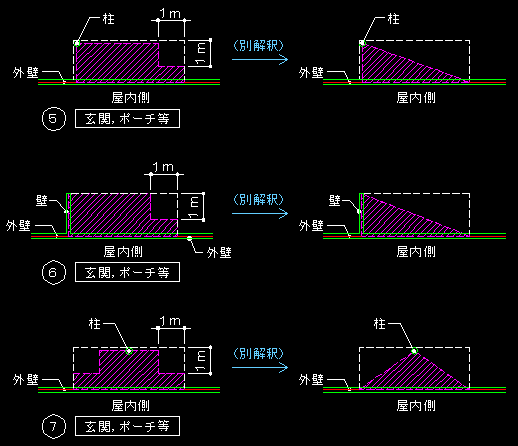
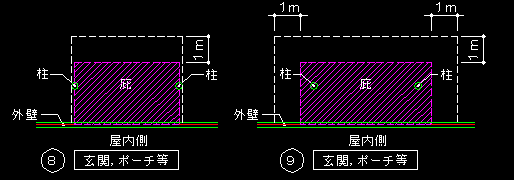
庇等の算定例 (2002K)
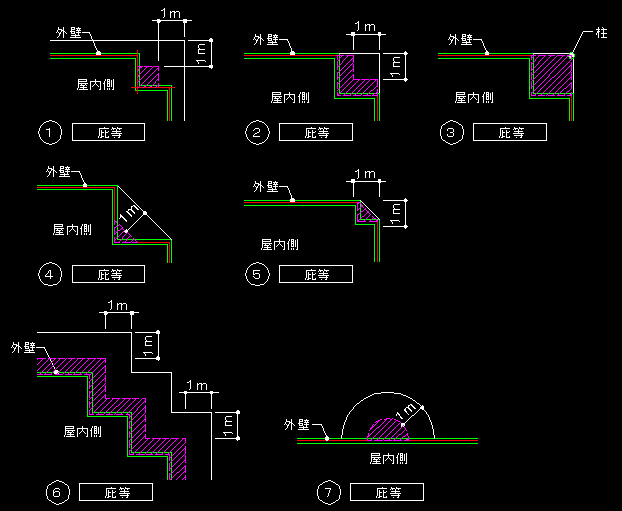
(平面図)
吹きさらしの廊下,バルコニー等の算定例1 (1995K)
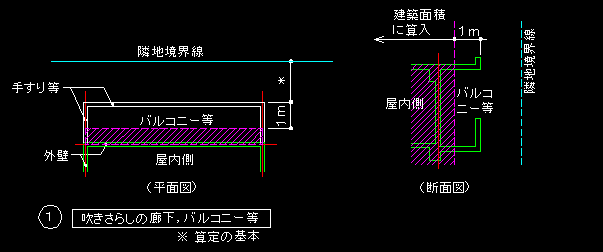
注意 :
手すり等の構造によっては,1m部分も算入される場合もある。
参考※
:
京都市の場合,隣地境界線から1m以上はなれていることが条件。1m以内の場合は全て含まれる。
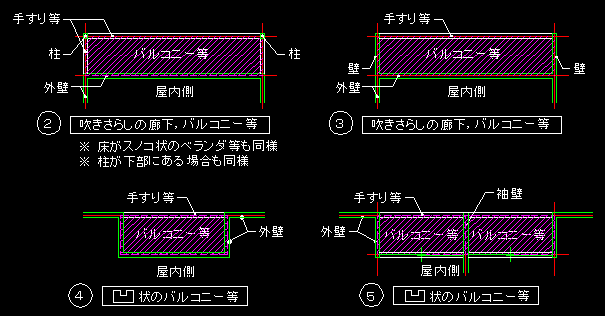
(平面図)
吹きさらしのバルコニー等の算定例2 (2009JCBAより)
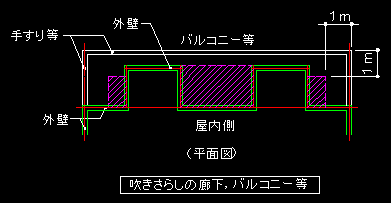
階数が2以上のベランダの算定例 (2008横浜市pdfより)
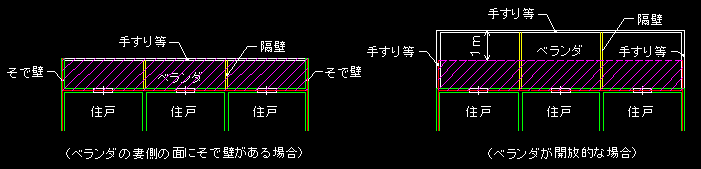
(平面図)
屋外階段の算定例 (2009JCBA及び2002K)
(平面図)
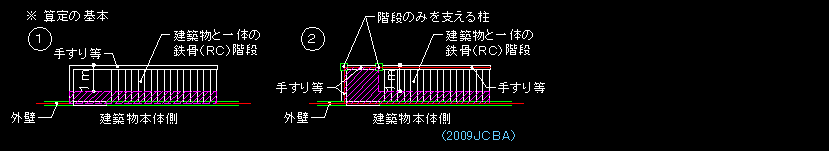
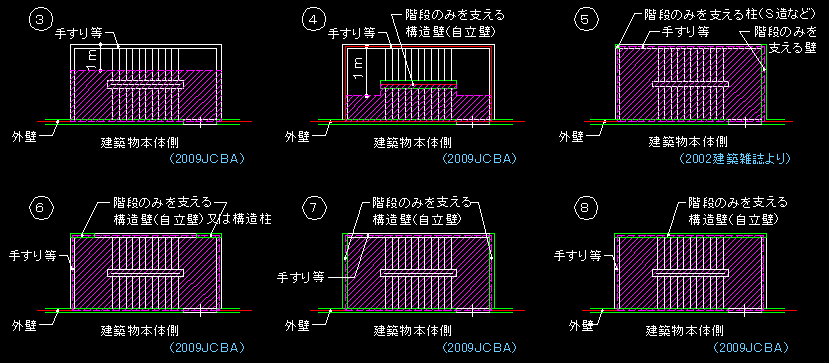
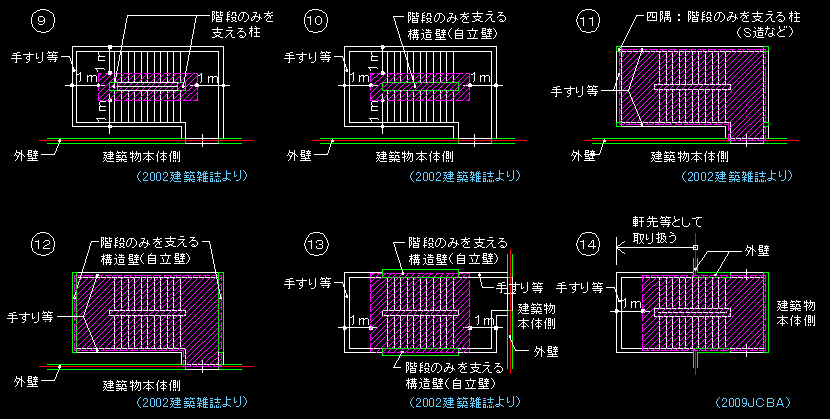
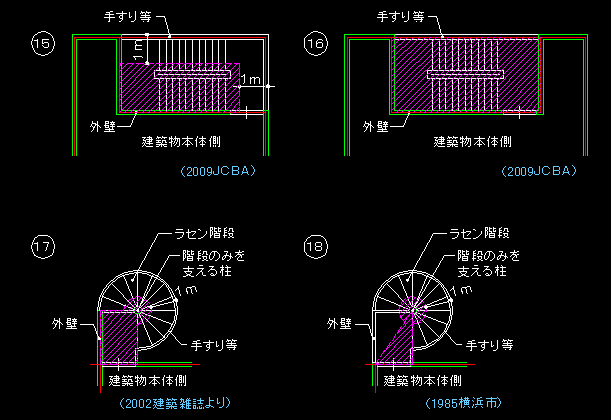
■ 005 高い開放性を有する建築物の建築面積の緩和例 (令2条1項二号,告示第1437号)
令2条1項二号の高い開放性を有すると認めて指定する構造
平成4年の法改正により,令2条1項二号の「建築面積」の定義のなかに,ただし書が追加された。
建設大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造物等については,その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は,建築面積に算入しないこととされた。
平成5年建設省告示第1437号
高い開放性を有すると認められる構造の条件
1.外壁を有しない部分が連続して4m以上あること。
2.柱の間隔が2m以上であること。
3.天井の高さが2.1m以上であること。
4.地階を除く階数が一であること。
注意).床面積は通常の算定万法により算定されるので注意すること。
 :以下,建築面積に算入される部分
:以下,建築面積に算入される部分
高い開放性を有する建築物の算定例
(玄関アプローチ等) (2006建H)
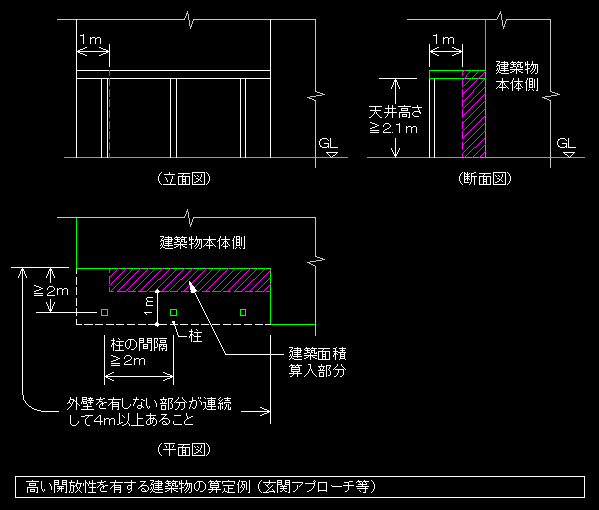
高い開放性を有する玄関,ポーチ等 例1,2 (2008横浜市pdfより)
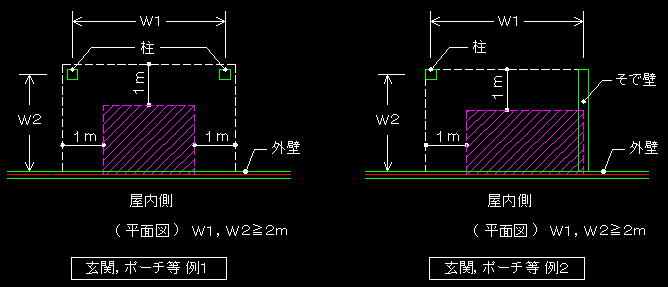
高い開放性を有する既製のカーポート等の算定例 (1995K)
四隅に柱がある場合
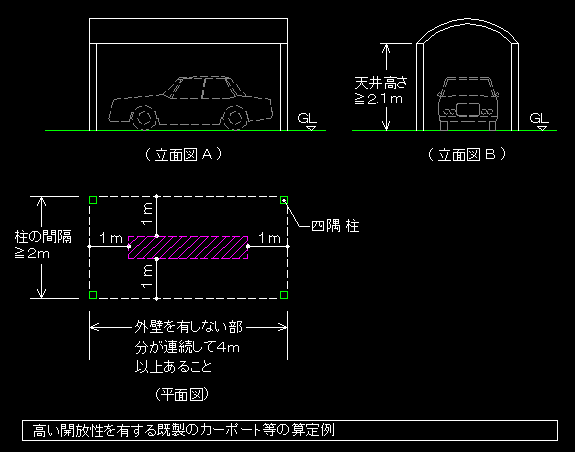
高い開放性を有する住宅等のカーポート 例1 (2008横浜市pdfより)
片側に柱がある片流れ屋根の場合(W≧2m)
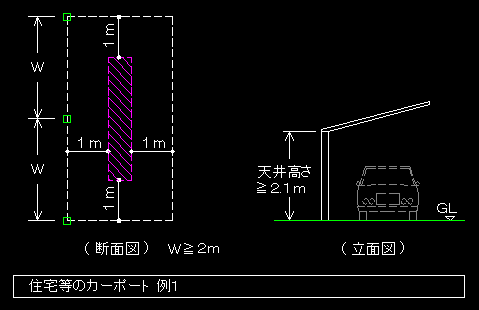
高い開放性を有する住宅等のカーポート 例2 (2008横浜市pdfより)
片側に柱がある片流れ屋根の場合(W<2m)
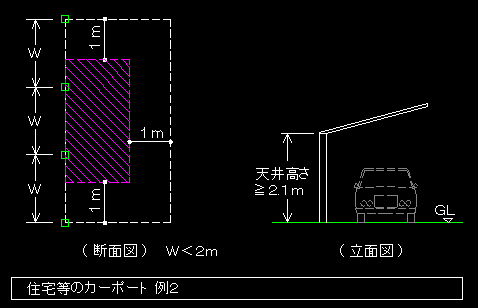
高い開放性を有する住宅等のカーポート 例3 (2008横浜市pdfより)
四隅に壁がある場合
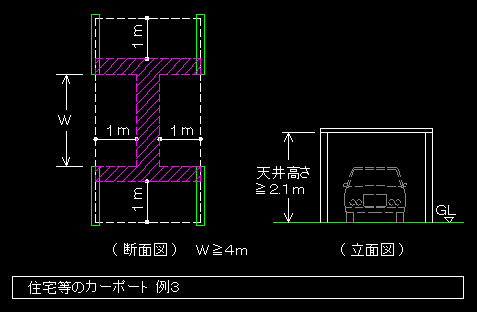
一部高い開放性を有する住宅等のカーポート 例4 (2008横浜市pdfより)
両側に柱がある片流れ屋根の場合
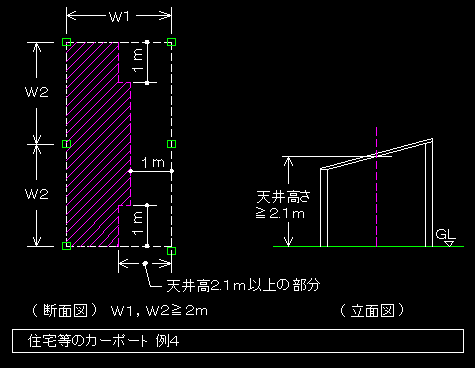
高い開放性を有する一層二段自走式駐車場の算定例 (2002K)
告示第1437号関連解釈
注意.二層三段自走式駐車場の場合は全て建築面積に算入される。
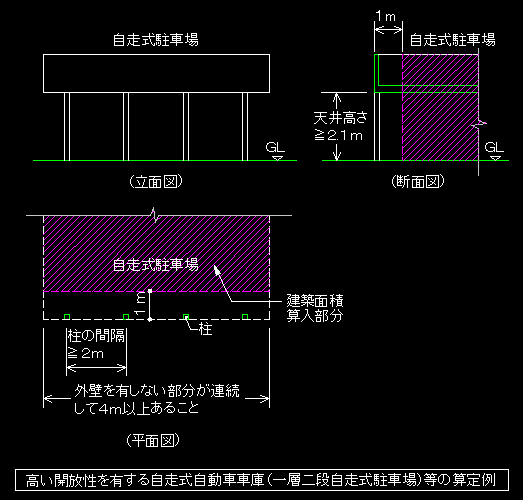
平成3年6月10日建設省住指発第210号
:一層二段自走式駐車場の建築面積の算定方法等について
(1層2段の立体自動車車庫については,法第84条の2の規定により「簡易な構造の建築物」として取り扱うことができる。)
1層2段の自走式自動車車庫は,平成4年の法改正等により建築物として取り扱うことが明確になった。
以下の例の①傾斜路の場合には,建築面積に算入しない。 (1995K)
②の外壁又はこれに変わる柱より外側に出ているはね出し部分の場合には,「軒,庇等」の扱いとし,幅1mを限度として建築面積に算入しない。
尚,はね出しでなくても,高い開放性を有する認めて指定する構造(H5建告第1437号示)に該当する場合は,その端から水平距離1m以内の部分は建築面積に算入しない。
注意.二層三段自走式駐車場の場合は全て建築面積に算入される。
① 傾斜路
・
屋上へ上がるための傾斜路の部分で,床版がエキスパンドメタル等の開放性のある部材でつくられ,その上部,下部に車を置かない。
・
その上部に屋根を設けず,かつ,その下部を外壁等で囲わない。
② はね出し部分(2階が1階の柱より外側にはね出している部分)
・ はね出し部分の下部の外側に壁,おおいがない。
・ はね出し部分の床版がエキスパンドメタル等の開放性のある部材でつくられている。
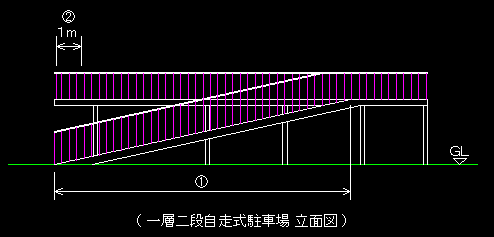
■ 006 スノコ状のバルコニーは建築面積算定の対象となるか (雑則関係
法第92条,令第2条第1項第2号)
※ はじめに
近年のスノコ状バルコニーの取り扱いについて (T建築事務所Webサイトからの情報の抜粋(+追記)です。転記,ご容赦願います。)
そもそも「雨が落ちてくるものは屋根ではない」という概念規定についての論議が長く続いていて,取り扱いは各所窓口で見解が分かれます。東京都でも区によって異なります。
概ね,基準は厳しくなっています。背景には法の網目をくぐる様な運用,築造後の形態変更等を防ぐ意図があります。
区名は明らかではありませんが,2013年(平成25年)以降に,東京都内特定行政庁の建築審査会において,そもそもスノコ状バルコニーは建築物であり,建築面積の算定の対象となる旨の裁決(22板建審請第2号審査請求事件)がありました。指定確認検査機関の建築確認申請処分が取消しになつた事件です。従来の緩和解釈が却下されたわけです。
現在はスノコ状バルコニー,グレーチングバルコニー等の取扱いは,建築基準法第2条第1号の土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するものだけでなく「これに類する構造のもの」も建築物に含まれるとされています。
これによってスノコ状バルコニー等は建築面積に算定されるとする特定行政庁が多くなっています。まったく認めない特別区や建築主事もいるので計画の時点で確認が必要です。
許容建築面積いっぱいだと,スノコ状バルコニーの取扱い次第で建築面積が変わり,前述のように審査請求の裁決で指定確認検査機関の建築確認申請処分が取消しになったこともあります。
一戸建ての住宅等
東京都,神奈川県の取り扱い例
以下,
解説・解説図共,東京都の世田谷区の取り扱い基準です。(2018年(平成30年)6月改正) (世田谷区ホームページ
最終更新日 令和2年4月1日 より)
基準が変わっている可能性があるのでご注意。
|
例.一戸建ての住宅等 (世田谷区)
|
|
原則,スノコ状であっても「屋根に類する構造」であるため,建築面積算定の対象となる。但し,専用住宅もしくは兼用住宅に設けるもので次の要件を全て満たすスノコ状のバルコニーに限り,建築面積に算入しないものとする。
|
「認められる例」
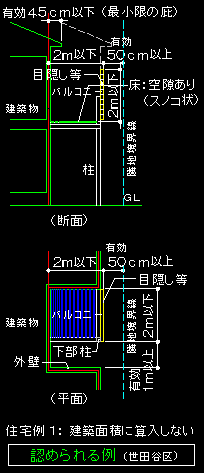 |
●
左図 : 建築面積に算入しない
各要件は図の通りですが,その他まとめると以下です。
1.適当な隙間(目透かし)があること。
2.奥行きはバルコニーの端(手すり,壁,目隠し,下階の柱がある場合はその端)から
外壁の柱芯まで2メートル以内であること。
3.バルコニーの下部は外気に有効に開放された,壁を有しない部分が周長の1/2以上で
あること。
4.バルコニー(手すり,壁,目隠し,下階の柱がある場合はその端)は隣地境界線から有効50センチメートル以上かつ建物間(梁等も含む)で有効1メートルの距離を有すること。
5.手すり,目隠しの高さはバルコニー床から2メートル以内であること。
6.バルコニー上部及び下部は,雨仕舞いに必要な最小限(45センチメートル以下)の
庇・軒先のみであること。
7.面積は建築面積の10分の1以下であること。(建築物が複数ある場合は,一の建築物の建築面積とする。)
なお,上記の要件を満たさない場合であっても,国土交通大臣が高い開放性を有する認めて指定する構造(H5建告示第1437号)に適合するものは,その算定方法により外端から1m後退した線で囲まれた部分を算入する。
注意).床面積は通常の算定万法により算定されるので注意すること。建築面積に算入される場合は床面積にも算入されるということ。
|
|
「認められない例」
: 建築面積に算入される
以下の例での各要件は図の通りです。
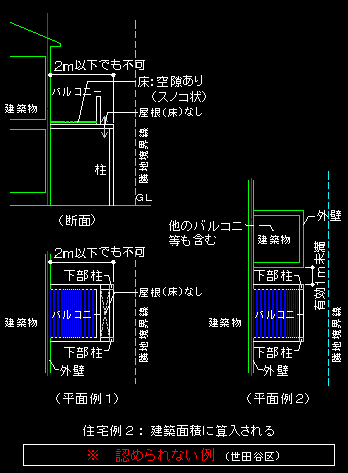 |
以下,参考). (T建築事務所Webサイトからの情報の抜粋(+追記)です。転記,ご容赦願います。)
●
以下,その他の東京都内の取り扱いです。2013年時点の情報です。基準が変わっている可能性があるのでご注意。
※ 東京都内で統一的な取り扱い基準があるわけではなく,まったく認めない特別区や建築主事もいるので計画の時点で確認が必要です。
各区の取り扱い概略
広さ(15㎡以下など) / 幅(4m以下など) / 手すり /
目隠し等の高さ / バルコニー下部の用途制限又は使用不可 /
庇は不可 / 取扱いは平成5年建設省告示第1437号(解釈には専門知識が必要です)による
/ 柱があれば建築面積算入(壁はもちろん) /
隣地からの延焼ライン内は不燃仕上げ又は外壁仕上げと同等とする
/ ……他
|
東京都各区の取り扱い (以下のその他の区についてはご確認ください。)
|
【品川区】
1.床は十分開放性のあるグレーチング・すのこ状であること。
2.建築物の外壁面等からの出幅が最も大きいところが有効で2m以下であること。
3.隣地境界線からバルコニーの先端までの有効離れ寸法が50cm以上であること。
4.バルコニーの周囲が袖壁等で囲まれていないこと。(一般的な立ち上がりの手すりで縦桟のもの(ピッチ10cm程度)は可)
5.バルコニーは1層のみであること。(雨がかりを防ぐ程度の局所的な庇(霧除け等)は可)
6.バルコニーがはね出しでない場合,バルコニー下部が柱のみで支えられ,簡易的なものであること。
7.バルコニー下部に,駐車場,ごみ置場等の用途が発生しないこと。発生の場合はグレーチング・すのこ状としてはみなさない。
※
以上の取扱いは,品川区において建築確認を受け付ける場合の取扱いです。指定確認検査機関に建築確認を申請する場合は,申請先の機関に要確認。
|
【練馬区】
1.戸建住宅に限る
2.庇がない事
3.15㎡未満であること
|
【北区】
1.取扱は
H5建設省告示第1437号による・・・・・基本的に柱があれば床面積・建築面積に算入
2.ただし個別に相談
|
【江戸川区】
江戸川区は,グレーチング状バルコニーについては,法第2条第1項第一号中の「屋根及び柱・・・(これに類する構造のものを含む)」により屋根として取扱っている。
ただし,専用住宅等におけるグレーチング状バルコニーについては,条件を満足したものに限り,柱があった場合でも先端から1mまで建築面積に算入しないものとしている。
なお,グレーチング状と通常のもの(開放性のないもの)が連続となっている場合は,一体のバルコニーとして建築面積に算入している。
1.バルコニー下部に用途がない
2.バルコニー先端から隣地境界線までの距離は50cm以上確保している
3.バルコニー上部に設ける庇は,出が30cm程度(樋を含む)である
4.柱は,バルコニーのみを支えるものであり,かつ不燃材料でつくられている
5.バルコニーは,建築物外壁面のうち1面のみの設置であり,かつ長さは当該外壁面長の1/2以下である
|
【新宿区】
1.スノコ状であっても通常の床があるバルコニーと同じ。柱があれば建築面積算入。
|
【渋谷区】
2.グレーチング等は問わず,柱つきバルコニーは建築面積算入を指導
|
【目黒区】
1.奥行き2m,幅4mまで不算入
2.バルコニーの下部の用途は問わない。下部が駐車場であれば床面積に算入。
3.二層グレーチングバルコニーは建築面積算入
4.上部庇は出が50cm程度なら不算入
5.延焼ラインは不燃仕上げ又は外壁仕上げと同等とする。
6.グレーチングバルコニーは一層まで
7.支える壁は2面まで
8.手すりの高さは1.3m以下
|
【杉並区】
1.柱の有無,隣地との離れに関わらず不算入
2.概ね奥行き2m,幅4mまで不算入
3.バルコニーを支える柱は良いが壁は不可
|
|
●
以下,神奈川県内の取り扱いです。基準が変わっている可能性があるのでご注意。
概ねは前述の「近年のスノコ状バルコニーの取り扱いについて」に準じています。
下記は2013年1月の情報です(横浜市,藤沢市を除く)。現在は取扱いが変わっている特定行政庁もあるのでご注意。
|
神奈川県各市の取り扱い (以下のその他の市についてはご確認ください。) |
【横浜市】
以下,2023年(令和5年)の取扱い情報です。(横浜市のサイトより)
横浜市建築基準法取扱基準集(令和5年5月版)
令和5年5月26日より令和5年5月版の運用を開始しました。
※横浜市建築基準条例及び横浜市建築基準法施行細則の一部改正に伴う所要の改正を行いました。
第1章 総則(PDF:543KB)
法第2条 用語の定義
1-2 すのこ状バルコニー等の取扱い
すのこ状、グレーチング状バルコニーその他これらに類する構造のものについては、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」(屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。))に該当するものとし、同法を適用する。
<解説>
すのこ状やグレーチング状等の孔やすき間を有する構造の工作物についても「一層二段の自走式自動車車庫に関する建築基準法上の取扱いについて(平成4年4月
16 日住指発 142
号)」のとおり、「建築物」(屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。))に該当し、孔やすき間のない通常のバルコニー等と同様に扱うことを示した。
<施行日>
この取扱いは、平成30年3月1日から施行する。
なお、この取扱いは、施行日以降に建築(新築・増築・改築・移転)工事に着手したものに適用するものとし、施行日より前に着手したものについては、この限りでない。
(建建企第351号 平成29年9月1日)
(※
その他要件の詳細は,お調べ願います。)
|
【川崎市】
1.基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
2.個別に判断・・・・・下部に庇があり雨が落ちない場合,下部に用途がある場合建築面積算入
|
【藤沢市】
※
2016年に取扱いを変更して建築面積算定対象としています。【2021.02.18】
(※
要件の詳細は,お調べ願います。)
|
【茅ヶ崎市】
1.建築面積不算入
2.ただし屋内的な用途に利用する場合は,建築面積算入かつ屋根としての性能を満たす事
|
【相模原市】
1.基本的にはスノコ状バルコニーは建築面積不算入
2.個別に判断・・・・・下部に庇があり雨が落ちない場合,下部に用途がある場合建築面積算入
|
参考1).許可なし増築できるのは何㎡まで
以下を参照してください。様々な注意,…他,記してあります。
左のフレーム(INDEX)の「建築確認制度,他」
→ 「■ 010 許可なしで増築できるのは何㎡まで 」
参考2).民法234条の「建物を築造するには,境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」
について
以下を参照してください。特例・参考・現実論,…他,記してあります。
左のフレーム(INDEX)の「建築確認制度,他」
→ 「■ 011 民法234条の「建物を築造するには,境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」
について
以下,上記のバルコニー関連抜粋です。
・ 50cmとは建物の外壁から隣地境界線までの最短距離であって,屋根や軒からの距離ではありません。
・
50cm 以上の離れは出窓やバルコニーなどについても適用されます。
バルコニーについては, 手すり壁等の構造及び
形態により外壁と同様にみなされる場合があります。
「目次」へ戻る