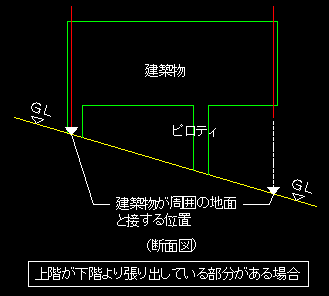
ピロティーのように上階が下階より張り出している部分(屋根又はひさしを除く)については,上階の建築物の部分を地表面に投影し,投影された外壁等の中心線を結んだ位置を「建築物が周囲の地面と接する位置」とみなす。
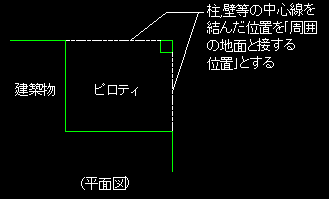
「建築基準法及び関連法解説」
全ページ
→
遠山英雄都市建築設計事務所 - HOMEへ
__________________________________________________
地盤面・階・建築物の高さ・天井の高さ
「 目 次
」
■ 001 地盤面/平均地盤面/地面
A.地盤面
(令2条第1項第6号,令2条第2項)
B.平均地盤面(法別表第4欄外,令135条の12)
C.地面
(令2条,法別表第4欄外)
地盤面の取扱い(法第92条,令第2条第2項)
1.上階が下階より張り出している部分がある場合
地面と接する位置にピロティ(,屋外階段等)がある場合
2.屋外階段,廊下,バルコニー等がある場合
(横浜市pdf./2009JCBAより
)
からぼり等がある場合の原則的な地盤面のとり方
斜面地における大規模な擁壁とともに設けられるからぼり等がある場合の地盤面のとり方
地面と接する位置の高低差が3mを超える場合の地盤面を算定する領域の設定の方法
(令2条第2項) (2008横浜市pdfより)
垂直な地盤面に建築物の一部が接する場合の地盤面のとり方
(2008横浜市pdfより)
建築物の形状により3mごとに分けることが不合理な場合
例1,2 (2008横浜市pdfより)
領域の設定
(2008横浜市pdfより)
■ 002 地階
令1条第2号に規定する用語「地階」の意義
(1) 床が地盤面下にある階
(2)
床面から地盤面までの高さ
(3) その階の天井の高さ
(4) 3分の1以上
地階の算定方法
床が地盤面下にあるかの判定(神奈川県下の行政庁の判定方法) (横浜市pdf./2009JCBA/1995K
)
■ 003 天井の高さ
天井の平均の高さ他
(排煙口設置における天井の高さ →
「排煙」参照)
■ 004 屋上部分の取扱い
斜線制限に関する屋上部分の適用関係
● 「建築物の高さ」について
(1)
屋上部分の取扱い基本 (令2条1項六号ロ等)
(2) 屋上部分が複数存在する場合
高さに算入されない
「その他これらに類する建築物の屋上部分」に該当するもの
「棟飾,防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物」に該当するもの(令2条第1項第6号ハ)
高さの算定一覧表
● 「階数」について
(令第2条第八号)
(3)傾斜地等において,建築物の部分により高さが異なっている場合
(4)傾斜屋根の屋上部分の高さ(h)は,原則としてその最下端から算定する
屋上部分とみなされない例
(5) 高さに算入しない屋上部分と算入される屋上部分
屋上階・地階の取り扱い
(階数の算定(令2条第1項第ハ号 関係))
屋上部分の「軒の高さ」の取扱い
(令2条1項七号)
道路斜線,日影規制が適用されない広告塔等の取り扱いについて
(法第88条1項)
一般階の軒の高さ
(令2条第1項第七号)
木造片流れ屋根の軒の高さ1,2
■ 005 小屋裏物置(天井裏,床下収納)などの階(数)の取り扱い
小屋裏物置(天井裏,床下収納)などの階(数)の取り扱い例
(平成12年6月1日住指発682号(令第2条第1項8号))
■ 006 避難階の取り扱い例
直通階段の設置(令第120条)
【避難施設等の範囲】(令第13条)
避難施設等
避難階
避難階の取り扱い例
(避難階:令13第1項第一号 関係)
避難階が複数ある例 1,2
「直通階段」ではない例
避難階の地上部分の要件
避難階に準じた性能を有する階の例
避難規定上の「階」と「階数」の取り扱い例
避難規定上別の階とみなす取り扱い例
吹抜けがある例/ツインビル等の例
■ 007 耐火構造における階の算定
耐火構造における階の算定
耐火性能に関する技術的基準(令107条)
・
吹抜き部分の取扱い
・
エキスパンション・ジョイント等により,構造的に分離された低層建築物の部分の取扱い
・
エキスパンション・ジョイントなしで一体の建築物の低層部分と高層部分の取扱い
■ 008 ラック式倉庫(立体自動倉庫),多層式倉庫 (2009JCBAより
)
ラック式倉庫(立体自動倉庫〉の階数及び床面積の合計の算定
■ 001 地盤面/平均地盤面/地面 (2007W)
用語の定義
A.地盤面
(令2条第1項第6号,令2条第2項)
法56条(高さ制限・天空率)を適用する際の高さの基準。傾斜地での3mを超える場合については令2条第2項(*)で定義しています。下記B.の『平均地盤面』とは別に定義されています。
(*令2条第2項
:傾斜地の建築物の接地高さが3mを越える場合は3m以内ごとに平均の高さを設け,地盤面ごとの建築物の部分の高さの基準とする。)
B.平均地盤面
(法別表第4欄外,令135条の12)
法56条の2(日影規制)を適用する際の高さの基準。上記A.の『地盤面』とは別に定義されています。
C.地面
(令2条,法別表第4欄外)
実際の敷地の形状,起伏面。前記A.の『地盤面』やB.の『平均地盤面』を求める際に必要です。
注意).
建築物の高さの基準を,一般に『平均地盤面』などと呼んでいるが,正しくは『平均地盤面』とは法56条の2(法別表第4欄外)に用いられる用語で,法56条内では単に『地盤面』と呼んでいる。
地盤面の取扱い(法第92条,令第2条第2項)
基本
建築物本体の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の中心線を結んだ位置を「建築物が周囲の地面と接する位置」とみなし,地盤面を算定する。
平均地盤の周長算定において,計算の便宜上外壁等の中心線で計算を行うこととし,その接する高さは建築物本体が実際に接する高さとする。
なお,周長算定を実際の外壁等の外側の面において算定する方が妥当と思われる場合はこの限りではない。この場合,「中心線」とあるのは,「外側の面」と読み替えるものとする。(横浜市も同様)
1.上階が下階より張り出している部分がある場合/地面と接する位置にピロティ(,屋外階段等)がある場合
| 1.上階が下階より張り出している部分がある場合 (横浜市pdf./2009JCBAより ) | 地面と接する位置にピロティ(,屋外階段等)がある場合 | |
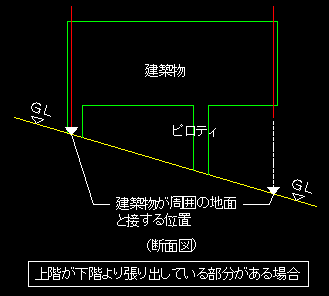 |
ピロティーのように上階が下階より張り出している部分(屋根又はひさしを除く)については,上階の建築物の部分を地表面に投影し,投影された外壁等の中心線を結んだ位置を「建築物が周囲の地面と接する位置」とみなす。 |
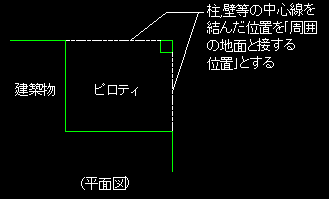 |
2.屋外階段,廊下,バルコニー等がある場合
(横浜市pdf./2009JCBAより
)
屋外階段,廊下,バルコニー等の部分にあっては,これらを地表面に水平投影し,水平投影された手摺り壁等の中心線を結んだ位置を「建築物が周囲の地面と接する位置」とみなす。
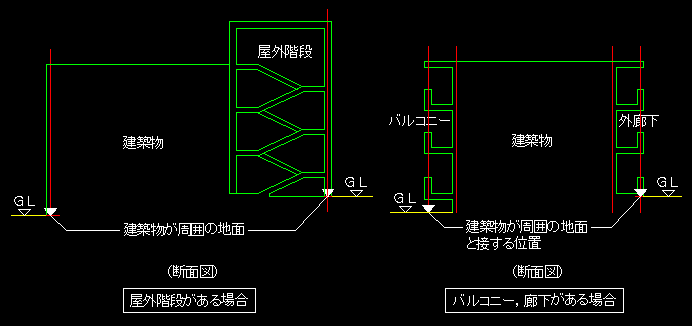
からぼり等がある場合の原則的な地盤面のとり方
(下図左)
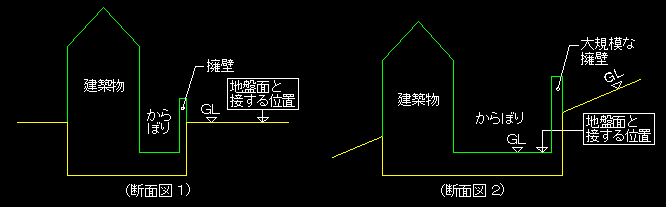
斜面地における大規模な擁壁とともに設けられるからぼり等がある場合の地盤面のとり方
(上図右)
(横浜市基準法取扱い)
からぼり等がある場合の「周囲の位置と接する位置の高さ」については,以下による。
からぼり :
通風,換気等の目的で地面下に設けられた建築物本体と周壁(周囲の土を押さえている壁)の間の空間を言う。
(図省略)
盛土がある場合
(図省略)
地面と接する位置の高低差が3mを超える場合
(令2条第2項)
地面と接する位置の高低差が3mを超える場合の地盤面を算定する領域の設定の方法
(下図左) (2008横浜市pdfより)
地面と接する位置の最低点又は最高点から3mごとに切り分け,領域A,B,Cを設定する。領域を設定後,3m以内ごとの平均の高さにおける水平地盤面(平均地盤面)ZA,ZB,ZCを算定し,高さを出す。
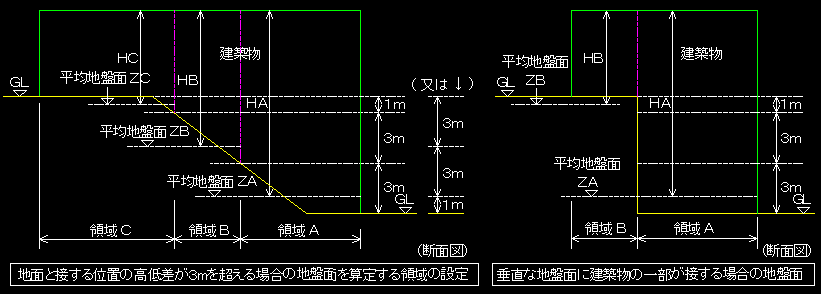
垂直な地盤面に建築物の一部が接する場合の地盤面のとり方
(上図右) (2008横浜市pdfより)
建築物を低い地盤面に接する部分と高い地盤面に接する部分とに切り分けて,領域A,Bを設定し,各領域ごとに平均の高さを算定。
領域A
: 高さHA
領域B
: 高さHB
建築物の形状により3mごとに分けることが不合理な場合
例1 (下図左) (2008横浜市pdfより)
計画的に造成されたひな壇状の土地に建築する建築物で,各部分ごとに領域を設定した建築物
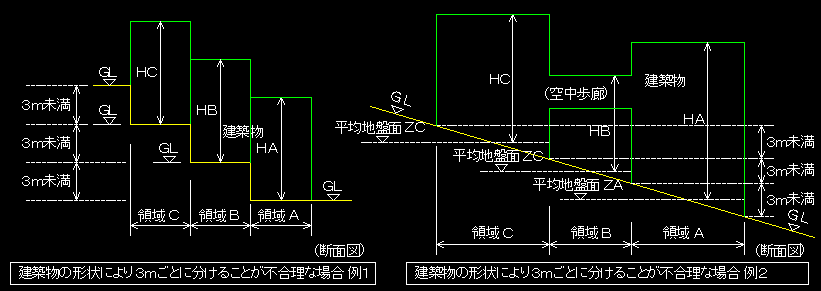
建築物の形状により3mごとに分けることが不合理な場合
例2 (上図右) (2008横浜市pdfより)
低い地盤と高い地盤に建築された建築物の部分で,当該部分を空中歩廊等で接続し,各部分ごとに領域を設定した建築物
領域の設定 (2008横浜市pdfより)
各領域の境界線は直線 ( ----
) とする。
高低差3mを超える場合 例1 (下図左)
領域境界線 : E点とF点を直線で結ぶ
各領域の周長
領域A : A-B-F-E-A
領域B : E-F-D-C-E
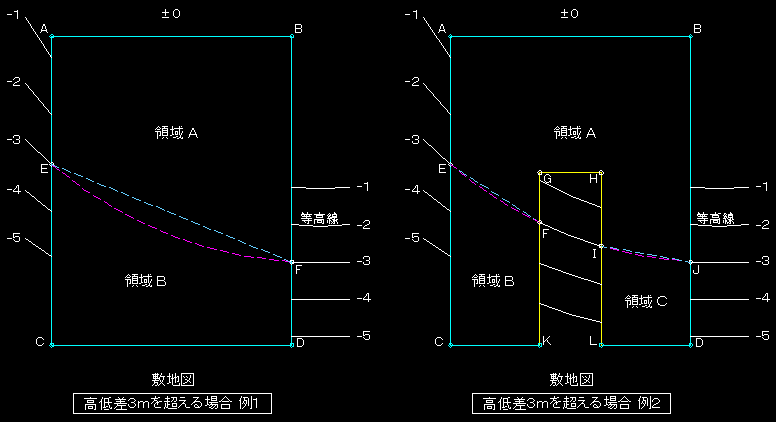
高低差3mを超える場合 例2 (上図右)
領域境界線 : E点とF点及びⅠ点とJ点を直線で結ぶ
各領域の周長
領域A : A-B-J-I-H-G-F-E-A
領域B : E-F-K-C-E
領域C : I-J-D-L-I
その他日影規制及び天空率制度における地盤面の取扱いについては別説明参照。
■ 002 地階
令1条第2号に規定する用語「地階」の意義
基本
:
地階の判定は,同一階で判定するものとし,部分的な判定は行わない。
(1) 床が地盤面下にある階
建築物の当該階の部分における床の一部が地盤面下にある階のうち,当該床の周長の過半が地盤より低い位置にある階とする。
(2)
床面から地盤面までの高さ
当該階における最も高い位置にある床面から,建築物の当該階の部分が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面(その接する位置の高低差が3mを超える場合においても,その高低差の平均の高さにおける水平面とする)までの高さとする。
注意).ここでいう「地盤面」は,令2条第2項に規定する地盤面とは異なり,ある階において建築物と接する地面の高低差が3mを超える場合であっても,原則として一の地盤面を設定することとなる。なお,法52条第4項に規定する地盤面(「・・・高低差3m以内ごとの平均の高さにおける・・・」)又は法別表第4(は)欄の平均地盤面とは異なる。
(3) その階の天井の高さ
当該階における最も高い位置にある床面から測り,当該階における最も高い位置にある天井までの高さとする。
注意).階ごとに1つとして定義。
(4) 3分の1以上
当該階の最も高い位置の床及び天井の1/3以上(h>H/3)とする。
地階の算定方法 (2006H)
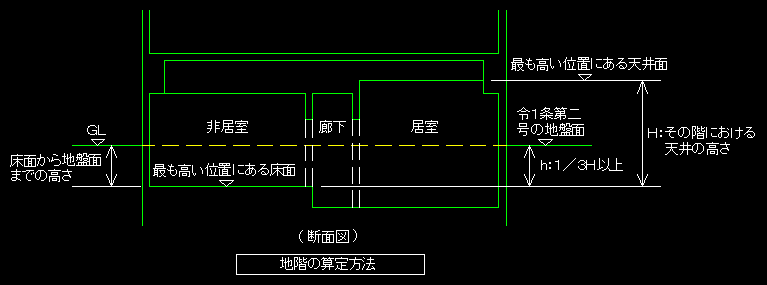
床が地盤面下にあるかの判定(神奈川県下の行政庁の判定方法) (横浜市pdf./2009JCBA/1995K
)
「地盤面」に関する取扱い例として,神奈川県下の行政庁が採用している令1条二号の「地階」の判定方法
(下図)。
ポイントは,
① 地盤面(*)下の床が複数ある場合は,それぞれ階ごとに判定する。
(*
ここでいう「地盤面」は,令2条第2項に規定する地盤面,法52条第4項に規定する地盤面又は法別表第4(は)欄の平均地盤面とは異なる。)
②
同一階では,部分ごとの判定は行わない。
の2点である。
メリットとしては,常識的には地階とはいえない階だが,一般的な方法で算定すると「地階」とせざるを得ないものも,この方法で算定すると「地階」にならず,一般的な「地階」の概念に近づけることができるという点である。
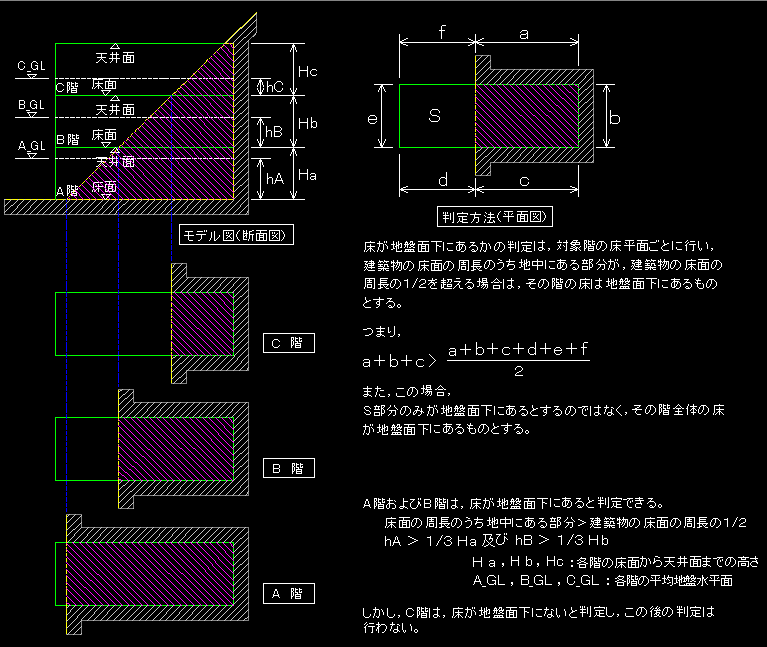
■ 003 天井の高さ (1995K
)
● 基本
天井の平均の高さ =
室の容積/室の面積
注意).地下街の地下道の天井の高さでは,平均をとらず最低部分の高さをとるので注意。
● 室の断面が一定の場合
天井の平均の高さ = 室の断面積/室の幅
● 天井の高さが極端に異なる場合
2つの天井高さH1及びH2があると考えた方が適切である。
● 特殊の天井(格子天井等)の場合(下図左)
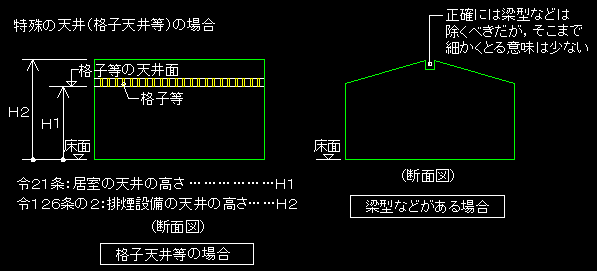
● 梁型などがある場合
(上図右)
(その他排煙口設置における天井の高さ
→ 「排煙」参照)
■ 004 屋上部分の取扱い
斜線制限に関する屋上部分の適用関係
● 「建築物の高さ」について
条文 令第2条第六号のロ
ロ 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項及び法第58条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係わる部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。
(高さについては,階段室は明確に謳っている。)
「令2条1項六号ロ」等の要約
建築物の屋上部分については,避雷設備,北側斜線,高度地区の北側斜線を除き,「階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分」の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合,その屋上部分の高さが12m(絶対高さの制限(第1種
・第2種低層住居専用地域)(*1)及び,日影規制の場合は5m(*2))までは「建築物の高さ」に算入しない。
*1
絶対高さの制限
法55条第1,2項/法別表第4(ろ)欄2の項,3の項及び4の項のロ
*2
日影規制
法56条の2第4項及び法別表第4
(1) 屋上部分の取扱い基本 (下図左) (1995K)
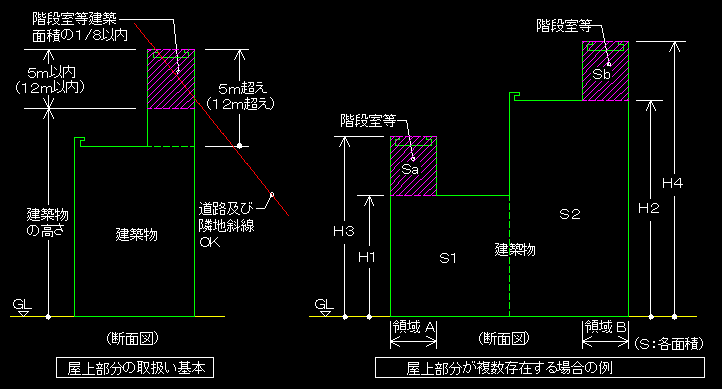
(2) 屋上部分が複数存在する場合
(上図右) (1995K)(横浜市も同様)
屋上面が複数存在する場合は,個々の屋上面の屋上部分の水平投影面積の合計と,全体の建築面積との比較により判断する。
(Sa+Sb)/(S1+S2)≦1/8のとき,
領域Aの高さ : H1, 領域Bの高さ : H2 となる。
Sa/S1≦1/8かつSb/S2≦1/8である必要は必ずしもない。
(Sa+Sb)/(S1+S2)>1/8のとき領域Aの高さ
: H3, 領域Bの高さ : H4 となる。
●高さに算入されない
「その他これらに類する建築物の屋上部分」に該当するもの
・屋上の利用のための階段室
・昇降機の乗降ロビー(通常の乗降に必要な規模程度(昇降路と同程度の規模)のものに限る)
・装飾塔(時計塔,教会の搭状部分),物見塔,屋窓
・各種機械室
:空調機械室,排煙機械室,発電室,吊上げ式自動車車庫の機械室等(横浜市)
・建築設備室
:保守点検,非常時等を除き,通常の利用に供さない室
・前記にのいずれかに付属する階段室,廊下等(保守点検,非常時等を除き,通常の利用に供さない室であること)
・高架水槽(周囲の目隠し部分を含む)
・キュービクル等の電気設備機器(周囲の目隠し部分を含む)
・クーリングタワー等の空調設備機器(周囲の目隠し部分を含む)
・雪下ろし搭屋
●
「その他これらに類する建築物の屋上部分」に該当しないもの (横浜市pdf./2009JCBAより
)
・パーキングタワー
パーキングタワーの高層部分は,形態上階段室等と似ているが,建築物の屋上に突出する部分ではないので,建築物の高さに算入される。
・屋外階段(ラセン階段のパイプ状の囲いなど)
屋外階段は建築物の部分であるので,たとえパイプ等の軽微なもので作られている場合であっても,建築物の屋上部分についてのみ建築物の高さに算入されない。
・居室,倉庫又は下階と用途上一体的に利用する吹抜けの部分等は,屋上部分とはみなされない。
令第2条第六号のハ
「棟飾,防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物」に該当するもの
● 建築物の高さに算入されない屋上突出物の例としては,
①
建築物の躯体の軽妙な突出物
・採光,換気のために設けた窓等の最小限の立上がり部分
・パイプ,ダクトスペース等の立上がり部分
・箱棟
②
部分的かつ小規模(軽微)な外壁等
・鬼瓦,風見鶏,装飾用工作物等(装飾塔に類するものを除く)
・防火壁
・手すり(開放性の大きいもの)
・パイプ,ダクトスペース等の立上がり部分
③
部分的かつ小規模(軽微)な建築設備
・建築設備機器
・避雷針,アンテナ等
④
建築物と一体的な煙突の部分
屋上突出部とは,建築物の屋上に部分的に設置され,かつ屋内的空間を有しないものをいう。従って,パラペットは,屋上部分の周囲に設けられるものであるため,高さに算入する。
高さの算定一覧表 (H1,H2,H3,Hp
:下図「高さのとり方」参照)
| 高さの算定一覧表 | |||||
| 制限内容 | 条文 | 基準点 | 高のとり方 | 高さに算入しないPH階の限度 | |
| 避雷針の設置義務 | 法33条 | 地盤面 | H2 | 除外なし | |
| 低層住居専用地域内の絶対高さ | 法55条 | 地盤面 | H1 | ≦5m | |
| 道路斜線 | 法56条1項1号 | 前面道路の 路面の中心 |
H3 | Hp≦12m | |
| 隣地斜線 | 法56条1項2号 | 地盤面 | H1 | Hp≦12m | |
| 北側斜線 | 法56条1項3号 | 地盤面 | H2 | 除外なし | |
| 日影規制 | 法56条の2 | 地盤面 | H1 | Hp≦5m(※) | |
| 高度地区 | 北側隣地との関係の制限 | 法58条 | 地盤面 | H2 | 除外なし |
| その他 | 地盤面 | H1 | Hp≦12m | ||
| 特例容積率適用地区内の建築物の高さ | 法57条の4,1項 | 地盤面 | H2 | 除外なし | |
| その他の規定 |
- |
地盤面 | H1 | Hp≦12m | |
※).日影規制の対象建築物(高さ>10m)となるかどうかの算定で,対象建築物となればPH階もすべて日影対象となる。
高さのとり方
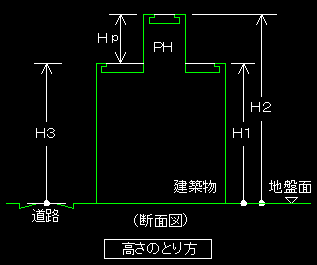
● 「階数」について
条文 令第2条第八号
八
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他の建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
(階数については,階段室は示されていないが。)
※ 注意).
「階数」に算入されなくても,「階」に含まれるものは床面積にも延べ面積にも算入される。
参考).階について
「階」については,「階数」と違って法文上に定義がなされていない。
例えば,階数は「階数が三以上の建築物」とか「最上階から数えた階数が二以上」のように使われ,「三階以上の階」といった場合は地上階数3と考えられる。また,階数に算入されない塔屋や地階等の部分でも,階には該当するので廷べ面積には算入される。
(3)傾斜地等において,建築物の部分により高さが異なっている場合
傾斜地等の屋上部分の例(下図左) (1995K)
Sa≦(S1+S2+S3)×1/8 ならばSa>S3×1/8
でもよい。
(4)傾斜屋根の屋上部分の高さ(h)は,原則としてその最下端から算定する
傾斜屋根の屋上部分の高さの例(下図中央) (1995K)
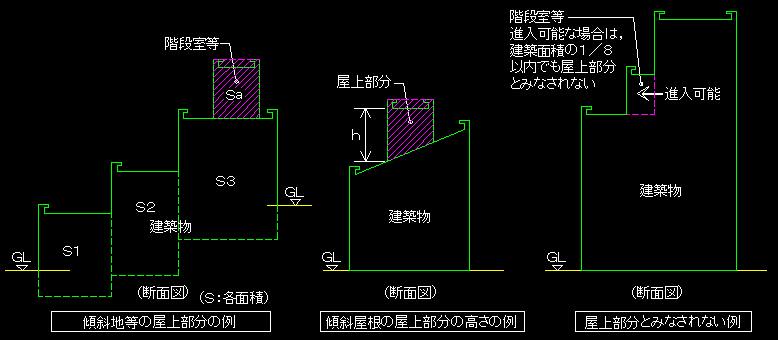
屋上部分とみなされない例(上図右) (1995K)
(5) 高さに算入しない屋上部分と算入される屋上部分
「階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分」とは,その部分以外の建築物の屋根面より高い位置に設けられるもののうち,屋上に設置することが適当であると考えられるものをいう。したがって,通常の居室や下階の部分と用途上一体として使用される物置専用の室,吹抜け等は,水平投影面積が建築面積の1/8以内であっても建築物の高さに算入する。
また,隣接するその建築物の部分(側方)から通常進入可能な部分は,階段室等であっても屋上部分とはみなさない。
| パイブ手すりの斜線制限の取扱い (2009JCBAより ) | |
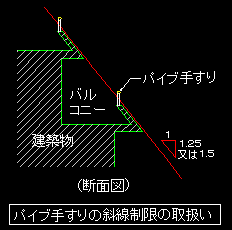
|
屋上以外のバルコニー等の手すりが,パイプ,金網等の形状の場合で,日照,通風の確保ができるものである場合は,高さ制限の趣旨から見て一般的にほとんど影響のない軽微なものといえるので,建築物の高さに算入しない。 ただし,ガラス状のものやパンチングメタルは,日照・通風の確保の観点から,建築物の高さに算入する。 |
屋上階・地階の取り扱い
階数の算定(令2条第1項第ハ号 関係)
屋上階部分にホールがある例 (下図左) (1995K)
屋上階に通常人が立ち入るホールがあるため階数に算入する(屋上の空調機械室は令2条1項八号の規定の「その他これらに類する部分」として認められる)。
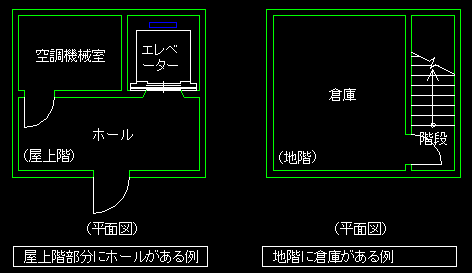
地階に倉庫がある例 (上図右) (1995K)
地階の倉庫に通じる階段があっても階段部分を含め水平投影面積が1/8以下であれば算入しない。
● 階数に算入されない「地階の倉庫,機械室その他これらに類する建築物の部分」
・倉庫,物入れ,トランクルーム
・各種機械室
・建築設備室
・地階に設けることが適当である居室以外の室
・前記のいずれかに付属する階段室,廊下等(地階に設けることが適当である居室以外の室であること)
屋上部分の「軒の高さ」の取扱い
「軒の高さ」(令2条1項七号)
屋上部分の取扱い
(1995K
)
屋上部分の取扱いについては,建築物の高さの場合,一定の要件に適合する階段室等の屋上部分については高さに算入しないという規定がある(令2条1項六号ロ)が,軒の高さの場合には,こうした規定は存在しない。このため,建築物の高さには算入されない階段室等の屋上部分も,軒の高さの算定については,すべて算入するという考えもある。しかし,建築物の高さに算入されない階段室等の屋上部分は,軽微な部分であるので,この部分を無視し,基本的には建築物の本体部分で軒の高さを算定することが妥当と孝えられる。したがって,日影規制の場合は高さが5m以内の屋上の塔屋等については,軒の高さには算入しない。また,他の軒の高さの制限の規定については,高さが12m以内の屋上の塔屋等については,軒の高さには算入しない。なお,軒の高さが2.3mに制限されている物置等については,屋上の塔屋等の存在は考えられない。
このほか高さが12m(5m)を超える階段室等の屋上部分については,建築物の高さの算定の場合には,12m(5m)までは高さに算入しない,という緩和規定がある(令2条1項六号ロ)が,軒の高さの場合,12m(5m)を減じるということは合理的でないので,軽微な部分でないとし,階段室等の屋上部分全体を含めて,軒の高さを算定することが合理的であろう。
(注. 2.3mに軒高を制限されている物置等は階段室等が存在することは考えられない。)
日影規制の対象建築物の判断の場合 1 (下図左) (1995K)
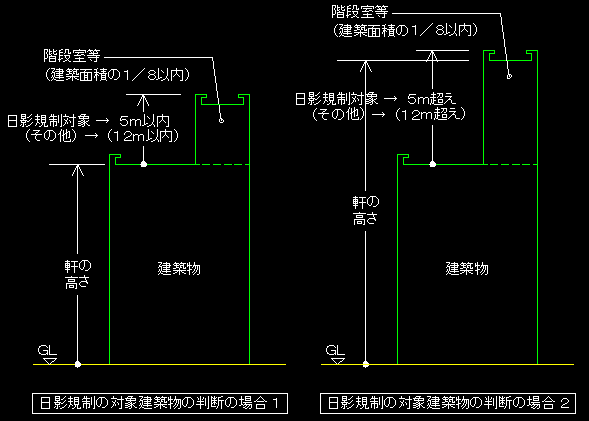
日影規制の対象建築物の判断の場合
2 (上図右) (1995K)
道路斜線,日影規制が適用されない広告塔等の取り扱いについて
法第88条1項
【内容】
・建築物に設置する高さ4mを超える広告塔は,準用工作物として取り扱う。ただし,外観上又は構造上建築物と一体とみなせる場合は,建築物の一部として取り扱う。
| 道路斜線,日影規制が適用されない広告塔等の例 (2002K) | |
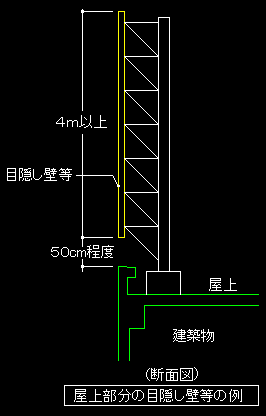
|
建築物に設置する高さが4mを超える広告塔(板),装飾塔その他これらに類するものは準工作物として取り扱い,道路斜線・日影規制等の規定は準用されない。 ただし,広告塔等が以下のケースのように外観上または構造上建築物と一体とみなせる場合は,建築物の一部として取り扱う。 1.広告塔等が建築物の外壁面と同一面 2.建築物との間に空間が設けられていない 3.外壁と同一の仕上げがなされている 4.建築物の柱を延長して広告塔等の支柱としている場合 こうしたことから,建築物の外壁の仕様と一体的にみられるものについては,建築物の躯体部分と,その遮音壁・目隠し壁等を構造的に切り離し,50㎝程度の空間を確保することで工作物として取り扱う特定行政庁が多いようだ。 建築物に設置する工作物である広告塔,広告板等でその高さが4mを超えるものは,法第88条第1項及び令第138条第1項第3号の規定により,準用工作物として,法第6条(建築確認),法第20条(構造耐力関係規定)などの規定が準用される。 |
軒の高さの算定
(令2条第1項第七号)
一般階の軒の高さ (1995K)
和小屋の軒の高さ (下図左)
/ 洋小屋の軒の高さ (下図中央)
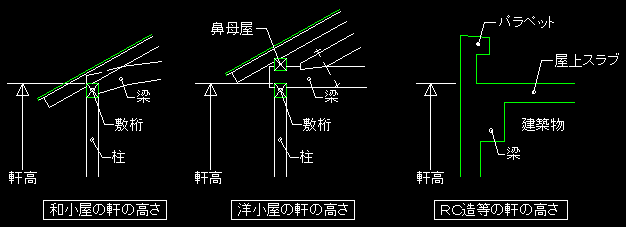
RC造等の軒の高さ (上図右)
RC造/SRC造/Sラーメン造/コンクリートブロック造(臥梁の上端)等における軒の高さの算定方法
どの高さを軒高として採用してよいのか明確ではないが,一般的には屋上スラブ上端までの高さとされている。日影規制における高さ算定の場合も同様。
軒の高さの算定(令2条第1項第七号)
一般的な小屋組による木造建築物などについてはさほど問題はないが,片流れ屋根の場合,判断が難しい。多くの特定行政庁では,原則として,高い側の軒の高さを当該建築物の軒の高さとするとしている。なお,屋根が小屋組で形成されているものは,それを支持する壁または柱の上端までとするとしている。
木造片流れ屋根の軒の高さ
1 (下図左) (2002K)
A :
小屋組がある場合の軒の高さ
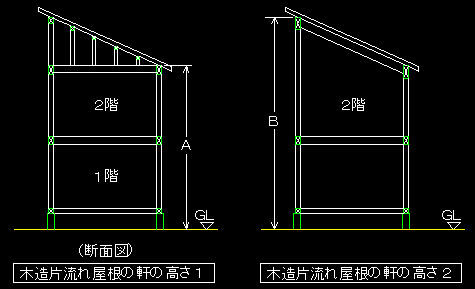
木造片流れ屋根の軒の高さ
2 (上図右)
B :
小屋組が無く,登り梁などで小屋裏を利用する場合の軒の高さ
■ 005 小屋裏物置(天井裏,床下収納)などの階(数)の取り扱い
(令第2条第1項8号)
小屋裏物置(天井裏,床下収納)などの階(数)の取り扱い例
平成12年6月1日住指発682号「建築基準法の一部改正」 (2002K
)
各スペースの最高の内法高さ≦1.4mで,かつ,水平投影面磧が各スペースの存する階の床面積の1/2未満であれば,階としては取り扱わない。昇降するためのはしご等が固定式であるか,取り外しが可能であるかも問わない(注.※)。
階に算入されないものは,床面積,延べ面積にも算入されない。
注.※ 物の出し入れのために利用するはしご等は,固定式としないこと。
(昭和55年2月7日建設省住指発第24号)
住宅とは専用,長屋及び店舗住宅のうち店舗部分床面積が延面積の1/2未満,かつ,床面積が50㎡以下のもをいう。
平成12年6月1日住指発682号
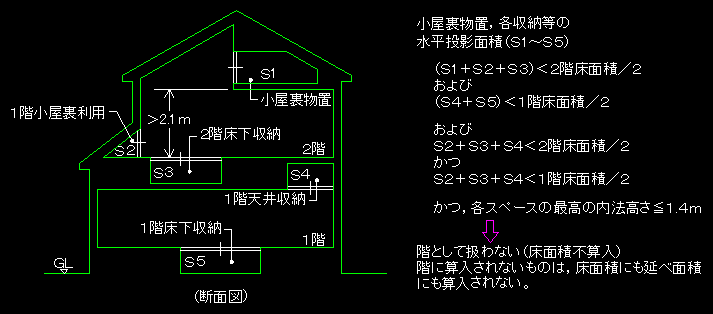
各スペースは,共同住宅,長屋等にあっては各住戸単位で算定する。かつ,建築物全体で規定を満たす必要がある。
階の中間に設ける各スペースは,水平投影面磧の合計が,その接する上下それぞれの階の床面積の1/2未満であること。
各スペースの用途は収納に限定される。
小屋裏物置等に窓等を設ける場合における開口部の面積については,建築主事に確認が必要である(横浜市の場合は以下を参照)。
横浜市 (横浜市pdf.より
)
小屋裏物置等に窓等を設ける場合は,当該部分の床面積の1/20を限度とする。ただし,当該物置等が上下に接する場合には,その水平投影面積の1/20を限度とする。
二以上の小屋裏物置等の部分が,上下に接する場合の小屋裏物置等の天井の高さの合計は,1.4m以下とすること。
階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)の当該部分は,居室の直上に設けないこと。ただし,当該部分の直下の天井の高さが2.1m以上である場合については,この限りではない。
小屋裏物置等を利用するために設置する階段については,令23条の規定を満たす必要がある。また,当該階段部分は床面積に算入される。
留意).木造建築物における小屋裏物置の注意点
(建設省通知1・5・2)
木造建築物の耐震壁の配置規定の整備
(令第46条並びに告示第1351号及び第1352号関係)
木造の建築物については,基準の明確化を図る観点から,木造建築物の耐震壁の配置の方法に関して建設大臣が定める基準によらなければならないこととした。
建設大臣が定める基準においては,建築物の部分ごとの耐震壁量の割合等を定めた。
また,小屋裏,天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において,当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で,かつ,その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば,当該部分については階として取り扱う必要はないものであるが,近年このような物置等を設置する事例が増加してきていることを踏まえ,軸組等の規定を整備した。なお,構造計算が必要となる場合においては,令第85条の規定に基づき当該部分の積載の実況を反映させて積載荷重を計算することが必要である。
木造の建築物に物置等を設ける場合には,以下①,②の検討が必要である。
① 建設省告示第1351号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項(構造耐力上必要な軸組等)の規定に基づき,木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を次のように定める。
平成12年5月23日 建設大臣 中 山 正暉
木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件
建築基準法施行令(以下,「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積(a)は,次の式により計算した値とする。ただし,当該物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の8分の1以下である場合は,零とすることができる。
a=(h/2.1)A
この式において,a ,h 及びA は,それぞれ次の数値を表すものとする。
a
階の床面積に加える面積(単位 平方メートル)
h
当該物置等の内法高さの平均の値(ただし,同一階に物置等を複数設ける場合にあってはそれぞれのhのうち最大の値をとるものとし,2.1を超える場合にあっては,2.1とする。)(単位
メートル)
A
当該物置等の鉛直投影面積(単位 平方メートル)
附則
この告示は,平成12年6月1日から施行する。
②
以下,つりあいの良い軸組(耐震壁)の配置による軸組のバランス算定時にも面積(a)を加算すること。
建設省告示第1352号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第46条第4項の規定に基づく,木造建築物の軸組の配置の基準
(階数が2以上または延べ面積が50平米を超える建集物の耐震壁の配置)
参考).東京都取扱い
小屋裏物置等の階としての取扱いにつて
通知文中の「また,小屋裏,天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において,当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で,かつ,その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば,当該部分については階として取り扱う必要はないものであるが,」については,意味不明な箇所がありますが,東京都では次のように取り扱うことになりました。(公式文書なし,調査課による口頭説明のみ。以下,文責:鈴木繁康)
1 従来の「小屋裏利用の物置等の取扱いについて(昭和55年建設省住指発第24号・建築指導課長・市街地建築課長通達)」は本年4月1日をもって無効とする。
2 次の基準に適合する小屋裏物置,床下物置等は,階及び床面積に算入しない。
1) 当該物置等の最高の内法高さが1.4m以下であること
2) 当該物置等の部分の床面積の合計が,直下階の床面積の2分の1以下であること(ただし,8分の1を超えると告示第1351号が適用されます)
なお,固定階段の設置は自由になります。
また,4月1日からは建築基準法は自治事務になり,法解釈権限は基礎的自治体に委譲されています。したがって,この取扱いは都内の市及び区の建築主事の判断を拘束するものではありません。
■ 006 避難階の取り扱い例
直通階段の設置(令第120条)
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては,避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその1に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
(表省略)
【避難施設等の範囲】(令第13条)
避難施設等
:
避難施設,消火設備,排煙設備,非常用の照明装置,非常用の昇降機又は防火区画
避難階
:
直接地上へ通ずる出入口のある階をいう(令第13条第1項第一号)。
避難階の取り扱い例 (避難階:令13第1項第一号 関係)
避難階が複数ある例 1 (1995K
)
下図(*)のように「任意の階から階段室のみを通って,避難階に到達できる階段」を「直通階段」という。
2階及び地下2階共,直接地上へ通ずる出入口のある階なので,避難階は2階及び地下2階の2つとなる。
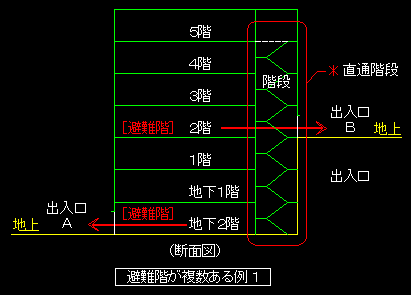
避難階が複数ある例 2 (下図左) (1995K
)
2階及び地下2階共,直接地上へ通ずる出入口のある階なので,避難階は2階及び地下2階の2つとなる。
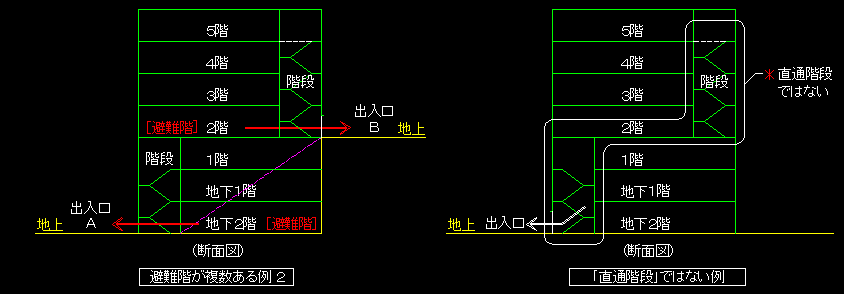
「直通階段」ではない例 (上図右) (2007W)
*「任意の階から階段室のみを通って,避難階に到達できない」ため,「直通階段」ではない。
避難階の地上部分の要件
(下図左) (1995K
)
出入口Aの地上部分は,避難上有効な空地が確保され,緊急車両等の進入可能な通路が空地に通じていることが必要である。
4階は避難階となる。
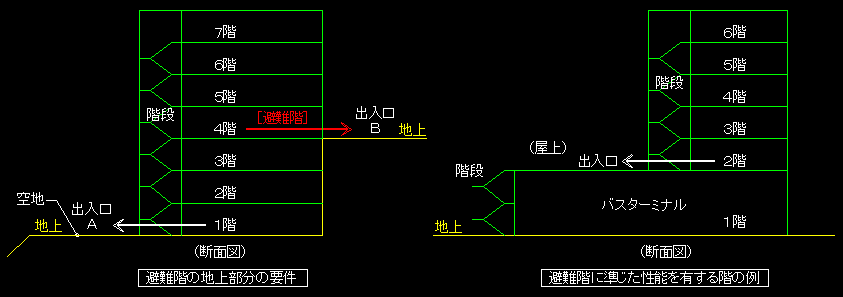
避難階に準じた性能を有する階の例
(上図右) (1995K
)
2階については避難階とはならないので,令120条に規定する直通階段が設置されていないことになる。この場合,1階の屋上からの避難経路があり,その経路の部分が避難時における有効な面積,防火・耐火性能を育すると認められる場合(日本建築センター性能評定),避難階に準じた階として取り扱うこともある。
避難規定上の「階」と「階数」の取り扱い例
「階」と「階数」
(階数:令2条第1項第ハ号,避難階:令13第1項第一号
関係)
避難規定上別の階とみなす取り扱い例
吹抜けがある例 (下図左) (1995K
)
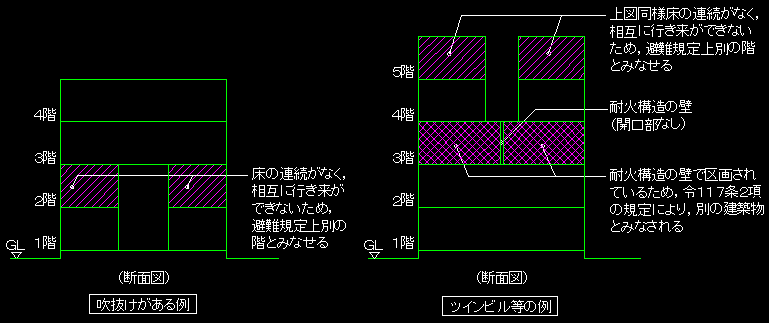
ツインビル等の例 (上図右) (1995K
)
以上のこうした取扱いは,床面積の合計の値に関連し,さらに階段の幅等(令23条1項),廊下の幅(令119条),2以上の直通階段の設置(令121条),避難階段の設置(令122条1項)などの規定にも関連してくる。
■ 007 耐火構造における階の算定 (1995K
)
耐火構造における階の算定
耐火性能に関する技術的基準(令107条)
・ 吹抜き部分の取扱い
建築物の吹抜き部分は,吹抜き部分と床を共有する階のうち,最上階から数えた階数が最も多い階数(6)となる。
令2条1項八号の規定による階数に算入されない塔屋等については,耐火時間は最上階(1)と同様の取扱いとなる。
・
エキスパンション・ジョイント等により,構造的に分離された低層建築物の部分の取扱い
また,外見上は一体的な建築物であっても,エキスパンション・ジョイント等により,構造的に分離された低層建築物の部分は,独立した別棟として,その部分の最上階(1~)から数えてよい。
地階部分の階数は,令2条1項八号の規定にかかわらず全て算入する。
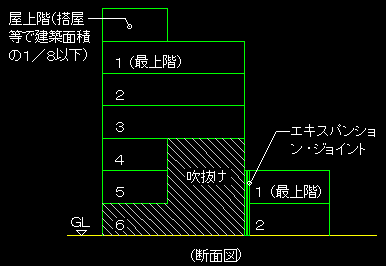
・
エキスパンション・ジョイントなしで一体の建築物の低層部分と高層部分の取扱い
エキスパンション・ジョイントなしで一体の建築物の場合は,低層部分の最上階からの1,2階は高層部分と同様に5,6階と算定する。
下図のように,高層部分の過重を負担しない「※」部分については,それぞれ単独で(最上階→2)考えてよいことになっている。
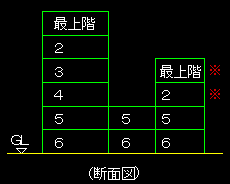
耐火構造の耐火時間についっては,法第2条七号,令第107条(耐火性能に関する技術的基準)を参照。
■ 008 ラック式倉庫(立体自動倉庫),多層式倉庫 (2009JCBAより
)
ラック式倉庫(立体自動倉庫〉の階数及び床面積の合計の算定は,以下のとおり取り扱う。
① 階数の算定
・階数は1とする。
② 床面積の合計の算定
・法第3章(第5節及び第8節を除く。)の規定を適用する場合については,ラックを設置している部分の高さ5mごとに床があるものとして床面積の合計を算定する。
・それ以外の場合については,当該部分の階数を1として床面積の合計を算定する。
多層式倉庫の階数及び床面積の合計の算定は,以下のとおり取り扱う。
① 階数の算定
人が作業可能な部分を通常の床とみなして,その部分を階として算定する。
② 床面積の合計の算定
人が作業可能な部分を通常の床とみなして,その部分の床面積の合計を算定する。
【解説】
・ラック式倉庫とは,物品の出し入れを搬送施設によって自動的に行い,通常人の出入りが少ない倉庫をいう。
・多層式倉庫とは,内部で人が物品の出し入れ等の作業を行う部分が重層的に設けられている倉庫をいう。なお,多層式倉庫については,人が作業可能な部分を床とみなして,通常の建築物と同様に建築基準法を適用する。
階数として算定する多層式倉庫の例
機械ではなく,人が物品を出し入れしたり,物品等を持って移動するなどの作業を行う部分は,通常の床とみなして階数及び床面積の算定対象とする。
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施工について(平成5年6月25日住指発225号,住街発第94号)
(以下省略)
「目次」へ戻る