サンプルファイルダウンロード (左のフレームの「法規関連資料のダウンロード」より)
a2_100_sujikai_check.dwg 表示 → DWF HTM (別ウィンドウで表示)
木造_筋かい計算図/計算表.dwg
a2_100_sujikai_check.xls (別ウィンドウで表示)
木造_筋かい計算表.xls (作成 Excel 2002)(DWGへの挿入用)
※ 2025年4月より壁量基準・柱の小径基準が改正 (2025.01.01 New) (各Webサイトより抜粋)
<構造基準の令第46条,第43条の改正の概略>
ポイント
木造建築物における省エネ化等による建物重量化に対応するため,2025年4月より壁量基準・柱の小径基準が改正されます。
壁量基準の適用可能範囲について,【2階建て以下,高さ13m・軒高9m以下,延べ面積500㎡以下】から【2階建て以下,高さ16m以下,延べ面積300㎡以下のすべての小規模木造住宅・建築物】へと見直される。
現行の令第46条第4項表2によるいわゆる「軽い屋根」「重い屋根」の区分により必要な壁量を算定する基準は廃止されます。また,枠組壁工法についても同様となります。
表計算ツール・早見表(試算例)の使用が可能です。
改正基準により,必要壁量が増え,必要となる柱の小径が大きくなる場合があります。
1年間の経過措置
なお,改正は令和7年4月1日に施行されますが,地階を除く階数が2以下,高さが13m以下および軒の高さが9m以下である延べ面積が300㎡以内の木造建築物については,以下の基準について新基準の円滑施行の観点から1年間(令和7年4月1日から2026年3月末まで),現行の基準での検証も可能とする経過措置が設けられます。
・ 壁量に関する基準
・ 柱の小径に関する基準
■ 壁量計算(令第46条)の改正
方法として以下の方法1~3のいずれかを行うことになります。
方法1,2は従来の壁量計算の改正で,方法3は別途構造計算を行う事で壁量計算を省略する方法です。
方法1:算定式により,建築物の荷重の実態に応じて必要な壁量を算定する方法
方法2:早見表(試算例)により,簡易に必要な壁量を確認する方法
方法3:構造計算(許容応力度計算等)により,安全性を確認する方法
方法1:算定式(【表計算ツール】使用)により,建築物の荷重の実態に応じて必要な壁量を算定する方法
屋根,外壁,太陽光パネルの仕様,階高,床面積比,積雪量などを考慮
※「軽い屋根」「重い屋根」といわれる区分に応じた必要壁量の算定は廃止
【表計算ツール】 (一財)日本建築防災協会・(一財)建築行政情報センターの資料
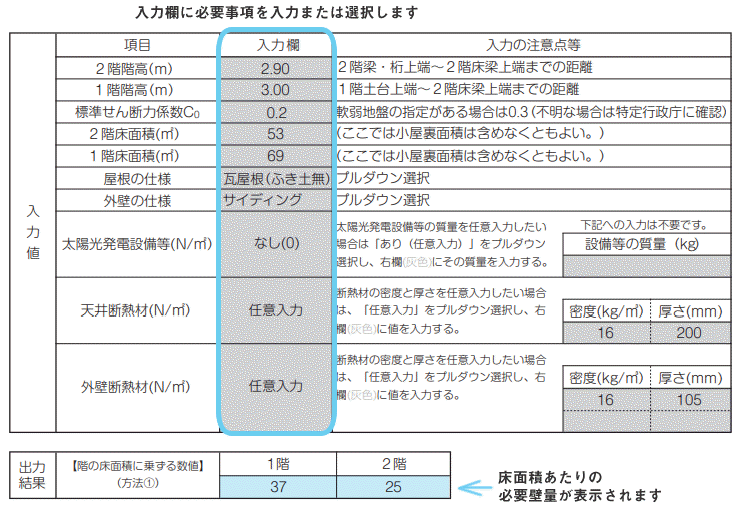
方法2:早見表(試算例)により,簡易に必要な壁量を確認する方法
【早見表】 (一財)日本建築防災協会・(一財)建築行政情報センターの資料
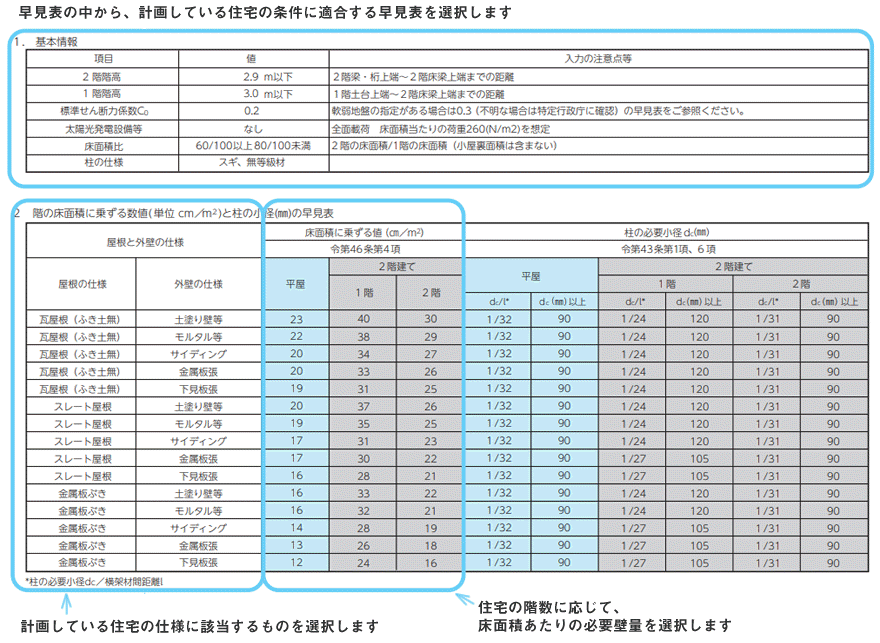
方法3:構造計算(許容応力度計算等)により安全性を確認する方法
・ 構造計算(許容応力度計算等)により安全性を確認する場合は,壁量計算を省略可能。
■ 柱の小径(令第43条)の改正
建築物の荷重の実態に応じて,算定式により柱の小径や柱の小径別の柱の負担面積を算定します。
方法1:算定式により,建築物の荷重の実態に応じて柱の小径および小径別の柱の負担可能な床面積を算定する方法
1-1:算定式と有効細長比により柱の小径を求める方法
1-2:樹種等を選択して算定式と有効細長比により柱の小径を求める方法
1-3:柱の小径に応じて柱の負担可能面積を求める方法
方法2:早見表(試算例)により,簡易に必要な柱の小径を確認する方法
方法3:構造計算(柱の座屈検討)により,安全性を確認する方法
方法1:算定式(【表計算ツール】使用)により,建築物の荷重の実態に応じて柱の小径および小径別の柱の負担可能な床面積を算定する方法
1-1:算定式と有効細長比により柱の小径を求める方法
入力欄に必要事項を入力または選択すると,柱の小径の最小寸法が表示されます。
【表計算ツール】 (一財)日本建築防災協会・(一財)建築行政情報センターの資料
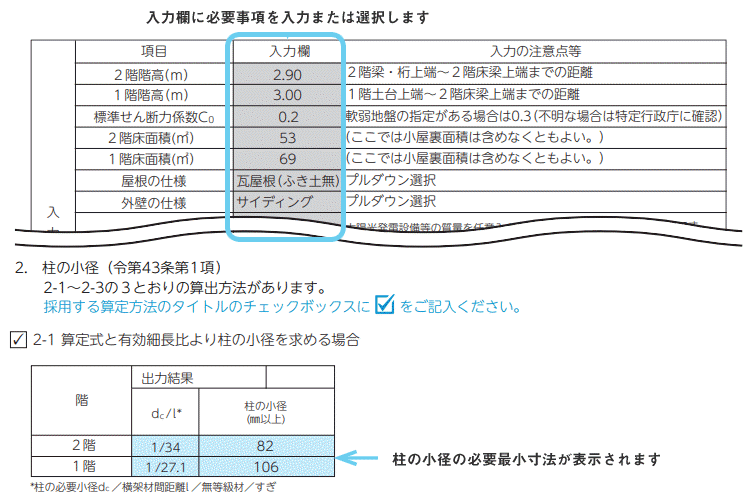
1-2:樹種等を選択して算定式と有効細長比により柱の小径を求める方法
柱材の種類(規格・樹種・等級等)を入力して,より実態に合った柱の小径を算出することができます。
(一財)日本建築防災協会・(一財)建築行政情報センターの資料
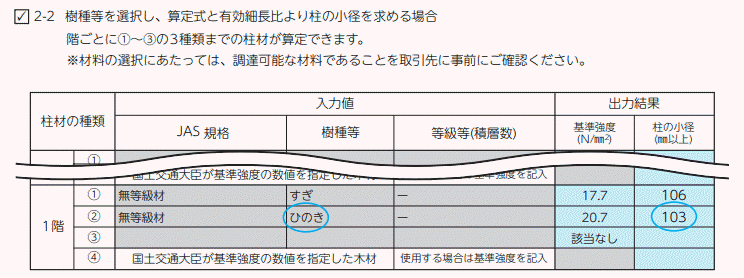
1-3:柱の小径に応じて柱の負担可能面積を求める方法
柱の小径を設定し,その柱が負担できる床面積(負担可能面積)を表計算ツールにより算出し,柱が負担している床面積(負担面積)と比較することで,柱の小径の基準への適合性を確認する方法
(一財)日本建築防災協会・(一財)建築行政情報センターの資料
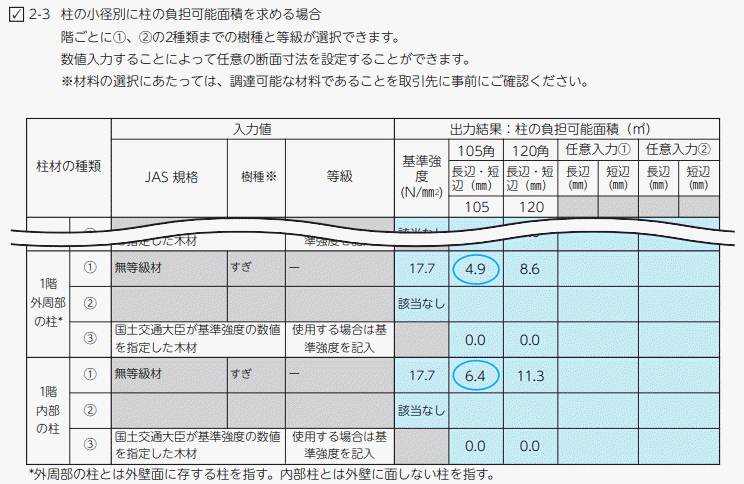
方法2:早見表(試算例)により,簡易に必要な柱の小径を確認する方法
【早見表】 (一財)日本建築防災協会・(一財)建築行政情報センターの資料
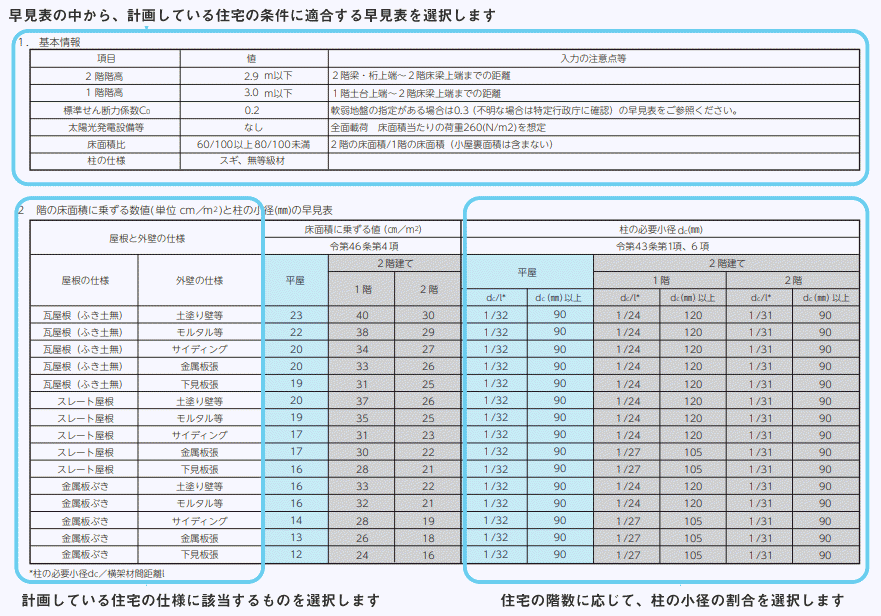
方法3:構造計算(柱の座屈検討)により,安全性を確認する方法
・ 構造計算(柱の座屈検討)により安全性を確認する場合は,「柱の小径」の確認を省略可能。
□ 壁量計算(令第46条)の改正 補足
・ 準耐力壁等を存在壁量に算入することができます。
準耐力壁等(耐力壁としての仕様を満たしていないが,一定の耐力を期待できる壁。準耐力壁 / 垂れ壁 / 腰壁等。)を存在壁量に算入することができます。準耐力壁等を含めて存在壁量を算出します。
(以下,詳細省略)
・ 壁配置のバランス(四分割法)
四分割法によって,耐力壁(※)の配置のバランスを確認します。
※)準耐力壁等は算入しません。
(以下,詳細省略)
・ 柱頭・柱脚の接合方法
耐力壁(※)が取り付いている柱の柱頭・柱脚は,発生する応力に耐えられる接合方法とします。
※)準耐力壁等は原則として倍率を0とします。ただし,1.5倍を超える場合はその倍率を用います。
柱頭・柱脚の接合方法の選択には2つの方法があります。
・N値計算法
・告示(平12建告第1460号第2号)の仕様
・N値計算法 (概略)
【平屋建て・2階建ての2階/2階建ての1階で上に2階がない部分】について
N=A1×B1-L
N:N値
A1:検討する柱の両側の壁倍率の差(筋かいの場合は補正した数値)
B1:出隅の場合0.8,その他の場合0.5
L:出隅の場合0.4,その他の場合0.6
【2階建ての1階で上に2階がある部分】について
N=A1×B1+A2×B2-L
N・A1・B1は上記と同じ
A2:検討する柱に連続する2階の柱の両側の壁倍率の差(筋かいの場合は補正した数値)
B2:2階が出隅の場合0.8,その他の場合0.5
L:出隅の場合1.0,その他の場合1.6
↓
柱頭・柱脚の接合金物の選択
求めたN値以上の許容耐力を持つ接合金物等を平12建告第1460号から選択します。
(以下,詳細省略)
他,その他のチェックが必要です。
1.基礎の仕様
2.屋根ふき材等の緊結
3.土台と基礎の緊結
4.横架材の欠込み
5.筋かいの仕様
6.火打材等の設置
7.部材の品質と耐久性の確認
8.指定建築材料のJIS・JAS等への適合
〈 各詳細については以下を参照してください。2022年改正〈2025年施行〉対応版です。必見です。 〉
※ 構造関係規定の解説について,以下で紹介されています。
編集協力国土交通省住宅局建築指導課参事官(建築規格担当)付の「改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て(軸組み工法)等の確認申請・審査マニュアル ダイジェスト版 (P21~28)」 / 他
※ 2階建ての木造一戸建て住宅(新築)の確認申請に必要な図書と明示すべき事項について,「四号特例」の見直しによって審査対象となる構造関係規定等を中心の確認申請図書の作成例が以下で紹介されています。
編集協力国土交通省住宅局建築指導課参事官(建築規格担当)付の「改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て(軸組み工法)等の確認申請・審査マニュアル ダイジェスト版 (P07~20)」 / 他
■ 建築基準法に見る木造住宅の耐震基準の変遷について
□ 1981年(昭和56年)
1978年の宮城県沖地震がきっかけで,建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準により,木造住宅の耐震基準も改正された。
壁量規定の見直しが行われ,構造用合板やせっこうボード等の面材を張った壁などが追加された。床面積あたりの必要壁長さや,軸組の種類・倍率が改定された。
□ 1995年(平成07年)
建築基準法改正
・接合金物等の奨励
□ 2000年(平成12年)
建築基準法改正
○木造住宅においては
1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化に。(施行令38条/平12建告第1347号)
改正の要点
・地耐力に応じた基礎構造が規定され,地耐力の調査が事実上義務化となる。
地耐力20kN/㎡未満・・・基礎杭
20kN/㎡~30kN/㎡・・・基礎杭またはベタ基礎
30kN/㎡以上・・・基礎杭,ベタ基礎または布基礎
木造2階建てでは,30kN/㎡≒3.06トン/㎡(3.06t/㎡)が必要だといわれています。N値に換算すると約「3」です。3階建ては,40kN/㎡≒4.08トン/㎡(N値「4」)です。
※ 地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(=地耐力)は,「kN/㎡(1㎡あたりキロニュートン)」で表されます。告示1347号他,詳細を以下に記してあります。
左フレームINDEXの「耐震基準の改正の変遷,他」 → 「建築物に必要な地盤の地耐力(許容応力度)について」
2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様規定を特定。(施行令第47条 告示1460号)
改正の要点
・筋かいの端部と耐力壁の脇の柱頭・柱脚の仕様が明確になる。
・壁倍率の高い壁の端部や出隅などの柱脚ではホールダウン金物が必須になる。
3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。(簡易計算,もしくは偏心率計算 (施行令第46条 告示1352号))
改正の要点
・壁配置の簡易計算(四分割法,壁量充足率・壁率比),もしくは,偏心率の計算が必要となる。
・仕様規定に沿って設計する場合,壁配置の簡易計算を基本とする。
□ 2006年(平成18年)
改正耐震改修促進法
○ 改正のポイント
1)計画的な耐震化の推進
・ 国が基本方針を作成し,地方公共団体は耐震改修促進計画を作成する
2)建築物に対する指導等の強化
・ 道路を閉塞させる住宅等への指導・助言を実施
・ 地方公共団体による学校や老人ホーム等への指示
・ 地方公共団体の指示に従わない特定建築物の公表
・ 倒壊の危険性の高い特定建築物については建築基準法により改修を命令
3)支援措置の拡充
・ 耐震改修計画の認定対象に一定の改築を伴う耐震改修工事等を追加
・ 耐震改修支援センターによる耐震改修に係る情報提供等
■ 過去の大きな地震及び耐震基準の改正の変遷,他 以下に記してあります。 (2024.03.11追記)
左フレームINDEXの「耐震基準の改正の変遷,他」 を参照してください。
■ 審査省略制度対象外の木造戸建住宅の地盤調査の必要性について (2024.03.11追記)
構造等の安全性や省エネ審査にかかわる,審査省略制度対象外の木造戸建住宅の地盤調査の必要性について,以下に記してあります。
左フレームINDEXの「耐震基準の改正の変遷,他」 → 「2025年「建築確認制度法第6条第1項の四号関係の改正」」を参照してください。
■ 品確法による事実上義務化の地盤調査について (2024.03.11追記)
2001年の品確法(品確法住宅性能表示制度)スタートによって,新築住宅(建替えの及びリフォームでの増築も含みます)は事実上義務化の地盤調査を行わないと,住宅瑕疵担保責任保険に加入することが出来なくなりました。詳細は以下に記してあります。
左フレームINDEXの「耐震基準の改正の変遷,他」 → 「2001年 品確法住宅性能表示制度スタート」を参照してください。 (2024.03.11追記)
■ 布基礎とベタ基礎について (2024.03.22 New)
はじめに
「布基礎よりもベタ基礎のほうが強い」と考えられがちだが,布基礎でも根入れの深さや鉄筋とコンクリートのバランスなどを工夫することで十分な強度を得られる。工期については布基礎もベタ基礎もほぼ同じくらい。布基礎とベタ基礎のどちらが適しているかは地盤の強さ・地域・予算などの観点から慎重に選ぶことが重要。
布基礎は,長期に生ずる力に対する許容応力度(=地耐力)が30kN/㎡以上の場合に許される工法です。ベタ基礎は,20kN/㎡~30kN/㎡及び30kN/㎡以上の場合の工法です。20kN/㎡未満は,基礎杭が必要です。
木造2階建てでは,30kN/㎡≒3.06トン/㎡(3.06t/㎡)が必要だといわれています。N値に換算すると約「3」です。3階建ては,40kN/㎡≒4.08トン/㎡(N値「4」)です。
※ 地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(=地耐力)は,「kN/㎡(1㎡あたりキロニュートン)」で表されます。告示1347号他,詳細を以下に記してあります。
左フレームINDEXの「耐震基準の改正の変遷,他」 → 「建築物に必要な地盤の地耐力(許容応力度)について」
布基礎とベタ基礎の各特徴とメリット・デメリット
1.布基礎の主なメリット・デメリットについて
メリット
・ ベタ基礎と比べてコストを抑えられる
布基礎の場合,基本的に柱や壁部分のみに基礎を配置するので,建物全体に基礎を施すベタ基礎と比べて鉄筋やコンクリートの使用量が少なく,材料費・輸送費・人件費などを抑えやすい。
・ 部分によっては強度がベタ基礎よりも高まる
布基礎は,ベタ基礎よりも根入れを深くするよう定められていて,深い根入れを行った箇所ほど揺れに対する抵抗力が上がるため,部分的な強度をベタ基礎よりも高めることができる。
鉄骨部分に荷重が集中しやすい鉄骨住宅や,地面が凍結しやすい雪国の住宅などにも,布基礎が適している。
デメリット
・ ベタ基礎と比べて耐震性が劣る
面ではなく点と線で支える布基礎は,ベタ基礎と比べて耐震性がやや劣る。
また,基礎の安定性が地盤の強さに左右されやすい。弱い地盤の上に布基礎の建物を建てた場合,基礎の一部だけが沈んで建物の傾きやゆがみなどを引き起こす恐れがある。
一方で,もともと強い地盤の土地や,すでに地盤改良を行った土地であれば,布基礎でコストを抑えつつしっかりした住宅を建てられる。
・ シロアリ被害に遭う可能性がある
布基礎の床下部分は,地面がむき出しになっていることが多く,地面の湿気が建物へ伝わりやすくなり,木材の腐食やシロアリ被害のリスクが高まる。防湿用コンクリートや防湿用フィルムを敷くことでリスクを軽減できるが,ベタ基礎と比べると耐食性やシロアリへの耐性は低め。
シロアリ対策として,防蟻処理を施したり湿気を逃がすための通気口を設けたりする方法もあるが,通気口を作ると床下に冷気が入りやすくなるため,並行して冷え対策を行うこともポイントとなる。
2.ベタ基礎のメリット・デメリット
ベタ基礎は,阪神大震災以降に広まりました。建物の重さが分散されやすく,耐震性を高めることが可能。建築基準法関連法令では,ベタ基礎の根入れの深さを原則12cm以上,底盤の厚さを12cm以上と定めている。立ち上がり部分に関する規定は布基礎と同じ。
現在は多くの木造住宅にベタ基礎が採用されており,大手建築会社のなかにはベタ基礎を標準仕様とするところも少なくありません。また地盤の強さが一定以下と判断された土地では布基礎が許可されず,ベタ基礎一択となります。
ベタ基礎の主なメリットとデメリットは,布基礎とほぼ反対です。
メリット
・ 耐震性に優れている
ベタ基礎は建物の荷重を面で支えるため力が分散されやすく,布基礎よりも耐震性を高めやすい。鉄骨住宅と比べて,木造住宅は力が分散されやすい構造のため,特定のポイントに荷重がかかりにくい木造住宅にも,ベタ基礎が適している。ただし,ベタ基礎が必ずしも耐震性が高いわけではない。鉄筋の量が少なかったり,コンクリートが薄かったりすると,かえって布基礎よりも耐震性が下がることがある。
・ 湿気・シロアリ被害を防げる
ベタ基礎は床下すべてが厚いコンクリートで覆われており,建物と地面が直に接しない構造となっているため,湿気による木材の腐食やシロア被害を防ぎやすい。
木造住宅の場合,湿気を防げるかどうかは住宅の品質維持に大きく関わる。木造住宅のメンテナンスの手間を省いて長く住み続けたい場合は,ベタ基礎がおすすめ。
デメリット
・ コストが高くなる
建物の大きさが同じ場合,布基礎に比べてベタ基礎は多くの鉄筋とコンクリートを消費するため,材料費がかさむ。
また,布基礎に比べて多くの残土が発生するため,ベタ基礎では材料費に加えて残土の輸送・処理費用や人件費が増えやすい。
・ 寒冷地には向いていない
寒冷地では気温の低下によって地中凍結することがある。地中凍結すると地面が膨張して基礎を押し上げ,建物に大きなダメージを与えることがある。
そのため,寒冷地で住宅を建てる際は温暖な地域よりも深い根入れが必要なため,寒冷地ではコスト面を重視して布基礎が選ばれやすい。
□ ベタ基礎の配水管埋設について
維持管理・更新の容易性など,「長期優良住宅促進法」に対応の配水管を将来共交換できる基礎配水管さや方式で埋設する方法がおすすめ。さや(管)内部での配管の交換が可能になります。
例:タキロンシーアイ [ 基礎貫通部材セット]
基礎貫通部材セットの特徴
・ 住宅性能表示制度 維持管理対策等級2以上の取得が可能になる。
・ さや管構造で配管の周囲に空間を作るので,配管の切断が可能になる。
・ さや管とホルダーで配管をしっかりと支持するため,配管勾配のずれを防ぐ。
・ 専用のパッキン付ソケットで屋外から水の侵入を防ぐ。
・ さや方式で埋設することにより基礎貫通部材内部での配水管の交換が可能になる。
・ 住宅品質確保促進法・長期優良住宅促進法に対応。
※VU100及び配管は含まれていないので,施工の際には,別途VU100,VU75大曲エルボ,VU75配管が必要。
注意). さや(管)埋設するとき,鉄筋を切断しないこと。
□ ベタ基礎の水抜き穴について
基礎施工中に水が溜まっても自然と水が抜けるように「水抜き穴」を設けましょう。
基礎の水抜き穴は,ベタ基礎工事中に水が内部に溜まるのを防ぐためのもの。基礎工事が終わったあとは主な役目を終えているので,塞いでしまっても問題はない。
水抜き穴を塞いでしまうと「基礎内部の水を排出しにくくなる」などのいうデメリットが生じるが,水が溜まる原因はさまざまなので,ケースに応じた対処をしなければなたない。
水抜き穴の有無に関わらず,基礎に水が溜まってしまった場合は,原因を突き止めたうえで,各所の修理が必要になる。
基礎の水抜き穴はモルタルなどを使ってご自身で塞ぐこともできるが,プロでない限り完全に塞げないことがある。シロアリや水の侵入を防ぐためにも,水抜き穴を塞ぐときには,施工した住宅メーカーや専門業者に相談しましょう。
■ 構造的に成立していないベタ基礎にについて (2024.03.22 New)
構造的に成立していない「ベタ基礎」が多く見受けられます。
布基礎は,逆T字型をした断面の基礎で上部構造からの荷重を支えます。建物外周部と内部の力がかかる場所・耐力壁のある場所等に設けます。
ベタ基礎の場合,鉄筋コンクリートの「底盤」が下からの力を底盤面全体で受け,その力を「立上り(基礎梁)」に伝え,上からの力とつりあうという仕組みとなります。
布基礎はそれぞれの基礎部分単体で下からの力を受け,上からの力とつり合いますので,力を受ける部分のみ,飛び飛びで配置されていても成立するのと比べ,ベタ基礎の場合,底盤は,その厚みや配筋でもつ大きさごと,途切れなく切断されていない基礎梁によって有効に囲まれていなければ,構造的に成立しません。ベタ基礎を逆さまにしてみれば,柱と梁,スラブのRC構造と同様となり,柱間の梁が飛び飛びに切断されて配置されていると,梁は用を成さずにスラブに当たるベタ基礎を支えることが出来なくなります。
実際には,床下全体を点検可能にするため,人通口(基礎立上りの切断)が必要であったりするので,立上りを全く切断しないというのは不可能です。その場合,切断された部分は梁が連続するように補強する必要があります。切断に近い太い配管等の貫通口部分も同様です。
RC構造と同様にスラブ区画に基準(≦3,640×5,460)がありますスラブ四隅には柱が必要ですが,通り芯がずれて矩形(四角形)が構造確保できない,スラブ四隅には柱がないなど,まともにスラブ区画できる木造住宅はほぼ存在しない状況でしょう。
鉄筋コンクリート構造の鉄筋量は構造計算で決めますが,しかし,構造計算を行うことがほぼ無い木造住宅では,基礎の鉄筋を計算で決めるという概念を持たない建築士,建築業者が大半です。 告示1347号にベタ基礎の仕様規定「標準のベタ基礎形状と配筋」がありますが,仕様規定はスラブ区画に関係がない最低基準で,安全基準ではありません。仕様規定で安全性を確保できるスラブ区画は「1,600×1,600」と言われています。1坪のお風呂のスラブすら安全性を保てていないレベルで,とても危険なことなのです。
告示1347号「標準のベタ基礎形状と配筋」仕様規定(最低基準)では,底盤の厚さをより厚くするか,建物外周基礎部分のみ掘り下げて厚くコンクリートを打つことで,鉄筋のかぶり厚さと建物外周基礎の根入れ深さを確保することが推奨されています。
まとめ
※ ベタ基礎は前述の留意および推奨プラス,構造計算により,構造的に成立したスラブ区画の大きさに適したスラブの厚さ,鉄筋量を決めることが重要です。
■ 注意).告示第1351号 小屋裏物置(天井裏,床下収納)などの階(数)の取り扱い」
詳細解説は以下を参照
「地盤面・階・建築物の高さ・天井の高さ 〈別ウィンドウで表示〉 → ■ 005 小屋裏物置(天井裏,床下収納)などの階(数)の取り扱い」参照
→ 留意).木造建築物における小屋裏物置の注意点
→ ① 建設省告示第1351号
→ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項(構造耐力上必要な軸組等)の規定に基づき,木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を次のように定める。・・・・・・
「目次」へ戻る