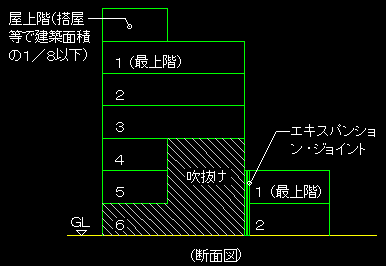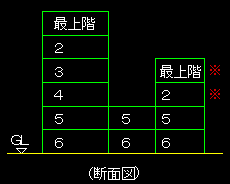�u���z��@�y�ъ֘A�@����v
�S�y�[�W
��
���R�p�Y�s�s���z�v������ - HOME��
�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�ω� �E ���ω\��
�u �� ��
�v
�� 004�@��
�K���j�D��27���̉���
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ ���K�͂Ȍ��z���̎�v�\�����K���̍�����
�^ �ωΗv���̊ɘa�@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
�� 001�@�ω\��
�i�@�Q���V���C�߂P�O�V���j
�@�@�@�@�@�@�ω\���̑ωΎ���
�@�@�@�@�@�@��
���� �u�ωΐ��\�Ɋւ���Z�p�I��i���z��@�{�s�ߑ�107���j�̍������v�@�i�ߘa5�N4��1�����{�s�j
�@�@�@�@�@�@�ω\���ɂ�����K�̎Z��
�� 002�@���ω\��
�i�@�Q���V���̂Q�C�߂P�O�V���̂Q�C�߂P�P�T���̂Q�̂Q�j
�@�@�@�@�@�@���ω\���̑ωΎ��ԁi���j
�� 003�@�ω\���̒��ӎ���
�@�@�@�@�@�@�ω\���̒��ӎ���
�@�@�@�@�@�@�@�� �����ɐ݂����g�b�v���C�g�̍\��
�@�@�@�@�@�@�@�� �S�������u���[�X�̑ωΔ핢�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�� �O�Ǒω��`�k�b�̎x���ދy�ю�t�������̑ωΔ핢�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�� �ωΌ��z���̉����X���u��ɐ݂���C�i�i���h����́j�ړI���u�������i���z�����j�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�� �ωΌ��z���̉��㕔���ɁC�{�̂̒��������čL�������x�������ꍇ�̒��̔핢�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�� �ωΌ��z�����̉��㕔��������Ή��ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�� ���]�l�b�g�^�����Z��ɐ݂���Z�˓�����p�K�i�͖ؑ��ő���邩
�@�@�@�@�@�@�@�� ���ωE�ώ��\���̊O�ǂɉR�ޗ��ł����؍ނ�O�f�M�邱�Ƃ͉\��
�i�u�h�E���h�\���v�̍����Q���j
�@�@�@�@�@�@�@�� �Ɛk�\���̑ωΐ��\�̒��ӓ_�ɂ���
�@�@�@�@�@�@���ω\���̒��ӎ���
�� 004�@���� �K���j�D��27���̉���
���K�͂Ȍ��z���̎�v�\�����K���̍�����
�^ �ωΗv���̊ɘa�@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
2019�N�̌��z��@��27���̉����ɂ���āC�ɘa����������200�u�����̖ؑ��R�K���ċ����Z���i�؎O���j�����z����ꍇ�ɂ��ωΗv�������K�v�Ȃ����z���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂����B1���ԏ��ω\���ł悢���ƂɂȂ�܂����B
�������C�ωΗv�����ɘa�����邽�߂ɂ������Е�m��̐ݒu��C�K�i�̈��S���u�̐ݒu���K�v�ł��B
�i�ڍ� �� �u�h��� �E
�h�Ώ��v�ȊԎd���v�i�ʂ̃E�B���h�E�ŕ\���j
�� �u�� �K���j�D��27���̉����v���Q�Ƃ��Ă��������B�j
�� 001�@�ω\�� �i�@�Q���V���C�߂P�O�V���j�@�i2007W�^2006H�j
�ω\�����p��̒�`���ς��܂����B�{�s�߂̋Z�p�I����ꕔ�d�l�K���ɂȂ�܂����B
�]���͎�v�\�����ɂ��āC���߂Œ�߂�ωΐ��\��L���邱�Ƃł������C����̐��\�K�艻�ɔ����C�u�ǁC���C�����̑��̌��z���̕����̍\���̂����C�ωΐ��\�Ɋւ��ā`�i�����j�`���ݑ�b����߂��\�����@��p������̖������ݑ�b�̔F����������v�ƑS�ʓI�ɉ�������܂����
�ω\���́C�ωΌ��z���̎�v�\�������Ƃ��ėp�����C�ǁC���C�����̎�v�\�����̕��ʂɂ��āC�����K���ɉ������|��y�щ��Ă�h�����邽�ߐ��߂Œ�߂�ωΐ��\�i���\�j��L����S�R���N���[�g���C������ŁC���b����߂��\�����@��p������̣�i�}�j�܂��͢��b�̔F��������̣��������ω\���̌����͉Ќ�ɔR�Ă��I������܂ŕ��u���Ă��|��Ȃ��Ƃ������ƁB�R���Ԃ���R�O���̑ωΎ�������߂��Ă���
�ω\���̑ωΎ��ԁi���ԁj �@�i�ωΌ��z���̖h������̑ωΎ��Ԃ����l�j�@�@�@��
���z���̕����̑ωΎ��ԋy�эŏ�K����̊K������������Ă��܂��B�i�ߘa5�N4��1�����{�s�j
| �ω\���̑ωΎ��ԁi���ԁj |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�v�� |
�ŏ�K
����
�̊K�� |
�� |
�� |
�� |
�͂� |
���� |
�K�i |
| �Ԏd�ؕ� |
�O�� |
| �ϗ͕� |
��ϗ͕� |
�ϗ͕� |
��ϗ͕� |
����
������ |
| ���� |
�Ȃ� |
�����i�P���j
�i�ʏ�̉Ёj |
�P�`�S |
�P |
�| |
�P |
�| |
�| |
�P |
�P |
�P |
�O.�T |
�O.�T |
| �T�`�P�S |
�Q |
�Q |
�Q |
�Q |
�Q |
| �T�` |
�R |
�R |
�ՔM���i�Q���j
�i�ʏ�̉Ёj |
�| |
�P |
�P |
�P |
�P |
�O.�T |
�| |
�P |
�| |
�| |
�| |
�Չ����i�R���j
�i�����̒ʏ�̉Ёj |
�| |
�| |
�| |
�P |
�P |
�O.�T |
�| |
�| |
�| |
�O.�T |
�| |
�ωΐ��\�Ɋւ��Ẳ������ꂽ���߂��C�ωΐ��\�Ɋւ���Z�p�I����C�ʏ�̉Ђɂ��ΔM����莞�ԉ�����ꂽ�ꍇ�ɁC���Ɍf����v���������̂ł�������Ƃ��܂��B
�i��107���W�j
1.
�\���ϗ͏�x��̂���ό`�Ȃǂ̑������Ȃ����̂ł��邱�Ɓi�Ύ��ʼn��Ȃ����Ɓj�B
�i�����j
2. ���Y���M�ʈȊO�̖ʁi�����ɖʂ�����̂Ɍ���j�̉��x���R���R�ĉ��x�ȏ�ɏ㏸���Ȃ����̂ł��邱�Ɓi�Ύ��Ŕ��Α����R���Ȃ����Ɓj
�B�i�ՔM���j
3.
���O�ɉΉ����o�������ƂȂ�ƂȂ邫�̑��̑������Ȃ����̂ł��邱�Ɓi�Ύ��ʼn��������Ȃ����Ɓj
�B�i�Չ����j
��L��1,2�Ɋւ��Ă��ʏ�̉���z�肵�Ă���C3�Ɋւ��Ă͉���������̉Ђ�z�肵�Ă��܂��B
1.�������Ɋւ��Ẳ��M���Ԃ́C�]���̋K��P���C�ǁC���C�͂�C���ɂ��ĊK���ɉ����ĂP���Ԃ���R���Ԃ̉Ђɑς��邱�ƂƂ��C�����ɂ��Ă͂R�O���Ƃ��Ă��܂��B�K�i�ɂ��Ă͎��Ԃ̎w��͖��������ł����C�ωΎ��Ԃ𑪒肷����@���m�����Ă��������R�O���Ƃ��ĐV���ɒ�߂܂����B
2.���ՔM���Ɋւ��ẮC�ʏ�̉Ђ���P���Ԓ��x�Ȃ̂ŁC�K���ɂ�鍷��݂����P���ԁi��ϗ͕ǂʼn��Ă̂�����̂��镔���ȊO�̕����͂R�O���j�Ƃ��܂����B
3.���Չ����Ɋւ��ẮC�O�ǂ���щ����̗��ʂ̉��x�̏㏸�ɂ���ĉЂ����O���ɒB���Ȃ���Ƃ��āC�K���ɂ�鍷��݂����R�O������P���ԂƂ��Ă��܂��B�i����1399���܁j
�ʏ�̉��ɂ��Ắu�����̍\���v���Q�ƁB
��
���� �u�ωΐ��\�Ɋւ���Z�p�I��i���z��@�{�s�ߑ�107���j�̍������v
1.5�����C2.5���ԑω\���̐V��
���z��@�{�s�߂̈ꕔ���������鐭�߁i�ߘa5�N���ߑ�34���j���ߘa5�N4��1�����{�s����C�ωΐ��\�Ɋւ���Z�p�I��i���z��@�{�s�ߑ�107���j�̍��������Ȃ���܂����B�T�v���ȉ��Ɏ����܂��B
�ؑ��ɂ��ωΐv�j�[�Y�̍��������w���z���ɓK�p�����ωΐ��\��i�Ў��̓|��h�~�̂��߂ɕǁC�������ς���ׂ����ԁj�����������邱�ƂŖ؍ޗ��p�̑��i��}��ړI����C�K���ɉ����ėv��������ωΐ��\���60�����݂���30�����݂��k������܂����B
�E
�ŏ�K���琔�����K����5�ȏ�9�ȉ��̊K�ł�1.5���Ԃ̑ωΐ��\�Őv���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B���z���̕������Ԏd�ؕ�������O���i�ϗ͕��Ɍ���j�C���C�����т����ł��B
�E
�ŏ�K���琔�����K����15�ȏ�19�ȉ��̊K�ł�2.5���Ԃ̑ωΐ��\�Őv���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B���z���̕���������������ł��B
�܂��C����ɔ����đω\���̍\�����@���߂錏�i����12�N���ݏȍ�����1399���j�ɂ��Ă̗Ꭶ�d�l���lj������\��ł��B
|
�����@�ω\���̑ωΎ��ԁ@�i���ԁj |
| �@�ŏ�K����̊K�� |
�� |
�� |
�� |
�͂� |
���� |
�K�i |
| �Ԏd�ؕ� |
�O�� |
| �ϗ͕� |
�ϗ͕� |
| �ŏ�K�y�тQ�ȏ�S�ȓ� |
�P |
�P |
�P |
�P |
�P |
�O.�T |
�O.�T |
| �T�ȏ�X�ȓ� |
�P.�T |
�P.�T |
�P.�T |
�P.�T |
�P.�T |
| �P�O�ȏ�P�S�ȓ� |
�Q |
�Q |
�Q |
�Q |
�Q |
| �P�T�ȏ�P�X�ȓ� |
�Q |
�Q |
�Q.�T |
�Q |
�Q.�T |
| �Q�O�ȏ� |
�Q |
�Q |
�R |
�Q |
�R |
�ω\���ɂ�����K�̎Z��@�i1995K
�j
���z���̐����������́C�����������Ə������L����K�̂����C�ŏ�K���琔�����K�����ł������K���i�U�j�ƂȂ�B
�߂Q���P�������̋K��ɂ���K���ɎZ������Ȃ��������ɂ��ẮC�ωΎ��Ԃ͍ŏ�K�i�P�j�Ɠ��l�̎戵���ƂȂ�B
�܂��C�O����͈�̓I�Ȍ��z���ł����Ă��C�G�L�X�p���V������W���C���g���ɂ��C�\���I�ɕ������ꂽ��w���z���̕����́C�Ɨ������ʓ��Ƃ��āC���̕����̍ŏ�K�i�P�`�j���琔���Ă悢�B
�n�K������ꍇ�̒n�K�����̊K���́C�߂Q���P�������̋K��ɂ�����炸�S�ĎZ������B
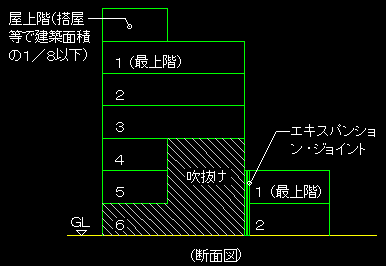
���}�̂悤�ɁC�G�L�X�p���V������W���C���g�Ȃ��ň�̂̌��z���̏ꍇ�́C��w�����̍ŏ�K����̂P�C�Q�K�͍��w�����Ɠ��l�ɂT�C�U�K�ƎZ�肷��B
���w�����̉ߏd�S���Ȃ��u���v�����ɂ��ẮC���ꂼ��P�ƂŁi�ŏ�K�i�P�j���Q�j�l���Ă悢���ƂɂȂ��Ă���B
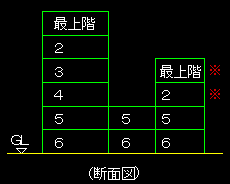
���z��@�i���a25�N�@����201���j��2��掵���̋K��Ɋ�Â��C�ω\���̍\�����@
H�P�Q�����P�R�X�X����P�`��U �i�ȗ��j
�� 002�@���ω\�� �i�@�Q���V���̂Q�C�߂P�O�V���̂Q�C�߂P�P�T���̂Q�̂Q�j�@�i2007W�j
���ω\�����p��̒�`���ς��܂����B�{�s�߂̋Z�p�I����ꕔ�d�l�K���ɂȂ�܂����B
�]���͏��ω\���́C�ω\���ȊO�̍\���ł����āC�ω\���ɏ����鐭�߂Œ�߂�ωΐ��\��L���邱��
�ł������C����̐��\�K�艻�ɔ����C�u�ǁC���C�����̑��̌��z���̕����̍\���̂����C���ωΐ��\�Ɋւ���
�`�i�����j�`���ݑ�b����߂��\�����@��p������̖������ݑ�b�̔F����������v�ƑS�ʓI�ɉ�������܂����B
���ω\���́C���ωΌ��z���̎�v�\�������Ƃ��ėp�����C�ǁC���C�����̎�v�\�����̕��ʂɂ��āC���Ă�}�����邽�߂����߂Œ�߂鏀�ωΐ��\�i���\�j��L������̂ŁC���b����߂��\�����@��p������̣�iH�P�Q�����P�R�T�W���j�܂��͢��b�̔F��������̣��������ω\���̂悤�ɉЂ̒��Ό�܂ł̈��S���S�ۂ͋��߂��Ă��Ȃ��B�R�O���܂��͂S�T���̑ωΎ�������߂��Ă���
�Ȃ��C�R�K���ċ����Z���i�@�Q�V���P�������������C�߂P�P�T���̂Q�̂Q�j�ɂ��Ă͕ǁC���C���C�͂�y�щ����̌����̉��Ă̂�����̂��镔���̕��ʂ�ʏ�̂S�T�����ωΐ��\�ł͂Ȃ��C�P������ݒ肵�Ă���
���ω\���̑ωΎ��ԁi���j
| ���ω\���̑ωΎ��ԁi���j |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�v�� |
��
|
�� |
�� |
�͂� |
���� |
|
�K�i |
| �ϗ͕� |
��ϗ͕� |
�Ԏd
�ؕ� |
�O�� |
�Ԏd
�ؕ� |
�O�� |
���� |
����
������ |
����
������ |
| ���� |
�Ȃ� |
���� |
�Ȃ� |
�S�T
��
��
��
�� |
����
�i�ʏ�̉Ёj |
�S�T |
�S�T |
�| |
�| |
�| |
�S�T |
�S�T |
�S�T |
�R�O |
�| |
�| |
�R�O |
�ՔM��
�i�ʏ�̉Ёj |
�S�T |
�S�T |
�S�T |
�S�T |
�R�O |
�| |
�S�T |
�| |
�| |
�S�T |
�R�O |
�| |
�Չ���
�i�����̒ʏ�̉Ёj |
�| |
�S�T |
�| |
�S�T |
�R�O |
�| |
�| |
�| |
�R�O |
�| |
�| |
�| |
�P
��
��
��
��
��
|
����
�i�ʏ�̉Ёj |
�U�O |
�U�O |
�| |
�| |
�| |
�U�O |
�U�O |
�U�O |
�R�O |
�| |
�| |
�R�O |
�ՔM��
�i�ʏ�̉Ёj |
�U�O |
�U�O |
�U�O |
�U�O |
�R�O |
�| |
�U�O |
�| |
�| |
�U�O |
�R�O |
�| |
�Չ���
�i�����̒ʏ�̉Ёj |
�| |
�U�O |
�| |
�U�O |
�R�O |
�| |
�| |
�| |
�R�O |
�| |
�| |
�| |
���ωΐ��\�Ɋւ��Ẳ������ꂽ���߂��C���ωΐ��\�Ɋւ���Z�p�I����C�ʏ�̉Ђɂ��ΔM����莞�ԉ�����ꂽ�ꍇ�ɁC���Ɍf����v���������̂ł�������Ƃ��܂��B
�i��107����2�W�j
1.
�\���ϗ͏�x��̂���ό`�Ȃǂ̑������Ȃ����̂ł��邱�Ɓi�Ύ��ʼn��Ȃ����Ɓj�B
�i�����j
2. ���Y���M�ʈȊO�̖ʁi�����ɖʂ�����̂Ɍ���j�̉��x���R���R�ĉ��x�ȏ�ɏ㏸���Ȃ����̂ł��邱�Ɓi�Ύ��Ŕ��Α����R���Ȃ����Ɓj
�B�i�ՔM���j
3.
���O�ɉΉ����o�������ƂȂ�ƂȂ邫�̑��̑������Ȃ����̂ł��邱�Ɓi�Ύ��ʼn��������Ȃ����Ɓj
�B�i�Չ����j
��L��1,2�Ɋւ��Ă��ʏ�̉���z�肵�Ă���C3�Ɋւ��Ă͉���������̉Ђ�z�肵�Ă��܂��B
1.�������Ɋւ��Ẳ��M���Ԃ́C�]���̋K��P���C�ǁC���C�͂�C���ɂ����R�O������S�T���Ԃ̉Ђɑς��邱�ƂƂ��C�����ɂ��Ă͒�߂Ă��܂���B�K�i�ɂ��Ă͎��Ԃ̎w��͖��������ł����C�ωΎ��Ԃ𑪒肷����@���m�����Ă��������R�O���Ƃ��ĐV���ɒ�߂܂����B
2.���ՔM���Ɋւ��ẮC�ʏ�̉Ђ���P���Ԓ��x�Ȃ̂ŁC�S�T�����x�ς����Ώ��h�����ɂ����ĉ��Ă�h�~�ł���Ƃ����l�����ł��B�i��ϗ͕ǂʼn��Ă̂�����̂��镔���ȊO�̕����͂R�O���j
3.���Չ����Ɋւ��ẮC�O�ǂ���щ����i�����܂ށj�̗��ʂ̉��x�̏㏸�ɂ���ĉЂ����O���ɒB���Ȃ���Ƃ��āC�K���ɂ�鍷��݂����R�O������S�T���ԂƂ��Ă��܂��B�i����1.358���܁j
�ʏ�̉��ɂ��Ắu�����̍\���v���Q�ƁB
���������ӂ��ׂ��_�́C���@�ł́u���ω\���v�́u�ω\���ȊO�̍\���v�ƈʒu�t���Ă��܂������C����̐��\�K�艻�ɔ����C��ʂ̐��\��L����ޗ����ɂ��ẮC���ʂ̍ޗ��Ɋ܂܂����̂Ƃ���܂����̂ŁC�u���ω\���v�ɂ́u�ω\���v���܂܂��邱�ƂƂȂ�܂����B
���z��@�i���a25�N�@����201���j��2��掵���̓�̋K��Ɋ�Â��C���ω\���̍\�����@
H�P�Q�����P�R�T�W����P�`��U �i�ȗ��j
�Q�l�j�D
�Ϗ��ω\���̉Δ핢�̗�
t = �P�T�����@�p�{�[�h�i�S�T���j
t = �P�U�����@�����p�{�[�h�i�P���ԁj
�� 003�@�ω\���̒��ӎ����@�i2006H�j
�ω\���̒��ӎ���
�� �����ɐ݂����g�b�v���C�g�̍\��
�ωΌ��z���̉������R�O���ω̗v��������C�g�b�v���C�g�Ƃ��ăA�N�����h�[�����g�p����ꍇ�́C�ԓ���K���X�݂��铙�̑Ή����K�v�ł���
�� �S�������u���[�X�̑ωΔ핢�ɂ���
�S���u���[�X�\����ωΌ��z���Ƃ���ꍇ�C�u���[�X���̋����͎�v�\�����ɊY�����Ȃ��̂Ō����Ƃ��đωΔ핢������K�v�͂Ȃ���������C�����͂����łȂ������������S������͎̂�v�\�����Ƃ݂Ȃ��C�ωΔ핢���K�v�ł���B
�� �O�Ǒω��`�k�b�̎x���ދy�ю�t�������̑ωΔ핢�ɂ���
�ʂɑ�b�F������ωp�l���i�`�k�b���j�͂��ꂼ��̎d�l���ɏ]�����ƂɂȂ邪�C����ȊO�i��b�F��ȊO�j�̈�ʂ̂��̂́C���n�ނ̂���������C���ړ��̋������̘g�g��y�Ѣ�ωp�l�����x�����邽�߂̋�������t���������łȂ��C������x������Ԓ��C�������̉��n�ނɂ��Ă��ωΔ핢������ȂǑωΐ��\��L����K�v�������
�� �ωΌ��z���̉����X���u��ɐ݂���C�i�i���h����́j�ړI���u�������i���z�����j�ɂ���
�C�i����ړI�Ƃ��C�����������g�p���Ȃ��s�R�ޗ��ő���ꂽ�u�������i���z�����j�ɂ��ẮC�O������̉��Ă�����Ђɂ��e���͂Ȃ����߁C�u���������ω\���̉����X���u����̂ƍl���C�u�����������̑ωΔ핢�̕K�v���͂Ȃ��
�� �ωΌ��z���̉��㕔���ɁC�{�̂̒��������čL�������x�������ꍇ�̒��̔핢�ɂ���
��ʓI�ɂ́C���Y�������z���{�̂̎�ˍ\�i�\����d�v�Ȃ��́j�łȂ���C��v�\�����ɊY�����Ȃ����̂Ƃ��đωΔ핢�͕s�v�Ƃ���Ă���B�Ȃ��C�L�����̐ݒu�ɓ������Ă͍����Z�����e�K���̖�������̂ŁC���O�ɍs�����Ɨv���k�
�� �ωΌ��z�����̉��㕔��������Ή��ɂ���
�����Ɉ����ωΐ��\�������߂��Ă���ꍇ�͒��ӂ��K�v�
��ʓI�ɂ́C�A����y�Ȃǂ́C���z���Ƃ��Ĉ����Ă��Ȃ��̂�����ł��邪�C�A���Ȃǂ̐����ɂ���Ă͖h�Ώ�x������������Ƃ�������щΖh�~��ωΐ��\�Ȃ�Ȃ��悤�z�����K�v�
�� ���]�l�b�g�^�����Z��ɐ݂���Z�˓�����p�K�i�͖ؑ��ő���邩
��v�\�����ɊY��������̂Ƃ��ēS���������ω\���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ����݂ł́C�؎��n�ޗ���p�����F��ω\��������B
�� ���ωE�ώ��\���̊O�ǂɉR�ޗ��ł����؍ނ�O�f�M�邱�Ƃ͉\��
�i�u�h�E���h�\���v�̍����Q���j
�����ɗᎦ����Ă��鏀�ωE�ω\���̊O�ǂ⌬�����؍���C�s�R�n�̊O�f�M�i�O���X�E�[���C���b�N�E�[���Ȃǁj�邱�Ƃ͉\�ł��顂����܂ł��̈����͕��ՓI�ɗp������\�����@�Ƃ��č����Œ�߂�ꂽ�d�l�K��̂��̂Ɍ����C��b�F��̍ޗ��ɂ��ẮC�����������O���ނ��܂߂ĔF�����K�v������
�Ȃ��C�S�R���N���[�g���C�S���S�R���N���[�g���C�S���R���N���[�g���̊O�ǂɎ{���O�f�M�ɂ��Ă͈ȉ��Ɍf����L�@�n�f�M�ނ��F�߂��Ă��顐��t���E���^���t�H�[���͌��ꔭ�A�̂��ߎ{�H��̂��������C�T�d�ɑΉ�����K�v������B
�L�@�n�f�M�ނ̗�
���A�v���X�`�b�N�nJIS���i�̗� �iJIS A �X�T�P�P�j
�r�[�Y�@�|���X�`�����t�H�[��
���o�@�|���X�`�����t�H�[��
�d���E���^���t�H�[��
�t�F�m�[���t�H�[��
�� �Ɛk�\���̑ωΐ��\�̒��ӓ_�ɂ���
�n�k�͂ɑ��錚���̍\���v�ɂ����āC�]���̢�ϐk��v�@�ɉ����āC�n�k�͂�}���܂��͐��䂵�C���̃G�l���M�[�������ɓ`���Ȃ��悤�ɂ��颖Ɛk����邢�͢���U��Ƃ����l�������ߔN���������悤�ɂȂ��Ă�����Ɛk�\���́C��b�Ɛk�����ԊK�Ɛk�Ƃɑ�ʂ���C�ωΐ��\��̒��ӓ_�͈ȉ��̂Ƃ���ł���
�E��b�Ɛk
H�P�Q�����Q�O�O�X���Ⴕ���͍��y��ʑ�b�̔F��ɂ��v�悳���B��b�͗߂P���P���R���̎�v�\�����ł͂Ȃ����ߑωΔ핢���̖@�I�`���͂Ȃ����C�\���ϗ͏��v�ȕ����ɂ͊Y������̂ʼnЎ��ɍ\���ϗ͂�ቺ�����Ȃ��[�u���]�܂����B
�E���ԊK�Ɛk
�ωΌ��z���̒����ɖƐk���u��݂���ꍇ�ɂ́C�ωΐ��\���m�ۂ��邽�߂̑[�u�Ƃ��đωΔ핢�i�ωΑсj��݂��邱�Ƃ������B���̍ہC�����Ƃ��č��y��ʑ�b�̔F�肪�K�v�ƂȂ顂Ȃ��C�r���K�ɖƐk���u��}�����C�K�ƊK��≏����H�@�ł́C�G����擙�̖h��敔���Ƃ̎�荇���ɂ͓��ɔz�����K�v�ł���B
���j�D�Ȃ��C�����P�Q�N�P�Q���Q�T���ɢ���z���̑ϐk���C�̑��i�Ɋւ���@������{�s���ꂽ���Ƃɂ��C���z���̑ϐk���C�̌v��̔F��������̂́C���z��@���̋K��i�@�Q�V���P���C�U�P���C�U�Q���P���j�ɓK�����Ȃ��Ă���ނȂ��Ƃ���Ă���
���ω\���̒��ӎ���
��v�\�����ł���Ԏd�ؕǂɗ������ꂼ��قȂ����d�l�ޗ���p���邱�Ƃ͉\��
��v�\�����ł���Ԏd�ؕǂ������iH�P�Q�����P�R�T�W���j�Ɏ����ꂽ���ω\���Ƃ���ꍇ�C�����ł͢�����ɂ��ꂼ�ꎟ�̂����ꂩ�̖h�Δ핢�D�D�D��Ƃ���̂ŁC�����Ƃ�����d�l�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���Жʂ������P�Tmm�̂��������{�[�h�Ƃ���C���Α��������P�Tmm�̂��������{�[�h�Ƃ���K�v������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u�ڎ��v�֖߂�