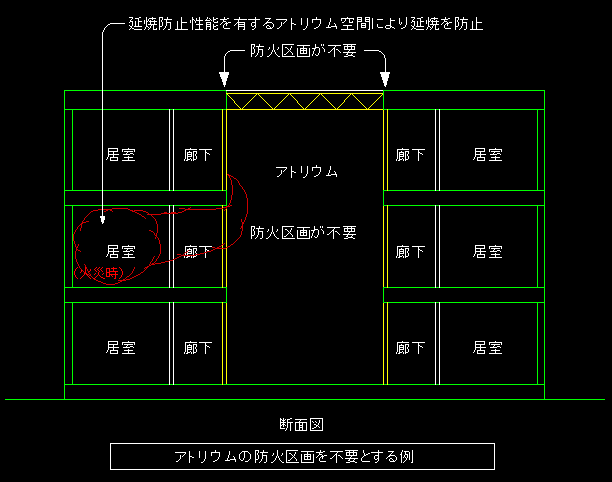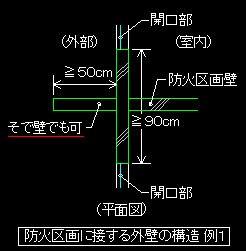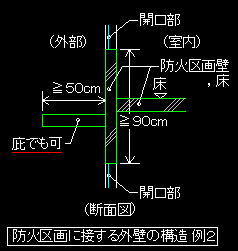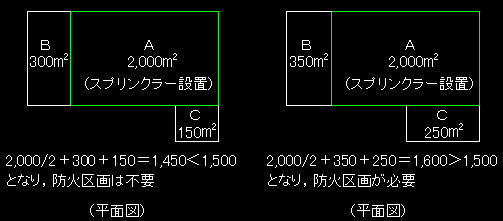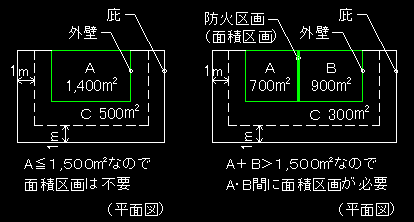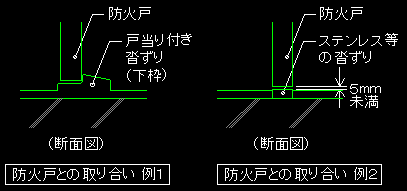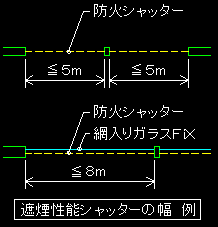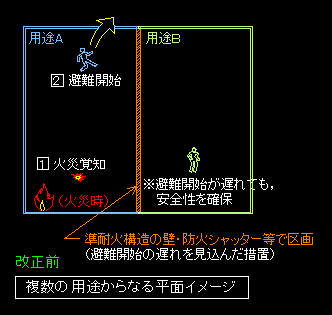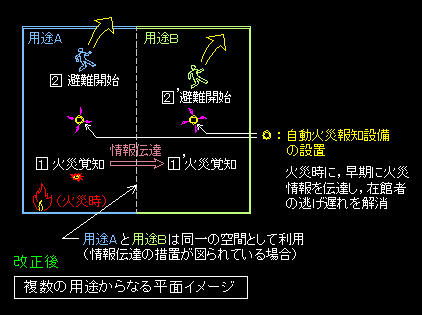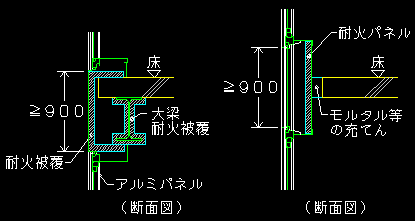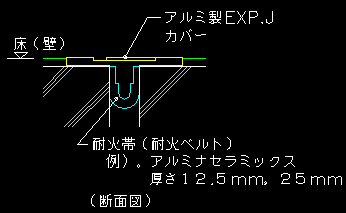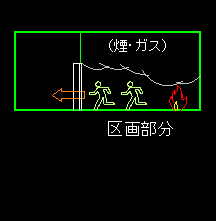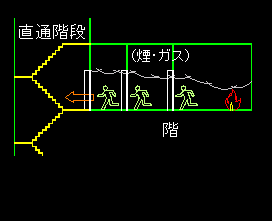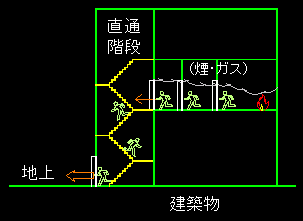「建築基準法及び関連法解説」
全ページ
→
遠山英雄都市建築設計事務所 - HOMEへ
__________________________________________________
防火区画 ・
防火上主要な間仕切り
「 目 次
」
防火区画
■ bk_001 防火区画の目的と規制
●
防火区画 (令112条)
防火区画一覧表 (令112条)
※2)
防火区画に用いる防火設備
(令112条14項,S48告示2563号(改正:H17告示1392号))
※
第112条第3項(新設)
(法第36条)
吹抜け等の空間を設けた場合における面積区画の合理化 (「国土交通省.htm」より抜粋)
●
防火区画に接する外壁の措置(スパンドレル等) (令112条10,11項)
●
防火区画を貫通する配管等の措置 (令112条15,16項,令113条2項,令114条5項,令129条の2の5第1項7号)(省略)
■ bk_002 防火区画の詳細
1 面積区画の留意事項 (令112条1項,面積区画)
(1) スプリンター等を設けた場合の倍読み規定
(1,500㎡区画の場合)
(2) 「劇場,体育館,工場その他これらに類する部分」で「用途上やむを得ない場合」について (1,500㎡区画)
1)
その他これらに類する用途の範囲
2) 「用途上やむを得ない場合」とは
(3) 準耐火建築物としなければならない建築物の面積区画の注意
① 一般防火戸(S48告示2564号)
② シャッター
(4) 耐火建築物の防火区画の壁は何時間の耐火構造とすべきか
(令112条1項,面積区画)
2 竪穴区画の留意事項 (令112条9項,竪穴区画)
(1)
竪穴区画における上下階を貫通する部分
1)
2層吹抜け
2)
映画館,メゾネット住戸
※
必見).第27条の改正
小規模な建築物の主要構造部規制の合理化
/ 耐火要件の緩和 (「国土交通省.htm」より抜粋)
(2)
自走式立体駐車場の竪穴区画について
(3)
防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備とは
3 異種用途区画が不要な場合とは(令112条12,13項,異種用途区画)
(1)
主たる用途に包含される従属用途の考え方(管理体制によるもの)
(2)
駐車場の異種用途区画についての注意点
3-2 警報設備の設置等がされた場合における異種用途区画の合理化について (「異種用途区画の緩和」) (「国土交通省.htm」より抜粋)
図解
4 防火区画を貫通する防火ダンパーの設置について(令112条16項) (省略)
5 防火区画に用いる防火設備等の煙感知器
(熱煙複合式感知器含む)の設置位置(令112条14項,16項) (省略)
6 その他の防火区画の留意事項
(1) カーテンウォールのスパンドレル
(2)
エキスパンション・ジョイント
(3)
和風便器等が防火区画の床を貫通する場合
■
003 避難安全検証法の見直しについて (「国土交通省.htm」より抜粋)
まとめ
図表
避難安全検証関連条文
建築基準法施行令第128条の6
建築基準法施行令第129条
建築基準法施行令第129条の2
各告示 (一部省略)
防火上主要な間仕切り
■ bm_001 114条区画
おさらい
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」について
防火上主要な間仕切壁の範囲と構造 (
令第114条 (,法第36条))
改正法 寄宿舎等における間仕切壁の防火対策の規制の合理化 (令112条2項,114条2項) (「国土交通省.htm」より抜粋)
(1)防火上主要な間仕切壁の範囲
(2)防火上主要な間仕切壁の構造
(令114条2項)
防火区画
■ bk_001 防火区画の目的と規制
(2006H)
●
防火区画 (令112条)
防火区画とは,主要構造部を耐火構造や準耐火構造とした建築物内を防火的に区画するものであり,区画の目的別に以下の4種類がある。
1. 面積区画
大規模な建築物の延焼を防止するために一定の面積以内ごとに防火区画し,火災を局所的に抑えようとするもの。
2. 高層区画
一般の消防のはしご車が届かず外部からの救助が期待できない11階以上の高層建築物の防火区画を,小区画とすることにより被害を最小限にとどめようとするもの。
3. 竪穴区画
火災時の煙突効果による火煙の伝播を防止しようとするもの。竪穴部分と他の部分との区画は遮煙性能が必要である。
4. 異種用途区画
建築物内に利用,形態,管理の異なる用途がある場合,それぞれの用途の安全性を図るため各用途間に防火区画を設けるもの。
防火区画一覧表 (令112条)
|
防火区画一覧表 (令112条)
|
| 区画 |
条項 |
対象建築物 |
区画面積(※1)
又は区画部分 |
区画方法 |
適用除外 |
| 床・壁 |
防火設備
(※2) |
| 面積区画 |
1項 |
主要構造部が耐火構造 |
≦1500㎡
|
耐火構造 |
特定防火設備
*閉鎖方法
・常閉
・煙感
・熱感 |
①
劇場等の客席,体育館,工場等で用途上やむを得ないもの
②
階段室,昇降機の昇降路(乗降ロビーを含む)で,耐火構造,1時間準耐火構造の床,壁,又は特定防火設備で区画された部分 |
主要構造部が準耐火構造
・ イ準耐
・ ロ準耐 |
1時間
準耐火構造 |
| 2項 |
法27条2項,法62条1項に基づく準耐火建築物
・ イ準耐(1時間準耐火構造を除く)
・ ロ準耐1号 |
≦500㎡
|
同上 |
①
体育館,工場等で天井(天井がない場合は屋根),壁の内装を準不燃材料とした部分
② 上欄②(階段室,・・・)と同じ部分 |
| 防火上主要な間仕切壁 |
準耐火構造 |
-
|
| 3頁 |
・
法21条1項ただし書き,法27条1項ただし書きに基づき1時間準耐火構造とした建築物
・
法27条2項,法62条1項,法67条の2第1項に基づく1時間準耐火建築物,準耐火建築物(口準耐2号) |
≦1000㎡
|
1時間
準耐火構造 |
特定防火設備
*閉鎖方法
・常閉
・煙感
・熱感 |
| 高層区画 |
5項 |
11階以上の部分 |
内装仕上げを難燃材料 |
≦100㎡
|
耐火構造 |
防火設備
*閉鎖方法
・常閉
・煙感
・熱感 |
・
階段室,昇降機の昇降路(乗降ロビーを含む),廊下その他の避難のための部分,200㎡以内の共同住宅の住戸で,耐火構造の床,壁,又は特定防火設備(5項は防火設備)で区画された部分 |
| 6項 |
内装仕上げ・下地を準燃材料
(1.2m以下の腰壁を除く) |
≦200㎡
|
特定防火設備
*閉鎖方法
・常閉
・煙感
・熱感 |
| 7項 |
内装仕上げ・下地を不燃材料
(1.2m以下の腰壁を除く) |
≦500㎡
|
| 竪穴区画 |
9項 |
主要構造部が準耐火構造で,地階又は3階以上に居室のある建築物 |
メゾネット住戸,吹抜き,階段,エレベーター昇降路,ダクトスペース等のたて穴形成部分のまわり |
準耐火構造 |
防火設備
*閉鎖方法
・常閉
・煙感
*遮煙性能 |
・
上欄1項適用除外の①の用途で,内装仕上げ及び下地を準不燃材料(1.2m以下の腰壁を除く)とし,その用途上区画することができないもの
・
避難階の直上階又は直下階のみに通じる吹抜き部分,階段部分等で内装仕上げ・下地を不燃材料としたもの
・
階数が3以下で,延べ面積が200㎡以内の住宅や共同住宅等の住戸の吹抜き,階段等の部分 |
異種
用途区画 |
12項 |
建築物の一部が法24条のいずれかに該当する建築物 |
該当用途部分相互間,及びその他の部分 |
同上 |
同上 |
-
|
| 13項 |
建築物の一部が法27条のいずれかに該当する建築物 |
該当用途部分相互間,及びその他の部分 |
1時間
準耐火構造 |
特定防火設備
*閉鎖方法
・常閉
・煙感
*遮煙性能 |
※1)
スプリンクラー等の自動消火設備を設けた部分は,その部分の面積を1/2(倍読み規定)として計算することができる。
※2)
防火区画に用いる防火設備
(下表)
(令112条14項,S48告示2563号(改正:H17告示1392号))
|
防火区画に用いる防火設備
|
常時閉鎖式防火戸
(常閉) |
一般タイプ |
・直接,手で開くことができること
・自動的に閉鎖すること(ストッパーがないものであり,よって,火災報知連動閉鎖機構は不要)
・一枚の戸の面積≦3㎡ |
| 昇降路タイプ |
・昇降路の出入口用
・人の出入後20秒以内に閉鎖するもの
・一枚の戸の面積≦3㎡ |
| 常時開放式防火戸 |
熱感連動 |
・随時閉鎖(いつでも手で閉めることができること)
・煙感知,熱感知または熱煙複合式感知連動閉鎖機構のあること
・常時閉鎖式防火戸と併設する場合を除き,直接手で開き,自動的に閉鎖するくぐり戸(幅≧75cm,高さ≧1.8m,敷居高≦15cm)を設ける。 |
| 煙感連動 |
・随時閉鎖(いつでも手で閉めることができること)
・煙感知または熱煙複合式感知連動閉鎖機構のあること
・常時閉鎖式防火戸と併設する場合を除き,直接手で開き,自動的に閉鎖するくぐり戸(幅≧75cm,高さ≧1.8m,敷居高≦15cm)を設ける。
・遮煙性能を有すること |
| 共通 |
開いた後に閉鎖する際の基準(ただし,人が通らない場所に設置する場合は適用外(※1))
・閉鎖作動時の運動エネルギー(1/2×MV2)≦10J(ジュール)以下
・防火設備の質量≦15kg(15kgを超える場合に,水平方向に閉鎖するもので閉じ力≦150N(スイング・スライディンク防火戸など),又は周囲の人と接触した場合に5cm以内で停止すること(防火シャッター・スクリーン) |
※1)
例として
・ ガラススクリーンと防火シャッター等を併用していてシャッターの降下位置に人が通れない場合
・ 防火シャッター等の降下位置の手前に手すりがあり,人が通行できないもの
・ カウンター部分に防火シャッター等を使用する場合など
以下,改正されています。
※ 第112条第3項(新設)
(法第36条)
吹抜け等の空間を設けた場合における面積区画の合理化 (「国土交通省.htm」より抜粋)
防火区画に関する規制の合理化
① 吹抜き等の空間を設けた場合における面積区画(第112条第3項関係)
主要構造部を耐火構造とした建築物の2以上の部分が、当該建築物の吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分に接する場合において、
当該2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の
認定を受けたものである場合においては、当該2以上の部分と当該空間部分とが特定防
火設備で区画されているものとみなして、当該建築物を1,500㎡以内ごとに区画し
なければならないとする第112条第1項の規定を適用するものとする。
改正の趣旨
・ 建築物内の延焼防止を目的として,壁,柱等を耐火構造とした建築物は,1500㎡ごと(スプリンクラー設備を設置した場合は3000㎡ごと)に,耐火構造の壁・床又は防火扉・防火シャッターで防火区画しなければならない。
・ この結果,アトリウムのような大空間で延焼防止を確保できる場合でも,一律に防火区画しなければならず,設計上の制約になっていると指摘がある。
(参考.アトリウムは、ガラスやアクリルパネルなど光を通す材質の屋根で覆われた大規模な空間のこと。
ホテルや大規模商業施設、オフィスビル、マンションのエントランスに設けられる例が多い。また、特定街区制度に基づく有効空地や、総合設計制度などに基づく公開空地を屋内に設定する際に設けられることも多い。)
改正内容
以下,アトリウムの例
| アトリウムの防火区画を不要とする例 |
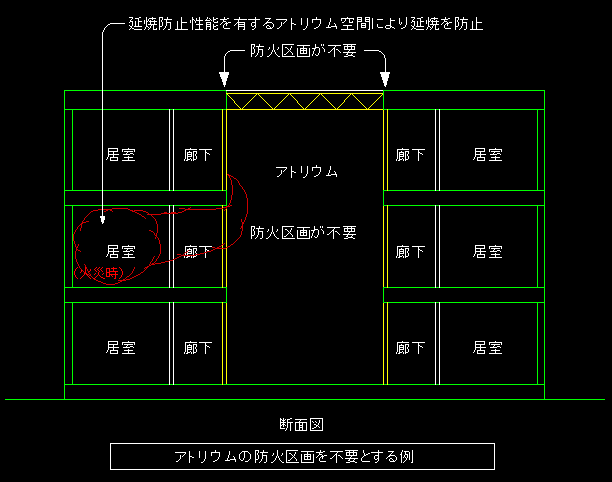 |
改正内容
アトリウム等によって,他の部分への延焼を有効に防止できる一定の条件を満たす場合には,当該アトリウム等と他の部分との間に防火区画(階層に渡る区画等)を不要とする。(竪穴区画も不要とする場合には別途全館安避難全性能の検証が必要)
参考).アトリウム空間の条件
・ ー定規模以上の空間(直径6m以上の円が内接できる,床面積1500㎡以下)であること
・ 収容可燃物量が少ないこと(用途が発生していないこと)
・ 吹抜き等の空間の規模等に応じた排煙設備を設けること
・
吹抜き等の空間に接する建築物の部分のー方で発生した火災による放射熱量を計算し,他方の部分(受熱面)での受熱量が燃焼に至る熱量を超えないことを確かめること等を告示にて規定。
|
●
防火区画に接する外壁の措置(スパンドレル等) (令112条10,11項)
面積区画(令112条2項の防火上主要な間仕切壁は除く),高層区画,竪穴区画と接する外壁は,区画相互間の延焼を防ぐため,接する部分を含み90cm以上の部分を耐火構造又は準耐火構造としなければならない(一般的にスパンドレルと呼んでいる)。ただし,外壁面から50cm以上突出した耐火構造又は準耐火構造のひさし,床,そで壁等で防火上有効に遮られている場合はこれに替えることも可能である。
防火区画に接する外壁の構造
| 防火区画に接する外壁の構造 |
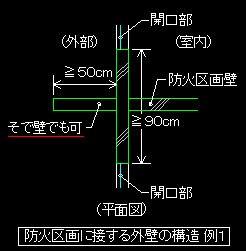 |
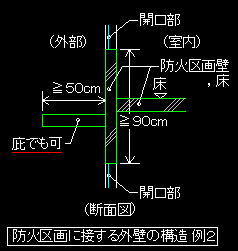 |
外壁,内壁,床
: 耐火構造,準耐火構造
※ 耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合は,特定防火設備または両面20分(遮炎)の防火設備を設けなければならない。 |
●
防火区画を貫通する配管等の措置 (令112条15,16項,令113条2項,令114条5項,令129条の2の5第1項7号)
(省略)
■ bk_002 防火区画の詳細
1 面積区画の留意事項 (令112条1項,面積区画)
(1) スプリンター等を設けた場合の倍読み規定 (1,500㎡区画の場合)
スプリンター等の自動消火設備を設けた部分は,その部分の面積を1/2として計算することができる。
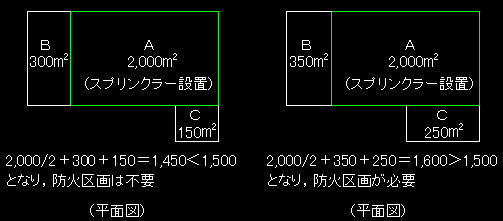
(2) 「劇場,体育館,工場その他これらに類する部分」で「用途上やむを得ない場合」について (1,500㎡区画)
1)
その他これらに類する用途の範囲
①工場類似の用途として不燃性物品を保管する立体的な倉庫,荷さばき施設が含まれ,体育館類似の用途としてボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場等のスポーツ練習場が含まれる。
②工場・倉庫等で荷さばきスペースとして利用される大規模な庇を有する場合,庇下が床面積に算人される部分であっても,十分に外気に開放されているものは,「その他これに類する用途に供する部分」として取り扱われる。
大規模な庇を有する工場・倉庫等の面積区画の考え方(下図)
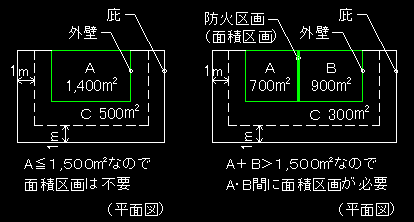
2) 「用途上やむを得ない場合」とは
劇場,映画館等の客席及び体育館等で,建物の機能上から判断して用途上やむを得ない場合が該当する。工場,倉庫,荷さばき施設にあっては,クレーン,ベルトコンベアー等が設けられている場合で区画することによって生産工程上建物の機能に支障を及ぼす部分が該当する。ただし,防火区画が免除された場合でも,その他の区画できる部分との防火区画は必要である。
なお,確認申請に当たって,防火区画の免除を受けようとするものは,生産工程フロー等の関係書類を付した「防火区画免除願い」の提出を求められる場合がある。
(3) 準耐火建築物としなければならない建築物の面積区画の注意
法規制により準耐火建築物とした建築物の500㎡,1,000㎡の区画は,体育館,工場等で仕上げを準不燃材料としたものは適用されないが,この場合でも防火区画が免除される場合を除き令112条1項による1,500㎡区画は必要である。
(4) 耐火建築物の防火区画の壁は何時間の耐火構造とすべきか
(令112条1項,面積区画)
「耐火構造の耐火時間
(耐火建築物の防火区画壁の耐火時間も同様)」を参照。
2 竪穴区画の留意事項 (令112条9項,竪穴区画)
(1)
竪穴区画における上下階を貫通する部分
階段,エレベーターシャフト,吹抜け部分,パイプシャフト等
1)
2層吹抜け
避難階の直上階又は直下階のみに通ずる吹抜け,階段等の部分は,当該部分の内装制限(下地,仕上げとも不燃)をすることにより緩和される。
なお,下地・仕上げを不燃材料とする範囲は,当該吹抜けを含め,耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備又は防火設備(遮炎性能両面20分)で区画された部分の全てとすることが望ましい(S44住指発149号通達)。
また,避難階の直上階又は直下階のみに通ずる吹抜けの部分とは,避難階と直上階又は避難階と直下階のそれぞれ2層にわたる空間のみを指し,避難階の直下階から直上階まで(地下1階~地上2)の3層にわたるものは緩和の対象とならない。
(図省略)
2)
映画館,メゾネット住戸
劇場,映画館等の竪穴区画の緩和(下地,仕上げ準不燃)及びメゾネット型住宅の竪穴区画の緩和については,当該部分内の竪穴区画が不要となるが,当該部分とその他の部分との防火区画は必要である。また,メゾネット型共同住宅(建築物内の住戸数が1のものを含む)の緩和については,住戸の階数が3以下,かつ,床面積200㎡以下のもの(令112条9項2号)に適用することができる(※
竪穴区画不要)ものである。なお,メゾネット型住戸内の竪穴区画不要の階段であっても,耐火建築物の主要構造部に当たるので,耐火構造(鉄骨造等)としなければならないので注意が必要である。
メゾネット型共同住宅の住戸の竪穴区画の例
・住戸の階数が3で床面積が200㎡以内,かつ住戸の部分とその他の部分を区画している場合は,住戸内専用階段の竪穴区画は不要。
・住戸の階数が4の場合は,住戸内専用階段の竪穴区画が必要となる。
※ 必見).第27条の改正
小規模な建築物の主要構造部規制の合理化
/ 耐火要件の緩和 (「国土交通省.htm」より抜粋)
木造3階建て建築基準法改正[法第27条の改正]で述べたように,2019年の建築基準法第27条の改正によって,緩和条件を満たせば200㎡未満の木造3階建て共同住宅(木三共)を建築する場合には耐火要件を満たす必要なく建築することが可能となりました。1時間準耐火構造でよいことになりました。
ただし,耐火要件を緩和させるためには自動火災報知器の設置や,階段の安全装置の設置が必要です。
小規模な建築物の主要構造部規制の合理化
法第27条第1項(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
改正
小規模な建築物では避難に要する時間が比較的短くなることから,避難上の安全性が確保されるとして基準の合理化が図られました。3階以上の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供するとして耐火建築物等とする必要がある建築物のうち,階数が3で延べ面積が200㎡未満のも(※)のについては,耐火建築物等とすることを要しないこととされました。
※).3階を病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。),ホテル,旅館,下宿,共同住宅,寄宿舎および児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)の用途に供するものは,所定の警報設備を設けたものに限る。
ロ準耐は,主要構造部を準耐火構造にしなくても,準耐火建築物になり,竪穴区画を不要とすることができます。
準耐火建築物の種別の選択は、設計に大きな影響をおよぼします。
「イ準耐火」または「ロ準耐火」のどちらを選ぶかで、建築基準法の制限が変わります。
「竪穴区画(建築基準法施行令112条)」は、その一例。
例えば、3階建の事務所ビルを設計するとして、主要構造部が準耐火構造で造られた「イ準耐火建築物」は竪穴区画が必要となります。
しかし、緩和条件を満たした「ロ準耐火建築物」であれば、主要構造部が準耐火構造ではないため竪穴区画が不要となります。
「準耐火建築物(ロ-2)」は、主要構造部を不燃材料でつくるため、主に鉄骨造の建物で用いられます。
以下の2つの基準を満たすこと。
・ 主要構造部:不燃材料で造り、"準耐火構造と同等の耐火性能"をもつこと
・ 延焼のおそれのある開口部:"建築基準法2条九の二号ロ"に該当する防火設備
(詳細省略)
参考).準防火地域3階の場合は,以下の2つのいづれかであれば主要構造部を準耐火構造にする必要はありません。
①ロ準耐にする(鉄骨造におすすめ)
②令第136条の2第2号ロで検討する(木造におすすめ)
上手く利用して,竪穴区画免除してみましょう。
注意).法改正前は,3階建ての特殊建築物を設計すると『耐火建築物』が必須となっていたので…主要構造部が耐火構造となり竪穴区画も強制的に設置でしたが,法改正によって主要構造部の耐火構造が免除されたことで,竪穴区画まで無くなってしまうのは避難上の危険性が高い…。
そこで,現行の竪穴区画は残しつつ,少し基準を緩和した『小規模建築物における竪穴区画』が追加されました。
国土交通省検討中の見直し案は,ここでは省略します。
(2)
自走式立体駐車場の竪穴区画について
自走式立体駐車場については,駐車スペースと上下階を連絡する車路が形態上,機能上分離することができないため,用途上やむを得ない場合と扱い,壁・天井の下地・仕上げとも不燃材料又は準不燃材料とすれば竪穴区画は免除されている。
ただし,管理室等の区画できる部分は区画しなければならない。また面積区画までは免除されないので注意が必要。
(3)
防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備とは
遮煙性能を有する防火戸は竪穴区画や異種用途区画,令126条の2第2項の区画(排煙上別棟建築物とみなす区画)に設ける防火設備に用いられ,告示2564号に規定されているように,遮煙性能を有する防火戸には次のものがある。
遮煙性能を有する防火戸
①
一般防火戸(S48告示2564号)
・
枠と接する部分を相じゃくりとしたり,あるいは定規縁や戸当りを設けるなど隙間が生じない構造のものとする。
なお,防火戸と床面とのおさまりについては,戸当り付き沓ずりが望ましい(下図左)が,やむを得ない場合でも床埋め込みのステンレス等の沓ずりとし,床との隙間は5mm未満とすること(下図右)。
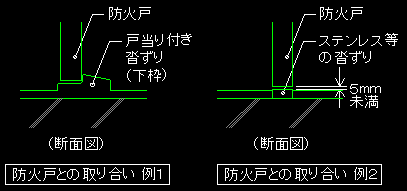
② シャッター
・ 内のり幅が5m以下で,遮煙性能試験に合格したものとする。
・ シャッターに近接して網入りガラス等防火戸を固定して併設したもので,内のり幅が8m以下のものとする。
| 遮煙性能シャッターの幅 |
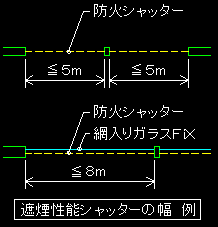
|
S48告示2564号
防火区画に用いる遮煙性能を有ずる防火設備の構造方法を定める件
1
ロ 防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分が相じゃくり,又は定規縁若しくは戸当りを設けたもの等閉鎖した際にすき間が生じない構造で,かつ,防火設備の取付金物が,取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けられたもの(シャッターにあっては,内のり幅が5m以下で,別記に規定する遮煙性能試験に合格したもの又はシャッターに近接する位置に網入リガラスその他法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を固定して併設したもので,内のリ幅が8m以下のものに限る。)とすること。
|
参考).
個別に大臣認定されている防火・防煙スクリーンは,シャッターに比べ収納スペースが小さく,またガイドレールのポストも不要で,さらに車椅子利用者も通リ抜けられるなどの特徴をもつ防火設備である。ただし設置にあたっては,(社)日本シャッター・ドア協会が,防火設備としての性能確保・維持を目的とした「技術標準」を自主的に策定しているので参考とすること。
3 異種用途区画が不要な場合とは(令112条12,13項,異種用途区画)
異種用途区画は,利用,形態,管理の異なる用途が混在する建築物において,各々の用途の安全性を図る目的で,各用途間を防火区画するものであるが,下記(1)のように区画が不要な例や,(2)の注意を要する場合がある。
(1)
主たる用途に包含される従属用途の考え方(管理体制によるもの)
異種用途区画は,建築物内のそれぞれの用途の管理体制及び使われ方等が各々異なることから,防火上の安全を確保するために必要となる区画であるが,火災の発生が同程度であり,統一のとれた管理・避難等が可能な建築物については,区画は不要と考えられる。例えば,百貨店の一角にある喫茶店・食堂,ホテルのレストラン等がこれに該当し,次の要件により,異種用途区画が不要と扱われている。
・ 管理者が同一であること。
・ 利用者が一体施設として利用するものであること。
・ 利用時間が同一であること。
・ 自動車車庫,倉庫以外の用途であること。
(2)
駐車場の異種用途区画についての注意点
駐車場は機能的に従属用途であっても,単体規定の適用において,例外的に独立用途として扱われることが多い。運転手控え室や監視室も他の部分として駐車場と区画すべきである。
3-2 警報設備の設置等がされた場合における異種用途区画の合理化について (「異種用途区画の緩和」) (「国土交通省.htm」より抜粋)
2020.4.1(施行)に改正があり,「異種用途区画の緩和」が追加になりました。
改正 第112条第18項 (法第36条)
………………
(省略)
………………
18 建築物の一部が法第27条第1項各号,第2項各号又は第3
項各号のいずれかに該当する場合においては,その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし,国土交通大臣が定める基準に従い,警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては,この限りでない。
適合させなければならない告示の内容について
国土交通省告示第250号
警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準を定める件
(詳細省略)
告示第250号の内容について
異種用途区画を緩和する為の4つの条件
・ 条件① 異種用途区画が発生する原因が,特定の用途である事
・ 条件② 床部分は必ず区画する事(緩和できるのは同一階の部分のみ)
・ 条件③ 隣接する部分は一部用途を設けないこと
・ 条件④ 警報設備(自動火災報知器)を両者の用途どちらにも設けること
(異種用途区画の緩和は特定の用途に対しては利用しやすいでしょう。)
この異種用途区画は発生する原因が,告示の各号に掲げる用途じゃないとそもそも緩和が使えません。
異種用途区画の原因が以下の場合
一 ホテル
二 旅館
三 児童福祉施設等(通所のみにより利用されるものに限る。)
四 飲食店
五 物品販売業を営む店舗
参考).共同住宅3階建だと法第27条第1項に該当するので異種用途区画が必要だと思いますが,これは緩和は使えないということです。なぜなら,告示に掲げる用途に共同住宅は含まれていないからです。
まずは異種用途区画が発生する原因が各号に該当するかどうかを確認しましょう。
以下,補足です。(内容が少し重複します。)
改正の趣旨
・ 従来,複数の用途からなる建築物は,火災時の情報共有がなされない場合,避難の著しい遅れにつながることから,用途間の延焼を防止する手段として,準耐火構造の壁・床又は防火扉・防火シャッターで防火区画しなければならない。
・
商業施設において物販店舗と飲食店が混在する場合,一体的に利用する施設にもかかわらず,異種用途間の防火区画が必要となり,設計上の制約となっていると指摘がある。
改正内容 (図解)
複数の用途(A,B)からなる平面イメージ
右図のように用途間の火災情報を共有するため,自動火災報知設備が設置されている場合,異種用途間の防火区画が不要となった。
|
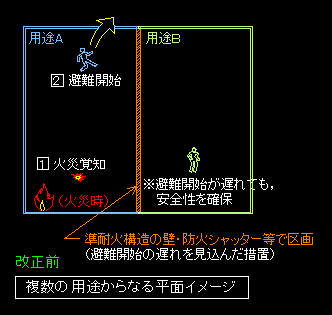
|
改正前
異種用途の間を,準耐火構造の壁・床又は防火扉・防火シャッターで区画する必要がある。
(避難開始の遅れを見込んだ措置)
|
同等の
安全性
←→
|
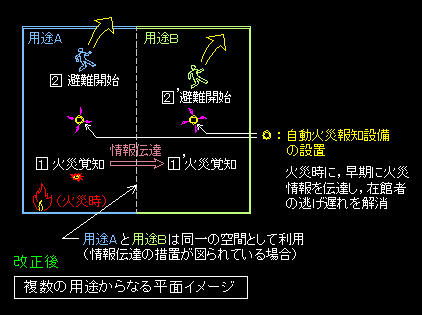
|
改正後
用途Aと用途Bは同ーの空聞として利用。
(情報伝逮の措量が図られている場合)
告示で規定の以下の条件を満たす場合,異種用途間の防火区画を不要とする。
① 隣接する2つの用途部分(※)に自動火災報知設備が設置されていること
② 隣接する2つの用途部分が同一階にあること
※.
隣接する2つの用途部分については,用途に制限があります。
|
4 防火区画を貫通する防火ダンパーの設置について(令112条16項)
換気,空気調和設備のための風道が防火区画を貰通すると,当該風道が火災拡大の原因になる場合がある。これを遮断するための防火措置として,ダンパーの設置が定められている。
(1)ダンパーの位置
(省略)
(2)ダンパーの設置の緩和(S49告示1579号)
(省略)
5 防火区画に用いる防火設備等の煙感知器
(熱煙複合式感知器含む)の設置位置(令112条14項,16項)
(S48告示2563号,2565号)
(省略)
6 その他の防火区画の留意事項
(1)カーテンウォールのスパンドレル
床スラブ等との取り合い部分(取り付け部)については,特に防煙性能を含めた区画の配慮が必要であり,床スラブとカーテンウォールとの間のすき間を耐火性能のある充填材を入れるのが一般的であるが,おさまりによっては施工が難しいこともある。特にガラス張壁の場合は注意を要する。
カーテンウォールのスパンドレル
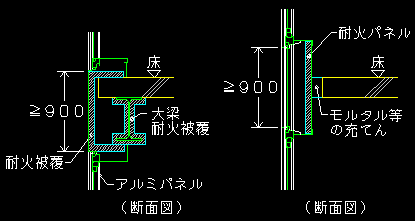
(2)エキスパンション・ジョイント
防火区画の壁・床にはエキスパンション・ジョイントを原則として設けるべきではないが,やむを得ず設ける場合には,以下の工法を参考に。
・ 両面を1.5mm以上の鉄板(ステンレスを含む)で覆い,内部にロックウール等の不燃材料を充填する。
・ 前記以外の工法で既製品を使用する場合については,耐火時聞に応じた耐火性能として評定を受けた以下の工法を参考に。
EXP.J の防火区画参考例
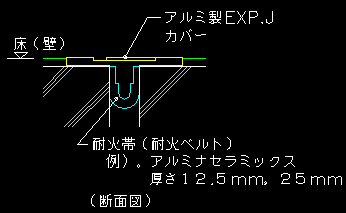
(例 :カネソウ(株)AX22AL‐50G 1時間耐火型(EAJ‐防炎‐4061適合品))
(3)和風便器等が防火区画の床を貫通する場合
和風便器やグリース阻集器が防火区画の床を貫通する場合は,火災の延焼・拡大を防止するため,所要の貫通部措置が必要である。その措置として,和風便器においては「防火区画貫通部60分遮炎性能」を満たすものとして大臣認定されている「和風便器用耐火カバー」が参考になる(二重スラブとする方法もあるが)。
■
003 避難安全検証法の見直しについて (「国土交通省.htm」より抜粋)
第128条の6(新設),第129条,第129条の2
適用除外の各条項
改正の趣旨
・
避難関係規定では,在館者の避難安全性を確保するため,廊下,階段等の避難施設,排煙設備,内装等について具体的な仕様規定が定められている。
・
一方で,こうした仕様規定によらず,自由度の高い設計に対応するため,平成12年に「避難安全検証法」が建築基準法に位置づけられている。
・
避難安全検証法によって安全性が確かめられた場合,建築物の個々の状態に応じて,一部の仕様規定を適用除外(※)とすることができる。
・ 避難安全検証法の位置づけから20年経過し,この間の技術的知見の蓄積を反映する必要がある。
※)除外される規定の例
廊下の幅,直通階段までの距離,排煙設備の設置,内装材料の制限等
改正内容
① 建築物の階の一部(区画部分)についてのみに避難安全検証法を適用できるよう方法を追加する
・現行の検証法は,階全体又は建築物全体のみ適用可能となっている。
・建築物の階の一部(区画部分)のみ安全性を検証するニーズに対応する。
② 在館者が避難に要する時間の計算方法を合理化する
・現行の検証法を位置づけた平成12年当時は,「避難開始時間」「出口までの歩行時間」「出口通過時間」の3要素を同時に進行するものとして計算する方法が確立されていなかった。
・技術的知見の蓄積によって,3要素を一体として計算する方法が確立されたことから手法のーつとして位置づける。
③ 現行の時間による判定法に加え,煙の高さによる判定法を追加する
・現行の判断基準 : 在館者の避難終了時間
<
煙が避難支障のある高さまで降下する時間
・技術的知見の蓄積によって,時間の経過に応じた煙の発生量を正確に数式化することが可能となった。
追加する判断基準
: 避難上支障のある煙の高さ
<
在館者の避難終了時の煙高さ
| 避難安全検証法の見直しについて(まとめ) 第128条の6(新設),第129条,第129条の2 適用除外の各条項
|
種類
|
区画避難安全検証法 (第128条の6)
|
階避難安全検証法 (第129条)
|
全館避難安全検証法 (第129条の2)
|
|
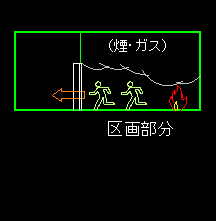
|
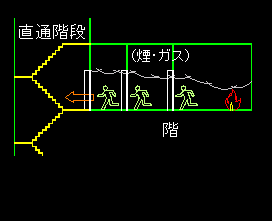
|
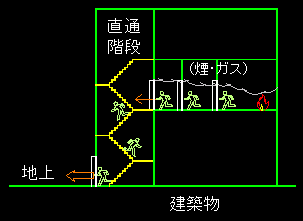
|
| 対象
|
(第1項)
区画部分
(ーの階にある居室その他の建築物の部分であって,準耐火構造の床若しくは壁又は一定の防火設備で区画されたもの)
|
(第1項)
建築物の階
|
(第1項)
建築物全体
|
要性
求能
|
(第2項)
「区画避難安全性能」
当該区画部分のいずれの室で火災が発生した場合においても,当該区画部分から当該区画部分以外の部分等までの避難を終了するまでの間,避難上支障がある高さまで煙・ガスが降下しないこと
|
(第2項)
「階避難安全性能」
当該階のいずれの室で火災が発生した場合においても,当該階から直通階段の一までの避難を終了するまでの間,避難上支障がある高さまで煙・ガスが降下しないこと
|
(第3項)
「全館避難安全性能」
当該建築物のいずれの室で火災が発生した場合においても,当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間,避難上支障がある高さまで煙・ガスが降下しないこと
|
検
証
方
法
|
避
難
時
間
判
定
法
|
(第3項第1号)
【 煙降下時間 >
区画避難時間
】
「煙・ガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」
>
「区画避難に必要な時間」
|
(第3項第1号)
【 煙降下時間 >
階避難時間
】
「煙・ガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」
>
「階避難に必要な時間」
|
(第4項第1号)
【 煙降下時間 >
全館避難時間
】
「煙・ガスが階段室又は直上階以上の階に流入する時間」
>
「全館避難に必要な時間」
|
煙
高
さ
判
定
法
|
(第3項第2号)
【 避難上支障ある煙高さ <
避難完了時の煙高さ
】
「避難上支障のある煙・ガスの高さ」 <
「区画避難に必要な時間が経過した時における煙・ガスの高さ」
|
(第3項第2号)
【 避難上支障ある煙高さ <
避難完了時の煙高さ】
「避難上支障のある煙・ガスの高さ」 <
「階避難に必要な時間が経過した時における煙・ガスの高さ」
|
(第4項第2号)
【 避難上支障ある煙高さ <
避難完了時の煙高さ
】
「階段に煙が流入する高さ」・「避難上支障のある煙・ガスの高さ」
<
「全館避難に必要な時間が経過した時当該階又は直上階以上の階の煙・ガスの高さ」
|
避難安全検証関連条文
INDEX
建築基準法施行令第128条の6
建築基準法施行令第129条
建築基準法施行令第129条の2
平成12年建設省告示第1440号
令和2年国土交通省告示第509号
(詳細省略)
令和2年国土交通省告示第510号 (省略)
令和2年国土交通省告示第511号 (省略)
以下,各条文
建築基準法施行令第128条の6
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)
居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第29第9号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(2以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。)のうち、当該区画部分が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第126条の2、第126条の3及び前条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2 前項の「区画避難安全性能」とは、当該区画部分のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この章において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該区画部分に存する者(当該区画部分を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「区画部分に存する者」という。)の全てが当該区画部分から当該区画部分以外の部分等(次の各号に掲げる当該区画部分がある階の区分に応じ、当該各号に定める場所をいう。以下この条において同じ。)までの避難を終了するまでの間、当該区画部分の各居室及び各居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
一 避難階以外の階 当該区画部分以外の部分であつて、直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。次条において同じ。)に通ずるもの
二 避難階 地上又は地上に通ずる当該区画部分以外の部分
3 第1項の「区画避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一 次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを当該区画部分からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ 当該区画部分の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該区画部分の各室の用途及び床面積並びに当該区画部分の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 当該区画部分の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ 当該区画部分の各火災室ごとに、区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間を、当該区画部分の各室及び当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該区画部分の各室等」という。)の用途及び床面積、当該区画部分の各室等の各部分から当該区画部分以外の部分等への出口の一に至る歩行距離並びに当該区画部分の各室等の出口(当該区画部分以外の部分等に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ 当該区画部分の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ヘ 当該区画部分の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二 次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ 当該区画部分の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ 当該区画部分の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ 当該区画部分の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
建築基準法施行令第129条
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第119条、第120条、第123条第3項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第124条第1項第二号、第126条の2、第126条の3並びに第118条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2 前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「階に存する者」という。)の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあつては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段(避難階にあつては、地上。以下この条において同じ。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3 第一項の「階避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ 当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 当該階の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
ニ 当該階の各火災室ごとに、階に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積、当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ホ 当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ヘ 当該階の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ 当該階の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 当該階の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
ハ 当該階の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ 当該階の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
建築基準法施行令第129条の2
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項、第119条、第120条、第123条第1項第一号及び第六号、第2項第二号並びに第3項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第124条第1項、第125条第1項及び第3項、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2 全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第123条第1項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
3 第1項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(次項第一号ロにおいて「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
4 第1項の「全館避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
一 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法
イ 各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項第一号に定めるところにより確かめること。
ロ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、当該建築物の各室の用途及び床面積、当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ 当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した時間が、ハの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
二 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
イ 各階が、前条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項第二号に定めるところにより確かめること。
ロ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、前号ロの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの階段の部分及び当該階の直上階以上の各階における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
平成12年建設省告示第1440号
(火災の発生のおそれの少ない室を定める件)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2第2項の規定に基づき、火災の発生のおそれの少ない室を次のように定める。建築基準法施行令第129条第2項の規定する火災の発生のおそれの少ない室は、次の各号のいずれかに該当するもので、壁及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを同法令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしたものとする。
一 昇降機その他の建築設備の機械室、不燃性の物品を保管する室その他これらに類するもの
二 廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するもの
令和2年国土交通省告示第509号 (詳細省略)
(区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の6第3項第一号イ、ロ、ニ及びホの規定に基づき、区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を次のように定める。
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第128条の6第3項第一号に規定する方法を用いる場合における同号イに規定する当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下「在室者」という。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
イ 次の式によって計算した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(以下「居室避難開始時間」という。)
(単位 分)
以下,省略
(複雑でややっこしい計算式が登場します。)
・
・
・
防火上主要な間仕切り
■ bm_001 114条区画 (2006H)/(2007W)
おさらい
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」について
構造耐力上主要な部分とは,建築物の構造耐力の安全確保の面から規制するために指定された部分をいい,主要構造部とは,防火上の観点から主要な役割を果たす部分を指している。
防火上主要な間仕切壁の範囲と構造 (令第114条 (,法第36条))
防火上主要な間仕切壁等は,小屋裏や天井裏を通じて火災が延焼拡大することを防ぐために設ける区画壁である。
|
令114条区画 |
| 用途等 |
建物の部分 |
構造 |
防火上の措置等 |
1項
長屋・共同往宅
|
各戸の界壁(※2) |
準耐火構造
|
・
小屋裏,天井裏をすき間なくふさぐこと
・
界壁等を貫通する配管,ダクトは防火区画と同等の措置をすること |
2項
学校・病院・診療所・児童福祉施設等・ホテル・旅館・下宿・寄宿舎・マーケット |
防火上主要な間仕切壁
(※3) |
3項
建築面積が300㎡を超える建物(※1)
(小屋組木造) |
小屋裏隔壁
(けた行間隔12m以内ごと) |
4項
延べ面積が各々200㎡を超える建築物の渡り廊下(小屋組木造)(けた行>4m)
|
渡り廊下の小屋裏隔壁 |
※1).3項については,次の要件のいずれかに該当する建築物は小屋裏隔壁が不要。
・
建築物の各室及び各通路について,壁・天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料・準不燃材料・難燃材料とされ,又はスプリンクラー設備等で自動式のもの及び排煙設備を設けたもの
・
周辺地域が農業に利用され,避難上及び延焼防止上支障がないものとして大臣が定める基準に適合する畜舎等
・ 主要構造部を耐火構造とした建築物
※2).1項の各戸の界壁の範囲と構造について
各戸の界壁とは,住戸間の壁を指し,住戸と廊下の境の壁は該当しない。ただし,中廊下式の共同住宅における廊下部分の小屋裏については,住戸間の延焼防止のため,各戸の界壁と同様の措置とする。なお,各戸の界壁は防火上重要なので,耐火建築物にあっては耐火構造,準耐火建築物にあっては準耐火構造としなければならない。
なお,共同住宅と長屋の各戸の界壁は,以下の遮音構造もあわせて必妻となるので注意が必要。
【遮音性能】
関連条文:法30条,令22条の3
長屋又は共同住宅の界壁について遮音性能が規定されました。
遮音性能とは「隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要と
される性能」ときちんと定義されました。また,令22条の3では従来は建設大臣が各振動数に対しての透過損失の
数値以上と認めて指定していたのを,はっきりこれらの数値以上であればいいと規定しています。(つまり数値さえ
満たしていれば、建設大臣の認定はいらなくなったわけです。)
| 振動数(Hz)
|
透過損失(db)
|
| 125
|
25
|
| 500
|
40
|
| 2000
|
50
|
※3).2項の防火上主要な間仕切壁の範囲及び構造について
火災時に人々が安全に避難できること(避難経路の確保),小屋裏や天井裏を通じての火災の急激な拡大を抑えること等を目的に一定単位ごとの区画及び避難経路とその他の部分との区画をするものであり,範囲は次のとおりとする。
改正法
寄宿舎等における間仕切壁の防火対策の規制の合理化 (令112条2項,114条2項) (「国土交通省.htm」より抜粋)
公布 :平成26年6月4日 施行日 :26年8月の予定
以下,国土交通省PDFより
○背景 ※「グループホーム」や「貸しルーム」は,建築基準法令上「寄宿舎」に該当。
・昨年2月の長崎市における認知症高齢者グループホーム火災(死者5名)を契機とし,「認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会」が消防庁に設置され,国土交通省も参加。
・そこでの議論を踏まえ,消防庁において消防法令を見直し,認知症高齢者グループホーム等の高齢者施設について原則全てにスプリンクラーの設置を義務付け(平成25年12月27日公布,平成27年4月1日施行)。その議論の中で「スプリンクラー設備を設けた場合には,建築基準法の防火規制を合理化すべきではないか」と指摘されたところ。
・これを受け,スプリンクラー設備を設けた場合や小規模で避難が極めて容易な構造とする場合について,防火対策の規制の合理化を検討。
※グループホームや貸しルームについては,住宅からの転用を容易にするため,従来より防火規制の緩和の要望があったところ。
○現行と合理化の内容
建築物の利用者の避難上の安全性が十分に確保される場合(スプリンクラー設備を設けた場合や小規模で避難が極めて容易な構造とする場合)に,寄宿舎等における間仕切壁の防火対策の規制を適用除外とする。
| 規定 |
規定内容 |
| 住宅 |
舎宿舎等
(現行) |
舎宿舎等
(見直し後) |
防火上主要な間仕切壁
(令第112条第2項,
令第114条第2項) |
適用外 |
居室と廊下の間や一定規模毎の居室間の壁等を防火性能の高いもの(準耐火構造)とし,小屋裏又は天井裏に達せしめること
|
以下のいずれかの場合は,間仕切壁の防火対策を適用除外とする。
・
床面積200㎡以下の階又は床面積200㎡以内毎に準耐火構造の壁等で区画した部分に,スプリンクラー設備を設けた場合
・
小規模(※1)で,各居室に煙感知式の住宅用防災機器又は自動火災報知設備が設けられ,①又は②のいずれかに適合する場合
①
各居室の出口から屋外,避難上有効なバルコニー又は100㎡以内毎の他の区画(屋外及び避難上有効なバルコニーは,幅員50cm以上の通路その他の空地に面するものに限る。以下「屋外等」という。)に,歩行距離8m(内装不燃化の場合は16m)以内で避難でき,かつ,各居室と避難経路とが壁及び常時閉鎖式の戸等で区画されているものであること
②
各居室から直接屋外等に避難ができるものであること
※1
居室の床面積の合計が100㎡以下の階又は居室の床面積の合計100㎡以内毎に準耐火構造の壁等で区画した部分 |
以下,国土交通省PDFより
(参考)準耐火構造の防火上主要な間仕切壁を設けないことに関して防火上支障がない部分を定める件等に関するパブリックコメントの募集について(1/2)
意見募集期間
:平成26年6月17日(火)~平成26年7月16日(水)
平成26年6月住宅局
準耐火構造の防火上主要な間仕切壁を設けないことに関して防火上支障がない部分を定める件等について(概要)
1.背景
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第2項及び第114条第2項においては,一定の建築物の防火上主要な間仕切壁は準耐火構造とするよう求めているところ。
今般,建築基準法施行令の一部改正(平成26年政令第○○○号)により,防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁については,準耐火構造としなくてもよいこととされたことから,当該部分を本告示で定める。
2.概要
準耐火構造の防火上主要な間仕切壁を設けないことに関して防火上支障がない部分として,次の①から③までに適合するものを定める。
①
居室の床面積の合計が100㎡以下の階又は居室の床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されている部分であること。
②
各居室に煙感知式の住宅用防災機器又は自動火災報知設備が設けられていること。
③ 次のア)又はイ)に該当する部分であること。
ア) 各居室の出口から屋外,避難上有効なバルコニー又は100㎡以内ごとの他の区画(屋外及び避難上有効なバルコニーにあっては,道又は道に通ずる幅員50cm以上の通路その他の空地に面するものに限る。以下「屋外等」という。)に歩行距離8m(居室及び避難経路の内装が不燃化されている場合には16m)以内で避難でき,かつ,各居室と避難経路とが壁及び常時閉鎖式の戸又は火災発生時に自動的に閉鎖する戸で区画されているものであること。
イ)
各居室から直接屋外等に避難ができるものであること。
また,本改正に伴い,建築基準法施行規則について,確認申請書として提出する図書に関して所要の改正を行う。
3.今後のスケジュール(予定)
公布 :平成26年8月上旬
施行 :公布の日
(参考)準耐火構造の防火上主要な間仕切壁を設けないことに関して防火上支障がない部分を定める件等に関するパブリックコメントの募集について(2/2)
○国土交通省告示第 号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第二項及び第百十四条第二項の規定に基づき,準耐火構造の防火上主要な間仕切壁を設けないことに関して防火上支障がない部分を次のように定める。
平成二十六年 月 日
国土交通大臣 太田 昭宏
準耐火構造の防火上主要な間仕切壁を設けないことに関して防火上支障がない部分を定める件
建築基準法施令(第一号において「令」という。)第百十二条第二項及び第百十四条第二項に規定する防火上支障がない部分は,居室の・・・・・・・・(省略)・・・・・・・・。
一 (省略)
二 (省略)
附則
この告示は,公布の日から施行する。
(1)防火上主要な間仕切壁の範囲
(2007W)
イ.学校にあっては,教室等相互を区画する壁及び教室等と避難経路(廊下,階段等)を区画する壁。ただし,教室と廊下を区画する壁で扉等が設けられたものにあっては,不燃材料で造られたパーテイションパネル等(建具を含む)で区画されているものは防火設備(防火戸)を設けた開口部(※4)として取り扱うことができる。
また,教室と廊下を区画する壁の大半が開口部の場合(枠組み及び開口部が不燃材で造られており,開口部と一体形成されたもの)は,当該壁の部分を開口部(※4)として取り扱うことができる。ただし,この場合には廊下の安全区画性能は劣るので,バルコニーを介して水平避難計画などもあわせて検討しておくこと。
また,廊下や間仕切壁に代わる防災避難上の対策がとられたオープンスクールの場合,防火上主要な間仕切壁の設置は不要である。
ロ.病院・診療所・児童福祉施設等,ホテル・旅館,下宿及び寄宿舎にあっては,病室,就寝室等の相互間の壁で,3室以下かつ100㎡以下(100㎡を超える室にあってはこの限りでない。)に区画する壁及び避難経路を区画する壁(※4)。なお,病室や就寝室等以外の室(火災発生の少ない室を除く。)も同様とする。
※4).開口部(開口部なしのフルオープンも含む)の天井裏部分については,114条区画の構造規制を受けるものとする。
ハ.マーケットにあっては,店舗相互問の壁のうち重要なものとする。
ニ.火気使用室とその他の部分を区画する壁とする。
(2)防火上主要な間仕切壁の構造
(令114条2項)
建築物の構造が耐火構造にあっては耐火構造,準耐火構造にあっては準耐火溝造とする。
原則として法第2条第五号の規定による主要構造部として以下のように取り扱うものとする。
| 防火上主要な間仕切壁の構造 |
| 建築物の構造種別 |
間仕切壁の種別 |
| 耐火 |
耐火(耐力壁の時間は位置により,非耐力壁は1時間とする) |
| 準耐火イ-1(法第27条ただし書) |
準耐火(1時間) |
| 準耐火イ-2 |
準耐火(45分) |
| 準耐火ロ-1(外壁耐火) |
準耐火(45分) |
| 準耐火ロ-2(主要構造部不燃) |
準耐火(45分・材料準不燃) |
学校,就寝等に供する法別表第1(い)欄(2)項用途の建築物(第1項に掲げる共同住宅を除く。),不特定多数が利用するマーケット等の建築物にあっては,火災時に建築物内の人々が火災の拡大に先んじて安全に避難できるように,防火上主要な間仕切壁については耐火構造又は準耐火構造とすることを義務づけたものである。なお,これらの間仕切壁については,第1項と同一の趣旨で,小屋裏又は天井裏まですき間なく区画しなければならず,学校における教室と廊下を区画する壁の場合においても小屋裏(天井裏)部分については構造規制を受けるものとする。
また,第1項及び第2項については,令第108条の3第3項の規定による耐火性能検証法により,該当建築物の部分で主要構造部について耐火構造とみなされる場合は本規定を適用する必要はない。
参考).以下,114条区画のLGS壁の例 (及び竪穴及び防火区画のLGS壁の例)
LGS巾65下地強化PB厚12.5+PB9.5両面貼り
(耐火1時間) (耐火:FP060NP-0259)
「目次」へ戻る