�����������cb�Ƃ��āC�̌��W�䗦���Z�o���邱�Ƃ��]�܂����B
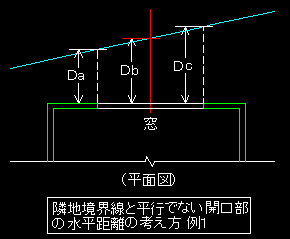

�u���z��@�y�ъ֘A�@����v
�S�y�[�W
��
���R�p�Y�s�s���z�v������ - HOME��
�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�̌��E���C
�u �� ��
�v
�̌�
�� 001�@�����̑��̊J������L���Ȃ��������i�߂P�P�P���C�߂P�P�U���̂Q�i�C�@�Q�W���2���j�j
�@�@�@�@�@�@�@�͂��߂ɁD
�߂P�P�P���̉����ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�����̑��̊J������L���Ȃ��������̂����炢�@�i�߂P�P�P��
�S���j
�@�@�@�@�@�@�@�y�����̑��̊J������L���Ȃ��������z�@�i�߂P�P�U���̂Q
�S���j
�@�@�@�@�@�@�@�Q�l�j�D�y�����̍̌��y�ъ��C�z
�� 002�@�֘A�@�߁i�@�Q�W���C�߂P�X���C�߂Q�O���j
�@�@�@�@�@�@�@�y�����̍̌��y�ъ��C�z�@�i�@��Q�W��
�S���j
�@�@�@�@�@�@�@�y�w�Z�C�a�@�C���������{�ݓ��̋����̍̌��z�@�i�߂P�X��
�S���j
�� 002-2�@���z��@��28���������@
�@�@�@�@�@�@�@�W�{�s�ߑ�19������������Ă��܂��B�{�s����2023�N�S���P���ł��B�@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
�� 003�@�����̍̌��i�y�ъ��C�j�@�i�@�Q�W���C�߂P�X���C�߂Q�O���i�L���ʐς̎Z����@�j�j
�@�@�@�@�@�@�@�P�D�̌���K�v�Ƃ��鋏���ƊJ�����̑傫��
�@�@�@�@�@�@�@�Q�D�߂P�X���R���̢�����T�T�N�P�W�O�O���
�@�@�@�@�@�@�@�R�D�̌���K�v�ȊJ������݂���K�v�̂Ȃ������̈����iH�V�Z�w���P�T�R���ʒB�j
�� 004�@�̌���W���ƍ̌��W��
�@�@�@�@�@�@�@�S�D�̌��Ɋւ���l�����i�@�Q�W���C�߂Q�O���P���j
�@�@�@�@�@�@�@�T�D�̌���W���̒l�����߂���@�i�߂Q�O���Q���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�Z�\
�T���v���t�@�C���_�E�����[�h
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�גn���E���ƕ��s�łȂ��J�����̐��������u�c�v�̍l����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̌��L���ʐς̎Z��^�̌��W�䗦�̋��ߕ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̌��W�䗦�̎Z���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̌��W�䗦�̋��ߕ� ��P�`�R
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̌��W�䗦�̋��ߕ� ��S�`�T
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����~�n���ɍ��w�̌��z���ƒ�w�̌��z��������ꍇ�́u�c�v�C�u�g�v�̂Ƃ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���z���Ɨגn���E���܂ł̐��������ɂ��ɘa
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ꍇ�̍̌���W���̎戵���i��20���2���j
�� 005�@�̌����L�����ǂ���
�@�@�@�@�@�@�@�̌����L�����ǂ���
�@�@�@�@�@�@�@�C���i�[�o���R�j�[�␁�����炵�̘L���ɖʂ���ꍇ
�@�@�@�@�@�@�@�Q���̌��̍l����
�i�@�Q�W���S���C�߂P�P�P���Q���j
�@�@�@�@�@�@�@�Q�����P���̈����̓���@�i
�@�Q�W���S���߂P�P�P���Q���j
�@�@�@�@�@�@�@�̌��ɗL���ȕ����̖ʐς̎Z����@�̊ɘa
�F�Q�����P���̈����@�i
���� �g�P�T�����O�R�O�R���j
���C
�� K001�@�֘A�@��
�@�@�@�@�@�@�@���g�p���鎺�ɐ݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����C�ݔ���
�@�@�@�@�@�@�@��
�䏊���C�ݔ��̐ݒu�Ɋւ���@�K�ɂ��Ă̗����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�r�C�i���C�j�t�[�h�T�^�iN=30�j�y�чU�^�iN=20�j���̑傫���ƍ\���C���ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�� �Q�l�j�D�d���~�[�@����g�p����ꍇ�̗��ӎ���
�i�@28��3���C��20����3�CS45����1826���j
�@�@�@�@�@�@�@�y������L���錚�z���̊��C�ݔ��ɂ��Ẵz�����A���f�q�h�Ɋւ���Z�p�I��z�@�i�ߑ�Q�O���̂W
�����j
�@�@�@�@�@�@�@���C�ݔ��̐ݒu���K�v�ȋ����Ɗ��C�ݔ��̎���@
�@�@�@�@�@�@�@
�̌�
�� 001�@�����̑��̊J������L���Ȃ��������i�߂P�P�P���C�߂P�P�U���̂Q�i�C�@�Q�W���2���j�j
�͂��߂ɁD
�߂P�P�P���̉����ɂ���
�߂P�P�P������������Ă��܂��B�ȉ����Q�Ƃ��Ă��������B
�u�r���E���������E�����K�v�i�ʂ̃E�B���h�E�ŕ\���j
�� �u���������E�����K�v �� �u��
M001�@���������Ɩ����K�ɂ����v
�� �u�߂P�P�P������������Ă��܂��v
���������̑��̊J������L���Ȃ��������̂����炢
�i�߂P�P�U���̂Q�C�i�@�Q�W���2���j�j
�y�����̑��̊J������L���Ȃ��������z
�߂P�P�U���̂Q
�@��35���i�@��87���3���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB����
��1���ɂ����ē����B�j�̋K��ɂ�萭�߂Œ�߂鑋���̑��̊J
������L���Ȃ������́C���̊e���ɊY�����鑋���̑��̊J����
��L���Ȃ������Ƃ���B
��@
�ʐρi��20���̋K����v�Z�����̌��ɗL���ȕ����̖ʐςɌ���B�j�̍��v���C���Y�����̏��ʐς�1/20�ȏ�̂���
��@
�J���ł��镔���i�V�䖔�͓V�䂩�牺��80�p�ȓ��̋���
���镔���Ɍ���B�j�̖ʐς̍��v���C���Y�����̏��ʐς�1/50�ȏ�̂���
2�@
�ӂ��܁C��q���̑������J�����邱�Ƃ��ł�����̂Ŏd��
�ꂽ2���́C�O���̋K��̓K�p�ɂ��ẮC1���Ƃ݂Ȃ��B
�y��116����2�̉���z
�� �ꍆ�����Ȃ����̌���̖��������ƂȂ��B
�� �����Ȃ����r����̖��������ƂȂ��B
�Q�l�j�D
�y�����̍̌��y�ъ��C�z
�@�Q�W���Q��
2�@
�����ɂ͊��C�̂��߂̑����̑��̊J������݂��C���̊��C��
�L���ȕ����̖ʐς́C���̋����̏��ʐςɑ��āC1/20�ȏ�
�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C���߂Œ�߂�Z�p�I��ɏ]��
�Ċ��C�ݔ���݂����ꍇ�ɂ����ẮC���̌���łȂ��B
�y�@28���2���̉���z
�� 2�������Ȃ������C��̖��������ƂȂ��B
�� 002�@�֘A�@�߁i�@�Q�W���C�߂P�X���C�߂Q�O���j
�y�����̍̌��y�ъ��C�z�@�i�@��Q�W��
�S���j
��28���@ �Z��C�w�Z�C�a�@�C�f�Ï��C��h�ɁC���h���̑������ɗނ��錚�z�������߁i�@�j�Œ�߂���̂������i���Z�̂��߂̋����C�w�Z�̋����C�a�@�̕a�����̑������ɗނ�����̂Ƃ��Đ��߁i�A�j�Œ�߂���̂Ɍ���B�j�ɂ́C�̌��̂��߂̑����̑��̊J������݂��C���̍̌��ɗL���ȕ����̖ʐς́C���̋����̏��ʐςɑ��āC�Z���ɂ����Ă�1/7�ȏ�C���̑��̌��z���ɂ����Ă�1/5����1/10�܂ł̊Ԃɂ��������߁i�B�j�Œ�߂銄���ȏ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C�n�K�Ⴕ���͒n���H�앨���ɐ݂��鋏�����̑������ɗނ��鋏�����͉����x������K�v�Ƃ����Ƃ��s����Ǝ����̑��p�r���ނȂ������ɂ��ẮC���̌���łȂ��B
2�@ �����ɂ����C�̂��߂̑����̑��̊J������݂��C���̊��C�ɗL���ȕ����̖ʐς́C���̋����̏��ʐςɑ��āC1/20�ȏ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C���߂Œ�߂�Z�p�I��ɏ]���Ċ��C�ݔ���݂����ꍇ�ɂ����ẮC���̌���łȂ��B
���߁i�@�j �˗߂P�X����P��
�E�E�E�E�E�E�i�ȗ��j
���߁i�A�j �˗߂P�X����Q�� �E�E�E�E�E�E�i�ȗ��j
���߁i�B�j �˗߂P�X����R�� �E�E�E�E�E�E�i�ȗ��j
3�@ �ʕ\��1�i���j���i1�j���Ɍf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���̋������͌��z���̒������C�������̑��̎��ł��܂ǁC����낻�̑����g�p����ݔ��Ⴕ���͊���݂��������i���߁i�@�j�Œ�߂���̂������B�j�ɂ́C���߁i�A�j�Œ�߂�Z�p�I��ɏ]���āC���C�ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���� �˗߂Q�O���̂Q�u���C�ݔ��̋Z�p�I��v
4�@ �ӂ��܁C��q���̑������J�����邱�Ƃ��ł�����̂Ŏd��ꂽ2���́C�O3���̋K��̓K�p�ɂ��ẮC1���Ƃ݂Ȃ��B
���߁i�@�j �˗߂Q�O�̂R�u���g�p���鎺�ɐ݂��Ȃ��ꂪ�Ȃ�Ȃ����C�ݔ��v
���߁i�A�j �˗߂Q�O���̂Q�u���C�ݔ��̋Z�p�I��v
�� ���ӎ���
�]���͑ΏۂƂȂ錚�z���̋����Ƃ����K�肳��Ă����̂ŁC���ׂĂ̋������Ώۂł����B����̉����i�����P�Q�N�U���P���{�s�j�ł͖@28����
�u���Z�̂��߂̋����C�w�Z�̋����C�a�@�̕a���v�Ƌ��������肳��lj�����܂����B��̓I�ɂ͐��߂ŁC�וۊق͍폜
�����L�̋����ȊO�ɁC�u�ۈ珊�̕ۈ玺�C�f�Ï��̕a���C���������{�ݓ��̐Q���v���lj�����Ă��܂��B
���̈Ӑ}�́C�����C����҂Ȃljq����̔z����K�v�Ƃ�����̂������Ԍp���I�Ɏg�p���鎺������Ƃ����Ă��܂��B
�y�w�Z�C�a�@�C���������{�ݓ��̋����̍̌��z�@�i�߂P�X��
�S���j
��19���@
�@��28���1���i�@��87���3���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�ȉ����̏��y�ю����ɂ����ē����B�j�̐��߂Œ�߂錚�z���́C���������{�݁C���Y���C�g�̏�Q�ҎЉ�Q���x���{�݁i����{�y�ю����o��Q�ҏ��{�݂������B�j�C�ی�{�݁i��Õی�{�݂������B�j�C�w�l�ی�{�݁C�V�l�����{�݁C�L���V�l�z�[���C��q�ی��{�݁C��Q�Ҏx���{�݁C�n�抈���x���Z���^�[�C�����z�[�����͏�Q�����T�[�r�X���Ɓi�������C�����P���C�A�J�ڍs�x�����͏A�J�p���x�����s�����ƂɌ���B�j�̗p�ɋ�����{�݁i�ȉ��u���������{�ݓ��v�Ƃ����B�j�Ƃ���B
2�@ �@��28���1���̐��߂Œ�߂鋏���́C���Ɍf������̂Ƃ���B
��@ �ۈ珊�̕ۈ玺
��@ �f�Ï��̕a��
�O�@ ���������{�ݓ��̐Q���i��������҂̎g�p������̂Ɍ���B�j
�l�@
���������{�ݓ��i�ۈ珊�������B�j�̋����̂��������ɓ������C���͒ʂ��҂ɑ���ۈ�C�P���C���퐶���ɕK�v�ȕX�̋��^���̑������ɗނ���ړI�̂��߂Ɏg�p��������
�܁@ �a�@�C�f�Ï��y�ю��������{�ݓ��̋����̂������@���Җ��͓�������҂̒k�b�C��y���̑������ɗނ���ړI�̂��߂Ɏg�p��������
3�@
�@��28���1���ɋK�肷��w�Z���ɂ����鋏���̑����̑��̊J�����ō̌��ɗL���ȕ����̖ʐς̂��̏��ʐςɑ��銄���́C���ꂼ�ꎟ�̕\�Ɍf���銄���ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�������C���\�́i1�j����i5�j�܂łɌf���鋏���ŁC���y��ʑ�b����߂��ɏ]���C�Ɩ��ݔ��̐ݒu�C�L���ȍ̌����@�̊m�ۂ��̑������ɏ�����[�u���u�����Ă�����̂ɂ����ẮC���ꂼ�ꓯ�\�Ɍf���銄������1/10�܂ł͈͓̔��ɂ����č��y��ʑ�b���ʂɒ�߂銄���ȏ�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
���y��ʑ�b����߂� ��
����55�N 1800�� �u�Ɩ��ݔ��̐ݒu�C�L���ȍ̌����@�̊m�ۂ��̑�������
... �v
�i�\�ȗ��j
�� 002-2�@���z��@��28��������
�i�ȉ��C�����O�i2022�N12��18���j�̏��ł��B�ŐV�̏������m�F�肢�܂��B�j
�W�{�s�ߑ�19������������Ă��܂��B�{�s����2023�N�S���P���ł��B�@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
2022�N6���Ɂu�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���v�����z����܂����B2022�N11��11���Ɏ{�s�������߂鐭�߂�K�v�ȋK��̐������s�Ȃ����߂��t�c���肳��܂����B
���̒��ɁC�u�̌��K���v�̍������̖@����������܂�
�̌��W�̉������w�i
�Ɩ��ݔ����̔��W�ɔ����C���\�N�O�ɔ�ׂ�Ίi�i�ɏZ��������ɂ�����K�v�Ȗ��邳�m�ۂ��e�Չ�����Ă��邱�Ƃɂ���悤�ł��B
�y 2023�N4��1���Ɏ{�s�����u�Z��̋����ɕK�v�ȍ̌���L���ȊJ�����ʐςɊւ���K���̍������v�T�v
�z
�u�Z��̋����ɕK�v�ȍ̌���L���ȑ����̖ʐς́C�����Ƃ��Ă͂��̋����̏��ʐς�1/7�ȏ�B
�A���C�Ɩ��ݔ��̐ݒu��L���ȍ̌����@���m�ۂ���[�u���Ȃ���Ă���ꍇ�́C���̋����̏��ʐς�1/10�܂ł͈͓̔��Ƃ���B�v
�y ���z��@��28 ��������
�z
��28���@�Z��C�w�Z�C�a�@�C�f�Ï��C��h�ɁC���h���̑������ɗނ��錚�z���Ő��߂Œ�߂���̂̋���(���Z�̂��߂̋����C�w�Z�̋����C�a�@�̕a�����̑������ɗނ�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂Ɍ���B)�ɂ́C�̌��̂��߂̑����̑��̊J������݂��C���̍̌��ɗL���ȕ����̖ʐς́C���̋����̏��ʐςɑ��āC5����1����10����1�܂ł̊Ԃɂ����������̎�ނɉ������߂Œ�߂銄���ȏ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C�n�K�Ⴕ���͒n���H�앨���ɐ݂��鋏�����̑������ɗނ��鋏�����͉����x������K�v�Ƃ����Ƃ��s����Ǝ����̑��p�r���ނȂ������ɂ��ẮC���̌���łȂ��B
�@
��
�������ł͌��z��@��28���̒��i�ɁC���s�@�́u�c�C�Z��ɂ��Ă͂V���̂P�ȏセ�̑��̌��z���ɂ��Ắc�v�Ƃ����������ύX����C�u�����̎�ނɉ����v�i���߂܂�C���z��@�{�s�߂Œ�߂銄���ȏ�j�Ƃ����������������܂��B
���z��@�{�s��19���́C���s�@�ł́u�w�Z�C�a�@�C���������{�ݓ��̋����̍̌��v�̋K��ł������C�����Ăł��u�����̍̌��v�ɕύX����܂��B
�Ӑ}�Ƃ��ẮC���\���ɂ��ƁC�u�̌��K��ɂ����C�L���Ȗ��邳�̊m�ۂ̑[�u���s���邱�Ƃ�O����C�Z��̋����ɕK�v�ȍ̌���L���ȊJ�����ʐςɊւ���K���������������B�v�Ə�����Ă���C�܂�C���݂̖@��28���̋K��ɂ��̌��K�肪�K�p������Z�����a�@�C�w�Z�Ƃ��������z���́g�̌���L���ȊJ�����ʐρh�ɂ��āC�u�Ɩ��v�ɂ���ďƓx���m�ۂ������C�ɘa����܂��B
�܂��C���̂悤�ɏ�����Ă��܂��B
���ۈ珊�̕ۈ玺���̎��Ԃɉ������̌��̑�֑[�u�̍�����
�ۈ珊�����w�Z���̏ꍇ�ƋL�ڂ�����܂����C���\���Ɂu�Z���v�Ə�����Ă���悤���Z����ΏۂɂȂ�܂��B
�̌��v�Z�̊m�ۂɊւ��āC�Ɠx���i������̍����̈ʒu�j�ɂ�����200���N�X�ilx�j�ȏ���m�ۂł�����C���݂�1/5��1/7�Ɋɘa���邱�Ƃ��ł����Ə�����Ă���̂ŁC���݂̏Z���1/7�ł������C1/10�܂Ŋɘa�����悤�ɂȂ�܂��B
���z��@�{�s��19���3���̉����_
���s�@�ł́C�����̎�ނƗL���̌��ʐς̊����ɂ͏Z��L�ڂ���Ă��܂���ł������C�u�Z��̋��Z�̂��߂̋����v�Ƃ��ċL�ڂ���Ă��܂��B�Z��̋��Z�̂��߂̋����̍̌���L���ȑ����̖ʐς͂��̋����̏��ʐς�1/7�ȏ�ƕ\�Ɏ�����Ă��܂����C���̌�̕��͈͂ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�y �@�߂̊T�v�� �z
�u���y��ʑ�b����߂��i�����ɋK��j�ɏ]���Ɩ��ݔ��̐ݒu�C�L���ȍ̌����@�̊m�ۂ��̑�����ɏ�����[�u���u�����Ă�����̂ɂ����ẮC���ʐς�1/7�ȏォ��1/10�܂ł͈͓̔��ō��y��ʑ�b���ʂɒ�߂銄���Ƃ���B�v
��
�Z��̋�����
�y�����Ă̊T�v�z
�@ �Z��̋��Z�̂��߂̋����ɂ�����Ɩ��ݔ��̐ݒu�C�L���ȍ̌����@�̊m�ۂ��̑������ɏ�����[�u�̊�ɂ��ẮC�u���ʂɂ�����50���b�N�X�ȏ�̏Ɠx���m�����邱�Ƃ��ł���悤�Ɩ��ݔ���ݒu���邱�Ɓv�Ƃ���B
�A �@�̑[�u���u�����Ă��鋏���ɂ����ẮC�����̑��̊J�����ō̌��ɗL���ȕ���
�̖ʐς̂��̏��ʐςɑ��銄���ō��y��ʑ�b���ʂɒ�߂���̂��u�P/10�v�Ƃ���B
�i
�o�T�F���y��ʏȁu�Ɩ��ݔ��̐ݒu�C�L���ȍ̌����@�̊m�ۂ��̑������ɏ�����[�u�̊����
��߂錏�̈ꕔ���������鍐���Ăɂ��āi�T�v�j�v�i�Z��nj��z�w���ہj�������j
�j
�Q�l�j�D�גn�Ƃ̋��������܂��č̌����m�ۂ��Â炢���̗L�����p���}����ł��傤�B
�Q�l�j�D�����X�g�b�N���p�̃j�[�Y�̑��l��
��������������X�g�b�N���C�ǂ����p����̂��Ƃ�����肪����܂��B�R���i�����ǂ̉e���ŋƖ��`�Ԃ��ω����C�������r������P�ނ����Ƃ�z�e���̔p�Ƃ̓����Ȃǂ�����C�������r����z�e���Ȃǂ��Z��ɗp�r�ύX���Ċ��p����j�[�Y���o�Ă��܂��B�������C���s�@�Ŏ������͍̌��K�肪�Ȃ��C�z�e���ɂ����Ă����s�@�̏Z��̍̌��K��Ƃ͈قȂ邽�߁C�Z��ɗp�r�ύX����ꍇ�́C�J�������L�����邩���݂�����K�v������C����������P�[�X����������܂��B������2023�N4���̖@�����ɂ��C�Z��̋����ւ̗p�r�ύX�����₷���Ȃ�܂��B
�܂���ʂ̏Z��̃��t�H�[���ɂ����Ă��C�����[�g���[�N�̕K�v�����瑋�̏��Ȃ����[�����Ȃǂ����ցi�����j�ɂ��邱�Ƃ��\�ɂȂ�C���t�H�[���H���̑��l���ɂ��q����܂��B
�� 003�@�����̍̌��i�y�ъ��C�j�@�i�@�Q�W���C�߂P�X���C�߂Q�O���i�L���ʐς̎Z����@�j�j
�P�D�̌���K�v�Ƃ��鋏���ƊJ�����̑傫��
�i�n�K���ɐ݂��鋏���C�Î��ȂǗp�r���ނȂ��������͏������i�@�Q�W�����P�����������j�B�j
| ���z�������� | ���� | |
| �| | �Z��������i���Z�̂��߂Ɏg�p�������́j | �P�^�V |
| �i�P�j | �c�t���C���w�Z�C���w�Z�C�����w�Z�C��������w�Z������ | �P�^�T �i���Q�j |
| �i�Q�j | �ۈ珊���ۈ玺 | |
| �i�R�j | �a�@�E�f�����a�� | �P�^�V |
| �i�S�j | ��h�Ɂi�Ɛg���j���Q���C���h���h���� | |
| �i�T�j | ���������{�ݓ��i��1�j���Q���i�����҂��g�p������̂Ɍ���j | |
| ���������{�ݓ��i�ۈ珊�����j�̋����̂����C�����ҁE�ʏ��҂ɑ����ۈ玺�C�P�����C���퐶���ɕK�v�ȕ�̋��^���̖ړI�̂��߂Ɏg�p�������� | ||
| �i�U�j | �i�P�j�̊w�Z�ȊO�̊w�Z������ | �P�^�P�O |
| �i�V�j | �a�@�E�f�Ï��E���������{�ݓ��̋����̂����C���@���ҁE�����҂��k�b���C��y�����̖ړI�̂��߂Ɏg�p�������� | |
��1�D���������{�ݓ��Ƃ�
���������{�݁C���Y���C�g�̏�Q�ҍX������{��(����{�ݥ�����o��Q�ҏ��{�݂�����)�C���_��Q�ҎЉ�A�{�݁C�ی�{��(��Õی�{�݂�����)�C�w�l�ی�{�݁C�m�I��Q�҉���{�݁C�V�l�����{�݁C�L���V�l�z�[���C��q�ی��{�݂������B
���Q�D�ȉ��u�Q�D�v�́u����55�N1800���v�Q��
���Ӂj�D
�]���C��\�̌��z�����Ώۋ����ȊO�̋�����1/10�ȏオ�v������Ă������C�����P�Q�N�̉������z��@�{�s�߂ɂ��Ώۋ����݂̂Ɍ��肳��܂����B
�Q�D�߂P�X���R���́u����55�N1800���v�@�i�ŏI�����@����12�N12��26���@���ݏȍ�����2465���j
�u�Ɩ��ݔ��̐ݒu�C�L���ȍ̌����@�̊m�ۂ��̑������ɏ�����[�u�̊�����߂錏�v
���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��19���3�����������̋K��Ɋ�Â��C�Ɩ��ݔ��̐ݒu�C�L���ȍ̌����@�̊m�ۂ��̑������ɏ�����[�u�̊�y�ы����̑����̑��̊J�����ō̌��ɗL���ȕ����̖ʐς̂��̏��ʐςɑ��銄���ŕʂɒ�߂���̂����̂悤�ɒ�߂�B
��1�@ �Ɩ��ݔ��̐ݒu�C�L���ȍ̌����@�̊m�ۂ��̑������ɏ�����[�u�̊
���@
�c�t���C���w�Z�C���w�Z�C�����w�Z�Ⴕ���͒�������w�Z�̋������͕ۈ珊�̕ۈ玺�ɂ����ẮC���̃C�y�у��ɒ�߂���̂Ƃ���B
�C�@���ʂ���̍�����50�p�̐����ʂɂ�����200lx�i���N�X�j�ȏ�̏Ɠx���m�ۂ��邱�Ƃ��ł���悤�Ɩ��ݔ���ݒu���邱�ƁB
���@�����̑��̊J�����ō̌��ɗL���ȕ����̂������ʂ���̍�����50�p�ȏ�̕����̖ʐς��C���Y�������͕ۈ玺�̏��ʐς�1/7�ȏ��ł��邱�ƁB
���@
���w�Z�C���w�Z�C�����w�Z���͒�������w�Z�����y�������͎����o�����i���P�j�Ō��z��@�{�s�ߑ�20����2�ɋK�肷��Z�p�I��ɓK���������C�ݔ����݂���ꂽ�����ɂ����ẮC�O���C�ɒ�߂���̂Ƃ���B
�i���P�D�i��j���i�C�j�̏Ɩ��ݔ���݂��邱�Ɓj
��2�@
�����̑��̊J�����ō̌��ɗL���ȕ����̖ʐς̂��̏��ʐςɑ��銄���ō��y��ʑ�b���ʂɒ�߂����
���@
��1��ꍆ�ɒ�߂�[�u���u�����Ă��鋏���ɂ����ẮC1/7�Ƃ���B
���@
��1��ɒ�߂�[�u���u�����Ă��鋏���ɂ����ẮC1/10�Ƃ���B
�R�D�̌���K�v�ȊJ������݂���K�v�̂Ȃ������̈����iH�V�Z�w���P�T�R���ʒB�j
���L�ɊY�����鋏���́C�@�Q�W���P�������������ɋK�肷�颉����x������K�v�Ƃ����Ƃ��s����Ǝ����̑��p�r���ނȂ�������Ƃ��Ĉ����C�̌��̂��߂̑����̑��̊J������݂���K�v���Ȃ��
�i�P�j�D�����x������K�v�Ƃ����Ƃ��s����Ǝ�
�@�D��w�C�a�@���̎������C�������C���ܓ������x������K�v�Ƃ�������C�����C���ܓ����s������
������w�Z�C���Z�̐��k�p�������������
�A�D��p��
�B�D�G�b�N�X���B�e���������@��ɂ�錟���C���Ó����s������
�C�D�����ȉ����x������v���鎡�Î��C�V��������
�i�Q�j�D���̑��g�p�r���ނȂ�����
����1�i�J������݂��邱�Ƃ��p�r��]�܂����Ȃ������j
�@�D�剹�ʂ̔������̑�������̗��R����h���w�u���u���邱�Ƃ��]�܂�������
�A�D�Z��̉��y���K���C���X�j���O���[����
�Չ���ςݏd�˂���������݂��铙�Չ��\���ł��邱�ƕ��тɓ��Y�Z��̎����y�я��ʐς����Ă��C�t���I�ȋ����ł��邱�Ƃ����炩�Ȃ��̂Ɍ���B
�C�D������
�X�^�W�I�C�@�B���C�O�����ō\���������̂������
�E�D���o���������O������̐k����������f�@�C�������̏�Q�ƂȂ鋏��
�A�D�Î��C�v���l�^��E���������C�f�ʓ����s�����ߎ��R�̌���h���K�v�̂��鋏��
������w�Z�C���Z�̎����o�����������
�B�D��w�C�a�@���̎������C�������C���Ŏ��C�N���[�����[�������ː��������̊댯������舵�����߁C���͈�`�q��������C�a���ۂ̎戵���C���ۍ�ƁC����Ȋ��̉��ł̌����C���Ó����s����ōێႵ���͂ق���̐N����h�����߁C�J�����̖ʐς��ŏ����Ƃ��邱�Ƃ��]�܂�������
�C�D���R�̌������ÁC�������̏�Q�ƂȂ鋏��
�A�D��Ȃ̐f�Î��C�����������R������Q�ƂȂ�@����g�p���鋏��
�C�D���Ȗ��͎��@��A�Ȃ̐f�Î��C���������l�H�Ɩ��ɂ��f�@�C���������s������
�i�R�j�D���̑��g�p�r���ނȂ�����
����2�i�����N�ҁC��a�ҁC�D�Y�w�C��Q�ҁC����ғ��ȊO�̎҂���痘�p���鋏���Ŗ@�I�ɍ̌���v���Ȃ������ɗނ���p�r�ɋ�������́j
�@�D�������i�I�t�B�X�I�[�g���[�V���������܂ށj�C��c���C���ڎ��C�E�����C�Z�����C�@�����C�Ō�w�l���i�i�[�X�X�e�[�V�����j�����������̑��������s�������ɗނ���p�r�ɋ����鋏��
�A�D�������C����������H�X���̐~�[�C���������̈�������̑���Ƃ��s�������ɗނ���p�r�ɋ����鋏��
�Z��̒������ŐH�����ƌ��p�������̂������B
�B�D����y�ьŒ肳�ꂽ�q����L���C�����C�s���葽���̎҂����p����p�r�ɋ�����u��������C���|��C�ϗ���C����C�W��ꓙ�ɗނ���p�r�ɋ����鋏��
�C�D�Ǘ��������C��q���C��t���C�h�����C���������������̊Ǘ����ɗނ���p�r�ɋ����鋏��
�D�D���X�����i�̔��Ƃ��c�ޓX�܂̔���ɗނ���p�r�ɋ����鋏��
�� 004�@�̌���W���ƍ̌��W�䗦
�S�D�̌��Ɋւ���l�����i�@�Q�W���C�߂Q�O���P���j
��{
�Z��Ȃǂ̋����̊J�����́C�u�����̏��ʐρv�ɑ��āu�p�r���Ƃ̊����v�ȏ�̍̌��L���ʐςłȂ���Ȃ�Ȃ��i�@28���j
�J�����̍̌��L���ʐς́C�u�����̊J�������Ƃ̖ʐρv�Ɂu�̌���W���v���悶�ē����ʐς����v���ĎZ�肷��i��20���j
�J�����̍̌��L���ʐρ������̏��ʐρ~�p�r���Ƃ̊���
�J�����̍̌��L���ʐρF�i�����̊J�������Ƃ̖ʐρ~�̌���W���j�̍��v
�p�r���Ƃ̊����F�P�^�T�`�P�^�P�O
��O�P
�n�K�������͒n���H�앨�ɐ݂��鋏�����܂��͉����x������K�v�Ƃ����Ǝ����͏����i�@28��{�����������j
��O�Q
�ӂ��܁C��q���̐����J���ł�����̂Ŏd��ꂽ�Q���́C�P���Ƃ݂Ȃ��i�@28��4���j
��O�R
���ݑ�b���ʂɎZ����@���߂����z���̊J�����ɂ��ẮC���̎Z����@�ɂ��i��20��1�����������u����������v�j
�T�D�̌���W���̒l�����߂���@�i�߂Q�O���Q���j�@�@�i�@�v�Z�\
�T���v���t�@�C���_�E�����[�h
�i�����E�B���h�E�ňړ��j�@�j
| �n��E�n�� | �̌���W�� | ||||
| �Z�莮 | �Z�莮�̗�O �i�߂Q�O���e���C�`�n�j |
��O�P �i�߂Q�O���Q�� �{�����������j |
��O�Q �i�߂Q�O���Q�� �{�����������j |
||
| �@ | �����w�Z����p�n�� �����w�Z����p�n�� ���풆���w�Z����p�n�� ���풆���w�Z����p�n�� ����Z���n�� ����Z���n�� ���Z���n�� |
�c/�g�~�U�|�P.�S | �C�@�J���������ɖʂ���ꍇ�ŁC�Z��l��1.0�����ƂȂ�ꍇ�F1.0 ���@�J���������ɖʂ��Ȃ��ꍇ�ŁC����������7m�ȏ��ŁC���C�Z��l��1.0�����ƂȂ�ꍇ�F1.0 �n�@�J���������ɖʂ��Ȃ��ꍇ�ŁC����������7m�����ŁC���C�Z��l�������ƂȂ�ꍇ�F0 |
�V���̏ꍇ�F �Z��l�~3 �O���ɕ�90cm�ȏ�̉����i�G�ꉏ�������j��������J�����̏ꍇ�F �Z��l�~0.7 |
�̌���W����3.0���̏ꍇ�F 3.0 |
| �A | ���H�ƒn�� �H�ƒn�� �H�Ɛ�p�n�� |
�c/�g�~�W�|�P | �C�@�J���������ɖʂ���ꍇ�ŁC�Z��l��1.0�����ƂȂ�ꍇ�F1.0 ���@�J���������ɖʂ��Ȃ��ꍇ�ŁC����������5m�ȏ��ŁC���C�Z��l��1.0�����ƂȂ�ꍇ�F1.0 �n�@�J���������ɖʂ��Ȃ��ꍇ�ŁC����������5m�����ŁC���C�Z��l�������ƂȂ�ꍇ�F0 |
||
| �B | �ߗ��ƒn�� ���ƒn�� �p�r�n��̎w��̂Ȃ���� |
�c/�g�~�P�O�|�P | �C�@�J���������ɖʂ���ꍇ�ŁC�Z��l��1.0�����ƂȂ�ꍇ�F1.0 ���@�J���������ɖʂ��Ȃ��ꍇ�ŁC����������4m�ȏ��ŁC���C�Z��l��1.0�����ƂȂ�ꍇ�F1.0 �n�@�J���������ɖʂ��Ȃ��ꍇ�ŁC����������4m�����ŁC���C�Z��l�������ƂȂ�ꍇ�F0 |
||
| �c/�g
�F���̐��l�̂����ł����������l�i�̌��W�䗦�j �c �F���������i�J�����̒���ɂ��錚�z���̕����ƁC�גn���E���܂��͓���~�n���̑��̌��z���������͓��Y���z���̑��̕����܂ł̐��������j �g �F���������i�J�����̒���ɂ��錚�z���̕�������J�����̒��S�܂ł̐��������j ��O1�F�J�������C���i�s�s�v������ł͖@42���ɋK�肷�铹�H�j�ɖʂ���ꍇ�C�גn���E���͂��̓��̔��Α��̋��E���Ƃ���i��20��2���{�����������j ��O2�F�������̋�n�܂��͐��ʂɖʂ���ꍇ�C�גn���E���͂��̋�n�܂��͐��ʂ̕���1/2�����גn���E���̊O���ɂ�����Ƃ���i���j |
|||||
�̌��̉����@
�� �Z����@�́C��̌��W�䗦��ɉ�������̌���W������Z�肵�C������J�����̖ʐςɏ悶�āC�̌���L���ȊJ�����̖ʐς����߂�����ɉ��������B�܂����ݑ�b���ʂɒ�߂�Z����@�ɂ�邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ����i�߂Q�O���P���j�B
�� ��̌��W�䗦��́C�J�����̒���ɂ��錚�z���̕�������גn���E�����܂ł̋����i�c�F���������j���C���̕�������J�����̒��S�܂ł̋����i�g�F���������j�ŏ��������l�̂����ł����������l�ł���B�Ȃ����������́C������́C��J�����̒��S�܂ł̋�����ƂȂ��Ă���B
�T���v���t�@�C���_�E�����[�h�@�i���̃t���[���́u�@�K�֘A�����̃_�E�����[�h�v���j
a1_150_houki_check_saikou_etc.dwg�@�@���� ��
README�@�@�@�\��
�FDWF�@HTM�@
�i�ʃE�B���h�E�ŕ\���j�@
�@�K�`�F�b�N�}�@�r��_�̌�_���C�v�Z�\
�i��j
�\�FExcel�����N�\�� �i.ver 2002�j
�r���J���f�ʃ^�C�v�\
�F�]������X�^�C���t�@�C���i.ctb�j
�_�E�����[�h �FT_office_monochrome.ctb�@�@README
�גn���E���ƕ��s�łȂ��J�����̐��������u�c�v�̍l����
�i1995K �j
| ���z�I�Ȕ��z�ɂ��Ƃ��
�i�����炪��ʓI�j �����������cb�Ƃ��āC�̌��W�䗦���Z�o���邱�Ƃ��]�܂����B |
�Q�l�j�D���@�Q�R�S���Ɋւ��閯�@�̉�����ɂ��Ƃ�� |
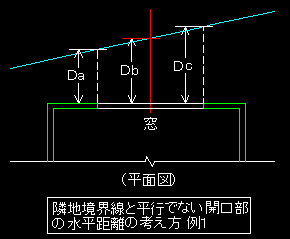 |
 |
�̌��L���ʐς̎Z��^�̌��W�䗦�̋��ߕ�
�̌��i�ߑ�20���j
| �u�̌��L���ʐς̎Z���
�P�v�i���������ɂ��Ⴂ�j �p�r�n��� �F�Z���n�p�r�n�^�����̎�� �F��h�ɂ̐Q���^�����̏��ʐ� �F70�u�^�p�r���Ƃ̊��� �F1/7�i��10�u�j �u�̌���W���v�Z�莮 �FD/H�~6-1.4 ( D/H �F�u�̌��W�䗦�v�Ƃ����C���̐��l�̂����ł����������l�Ƃ���j ( D/H�~6-1.4 �F�u�̌���W���v�Ƃ����j �K�v�ȑ��ʐόv�Z�� �F�����̏��ʐρ~1/7���̌���W�� |
|
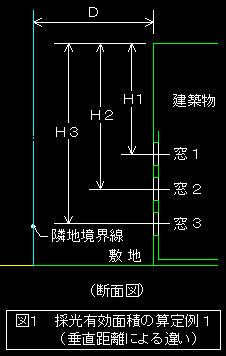
|
�� �F D��4m �CH 1��8m �CH 2��10m �CH 3��10.9m �u��1�̃P�[�X�v�@�̌���W�� �F 4/8�~6�|1.4��1.6 ���ʐς�160�����L���ƂȂ�K�v�ȑ��ʐς́C 70�u�~1/7��1.6��6.25�u �i6.25�~1.6��10�u ���J�����̖ʐρ~�̌���W�� �j ���������āC6.25�u�ȏ�̑��ʐςł���̌���L���ȊJ�����ƂȂ�B �u��2�̃P�[�X�v�@�̌���W�� �F 4/10�~6�|1.4��1.0 ���ʐς̂��ׂāi100���j���L���ƂȂ�K�v�ȑ��ʐς́C 70�u�~1/7��1.0��10�u �i10�~1.0��10�u ���J�����̖ʐρ~�̌���W�� �j ���������āC10�u�ȏ�̑��ʐςł���̌���L���ȊJ�����ƂȂ�B �u��3�̃P�[�X�v�@�̌���W�� �F 4/10.9�~6�|1.4��0.8 ���ʐς�80�����L���ƂȂ�K�v�ȑ��ʐς́C 70�u�~1/7��0.8��12.5�u �i12.5�~0.8��10�u ���J�����̖ʐρ~�̌���W�� �j ���������āC12.5�u�ȏ�̑��ʐςł���̌���L���ȊJ�����ƂȂ�B |
| �p�r�n�悲�Ƃ̐��������uD�v�ɂ��Ⴂ ���������uD�v�ɂ��ɘa �J���������ɖʂ��Ȃ��ꍇ�ŁC�e�p�r�n�悲�ƂɁC���ȏ�̐��������uD�v������C�Z��l��1.0�����̏ꍇ��1.0�Ƃ����ƋK�肵�Ă���B�ނ��Z��l��1.0���̏ꍇ�ɂ͂��̐��l�ƂȂ�B �u�Z���n�p�r�n��̏ꍇ�v D��7m�̏ꍇ�C�̌���W����1�����ł��C1.0�Ƃ��Ĉ����B ���Ȃ킿7m�ȏ�̐�����������������ׂĂ̑��͍̌���L���ȊJ�����ƂȂ�B �u�H�ƌn�p�r�n��̏ꍇ�v D��5m�̏ꍇ�C�̌���W����1�����ł��C1.0�Ƃ��Ĉ����B ���Ȃ킿5m�ȏ�̐�����������������ׂĂ̑��͍̌���L���ȊJ�����ƂȂ�B �u���ƌn�p�r�n��̏ꍇ�v D��4m�̏ꍇ�C�̌���W����1�����ł��C1.0�Ƃ��Ĉ����B ���Ȃ킿4m�ȏ�̐�����������������ׂĂ̑��͍̌���L���ȊJ�����ƂȂ�B |
|
| �̌��W�䗦�̎Z��� �����̊J�����Ƃ� �̌��̂��߂̑����̑��̊J�����������B�ǂ̈ꕔ���K���X�u���b�N��p����ꍇ�́C�������ߐ���ڒn�̑傫���ȂǍ̌����ʂ��l�����Čʂɔ��f�����B�h�A��V���b�^�[�ō̌����ʂ��Ȃ����̂͂���ɊY�����Ȃ����C�V���b�^�[�œ����͊J������Ă�����͓̂��Y�J�����Ƃ��Ĉ����Ă���B |
|
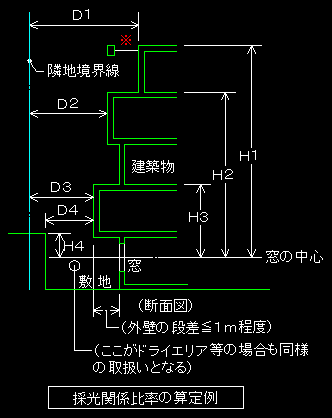 |
���������̂Ђ����ɂ��� �K���X�Ђ����i�ԓ���K���X�C�K���X�C�^�K���X���j�͈�ʓI�ɍ̌���x�Ⴊ�Ȃ����̂Ƃ��Ĉ����Ă���B��������[�ɗ���������ꍇ�͂c�̐��l��������������ĎZ�肳�ꂽ���B ������J�����̍����肷���i�K���X��c�i�q�Ȃǁj�����̌���x�Ⴊ�Ȃ����̂Ƃ��Ĉ����Ă���B �O�ǂɓʉ������錚���ł́C�c1�^�g1�C�c2�^�g2�C�c3�^�g3�C�c4�^�g4�̂����ŏ��̐��l�����̍̌��W�䗦�ƂȂ�B �o���R�j�[������ꍇ �o���R�j�[�̐�[����גn���E���Ԃł̐����������c�Ƃ���B |
�̌��W�䗦�̋��ߕ� ��P�`�R �i2007W�j
| �̌��W�䗦�̋��ߕ� ��P | �̌��W�䗦�̋��ߕ� ��Q | �̌��W�䗦�̋��ߕ� ��R |
| ���P�̍̌��W�䗦�́CD1/H1�ł���B ���Q�̍̌��W�䗦�́CD2/H2 �� D2/H3�̂����C�ŏ��̐��l�ƂȂ�B |
���R�̍̌��W�䗦�́CD1/H1 �� D2/H2 �̂����C�ŏ��̐��l�ƂȂ�B | �V���̍̌��W�䗦�́CD/H
�ƂȂ�B �Ȃ��C�u�̌���W���v�́CD/H ���Z�肵�C�Z�o�������l���R���悶�ē������l�ƂȂ�B |
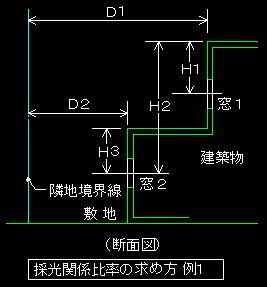 |
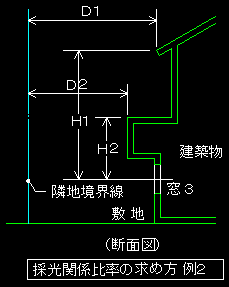 |
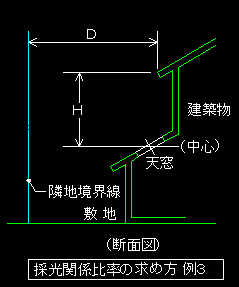 |
�̌��W�䗦�̋��ߕ� ��S�`�T �i1995K �j
| �̌��W�䗦�̋��ߕ� ��S | �̌��W�䗦�̋��ߕ� ��T | �V������V��܂ł̋������V�����a��蒷���ꍇ�̓V���̍̌��L���ʐς̋��ߕ� |
| L
�F �V���̌v
( �l�p�̏ꍇ�͒Z���ӂ̒��� ) H �F �V���K���X�ʂ���V��ʂ܂ł̋��� L '�F �v�Z����Y���̌���������גn���E���܂ł̋��� H '�F �����̍ō�������V���܂ł̋��� �V���̍̌��ʐς����̊J���ʐρ~�̌���W���ł����C�̌���W���̌v�Z�̕��@�� �k/�g �E�E�E�E�E�E�E�E�E�@ �k'/�i�g'�{�g�j�E�E�E�E�A �@,�A�̂��������������g���̌���W�����܂��B���ɏZ���n�n��Ň@���������Ƃ���Ɓi6�~�k/�g�|1.4�j�~3�ƂȂ�܂��B(�A��3����ꍇ��3�ƂȂ�܂�) |
�̌���W���̌v�Z�̕��@�� �k'/�i�g'�{�g�j �� �o6�~�k'/�i�g'�{�g�j�|1.4�p�~3�ƂȂ�܂��B (�A��3����ꍇ��3�ƂȂ�܂�) |
�v���R�v�� �v �F �̌��ɗL���Ȗʐ� �v�� �F �V�������̍̌��ɗL���Ȗʐ� �g���k�̏ꍇ �v���R�v���~�k/�g �Ƃ���l���������낤 �g �F �V��ʂ���V�����_�܂ł̍��� �k �F �V���̌a |
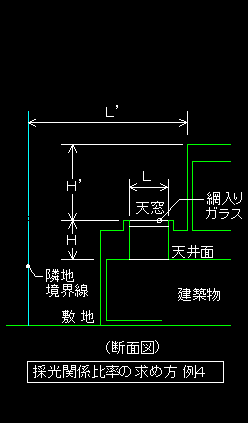 |
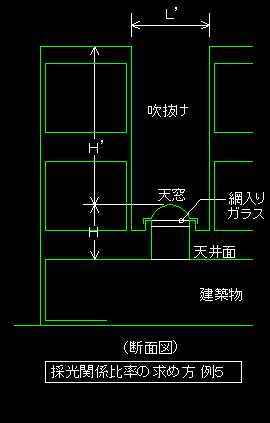 |
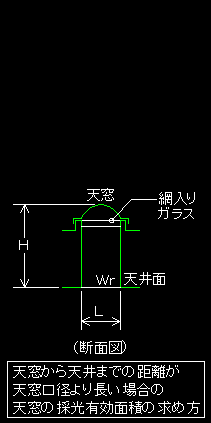 |
����~�n���ɍ��w�̌��z���ƒ�w�̌��z��������ꍇ�́u�c�v�C�u�g�v�̂Ƃ��
�i1995K �y�� Web�T�C�g�������j
| ����~�n���ɍ��w�̌��z���ƒ�w�̌��z��������ꍇ�́u�c�v�C�u�g�v�̂Ƃ�� | |
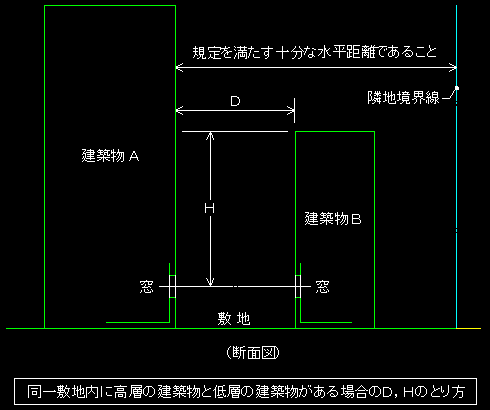
|
�ȉ��CWeb�T�C�g������� ���[�~�n���ɍ��w���ƒ�w��������ꍇ�̕�W���ɂ��Ă͌��z��@��̋K��ł͍��w���̍̌���W������w���̑Ό����܂ł̐��������ɂ�邪�C����͑Ό�����גn���E���Ƃ݂Ȃ��i���j�C���w���̏㕔�̓V��̌������҂�����̂ł���B�������C�Ό�������w���ł�����C���w������w���̏㕔�̓V��̌����\���Ɏ邱�Ƃ��ł��邽���C���w���ɂ����Ă���w���ɂ��̌���W�����̗p�ł�����̂Ƃ����B ���j �גn���E���܂ŏ\���ȋ��������邱�Ƃ��O���C�����̋��e�l�ɂ��Ă͐R���@�ւɂĊm�F���邱�ƁB ���]�Ԓu���i/���ԏ�j���̗�j�D ��w�����z���a���l�����̉������������]�Ԓu�ꓙ�̏ꍇ�C���w�����z���`�́u�g�v�̂Ƃ���͂�͂����]�Ԓu�ꓙ�̉�����[������u�g�v�ł悢�B �O�q���l�����w���ɂ����Ă���w���ɂ��̌���W�����̗p�ł����Ƃ������ƁB |
���z���Ɨגn���E���܂ł̐��������ɂ��ɘa
�i1995K �j
| ���z���Ɨגn���E���܂ł̐��������ɂ��ɘa�P | ���z���Ɨגn���E���܂ł̐��������ɂ��ɘa�Q |
| ���H�ɖʂ���ꍇ�̗גn���E���́C���H�̔��Α��̋��E����גn���E���ƍl���ĎZ�肷��B | �����C�L��C�쓙�ɖʂ���ꍇ�̗גn���E���́C�����̕���1/2�����{���̗גn���E���̊O���ɂ�����ƍl���ĎZ�肷��B |
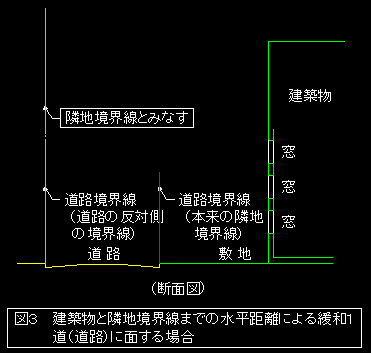 |
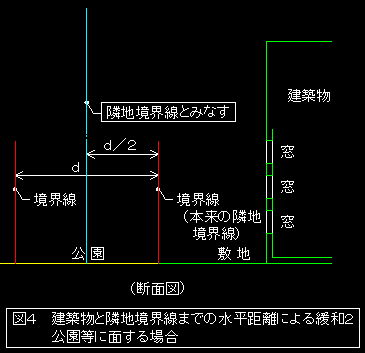 |
�����̍̌�
�@��28���1���C��2���C��4���C��19���C��20���C�i�g�P�T�N��������R�O�R���j
���������ꍇ�̍̌���W���̎戵���i��20���2���j
�i2009�i�b�a�`��� �j
| ��
���������ꍇ�̍̌���W���̎戵���i��20���2���j �̌���W���̒ጸ���́C�����̕�����0.9m�����̏ꍇ��1.0�i�����I�ɂ͒ጸ���Ȃ��j���C0.9m�ȏ�̏ꍇ��0.7���悸���������C���ڊO�C�ɐڂ���ʂꉏ�ɂ��ẮC�̌���W����ጸ���Ȃ�� |
|
| �����i�ʂꉏ��������j�ɂ��ẮC�O�ǂɖʂ��镔���̑唼���|���o�������̊J�����ł���C�̌���̊J������������������C���Y�����Ƌ����Ƃ͏�q���ɂ��d���Ă��邽�߁C���Y�������猩��ƁC����������̌����͒ጸ���邱�ƂƂȂ顂��̂悤�ȏꍇ�̕�Ƃ��āC�����̕���W��0.9m�ȏ��̂Ƃ��́C��������Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂ�0.7���x�̍̌�����������̂Ƃ��Ă��顂Ȃ��C�����ȊO�̉����L���ɂ��ẮC�����Ɠ��l�ɊO���ɖʂ��镔�����傫���C�̌���̊J������L����ꍇ�ɂ����āC���l�Ɏ�舵�����̂Ƃ��� ���̏ꍇ�C���������̖ʐς͋����̖ʐςɂ͊܂܂Ȃ�� | |
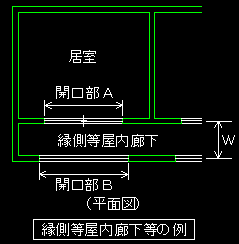 |
�����������L���̗� �y�J�����̍̌��L���ʐρz W��0.9m�̏ꍇ �����̊J����A�̖ʐρ~�̌���W���~1.0 W��0.9m�̏ꍇ �����̊J����A�̖ʐρ~�̌���W���~0.7�i�̌���W���̒ጸ���j ���j�D�J���� �FB��A |
��
��ӂ��܁C��q���̑������J�����邱�Ƃ��ł�������Ŏd��ꂽ2����̎戵���i�@��28���4���j
�̌��E���C�̋K��̓K�p�ɓ������Ă�1���Ƃ݂Ȃ�������ŋK�肳��Ă��颐����J�����邱�Ƃ��ł�����̣�Ƃ́C��̓I�ɂ́C�����˂�A�R�[�f�B�I���J�[�e���Ȃǂ���������
�����˂�A�R�[�f�B�I���J�[�e���Ȃǂ̂悤�ɁC�Ԏd�ؕǂƂ͈قȂ�C�J�����ɂ͈��̊J�������m�ۂ����悤�ȍ\���̂��̂ɂ��Ă͑ΏۂƂȂ�2���̈�̐����F�߂��邱�Ƃ���C�̌��E���C�̋K���C������2����1���Ƃ��Ĉ������Ƃ��ł��顂Ȃ��C�J�����ł����Ă��̌����E���C�����m�ۂ���ϓ_���玺���݂̓Ɨ����������Ȃ�\���̌ˁi�J���˂Ȃ��j�ɂ��ẮC�����ł���������J�����邱�Ƃ��ł�����̣�ɂ͊Y�����Ȃ��
�� 005�@�̌����L�����ǂ���
�̌����L�����ǂ���
�i1995K �j
| �J���L���C���O�K�i�ɖʂ���ꍇ �i�@�Q�O���Q���̉��p���߁j �����a�́C�J���L���ɖʂ��Ă���̂ō̌��͗L���ł���B���̏ꍇ�C�s�����ɂ���ẮC���X�O�p�ȏ�̉���������ꍇ�Ɠ����悤�Ɉ����Ă���Ƃ��������B �����`�͊J�����̑O�ɉ��O�K�i������̌��͗L���łȂ��B �i�̌����L���ł���ꍇ�̗L���ʐς̎Z��͑�Q�O���̒ʂ�B�j |
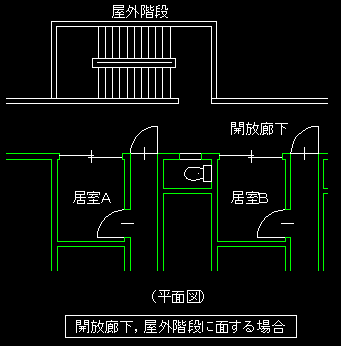 |
�A���R�[�u����ĘL��������ꍇ
�i1995K �j
| �A���R�[�u����ĘL��������ꍇ �i�@�Q�O���Q���̉��p���߁j �A���R�[�u����ĘL��������ꍇ�@�Q�O���Q���̉��p���ߘL���̑O��������x�̊J����������C��90�p�ȏ�̍L��������ꍇ�Ɠ��l�̈��������Ă��悢�Ǝv����B �i�̌����L���ł���ꍇ�̗L���ʐς̎Z��͑�Q�O���̒ʂ�B�j |
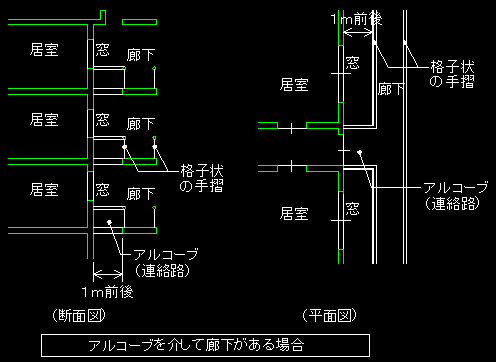 |
�C���i�[�o���R�j�[�␁�����炵�̘L���ɖʂ���ꍇ
���̉��O���ɃC���i�[�o���R�j�[�␁�����炵�̘L���ȂǁC�g�O�C�ɊJ�����ꂽ����h������ꍇ�C���s���ɉ������̌���W�����ጸ����܂��B
�̌��W�䗦��D/H�Ƃ��C�p�r�n��ʂɎZ�o�������l�ɁC���\���L���W�����|���č̌���W�������߂܂��B
| �������炵�L���E�o���R�j�[�Ȃǂ̉��s�� | �̌����L���W�� |
| 2���ȉ� | 100�� �i=1�j |
| 2�����`4���ȉ� | 70�� �i=0.7�j |
| 4���� | 0�� �i=0�j |
| �Ⴆ�C�Z���n�̗p�r�n��ł́u�̌���W�����iD/H�~6-1.4�j�~��\�L���W���v�ƂȂ�C���̊O�ɁC���s��4m���鉮��������ꍇ�́C�̌���W���u0�v�B �܂�C�@����͌��̓���Ȃ����Ƃ݂Ȃ������̂������킯�ł��B |
|
�Q���̌��̍l���� �i�@�Q�W���S���C�߂P�P�P���Q���j
�Q���i����
�`�C�a�j���P���Ƃ݂Ȃ��Ȃ��R��
�i1995K �j
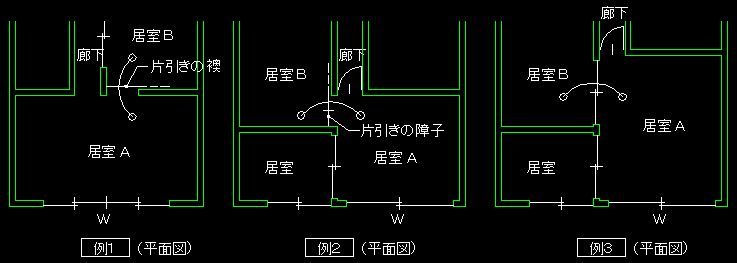
�Q�����P���̈����̓���@�i�@�Q�W���S���߂P�P�P���Q���j�@�i2006H�j
| �Q�����P���̈����̓��� | |
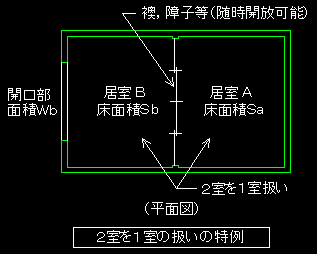 |
�Z��̏ꍇ �v���~�̌���W�����P�^�V�i�ra�{�rb�j �� ��O�̎��i�����a�j�����i�J�������V���b�^�[�̎ԌɂȂǁj�̏ꍇ�͂Q���̌��Ƃ݂͂Ȃ���Ȃ��B �܂��Ԍɂ��������ƌ����Ă�ɂ�����������B |
�̌��ɗL���ȕ����̖ʐς̎Z����@�̊ɘa
�F�Q�����P���̈����@�i���� �g�P�T�����O�R�O�R���j�@�i2006H�j
| �Q�����P���̈����̓���@�i����
�g�P�T�����O�R�O�R���j �ߗ��ƒn�斔�͏��ƒn����̏Z��̋����i�������͋����Z��ɂ����ẮC����̏Z�˓��̋����Ɍ���B�j �� ���̍����ɂ��ɘa�ŁC���}�̂悤�ɕǂȂǂŎd���Ă���Q���ł����Ă��C���̊J�����̏��������̌����m�ۂ��ꂽ���ƂɂȂ�C���������Ƃ��Č��݂��ꂽ�����z�����Z��i����������Z��܂ށj�ɗp�r�ύX����ۂ̃n�[�h�����P�������ꂽ���ƂɂȂ��B |
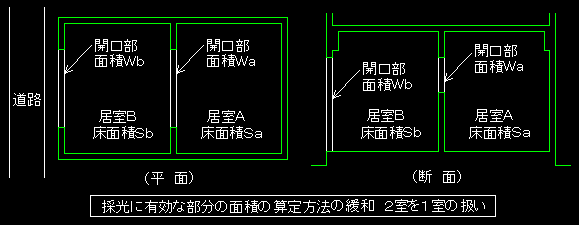 |
| �Z��̏ꍇ �va���r���^�V���v���~�j���i�r���{�r���j�^�V �i�j�F�J�����a�̕�W���j �� ��O�̎��i�����a�j�����i�J�������V���b�^�[�̎ԌɂȂǁj�̏ꍇ�͂Q���̌��Ƃ݂͂Ȃ���Ȃ��B �܂��Ԍɂ��������ƌ����Ă�ɂ�����������B |
���C
�� K001�@�֘A�@��
�֘A�@��
�y�����̍̌��y�ъ��C�z�@�i�@��Q�W��
�����j
��28���@
�Z��C�w�Z�C�a�@�C�f�Ï��C��h�ɁC���h���̑������ɁE�E�E�E�E�E�E�E�E�B
2�@ �����ɂ͊��C�̂��߂̑����̑��̊J������݂��C���̊��C�ɗL���ȕ����̖ʐς́C���̋����̏��ʐςɑ��āC1/20�ȏ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C���߂Œ�߂�Z�p�I��ɏ]���Ċ��C�ݔ���݂����ꍇ�ɂ����ẮC��������łȂ��B
���߁i�@�j �� �߂P�X���P��
�E�E�E�E�E�E�i�ȗ��j
���߁i�A�j �� �߂P�X���Q�� �E�E�E�E�E�E�i�ȗ��j
���߁i�B�j �� �߂P�X���R�� �E�E�E�E�E�E�i�ȗ��j
3�@ �ʕ\��1�i���j���i1�j���Ɍf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���̋������͌��z���̒������C�������̑��̎��ł��܂ǁC����낻�̑����g�p����ݔ��Ⴕ���͊���݂������́i���߁i�@�j�Œ�߂���̂������B�j�ɂ́C���߁i�A�j�Œ�߂�Z�p�I��ɏ]���āC���C�ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���� �˗߂Q�O���̂Q�u���C�ݔ��̋Z�p�I��v
4�@ �ӂ��܁C��q���̑������J�����邱�Ƃ��ł�����̂Ŏd��ꂽ2���́C�O3���̋K��̓K�p�ɂ��ẮC1���Ƃ݂Ȃ��B
���߁i�@�j �� �߂Q�O�̂R�u���g�p���鎺�ɐ݂��Ȃ��ꂪ�Ȃ�Ȃ����C�ݔ��v
���߁i�A�j �ˁ@�߂Q�O���̂Q�u���C�ݔ��̋Z�p�I��v
�y�ΖȂ��̑��̕����̔�U���͔��U�ɑ���q����̑[�u�z
��28����2��O���@�i�����j
��@�i�ȗ��j
��@�i�ȗ��j�@
�O�@ ������L���錚�z���ɂ����ẮC�O2���ɒ�߂���̂̂ق��C�Ζȓ��ȊO�̕����ł��̋������ɂ����ĉq����̎x����邨���ꂪ������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂镨���̋敪�ɉ����C���z�ޗ��y�ъ��C�ݔ��ɂ��Đ��߂Œ�߂�Z�p�I��ɓK�����邱���B
�y���C�ݔ��̋Z�p�I��z�@�i�ߑ�Q�O���̂Q
�����j
��20����2�@ �@��28���2�����������̐��߂Œ�߂�Z�p�I��y�ѓ����3���i�@��87���3���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�����1���ɂ����ē����B�j�̐��߂Œ�߂���ꌚ�z���i�ȉ����̏��ɂ����āu���ꌚ�z���v�Ƃ����B�j�̋����ɐ݂��銷�C�ݔ��̋Z�p�I��́C���̂Ƃ���Ƃ���B
�i�ȉ��ȗ��j
�� �@�B���C�ݔ��̐ݒu�̋`���t���y���V�b�N�n�E�X��ɌW��K���ɂ��Ă̏ڍׂ����t���[����INDEX�́u�V�b�N�n�E�X��E�Ζ��v���Q�Ƃ��Ă��������B
�y���g�p���鎺�ɐ݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����C�ݔ����z�@�i�ߑ�Q�O���̂R
�����j
��20����3�@ �@��28���3���̋K��ɂ�萭�߂Œ�߂鎺�́C���Ɍf������̂Ƃ���B
�i�ȉ��ȗ��j
�� �֘A�@
���C�ݔ��̍\�����@���߂錏
���a45�N12��28�� ���ݏȍ�����1826���i�ŏI���� ����12�N12��26��
���ݏȍ�����2465���j
��3 �������i�䏊�j���ɐ݂��銷�C�ݔ�
�� �i�ȗ��j
�� �ߑ�20����3��2����ꍆ�C�i4�j�̋K��ɂ�荑�y��ʑ�b����߂鐔�l�́C���̃C���̓��Ɍf����ꍇ�ɉ����C���ꂼ��C���̓��ɒ�߂鐔�l�Ƃ��邱�ƁB
�C
�r�C�����͔r�C���Ɋ��C���݂���ꍇ�@���̎��ɂ���Čv�Z�������C��̗L�����C�ʂ̐��l
V = 40KQ
���̎��ɂ����āCV �C40�CK �y�� Q �́C���ꂼ�ꎟ�̐��l��\�����̂Ƃ���B
V �F���C��̗L�����C�� �i�P�� m3/���ԁj
40 �FN�l�ŁC �r�C�i���C�j�t�[�h�̌`��E���@�ƍ\���y�єr�C�i���C�j�t�[�h�̂Ȃ��ꍇ�ɂ���߂�ꂽ���l�i40�^30�^20�j�@�@�i
�ڍ� �j�i�����E�B���h�E�ňړ��j
K
�F�R���̒P�ʔR�ėʓ�����̗��_�p�K�X�ʁi�ʕ\�i���j���Ɍf����R���̎�ނɂ��ẮC���\�i��j���Ɍf���鐔�l�ɂ�邱�Ƃ��ł���B�ȉ������B�j
�i�P�� m3�j�@�i
��F�i1�j�s�s�K�X�i13A�j�^LP�K�X�i�v���p����́j �� 1kW���ɂ�0.93m3
�j �@
Q �F���g�p����ݔ����͊��̎����ɉ������R�������
�i�P�� kW����kg/���ԁj
�� �r�C�����͔r�C���Ɋ��C���݂��Ȃ��ꍇ�C���̎��ɂ���Čv�Z�����r�C���̗L���J���ʐϖ��͔r�C���̗L���f�ʐς̐��l
�i�ȉ��ȗ��j
����j�D���C����K�v���C���i�L�����C�ʁj�uV�v�͐~�[�Ȃǂ̊������_�p�K�X�����狁�߂܂��B
V = NKQ
���̎��ɂ����āCV
�CK
�y��
Q
�́C���ꂼ�ꎟ�̐��l��\�����̂Ƃ���B
V
�F���C����K�v���C���i�L�����C�ʁj
�i�P�ʁF��3/h�j
N �F�r�C�i���C�j�t�[�h�̌`��E���@�ƍ\���y���r�C�i���C�j�t�[�h�̂Ȃ��ꍇ�ɂ����߂�ꂽ���l�i40�^30�^20�j�@�@�i
�ڍ� �j�i�����E�B���h�E�ňړ��j
K
�F�R���̒P�ʔR�ėʓ���������_�p�K�X���i�ʕ\�i���j���Ɍf����R���̎�ނɂ��ẮC���\�i��j���Ɍf���鐔�l�ɂ�邱�Ƃ��ł���B�ȉ������B�j
�i�P�ʁF��3/kW�Eh������3/kg�j�@�i
kW�Eh �̓L�����b�g���Ɠǂ� �j
�ȉ��C�ʕ\�i�y�юQ�l�j�B���_�r�K�X��"K"�́C0.93��3/kW�Eh�ƌŒ�̐��l�ɂȂ��Ă���B
�E �s�s�K�X�i12A,13A,5C,6B�i/�u�^���G�A�K�X�j�j
�F 0.93��3/kW�Eh
�E LP�K�X�i�v���p����́j �F 0.93��3/kW�Eh
�i����12.9��3/kg�j
�E ����
�F 12.1��3/kg
Q
�F���g�p����ݔ����͊��̎����ɉ��������M���ukW�v�܂��͔R��������ukg/h�y����3/h�v
�ȉ��C�s�s�K�X13A�̃R�����Q�l�l�i���M�ʁ^�R������ʁj
1���R���� �F 4.20kW �^ 0.301kg/h
2���R���� �F 6.88kW �^ 0.493kg/h
3���R���� �F 8.05kW �^ 0.577kg/h
�Q�l�j�D���M�ʁukW�v�܂��͔R������ʁukg/h�y��m3/h�v�̋��P�ʂɂ���
�E kW�ŕ\������Ă�����̂�kcal/h�Ɋ��Z����ꍇ�́C1kW��860kcal/h�i859.85kca��/h�j�Ȃ̂ŁC�ukW�~860
= m3/h�v�Ckcal/h��kW�����Z����ꍇ�́ukcal/h��kW
= m3/h�v�ƂȂ�܂��B
�E
1�s/h��14kW�Ƃ��Ă���̂ŁCkW�ŕ\������Ă�����̂��s/h�Ɋ��Z����ꍇ��14�Ŋ����B
���C����7�N1��1�������{�H�ƋK�i(JIS)�́C�K�X����ʂ̒P��
kcal/h ��W �ɁC�s/h �� kW �ɂƁCSI �P�ʂɕς��܂����B
�Q�l�j�D�ȉ��C�K�v���C���i�L�����C�ʁj�uV�v���v�Z���ł��B
�� �Z��̃L�b�`����
�����W�t�|�h�t�@��500m3/h
�i�r�C�t�[�h�T�^�iN=30�j�ɑ����j
�K�X�����10.47kW
�i3���R�����{�O�����i�V�X�e���L�b�`���j�j
�K�v���C��
�uV = NKQ�v
V��30�~0.93�~10.47��292.11
��3/h�@�@�i��500m3/h�j
�Q�l�܂łɁj�D�O�q�̃K�X����ʁukW�v�����P���ukcal/h�v�\���̏ꍇ�̌v�Z��@�i����7�N�ȍ~���K�X����ʂ��\�����ukW�v�ł��B�j
�����W�t�|�h�t�@��500��3/h�~10mmAq �i�u�r�C�t�[�h�T�^�v�iN��30�j�ɑ����j
�K�X����ʁF9,000kcal/h �i3���R�����{�O�����i�V�X�e���L�b�`���j�j
�@ �i�Q�l1 �F �PkW�͊��Z�����859.85kcal/h�Ȃ̂ŁC�V�����P�ʂł�9,000kcal/h��859.85kcal/h��10.47kW�ł��B�j
�K�v���C�� �uV = NKQ�v
V��30�~0.00108�~9,000��291.6
��3/h �@�@�i��500m3/h�j
�@ �i�Q�l2 �F �R���̎�ނ̓s�s�K�X13A�i6B/�u�^���E�G�A�K�X�j��0.00108K/kcal�ł��B�j
�i�Q�l3 �F ���^�̃����W�t�|�h�t�@���ł͔r�C�ʁi���ʁj�\���Ɂu500��3/h�~10mmAq�v�ƁC���͒P�ʁummAq�v�i�~�����[�g���A�N�A�j���\�L���Ă��邱�Ƃ��L��܂����C���݂ł́ukPa�v�i�L���p�X�J���j���́uMPa�v�i���K�p�X�J���j�ŕ\�����܂��B�ummAq�v�͕���6�N�i1994�N�j�ȑO�̕\���ł��B�A�N�A�̓��e����Łu���v�Ƃ����Ӗ��ŁC�u�����v�Ƃ��Ă̕\���ł��B�j
�ȉ��C����ɎQ�l�܂ł�
10mmAq��0.098 kPa�@�@ �i1,000 kPa��1 MPa�j
1mmAq ��9.80665 Pa �@�iPa�i�p�X�J���j�F�@�O�È��i���͂�\����{�P�ʁj�j
�� �䏊���C�ݔ��̐ݒu�Ɋւ���@�K�ɂ��Ă̗���
�r�C�i���C�j�t�[�h�T�y�чU�^�̐ݒu����
�r�C�ʂ𗝘_�p�K�X�ʂ�30�{�y��20�{�i�萔�F30�y��20�j�ɂ��邱�Ƃ��ł���r�C�t�[�hI�^�y�чU�^�̐ݒu�����́C�Ό��܂��͒����@��ɐ݂���ꂽ�r�C������t�[�h���[�܂ł̍�����100cm�ȉ��ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
�� �r�C�i���C�j�t�[�h�T�^�iN=30�j�C�U�^�iN=20�j���`��E���@���\���y���r�C�i���C�j�t�[�h�̂Ȃ��ꍇ�iN=40�j�C���ɂ���
�@
�@
4�D�}�t���[�E���˂��g�p�̏ꍇ�́uN=2�v
�����j�D12kw����K�X���[�����W���]���C�K�X䥖ˋ@�ȂǁC�t�[�h���[����1m�̋K���K�p����ƁC������ƂɎx�Ⴊ�����Ă��܂��ꍇ������܂��B�����������P�[�X�ł́C�r�C�t�[�h���ݒu����Ă��܂���N=40�Ōv�Z���邱�ƂɂȂ�܂��B
�� �Q�l�j�D�d���~�[�@����g�p����ꍇ�̗��ӎ����@�i�@28��3���C��20����3�CS45����1826�j
�d�C�������h�g�N�b�L���O�q�[�^�[�i�d���U�����M��������j���͒��ډC���g�p������̂łȂ����߁C�C�g�p���̊��C�ݔ��̓K�p�͂Ȃ����C�M�C�����C�C�L�C���̂ɂ��s���������⌋�I�h�~���ǍD�Ȏ�������ۂ̂��߁C���̊��C�ݔ���݂������
��ʓI�ȉƒ�p�d���~�[�́w���z�ݔ��v�E�{�H��̎w���w�j�x�ł��~�j�L�b�`����200��3/���C��ʉƒ�p��300��3/���ȏ�̊��C�����]�܂����ڈ��Ƃ���Ă��܂��B
�Ɩ��p�̓d���~�[�ɂ��ẮC�K�v���C�ʁ�30�~��i����d�́ikW�j�ŋ��߂�C�܂��͐~�[�̊��C��20��^h�ɂ���C�Ƃ����ڈ�������܂��B
�����j�D���������p���Ă���~�[�Ȃǂ́C�V�b�N�n�E�X��Ƃ��Ċ��C�ݔ��i24���ԏ펞���C�j���K�v�ƂȂ�̂Œ��ӂ��K�v�
�y������L���錚�z���̌��z�ޗ��ɂ��Ẵz�����A���f�q�h�Ɋւ���Z�p�I��z�@�i�ߑ�Q�O���̂V
�����j
��20����7�@
���z�ޗ��ɂ��Ẵz�����A���f�q�h�Ɋւ���@��28����2��O���̐��߂Œ�߂�Z�p�I��́C���̂Ƃ���Ƃ���B
�i�ȉ��ȗ��j
�i�֘A�@�j
�֘A���Ċm�F�\���̍ۂɈȉ��̒�o�}�����K�v�ł��B�i���z��@�{�s�K��
��1����3�j
�}���̏��� �F�L�����C�ʖ����L�����C���Z�����Z�o�����ۂ̌v�Z��
�������ׂ����� �F�L�����C�ʖ��͗L�����C���Z���y�т����Z�o���@�^���C���y���K�v�L�����C��
�y������L���錚�z�������C�ݔ��ɂ��Ẵz�����A���f�q�h�Ɋւ���Z�p�I��z�@�i�ߑ�Q�O���̂W
�����j
��20����8�@
���C�ݔ��ɂ��Ẵz�����A���f�q�h�Ɋւ���@��28����2��O���̐��߂Œ�߂�Z�p�I��́C���̂Ƃ���Ƃ���B
�i�ȉ��ȗ��j
�ȏ�C�V�b�N�n�E�X��Ƃ��Ă̊��C�ݔ��ݒu�̋`���t���ɂ��Ă����t���[����INDEX���ȉ����Q�Ƃ��Ă��������B
�u�V�b�N�n�E�X��E���v
��
�� �V�b�N�n�E�X��ɌW��K���̊T�v
�� ��
���C�ݔ��̋`���t���E�E�E�E�E�E�i�ߑ�Q�O���̂W�j
��
�V�b�N�n�E�X��Ƃ��Ă����C�ݔ��ݒu�̋`���t��
�y�n�K�ɂ�����Z��̋����̋Z�p�I��z�@�i�ߑ�Q�Q���̂Q
�����j
��22����2�@ �@��29���i�@��87���3���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�j�̐��߂Œ�߂�Z�p�I��́C���Ɍf������̂Ƃ���B
�i�ȉ��ȗ��j
�y���C�ݔ��z�@�i�ߑ�P�Q�X���̂Q�̂U
�����j
��129����2��6�@
���z���i���C�ݔ���݂���x�����������������B�ȉ����̏��ɂ����ē����B�j�ɐ݂��鎩�R���C�ݔ��́C���ɒ�߂�\���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�i�ȉ��ȗ��j
�E
�E
�E
�E
�i�ȉ��{�s�K���C�������ȗ��j
���C�ݔ��̐ݒu���K�v�ȋ����Ɗ��C�ݔ��̎��
| �ݒu���`���t�����鋏�� | �ݒu���ׂ����C�ݔ��̎�� | �W�@�� |
| ��ʂ̋����i���L���ꌚ�z���̋����������j | �C�D���R���C�ݔ� ���D�@�B���C�ݔ� �n�D�����Ǘ������̋�C���a�ݔ� |
�@28��2�� ��20����2 ��129����2��6 S45����1826�� |
| ���ꌚ�z���i����C�f��فC���|��C�ϗ���C����C�W���j�̋��� | ���D�@�B���C�ݔ� �n�D�����Ǘ������̋�C���a�ݔ� |
�E
�E
�E
�E
�i�ȉ��ڍȗ��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �u�ڎ��v�֖߂�