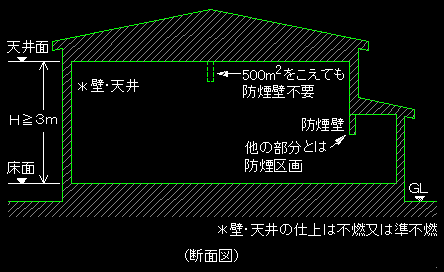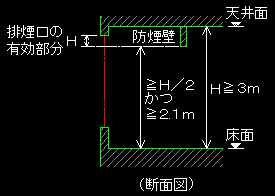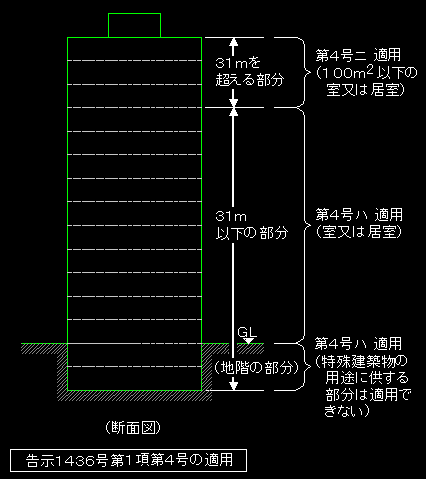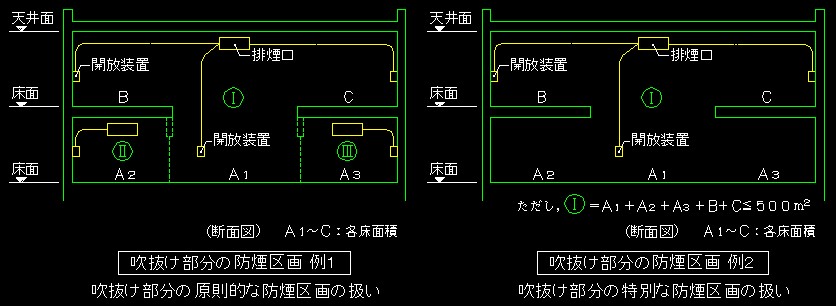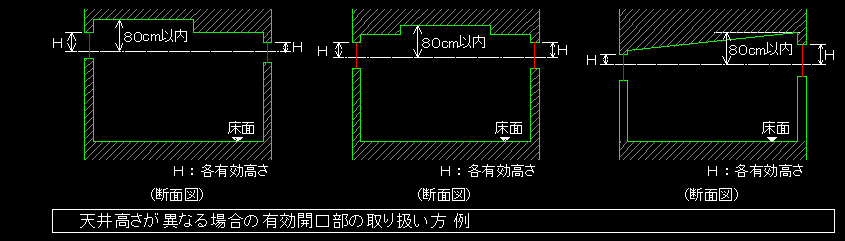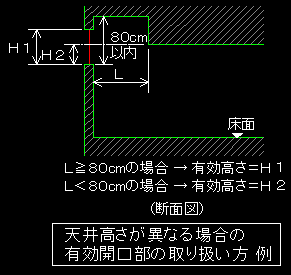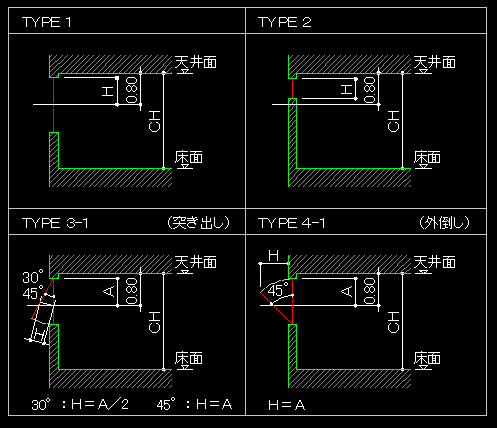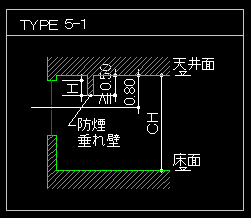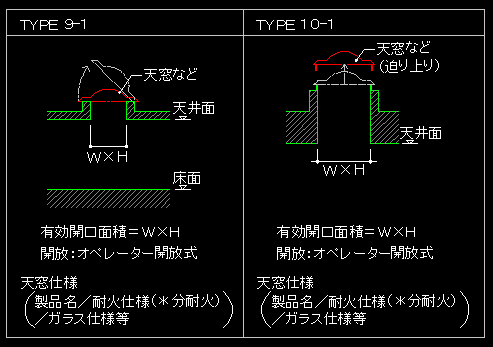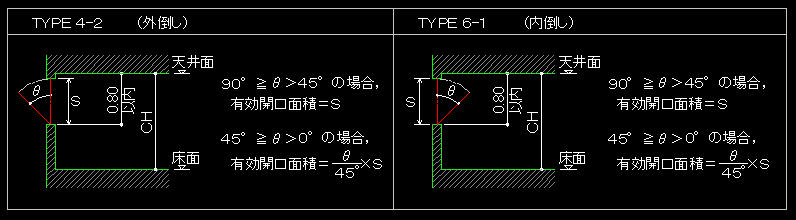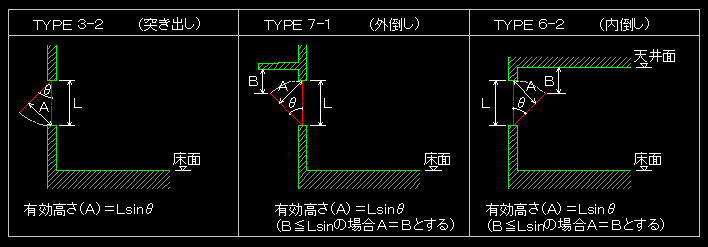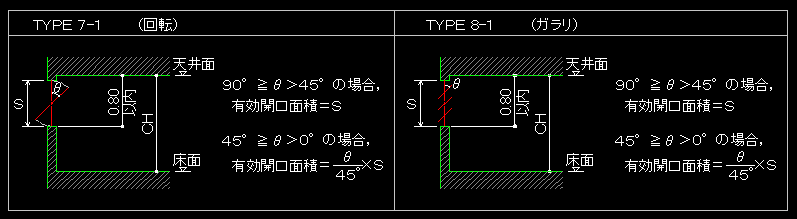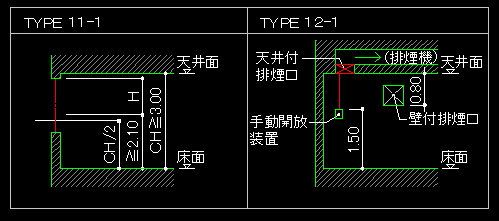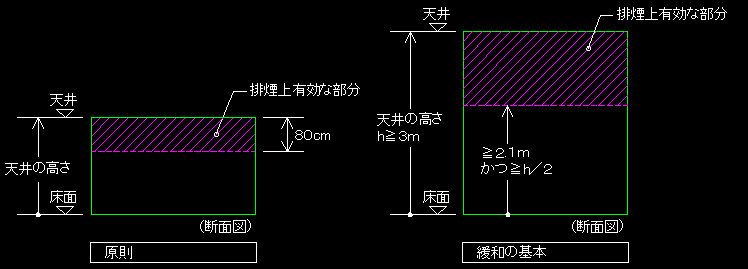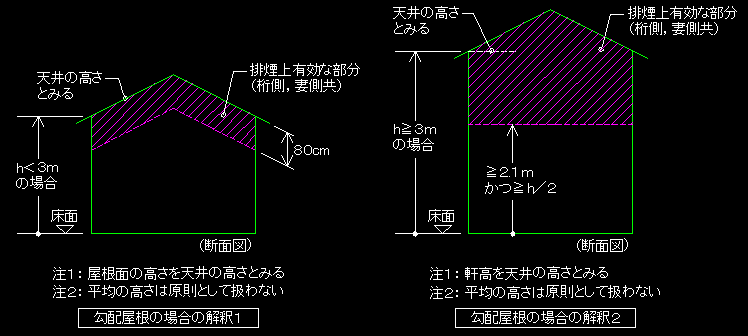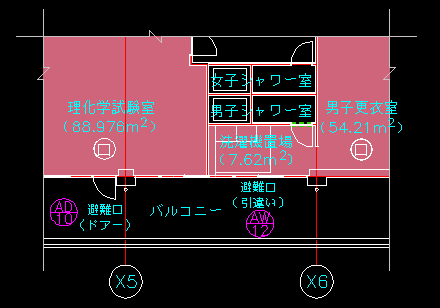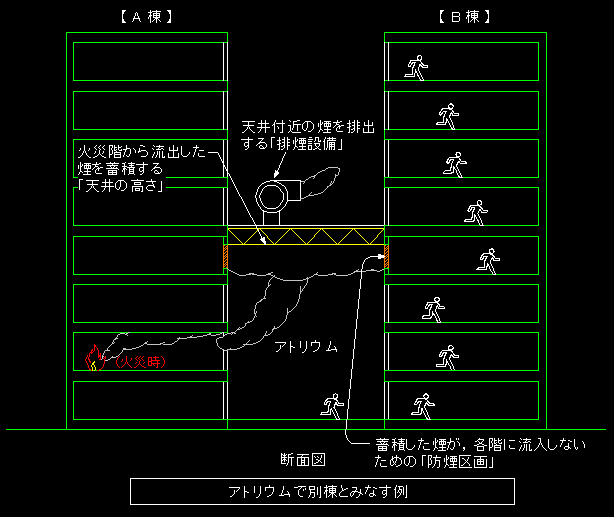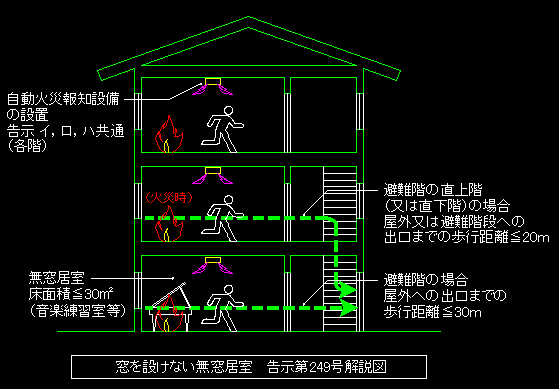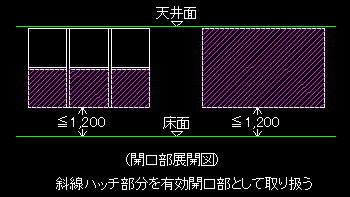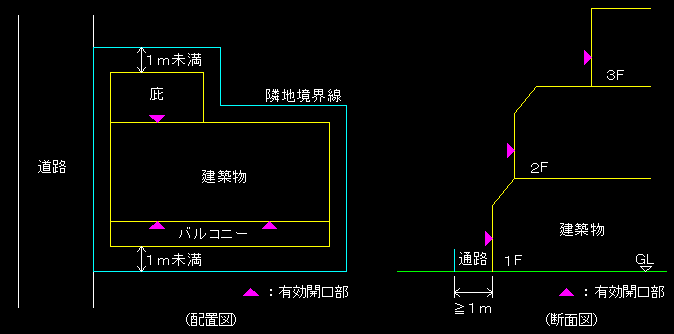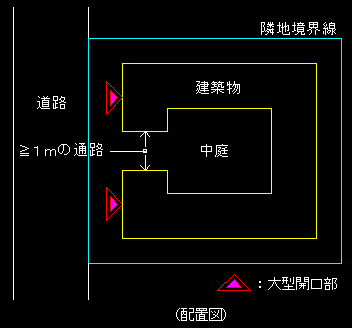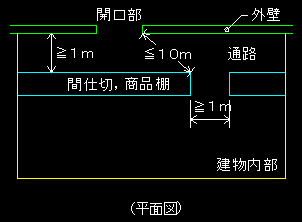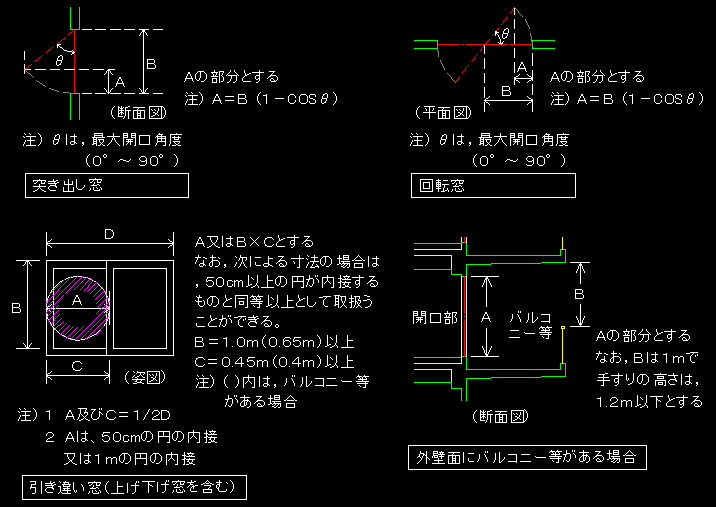�u���z��@�y�ъ֘A�@����v
�S�y�[�W
��
���R�p�Y�s�s���z�v������ - HOME��
�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�r���E���������E�����K
�u �� ��
�v
�r��
�͂��߂�
�g12����1436���͕���27�N3��18���ɉ������ꓯ���{�s����Ă��܂��B
�� 001�@���z��@�{�s�ߑ�P�Q�U���̂Q
�@�@�@�@�@�@�@���z��@�{�s�ߑ�P�Q�U���̂Q �S��
�@�@�@�@�@�@�@�i�P�j�r���ݔ���K�v�Ƃ��錚�z��
�i�u�߂P�Q�U���̂Q�v�y�т����������̂܂Ƃ߁q�\�r�j
�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�j�r���ݔ��̍\����i�߂P�Q�U���̂R�j�@�T��
�@�@�@�@�@�@�@�����@�����P�Q�N�P�S�R�U��
�S���@�i�r���ݔ��̊ɘa�j
�@�@�@�@�@�@�@�uH�P�Q�����P�S�R�U����ꍆ�`��O���v�r���ݔ��̍\����̊ɘa�̂܂Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@H�P�Q�����P�S�R�U����@�r���ݔ��̍\����̊ɘa
�T���}
�@�@�@�@�@�@�@H�P�Q�����P�S�R�U����O���@�r���ݔ��̍\����̊ɘa
�T���}
�@�@�@�@�@�@�@�uH�P�Q�����P�S�R�U����l���v�r���ݔ��̊ɘa�̂܂Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�uH�P�Q�����P�S�R�U���l���v�K�p�̗��ӎ���
��
�L���̔r���ݔ��͖{���ɕK�v��
�@�@�@�@�@�@�@��
�h�����̍\��
�@�@�@�@�@�@�@��
�����������̖h�����ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@��
���R�r���ɂ��Ă̗��ӎ���
�@�@�@�@�@�@�@�B
�V�䍂�����قȂ�ꍇ�̗L���J�����̎���
�@�@�@�@�@�@�@�r�������̓V��̈ꕔ�������ꍇ��
�@�@�@�@�@�@�@���̑��̗��ӎ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�B�r���ɂ��Ă̗��ӎ���
�i�ȗ��j
�@�@�@�@�@�@�@���R�r���J���̊e��f�ʃ^�C�v�@��
�P�`�P�Q�@�i�T���v���t�@�C���_�E�����[�h�j
�� 002�@�r�����ݒu�ɂ�����V��̍���
�@�@�@�@�@�@�@�r�����ݒu�ɂ�����V��̍���
�@�@�@�@�@�@�@�����^�ɘa�̊�{
�@�@�@�@�@�@�@���z�����̏ꍇ�̉��߂P�^���z�����̏ꍇ�̉��߂Q
�@�@�@�@�@�@�@�h���ǂ̍ގ��ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�����S���ؖ@�i�ߑ�P�Q�X���̂Q�C�ߑ�P�Q�X���̂Q�̂Q�j
�� 003�@��
�����u����12�N���ݏȍ�����1436���v�ɂ���
�� 004�@�r���ݔ��̐ݒu��̍������i�r���K��̕ʓ��݂Ȃ��K�p�͈̔͂̊g��j�ɂ����@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
���������E�����K
�� M001�@���������Ɩ����K�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@���z��@�́u���������v�Ə��h�@�ɂ����颖����K�
�@�@�@�@�@�@�@���z��@��̖��������Ɋւ���e��K��
�@�@�@�@�@�@�@�߂P�P�P������������Ă��܂��@
�iWeb�T�C�g��蔲���j
�@�@�@�@�@�@�@�w���h�@�ɂ����颖����K��x�@�i�T���v���t�@�C���_�E�����[�h�j
�@�@�@�@�@ ���h�@�ɂ����颖����K��Ɣ��肳����
�@�@�@�@�@�@�@������K��̍ו����ӎ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�P �J�����̈ʒu
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�i�P�j
�K����T���̂Q��Q����P���ɋK�肷��u���ʂ���J�����̉��[�܂ł̍����v�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�i�Q�j
�K����T���̂Q��Q����Q���ɋK�肷��u�ʘH���̑��̋�n�v�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ �I
���͂������ň͂��Ă��钆�듙�ŁC���Y���납�瓹�ɒʂ���ʘH������C�E�E�E�E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�R�j
�K����T���̂Q��Q����S���ɋK�肷��u�J���̂��ߏ펞�ǍD�ȏ�ԁv�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q �J�����̍\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�P�j �K���X���^�i�Q�j �V���b�^�[�t�J�����^�i�R�j �h�A�^�i�S�j ��d��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �\�|�P
�i �i�P�j �K���X�� �̎戵�� �j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �\�|�Q�@�L���J����
�@�@�@�@�@�@�@�@�R ���̑�
�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ƃ́i�����炢�j�@�i�@�Q���P���S���j
�r��
�͂��߂�
�g12����1436���͕���27�N3��18���ɉ������ꓯ���{�s����Ă��܂��B
��q�́u ��
003�@��
�����u����12�N���ݏȍ�����1436���v�ɂ��� �v���Q�Ƃ��Ă��������B
�� 001�@���z��@�{�s�ߑ�P�Q�U���̂Q
�R�� �r���ݔ�
���z��@�{�s�ߑ�P�Q�U���̂Q �S��
�y�ݒu�z
��P�Q�U���̂Q�@�@�ʕ\��P�i���j���i�P�j������i�S�j���܂łɌf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���ʼn��זʐς��T�O�O�u������́C�K�����R�ȏ�ʼn��זʐς��T�O�O�u���錚�z���i���z���̍������R�Pm�ȉ��̕����ɂ��鋏���ŁC���ʐςP�O�O�u�ȓ����ƂɁC�Ԏd�ؕǁC�V��ʂ���T�O�p�ȏ㉺���ɓˏo��������ǂ��̑������Ɠ����ȏ�ɉ��̗�����W������͂̂�����̂ŕs�R�ޗ��ő���C���͕���ꂽ���́i�ȉ��u�h���ǁv�Ƃ����B�j�ɂ���ċ�悳�ꂽ���̂������B�j�C��P�P�U���̂Q��P����ɊY�����鑋���̑��̊J������L���Ȃ��������͉��זʐς��P,�O�O�O�u���錚�z���̋����ŁC���̏��ʐς��Q�O�O�u������́i���z���̍������R�Pm�ȉ��̕����ɂ��鋏���ŁC���ʐςłP�O�O�u�ȓ����Ƃɖh���ǂŋ�悳�ꂽ���̂������B�j�ɂ́C�r���ݔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C���̊e���̂����ꂩ�ɊY�����錚�z�����͌��z���̕����ɂ��ẮC���̌���łȂ��B
�@�ʕ\��P�˖@�ʕ\��P�u�ωΌ��z�����͏��ωΌ��z���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����c�v
��@�@�ʕ\��P�i���j���i�Q�j���Ɍf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���̂����C���ω\���̏��Ⴕ���͕ǖ��@��Q���㍆�̃j���ɋK�肷���h�ΐݔ��ŋ�悳�ꂽ�����ŁC���̏��ʐς��P�O�O�u�i�����Z��̏Z�˂ɂ����ẮC�Q�O�O�u�j�ȓ��̂���
�@�ʕ\��P�˖@�ʕ\��P�u�ωΌ��z�����͏��ωΌ��z���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����c�v
��@�w�Z�C�̈�فC�{�[�����O��C�X�L�[��C�X�P�[�g��C���j�ꖔ�̓X�|�[�c�̗��K��i�ȉ��u�w�Z���v�Ƃ����B�j
�O�@�K�i�̕����C���~�@�̏��~�H�̕����i���Y���~�@�̏�~�̂��߂̏�~���r�[�̕������܂ށB�j���̑������ɗނ��錚�z���̕���
�l�@�@�B����H��C�s�R���̕��i��ۊǂ���q�ɂ��̑������ɗނ���p�r�ɋ����錚�z���Ŏ�v�\�������s�R�ޗ��ő���ꂽ���̂��̑������Ɠ����ȏ�ɉЂ̔����̂�����̏��Ȃ��\���̂���
�܁@�Ђ����������ꍇ�ɔ���x��̂��鍂���܂ʼn����̓K�X�̍~���������Ȃ����z���̕����Ƃ��āC�V��̍����C�Njy�ѓV��̎d�グ�ɗp����ޗ��̎�ޓ����l�����č��y��ʑ�b����߂����
���y��ʑ�b����߁ˍ����P�Q�N�P�S�R�U���u�Ђ����������ꍇ�ɔ���x��̂��鍂���܂ʼn����́c�v
�Q�@���z�����J�����̂Ȃ����ω\���̏��Ⴕ���͕ǖ��͖@��Q���㍆�̃j���ɋK�肷���h�ΐݔ��ł��̍\������P�P�Q���P�S����ꍆ�C�y�у����тɑ���Ɍf����v���������̂Ƃ��āC���y��ʑ�b����߂��\�����@��p������̖��͍��y��ʑ�b�̔F��������̂ŋ�悳��Ă���ꍇ�ɂ����ẮC���̋�悳�ꂽ�����́C���̐߂̋K��̓K�p�ɂ��ẮC���ꂼ��ʂ̌��z���Ƃ݂Ȃ��B
���y��ʑ�b����߁ˍ����S�W�N�Q�T�U�S����h���ɗp����Չ����\��L����h�ΐݔ��̍\�����@�c�
�u�߂P�Q�U���̂Q�v���C�����������܂߂ĕ\�ɂ܂Ƃ߂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B
�i�P�j�r���ݔ���K�v�Ƃ��錚�z�� �i�߂P�Q�U���̂Q�j
|
|
�@ |
�Ώی��z�����͂��̕��� |
�ݒu�Ə�����錚�z���y�т��̕��� |
|
�@ |
�� ��P��
���ꌚ�z��
�i�@�ʕ\�P�i���j���i�P�j�`�i�S�j�j |
�i�P�j����C�f��فC���|��C�ϗ��ՁC����C�W��� |
���זʐρ��T�O�O�u
�i���ӂP�̂P�C�Q�j
|
--- |
��
��P����O��
�K�i�̕����C���~�H�̕����C��~���r�[���̑������ɗނ��錚�z���̕���
�i���ӂP�̂U�C�V�j
�� ��P����l��
�@�B����H��C�s�R�����i�q�ɂȂǂŁC��v�\�������s�R�ޗ��̂��́C���̑������ȏ�ɉЂ̔����̂�����̏��Ȃ��\���̂���
�i���ӂP�̂W�j
�� ��P����l��
H�P�Q�����P�S�R�U���S���ɊY�����錚�z���̕����i�\�Q-�U�V�Q�Ɓi�����ɂ��e�ɘa�j�j
�i���ӂU�j
�� ���Q��
���z�����J�����̂Ȃ����ω\�������h�ΐݔ��i�펞�����͉����m��A���j�Ŋ��S�ɋ�悳��Ă���ꍇ�́C������悳�ꂽ�����͕ʂ̌��z���Ƃ݂Ȃ����@�`�C�ɊY�����邩�ǂ�����������悢�B
���i���ӂT�j
|
|
�i�Q�j�a�@�C�f�Ï��i�a����������́j�C�z�e���C���فC���h�C�����Z��C��h�ɁC���������{�ݓ� |
�� ��P����ꍆ
�P�O�O�u�ȓ��ɖh��悳�ꂽ�����i�����Z��̏Z�˂��Q�O�O�u�ȓ��j
�i���ӂP�̂R�C�S�C�T�j |
|
�i�R�j�w�Z�C�̈�فC�����فC���p��,�}���فC�{�[�����O��C�X�L�[��C�X�P�[�g��C���j��C�X�z�[�c���K�� |
�� ��P�����
�w�Z�C�̈�فC�{�[�����O��C�X�L�[��C�X�P�[�g��C���j��C�X�|�[�c���K�� |
|
�i�S�j�S�ݓX�C�}�[�P�b�g�C�W����C�L���o���[�C�i�C�g�N���u�C�J�t�F�[�C�o�[�C�_���X�z�[���C�V�Z��C���O����C�ҍ��C���H�X�C�����X�C���̓X�܁i���P�O�u�j |
--- |
|
�A |
�� ��P��
�K�����R�ŁC���זʐρ��T�O�O�u�̌��z��
�i���ӂQ�̂P�j |
�������R�Pm�̕����łP�O�O�u�ȓ����Ƃɖh���ǂŋ�悳�ꂽ����
�i�C�̖��������̃`�F�b�N�͕K�v�j
�i���ӂQ�̂Q�j |
|
�B |
�� ��P��
���זʐρ��P,�O�O�O�u�̌��z���ŁC���ʐρ��Q�O�O�u�̋���
�i���ӂR�j |
����
|
|
�C |
�� ��P��
�߂P�P�U���̂Q��P���Q���ɊY������J������L���Ȃ�����
�i���ӂS�̂P�j |
---
�i���ӂS�̂Q�j |
�m���Ӂn
�@�D
���ӂP�j�D
�P�D���T�O�O�u�ɋ�悵�Ȃ��ƂP/�T�O�̊J�������m�ۂ��Ă��r���ݔ��͕K�v�ƂȂ�B
�Q�D���T�O�O�u�ɋ�悵���ꍇ�C�����͂P/�T�O���m�ۂ���n�j�ƂȂ�i��q���C������Ƃ������Ɓj�B
�R�D�����͂P/�T�O�J�����̊m�ۂ��K�v�B
�S�D�Z��͏��ʐρ��Q�O�O�u�̏ꍇ�C���C�P/�Q�O���m�ۂ���Ă���P/�T�O�J�������K�v�Ȃ��B
�T�D�u���ʐρ��P�O�O�u�{���������v�́u������P�S�R�U����P����S���̃n�́i�S�j�v�̕��@������i�P/�T�O�J�����s�K�v�j�B
�U�D���̑������ɗނ��錚�z���̕����Ƃ�
��
�L���C�q�ɋy�ѓ�������
�V�D��q���@�C�A�ȊO�͂P/�T�O�J�����͕K�v�Ȃ��B
�W�D�@�B����H�ꓙ�̗�
�� �r�����ʐςP�T�O�O�u
�A�D
���ӂQ�j�D
�P�D�K���͒n�����܂߂ĎZ�肷�邱�ƁB
�Q�D�P�O�O�u�ȓ����Ƃɖh���������C���P/�T�O���m�ۂ���Ă���Δr���ݔ��͕K�v�Ȃ��Ƃ����Ӗ��i���X�P/�T�O���m�ۂ���Ă��Ă����T�O�O�u�̋�悪����Ă��Ȃ���Δr���ݔ����K�v�Ȃ��߁j�B�u�T�O�O�u�̋��v���C�u�P�O�O�u�̖h�����{�P/�T�O�̊J�����v���ǂ��炩�Ƃ������ƁB
�B�D
���ӂR�j�D
�����̏��ʐς̍��v�ł͂Ȃ��C���ꂼ��̋����̏��ʐς̈ӁB
�C�D
���ӂS�j�D
�P�D�r����̖��������̂��ƁB
�Q�D�����ȊO�̘L���C�q�ɋy�ѓ��������͏������Ƃ������Ƃ����C�n��C�s�����ɂ���Ă͘L�������͊܂߂�悤�w������邱�Ƃ�����i�@�C�A����������Ă��Ă��j�B�Ȃ��C�L�������͍����̊ɘa������B
�����ӂT�j�D
�����Q���̈����͖{���������z���̑����z�ɔ����~�ϑ[�u�Ƃ��Đ݂���ꂽ���̂ł���C�V�z�̌��z���ɂ͓K�p���Ȃ��Ƃ���s����������܂��B�܂��C�K�p����ꍇ�ł��C�s�����ɂ���Ă͌��z���̌`�Ԃ�ʐςɏ��������Ă��܂��B
�Q�l�j�D�Q�����K�p���ꂽ��
�i�R���@�ցF�r���[���x���^�X�W���p���@�\���n�F�{���s�C�j
�戵��
�E
�h����悵�������P�S�R�U���S���ɊY�����錚�z���̕����͕ʂ̌��z���̕����Ƃ݂Ȃ��C�T�O�O�u�ȉ��̋����̗p����ꍇ�̎Z��ɂ��܂܂Ȃ��ėǂ��i���O����j�B
�E
�܂��C�T�O�O�u�ȉ��̋��̏ꍇ�C�L���Ƌ����̊Ԃ͖h�����̐��\�͕K�v�Ȃ��B
�E
�r���v�Z�ɂ��V�䂩��̗L�������́C�g���W�O�����Ƃ���B
�E
�h�ΐݔ��ł���h���ɗp������́C�Չ����\���K�v�B
���ӂU�j�D
�g12����1436���͕���27�N3��18���ɉ������ꓯ���{�s����Ă��܂��B��q�́u
��
003�@��
�����u����12�N���ݏȍ�����1436���v�ɂ���
�v���Q�Ƃ��Ă��������B
�� ���C�����j�D
�E
���o�H�ł���L���Ƌ����Ƃ�h�����Ƃ��邱�Ƃ��C����x����������̂Ŗ]�܂����Ȃ��B
�E ���[�h�������₽��ǂŋ�悳�ꂽ2�ȏ�̖h�����ɋ@�B�r���Ǝ��R�r���p���邱�Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�E
�h�����ŁC��X�ɊԎd�肳�ꂽ���[�h�����Ƃ݂Ȃ��ꍇ�̎戵���i�@��35���C�ߑ�126����2�C3�j
�Ԏd�ؕǂ̏㕔���r����L���ɊJ������Ă���ꍇ��2���i�A������3���͕s�j�ɂ��ẮC�����Ƃ��āC����h�����Ƃ݂Ȃ����̂Ƃ���B�������C�u�r����L���ɊJ������Ă���v�Ƃ́C���̏����ɊY������ꍇ�Ƃ���B
�@ �Ԏd�ؕǂ̏㕔���V��ʂ���50cm�����܂ł̕������J������Ă������ƁB
�A ���Y�J�������̖ʐς����ꂼ���r���S���鏰�ʐς�1/50�ȏ�ł��邱���B
���O�ɑ��đO�̎��i�`�j�{���̎��i�a�i���͂a�C�b�j�j�Ƃ���ƁC�a�i���͂a�C�b�j�����ʐς�1/50�̊J���i��J�j���K�v�ŁC�����`�����S����1/50�̊J���͂`�{�a�i���͂a�C�b�j�̏��ʐς�1/50�ȏオ�K�v�ƂȂ�B
�i�Q�l �F���a46�N12��4���Z�w����905���j
�i�Q�j�r���ݔ��̍\����i�߂P�Q�U���̂R�j�@�T��
���R�r���ݔ� �� �����ɂ��C���R�ɉ���r�o����\��
�@�B�r���ݔ� �� �r���@�ɂ��C�����I�ɉ���r�o����\��
���R�y�ы@�B�r���ݔ��̍\����i�߂P�Q�U���̂R��P���j
�i�ȗ��j
�r���ݔ��̊ɘa�i�����j
���Ӂj�D
�ȉ��C����12�N����1436���͕���27�N3��18���ɉ������ꓯ���{�s����Ă��܂��B��l���ɂ̓C������j���������āC���̂�����ł����Ă��r���ݔ��ݒu�`�����Ə��������̂ŁC�����C���̎����V����������lj����Ă��܂��B���������C�n���C�j����1�����Ƒ���ɂ���C�ꂼ��n���C�j���C�z���ɂȂ��Ă��܂��B
���C��q�́u ��
003�@��
�����u����12�N���ݏȍ�����1436���v�ɂ���
�v���Q�Ƃ��Ă��������B
�k���z��@�W���� �S���l
�i������̑S���ł��B�j
�����P�Q�N�P�S�R�U��
�Ђ����������ꍇ�ɔ���x��̂��鍂���܂ʼn����̓K�X�̍~���������Ȃ����z���̕������߂錏
���z��@�{�s�߁i���a�Q�T�N���ߑ�R�R�W���j��P�Q�U���̂Q��P����܍��̋K��Ɋ�Â��C�Ђ����������ꍇ�ɔ���x��̂��鍂���܂ʼn����̓K�X�̍~���������Ȃ����z���̕��������̂悤�ɒ�߂�B
���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��P�Q�U���̂Q��`����܍��ɋK�肷��Ђ����������ꍇ�ɔ���x��̂��鍂���܂ʼn����̓K�X�̍~���������Ȃ����z���̕����́C���Ɍf������̂Ƃ���B
���@���Ɍf�����ɓK������r���ݔ���݂������z���̕���
�@�C�@��P�Q�U���̂R��P����ꍆ�����O���܂ŁC�掵�������\���܂ŋy�ё�\�ɒ�߂�
�@���@���Y�r���ݔ��́C�P�̖h����敔���i�ߑ�P�Q�U���̂R��P����O���ɋK�肷��h����敔���������B�ȉ������B�j�ɂ̂ݐݒu�������̂ł��邱�ƁB
�@�n�@�r�����́C�펞�J����Ԃ�ێ�����\���̂��̂ł��邱�ƁB
�@�j�@�r���@��p�����r���ݔ��ɂ����ẮC�蓮�n�����u��݂��C���Y���u�̂�����ő��삷�镔���́C�ǂɐ݂���ꍇ�ɂ����Ă͏��ʂ����W�O�p�ȏ�P.�Tm�ȉ��̍����̈ʒu�ɁC�V�䂩��艺���Đ݂���ꍇ�ɂ����Ă͏��ʂ��炨���ނ��P.�Wm�̍����̈ʒu�ɐ݂��C���C���₷�����@�ł��̎g�p������@��\�����邱�ƁB
���@�ߑ�P�P�Q���P����ꍆ�Ɍf���錚�z���̕����i�ߑ�P�Q�U���̂Q��P����y�ё�l���ɊY��������̂������B�j�ŁC���Ɍf�����ɓK��������́B
�@�C�@�ߑ�P�Q�U���P�������攪���܂ŋy�ё�\�������\�܂łɌf����
�@���@�h���ǁi��P�Q�U���̂Q��P���ɋK�肷��h���ǂ������B�ȉ������B�j�ɂ���ċ�悳��Ă��邱�ƁB
�@�n�@�V��i�V��̂Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮC�����B�ȉ������B�j�̍������Rm�ȏ�ł��邱�ƁB
�@�j�@�Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���̎d�グ�����s�R�ޗ��ł��Ă��邱�ƁB
�@�z�@�r���@��݂����r���ݔ��ɂ����ẮC���Y�r���@�́C�P���ԂɂT�O�O㎥�ȏ��ŁC���C�h����敔���̏��ʐρi�Q�ȏ�̖h����敔���ɌW��ꍇ�ɂ����ẮC�����̏��ʐς̍��v�j�P�u�ɂ��P㎥�ȏ��̋�C��r�o����\�͂�L������̂ł��邱�ƁB
�O�@���Ɍf�����ɓK������r���ݔ���݂������z���̕����i�V��̍������Rm�ȏ��̂��̂Ɍ���B�j
�@�C�@��P�Q�U���̂R��P���e���i��O�����r�����̕ǂɂ�����ʒu�Ɋւ���K��������B�j�Ɍf����
�@���@�r�������C���ʂ���̍������C�Q.�Pm�ȏ��ŁC���C�V��i�V��̂Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮC�����j�̍������P/�Q�ȏ��̕ǂ̕����ɐ݂����Ă��邱�ƁB
�@�n�@�r�������C���Y�r�����ɌW��h����敔���ɐ݂���ꂽ�h���ǂ̉��[������ɐ݂����Ă��邱�ƁB
�@�j�@�r�������C�r����C�L���ȍ\���̂��̂ł��邱�ƁB
�l�@���̃C����j�܂ł̂����ꂩ�ɊY�����錚�z���̕���
�@�C�@�K�����Q�ȉ��ŁC���זʐς��Q�O�O�u�ȉ��̏Z��͏��ʐς̍��v���Q�O�O�u�ȉ��̒����̏Z�˂̋����ŁC���Y�����̏��ʐς��P/�Q�O�ȏ�̊��C��L���ȑ����̑��̊J������L�������
�@���@���K���͔��K�̒���K�ŁC���Ɍf�����ɓK�����镔���i���Y��ɓK�����铖�Y�K�̕����i�ȉ��u�K�������v�Ƃ����B�j�ȊO�̌��z���̕����̑S�Ă��ߑ�126����2��1����ꍆ�����O���܂ł̂����ꂩ�C�O�e���Ɍf������̂̂����ꂩ�Ⴕ���̓C�y�уn����z�܂ł̂����ꂩ�ɊY������ꍇ���͓K�������ƓK�������ȊO�̌��z���̕����Ƃ����ω\���̏��Ⴕ���͕ǎႵ���͓����2���ɋK�肷��h�ΐݔ��ŋ�悳��Ă���ꍇ�Ɍ���B�j
�i1�j
���z��@�ʕ\���i���j���Ɍf����p�r�ȊO�̗p�r���͎��������{�ݓ��i��������҂̎g�p������̂������B�j�C�����فC���p�َႵ���͐}���ق̗p�r�ɋ�������̂ł��邱�ƁB
�i2�j �i1�j�ɋK�肷��p�r�ɋ����镔���ɂ�����傽��p�r�ɋ������e�����ɉ��O�ւ̏o�����i���O�ւ̏o���C�o���R�j�]���͉��O�ւ̏o���ɋߐڂ����o���������B�ȉ������B�j�i���Y�e�����̊e�����瓖�Y���O�ւ̏o�����܂ŋy�ѓ��Y���O�ւ̏o�������瓹�܂ł̔���x�Ⴊ�Ȃ����̂Ɍ���B�j���̑����Y�e�����ɑ�����҂��e�Ղɓ��ɔ��邱�Ƃ��ł���o�����݂����Ă��邱���B
�@�n�@���z��@�i���a�Q�T�N�@����Q�O�P���B�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j��Q�V��Q����̊댯���̒����ꖔ�͏�����C�����ԎԌɁC�ʐM�@�B���C�@�ۍH�ꂻ�̑������ɗނ��錚�z���̕����ŁC�@�߂̋K��Ɋ�Â��C�s�R���K�X���ΐݔ����͕������ΐݔ���݂�������
�@�j�@�����R�Pm�ȉ��̌��z���̕����i�@�ʕ\��P�i���j���Ɍf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���̎傽��p�r�ɋ����镔���ŁC�n�K�ɑ�������̂������B�j�ŁC���i�����������B�j�ɂ����Ắi��j���́i��j�ɁC�����ɂ����Ắi�O�j���́i�l�j�ɊY���������
�@�@�i��j�@�Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���̎d�グ�����s�R�ޗ��ł��C���C���O�ɖʂ���J�����ȊO�̊J�����̂����C�������͔��̗p�ɋ����镔���ɖʂ����̂ɖ@��Q���㍆�̃j���ɋK�肷���h�ΐݔ��ŗߑ�P�P�Q����P�S����ꍆ�ɋK�肷��\���ł�����̂��C����ȊO�̂��̂��˖��͔����C���ꂼ��݂�������
�@�@�i��j�@���ʐς��P�O�O�u�ȉ��ŁC��P�Q�U���̂Q��P���Ɍf�����h�����ɂ��������ꂽ����
�@�@�i�O�j�@���ʐςP�O�O�u�ȓ����Ƃɏ��ω\���̏��Ⴕ���͕ǖ��͖@��Q���㍆�̃j���ɋK�肷���h�ΐݔ��ŗߑ�P�P�Q����P�S����ꍆ�ɋK�肷��\���ł�����̂ɂ�����������C���C�Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���̎d�グ�����s�R�ޗ��ł�������
�@�@�i�l�j�@���ʐς��P�O�O�u�ȉ��ŁC�Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���̎d�グ���s�R�ޗ��ł��C���C���̉��n��s�R�ޗ��ő���������
�@�z�@�����R�Pm���錚�z���̏��ʐςP�O�O�u�ȉ��̎����͋����ŁC�ω\���̏��Ⴕ���͕ǖ��͖@��Q���㍆�̓�ɋK�肷���h�ΐݔ��ŗߑ�P�P�Q���P�S����ꍆ�ɐe�肷��\���ł�����̂��������C���C�Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���̎d�グ�����s�R�ޗ��ł�������
�uH�P�Q�����P�S�R�U����ꍆ�`��O���v�r���ݔ��̍\����̊ɘa�̂܂Ƃ�
���Ɍf����\���Ƃ������̂́C�r���ݔ��̍\����̈ꕔ���K�p���O�Ƃ����B
|
��ꍆ
|
�� �r�����̕���ԕێ����̊ɘa
�ȉ��̏��������ꍇ�́C�蓮�J�����u�̐ݒu��r�����̕��펞����Ԃ̕ێ��̋K�肪�K�p����Ȃ��B�x���`���[�^�[����݂����ꍇ�Ȃǂ�����ɊY���B�܂��C�߂P�Q�U���̂R��P�P���i�����Ǘ����Ő��䥊Ď��j�̋K����K�p����Ȃ��B
�@ �P��̖h����敔���ł��邱��
�A �r�����͏펞�J����Ԃ�ێ�
�B �r���@��p����ꍇ�͎蓮�n�����u��݂���B
�i�ǂɐ݂���ꍇ�͏��ʂ���O.�Wm�`�P.�Tm�̍����C�V�䂩��݂艺����ꍇ�́C���ʂ�肨���ނ��P.�Wm�̍����j |
|
��� |
�� �T�O�O�u�ȏ�̖h���ݔ��̍\���̊ɘa
�u�p�r�v
����C�f��فC����C�W��ꓙ�̋q�ȁC�̈�فC�H��C�q�ɓ��̌��z���̕����Ɍ���B
�u�V�䍂�v
�V�䍂�i�V�䂪�Ȃ��ꍇ�͉������j���Rm
�u����v
���̕����Ɩh���ǂŋ�悳��Ă��邱�ƁB
�u�����v
�ǁC�V��̎d�グ��s�R���͏��s�R�ޗ��Ƃ��邱�ƁB
�u�r���@�v
�@�B�r���̏ꍇ�̔r���@�̔r�o�\�͂́��T�O�O㎥/min�C���C�h����敔���ʐςP�u�ɂ����P�u/�����i�Q�ȏ�̖h�����ɌW����̂͂��̏��ʐς̍��v�j�Ƃ��邱�ƁB |
* ���� �T�O�O�u�������Ă��h���Ǖs�v���̕����Ƃ͖h�����
* �ǥ�V��̎d��͕s�R���͏��s�R
�i���}�uH�P�Q�����P�S�R�U������@�r���ݔ��̍\����̊ɘa
�T���}�v�Q�Ɓj
|
|
��O�� |
�� �r�����̈ʒu�̊ɘa
�V�䍂���Rm�ȏ�̌��z���̕����̔r�����̈ʒu�͉��L�Ƃ��邱�Ƃ��ł���i�ʏ�̓V�䂩��W�Ocm�ȓ����ɘa�����j�B
�@ ���ʂ���̍����͂Q.�Pm�ȏ�
�A �V�䍂���̂P/�Q�ȏ�
�B �h���ǂ̉��[����� |
�r�����̗L������
�h����
��H/�Q�����Q.�Pm
H���Rm
�i���}�uH�P�Q�����P�S�R�U����O���@�r���ݔ��̍\����̊ɘa
�T���}�v�Q�Ɓj
|
H�P�Q�����P�S�R�U������r���ݔ��̍\����̊ɘa
�T���}�@�i2006H�j
�ȉ��͔r���ݔ��̍\����̈ꕔ���K�p���O�Ƃ����B
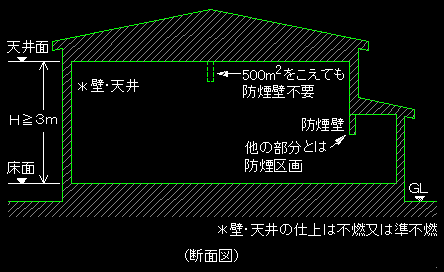
H�P�Q�����P�S�R�U����O���@�r���ݔ��̍\����̊ɘa
�T���}�@�i2006H�j
�ȉ��͔r���ݔ��̍\����̈ꕔ���K�p���O�Ƃ����B
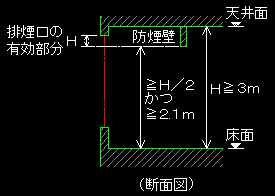
�uH�P�Q�����P�S�R�U����l���v�r���ݔ��̊ɘa�̂܂Ƃ�
�i���ӁD����27�N3��18���ɉ������ꓯ���{�s����Ă��܂��B��l���̃����C�n���C�j����1�����Ƒ���ɂ���C�ꂼ��n���C�j���C�z���ɂȂ��Ă��܂��B�j
���Ɍf���錚�z���⌚�z���̕����ɂ��Ă͔r���ݔ��̐ݒu���Ə������B
�i������̋L�q�ł��B�j
|
|
�@ |
���z���̑Ώە����̈ʒu |
�����̗p�r |
���ʐς̐��� |
���̕��@ |
���n�C�d�グ�̐��� |
|
��l�� |
�j |
�i��j |
�R�Pm�ȉ��̕���
�i�n�K�̓��ꌚ�z���̎傽�镔���͏����j |
��
�i�L���܂ށj
�i���ӂP�j
|
�����Ȃ� |
�������͔��̗p�ɋ����镔���ɖʂ�����͖̂h�ΐݔ��C����ȊO�͌˖��͔���݂���
|
�d�グ�����s�R�ޗ� |
|
�i��j |
���P�O�O�u |
�h���ǂŋ�悷��
�i�����ӂQ�j |
�����Ȃ� |
|
�i�O�j |
���� |
�P�O�O�u�ȓ����Ƃɏ��ω\�����͖h�ΐݔ��ŋ�悷��
|
�d�グ�����s�R�ޗ� |
|
�i�l�j |
���P�O�O�u |
�����Ȃ�
�i�����ӂQ�j |
���n�C�d�グ�Ƃ��s�R�ޗ� |
|
�z |
�R�Pm�������镔�� |
���y�ы��� |
���P�O�O�u |
�ω\�����͖h�ΐݔ��ŋ�悷��
|
�d�グ�����s�R�ޗ� |
|
�C |
�K�����Q�̏Z�����ʼn��זʐρ��Q�O�O�u�C���C�����Ɋ��C��L���ȑ��i�������ʐς̂P/�Q�O�ȏ�j���������
|
|
�n |
�댯���̒�����C�����ԎԌɁC�ʐM�@�B���C�@�ۍH�ꓙ�ŕs�R���K�X�܂��͕������ΐݔ���݂������� |
|
�� |
�i�O�q������27�N3��18�������C�����{�s�̑S���u����1436����P����l�������v���Q�Ƃ��Ă��������B�����������ł��B�j |
���ӂP�j�D��l���j�i��j�C�i��j
�� �� ���i���������j
�����ӂQ�j�D��l���j�i�l�j�C�i��j
�h�����͓V��ʂ���T�Ocm�ȏ㉺���ɓˏo�����h���ǁi����ǁj�ɂ���悷�邱�Ƃ������ł��邪�C�h�������\�����Ă���Ԏd�ؕǓ������������̌����݂���ꂽ�ꍇ�C�˂̏㕔�̕s�R�ޗ��̂���ǂ͂T�O�����K�v�����C�펞�������͉����m��A���̕s�R�ޗ��̌����݂���ꂽ�ꍇ���˂�h���ǂƂ݂Ȃ������C��������R�Ocm�ȏ��i�T�O���������j�Ƃ��邱�Ƃ��ł����B
�Q�l�j�D
�� �uH�P�Q�����P�S�R�U���l���v�K�p�̗��ӎ���
�i���ӁD����27�N3��18���ɉ������ꓯ���{�s����Ă��܂��B�����S���n�͍����S���j�ɂȂ��Ă��܂��B�j
H�P�Q�����P�S�R�U����S���@�r���ݔ��̍\����̊ɘa
�T���}�@�i2006H�j
�ȉ��͔r���ݔ��̍\����̈ꕔ���K�p���O�Ƃ����B
|
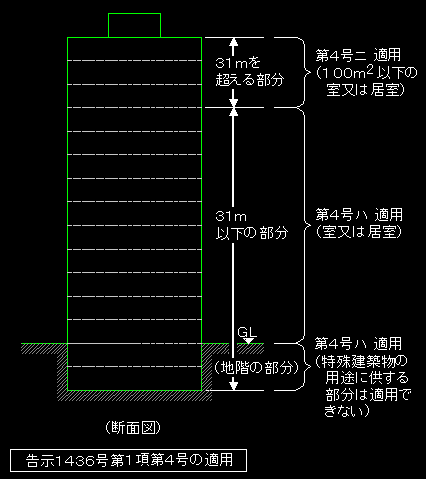 |
�@
�����S���j�̒n���̓��ꌚ�z���̗p�r�ɋ����镔���́C�����������i�c�c���ꌚ�z�����傽��p�r�ɋ����镔���i���j�Œn�K�ɑ�������̂͏����B�j�Ƃ���C�{������K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����C���Y�����̗��p�`�Ԃ����Y�p�r���̂��̂łȂ�����K�p���邱�Ƃ��ł���B
�Ⴆ�Ε��i�̔��X�܂̒n�K�ɂ��鎖���������Y���B
|
�A
�L���̍����K�p�ɂ��Ă͏]���C���̎戵���ɂ��������ꂽ���C�L���ȊO�̗p�r���p�����˂Ȃ���ʓI�ȘL���͢�Ђ̔����̂�����̏��Ȃ�����Ƃ��č����̢����������\�ƂȂ����B���������̈����́C�����܂Ŕ����S���ؖ@�̢�Ђ̔����̂�����̏��Ȃ�����iHl�Q�����P�S�S�O���j�̎�|�܂������̂ł��邽�߁C�a�@���̌��z���ŁC����̎�҂̔��o�H�ƂȂ�ꍇ�ɂ��ẮC�r���ݔ��̐ݒu���]�܂��B
��
�L���̔r���ݔ��͖{���ɕK�v��
�]���C�������iS�S�V�����R�O���C�R�P���C�R�Q���C�R�R���j�ł��ꂼ��ʂɊɘa����Ă����r���ݒu�Ə��̋K�肪�C�V�����iHl�Q�����P�S�R�U���CHl�R�����U�V���j�Ţ�Ђ����������ꍇ�ɔ���x��̂��鍂���܂ʼn����̓K�X�̍~���������Ȃ����z���̕������߂錏��Ƃ����`�ł܂Ƃ߂�ꂽ�B�P�ɐ������ꂽ�����Ŏ戵���̎�|���ς�������̂ł͂Ȃ��B�������]���C�L���̍����K�p�i�������R�R���j�ɂ��Ă͢����ɂࢋ�����ɂ��Y�����Ȃ����̂Ƃ��Ĉ����Ă������C���̘L���i�A�j�ɂ��Ă͐V�����̢����Ƃ��ēK�p���\�ƂȂ����B
�Ȃ��C���߂ŋK�肳��Ă���r���̍\����͏]���C�����Ŕ������������z�������ĊO���ɒǂ������@���Ƃ��Ă������C����ȊO�̔r�������Ƃ��āC���C��L�����ɍs�����Ƃɂ���Ĕ��o�H�ւ̉��g�U��h�~������������������iHl�Q�����P�S�R�V���j�ɒlj����ꂽ�B
��
�B ���h�@�ɂ��C�r���ݔ���ݒu����ꍇ�́C�����Ƃ��Č��z��@�̔r�������͓K�p�ł��Ȃ��B
�� �h�����̍\��
�h���ǂɂ��Ă͗߂P�Q�U���̂Q�Ţ�Ԏd�ؕǁC�V��ʂ���T�Ocm�ȏ������ɓˏo��������Ǔ����s�R�ޗ��ő���C���͕���ꂽ���̣�ƋK�肳��Ă���B
����Nj��͈��w����������~�����邱�Ƃɂ���ĉ��̊g�U��h�~���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��C�Ԏd�ؕNj��͐���ǂ̋@�\�ɉ����C�������߂�ړI���������邱�Ƃ��ł���B�������Ėh�����ɗ��܂������͈��̔r���ݔ��ɂ�艮�O�֔r�o����Ă����B
�h�����ɂ��Ă͎��̓_�ɗ���
�ǂɂ�����
�� ���d�ؕ�
�Ԏd�ؕǂ���������ꍇ�́C���̏㕔�̏��Ǐ�͂R�Ocm�ȏ�Ƃ��C�����̂��s�R�ޗ��i�펞�����j�Ƃ��邱�Ƃ������Ƃ����i�V��܂ł̃t���T�b�V���͖]�܂����Ȃ��j�B
����ǂɂ���� �� �Œ萂���
�V�䗠�܂ŒB����K�v���͌����I�ɂ͂Ȃ��B�K���X�͍����ŕs�R�ޗ��ƒ�߂��Ă���̂Ő���ǂƂ��Ďg�p���邱�Ƃ͂ł���B�������C��U�h�~��h�Ώ�̊ϓ_����C������K���X��ԓ���K���X�������B
����ǂɂ���� �� ���������
��������ǂ̍쓮�ɂ��ẮC�����m�@�A���Ƃ��C����ǂ̋ߐڕ����Ɏ蓮�~�����u��݂���K�v������B�܂��C�쓮��͐���lj��[���珰�ʂ܂ł��P.�Wm�̋�Ԃ��m�ۂ��C���̐ڐG��Q�ƂȂ�Ȃ��悤�ɂ���B�Ȃ��C�G����敔�����h�Υ�h���V���b�^�[��݂���ꍇ�́C����炪����ǂ����˂邱�Ƃɂ͂Ȃ邪�C�Ў��ɉ����m�킪�����Ɋ��m������ւ̘R�������Ȃ����邽�߂ɁC�����Ƃ��āC���̒G����敔���ɋߐڂ����R�Ocm�ȏ�̌Œ�h������݂���K�v������B
�� �����������̖h�����ɂ���
�r���ݔ��̐ݒu�͊e�K���Ƃɂ��ꂼ��h����悵����r�o���邱�Ƃ������Ƃ��邪�C���K�Ƃ��̒���K�C�����K�݂̂ɒʂ����̐�������Ԃɂ����ẮC���̕����̖ʐς��傫������x�Ⴊ�Ȃ��ꍇ��C�H�ꓙ�ŗp�r���ނȂ��ꍇ�͓���̋��Ƃ��邱�Ƃ���ނȂ����̂Ƃ����B
�@ �����������̌����I�Ȗh�����̈���
�i���}���j�@�@�i2006H�j
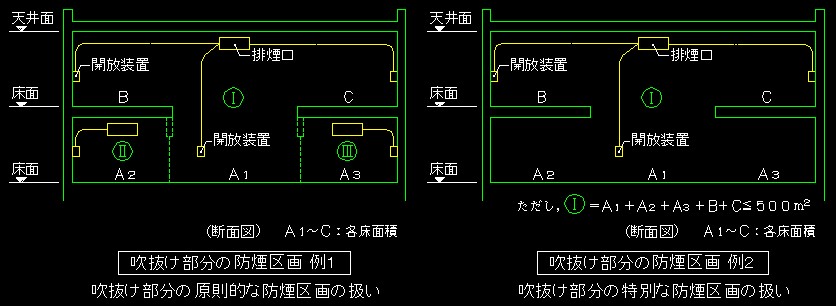
�A �����������̓��ʂȖh�����̈���
�i��}�E�j�@�@�i2006H�j
����x�Ⴊ�Ȃ��ꍇ��p�r���ނȂ��ꍇ�͂P�̖h�����Ƃ��Ĉ����C�J������͐}�Ɏ����ʒu�ɐ݂���B
�� ���R�r���ɂ��Ă̗��ӎ���
�@
�r�����i���j�̓��O�ɃV���b�^�[������ꍇ�̈���
���R�r�����̓��O���ɖh�Ɨp�ȂǂŃV���b�^�[��݂���ꍇ�́C�p�C�v�V���b�^�[���r����x�Ⴊ�Ȃ������Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C�V���b�^�[�������Ă����ԂŌ��z�������p����Ȃ����Ƃ����炩�ȏꍇ�͂��̕K�v�͂Ȃ��B
�A �r�����̎蓮�J�����u�̕���
�O�|�������̎蓮�J�����u�͒P�ꓮ��i�����^�b�`�J�����j�ɂ�葀��ł���K�v������C�`�F�[�������������̂��̂�o�[��|�������̂��̂Ƃ��C�n���h�����̉�]����̏ꍇ�͂P��]���x�ŊJ���ł����������̂�����̂Ƃ������B
�r�����̎蓮�J�����u
�X�e�C�_���o�[�t���r�����̎蓮�J�����u�i���j�̏�����̕ǎ�t�������i���u�̒��S�j�k
�́C�W�O�O���k���P,�T�O�O�Ƃ���B�V�䂩��݂艺����ꍇ�́C���ʂ�肨���ނ��P.�Wm�̍����Ƃ���B
���蓮�J�����u�́C�����^�b�`�J�����Ƃ���B�Ȃ��C�d�C���ɂ����Ă͗\���d����݂���K�v������B
�B
�V�䍂�����قȂ�ꍇ�̗L���J�����̎����@�i2006H�j
�����C�����V�䂩��W�Ocm�ȓ��y�іh���ǂ̉��[�ȏ��i���}�̊e�g�j��L���J�����Ƃ���B
���ϓV�䍂���W�Ocm�ȓ��Ƃ���l����������B
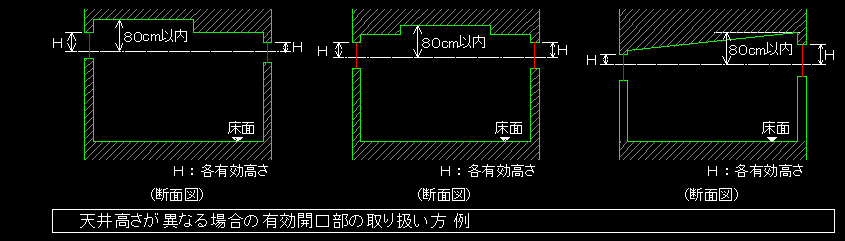
�r�������̓V��̈ꕔ�������ꍇ�͉��}�̎戵���Ƃ���Ă���B�@�i2006H�j
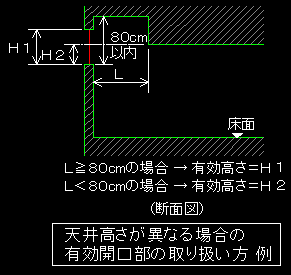
�k���W�Ocm�Ȃ��H�P��L���Ƃ���B�k���W�Ocm�Ȃ��H�Q��L���Ƃ���B
�� ���̑��̗��ӎ����@�i2006H�j
a�D���R�r�����̑O�ʂŁC���ڊO�C�ɊJ��������Ԃ́C�גn���E���i�y�ѓ���~�n���̑��̌��z���Ⴕ���͓��Y���z���̑��̕����j���L�����Q�Tcm�ȏ�����m�ۂ��邱�ƁB�����C�L��C�쓙�̋�n���͐��ʂȂǂɖʂ��镔���ł���Ζ��͂Ȃ��B�Ȃ��C�O�|�����C��]�����͊J�����ꂽ��ԂŁC���R�גn���E������ˏo���Ȃ����ƁB
b�D���R�r�����̓�������q���͓�d�T�b�V��������ꍇ�́C�r�������x�Ⴊ�Ȃ���Δr����L���Ȃ��̂Ƃ��Ĉ������Ƃ��ł���B
c�D�����ɐ݂����x���`���^�[�́C�r�����ʂ����҂ł���̂ŁC���R�r�����Ƃ��Ĉ������Ƃ��ł���B
d�D�_�N�g�ɂ�鎩�R�r���͌����Ƃ��ĔF�߂��Ȃ��B���R�r���̓_�N�g�������v�Z�ł���قLj�肵�Ă��Ȃ����炾�B�������C�c�_�N�g���̓V���t�g�����̕�����p���Ŕr����L���Ȃ��̂ł���ΔF�߂���ꍇ������B
�� �@�B�r���ɂ��Ă̗��ӎ���
�i�ȗ��j
�� ���R�r���J���̊e��f�ʃ^�C�v�i
�߂P�Q�U�̂Q�C�R �j�@�@�i�T���v���t�@�C���_�E�����[�h�j
�g���r���L�����i���j
�b�g���V�䍂�܂��͕��ϓV�䍂�i���j
�r���ݔ��蓮�J�����u�ǖʎ�t �F �e�k�{�O.�W�`�P.�T���@�i�^�V��݂�
�F �e�k�{�P.�Wm�j
�^�C�v�@�� �P�C�Q�C�R-�P�C�S-�P
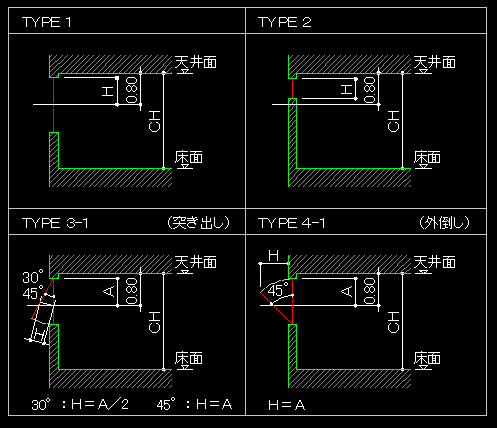
�^�C�v�@�� �T
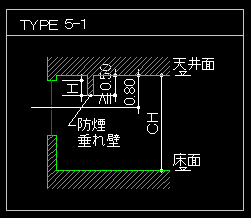
�^�C�v�@�� �X-�P�C�P�O-�P
�V���͎d�l���ȉ��L���邱�ƁB
���i���^�ωΎd�l�i�����ωj�^�K���X�d�l��
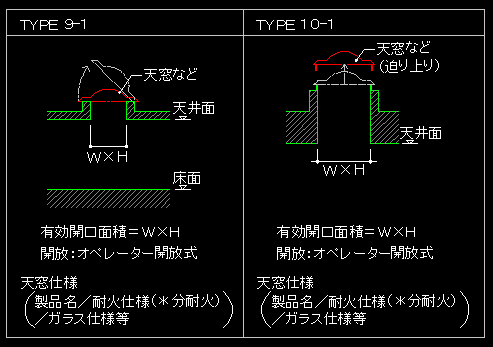
�^�C�v�@�� �S-�Q�C�U-�P
�r�S�U.�P�Q.�S��X�O�T���ʒB�̍l�����@�i�i�b�a�`�w�h�Δ��K��̉���Q�O�O�Q�x�����l�j
��������V��ʂ�艺���W�Ocm�ȓ��ɂ�����̂Ƃ���B
�X�O������>�S�T���̂Ƃ��L���J���ʐ�=�r
�S�T������>�O���̂Ƃ��L���J���ʐ�=�Ɓ^�S�T���~�r
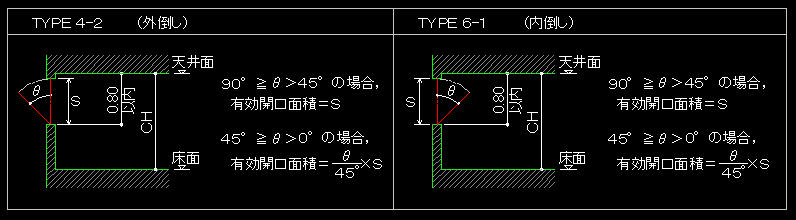
�^�C�v�@�� �R-�Q�C�V-�P�C�U-�Q
�i���j���{���z�Z���^�[�w�r���ݔ��Z�p��x �̍l����
�u�s�x�o�d �V-�P�v�̊O�|�������̔r����L���ȊJ�����Ƃ�
�O�|�������̔r�����̗L���J���ʐς̂Ƃ���ɂ͉�������ɂ����������B�܂��C�����S���ؖ@��K�p����ۂɂ́C���C�v���x�[�X�ɂ����L���J���ʐς̍l�����������C����ɍ����������Ă���B
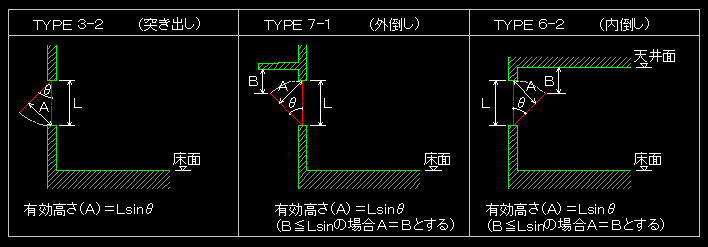
�^�C�v�@�� �V-�P�C�W-�P
�r�S�U.�P�Q.�S��X�O�T���ʒB�̍l�����@�i�i�b�a�`�w�h�Δ��K��̉���Q�O�O�Q�x�����l�j
��������V��ʂ�艺���W�Ocm�ȓ��ɂ�����̂Ƃ���B
�X�O������>�S�T���̂Ƃ��L���J���ʐ�=�r
�S�T������>�O���̂Ƃ��L���J���ʐ�=�Ɓ^�S�T���~�r
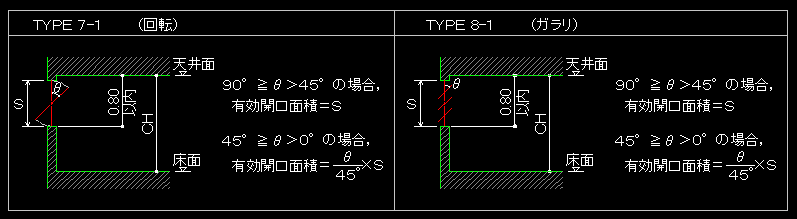
�^�C�v�@�� �P�P�C�P�Q
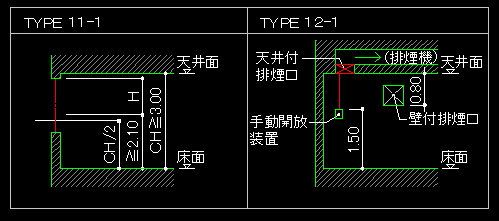
�T���v���t�@�C���_�E�����[�h�@�i���̃t���[���́u�@�K�֘A�����̃_�E�����[�h�v���j
a1_150_houki_check_saikou_etc.dwg�@�@���� ��
README�@�@�@�\��
�FDWF�@HTM�@
�i�ʃE�B���h�E�ŕ\���j�@
�@�K�`�F�b�N�}�@�r��_�̌�_���C�v�Z�\
�i��j
�\�FExcel�����N�\�� �i.ver 2002�j
�r���J���f�ʃ^�C�v�\
�F�]������X�^�C���t�@�C���i.ctb�j
�_�E�����[�h �FT_office_monochrome.ctb�@�@README
�� 002�@�r�����ݒu�ɂ�����V��̍���
�r�����ݒu�ɂ�����V��̍���
�����@�i���}���j�@�i1995K�j
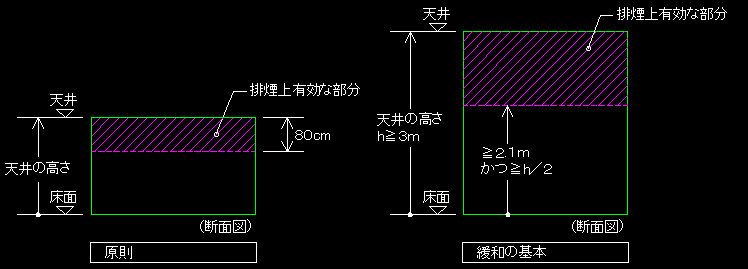
�ɘa�̊�{�@�i��}�E�j
�i���������P�Q�N�P�S�R�U����P����n�C��O�����j
���z�����̏ꍇ�̉��߂P�@�i���}���j�@�i1995K�j�i�u���z���̖h�Δ��K��Ɋւ���^�p�w�j�v�̉��߂ɂ��j
���P�F �����ʂ̍�����V��̍����Ƃ݂�
���Q�F ���ς̍����͌����Ƃ��Ĉ���Ȃ�
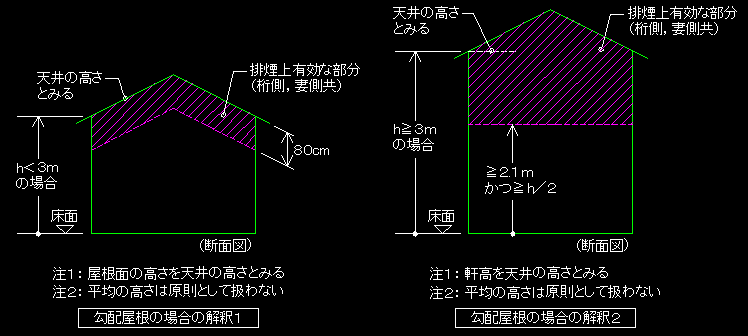
���z�����̏ꍇ�̉��߂Q�@�i��}�E�j�@�i1995K�j�i�u���z���̖h�Δ��K��Ɋւ���^�p�w�j�v�̉��߂ɂ��j
�i���������P�Q�N�P�S�R�U����P����n�C��O�����j
���P�F ������V��̍����Ƃ݂�
���Q�F ���ς̍����͌����Ƃ��Ĉ���Ȃ�
�h���ǂ̍ގ��ɂ���
�h���ǂ͕s�R�ޗ��Ƃ���悤��߂��Ă��邪�C�K���X��p����ꍇ�@�K��i��͖���Ȃ��B�������h�����\�Ɣj�����̈��S��C�ԓ��E�����K���X�Ƃ��C���ʔK���X�E�t���[�g�K���X�Ȃǂ͂Ȃ�ׂ��g�p���Ȃ��悤�ɁB
�����S���ؖ@�i�ߑ�P�Q�X���̂Q�C�ߑ�P�Q�X���̂Q�̂Q�j�@�i2006H�j
�i�P�j�K�����S���ؖ@�̓K�p�͈̔�
�i�Q�j�S�ٔ����S���ؖ@�K�p�͈̔�
�����S���ɂ��K�p���O�ƂȂ�d�l�K��
�h���^���{�݁^���O�ւ̏o���^�r���ݔ��^��������
��L�́C�K�p���O�ƂȂ�K��ł���K�����S���ؖ@�ƑS�ٔ����S���ؖ@�ɂ���ĈقȂ�B
�i�ȉ��ȗ��j
�� 003�@��
�����u����12�N���ݏȍ�����1436���v�ɂ���
�i�����Ƃ��F�����y�ю{�s������27�N3��18���̂��߁C�ȉ������������ł��B�j
���̍��������́C3�����������ߕ���27�N�ł̌��z��@�ɂ͋L�ڂ���Ă��܂���B���y��ʏȂ́u�����E�ʒB�����V�X�e���v�ł�2010�N�Ȍ�̌��z�֘A�����͌��J����Ă��܂���B���������Ηǂ��̂ł������ʂ͎茳�ɖ����C�d�q����̉{��������1�����ԂƂȂ��Ă��܂��B
�u�����̊T���v
�iWeb�T�C�g���j
�r���ɘa�����ƌĂ�镽��12�N���ݏȍ�����1436��������27�N3��18���ɉ������ꓯ���{�s����Ă��܂��B���̉����ŁC���ꌚ�z���łȂ��p�r�ŁC���ڂɉ��O�ɏo�邱�Ƃ��ł��Ă��̂܂ܓ��܂Ŕ��ł��鋏���ɂ��Ă͔r���ݔ��ݒu���Ə�����Ă��܂��B
�����ɂ͋����̐����͋K�肳��Ă��܂��C�����ɏo���ꂽ���Z�w����4784������27�N3��18�����Z�p�I�����ŋ������̕��s������10���ȓ����ڈ��ł��邱�Ƃ��o�����瓹�܂ł̒ʘH�ɂ��Ă����������Ƃ��Ď�����Ă��܂��B
��̓I�ɂ͔r���ɘa�����ƌĂ������1436����l����1���ڒlj�����܂����B�Ȍ��Ɍ����Ɠ�����p�r�ɂ��āC����̏���������ꍇ�͔r���ݔ���ݒu�s�v�Ƃ���Ƃ������̂ł��B
�Q�l�F�V�����r���ɘa�����̈Ӗ�������l�����iWeb�T�C�g���j
���̍������lj����ꂽ�w�i�́C�������z�O���p�u���b�N�R�����g��W�T�v������Ƃ킩��܂��B
����W���̊T�v��蔲��
�����C�p�Z��r���Ȃǂ������X�g�b�N�̊��p�j�[�Y�����܂��Ă��Ă���B
���y��ʏȂł́C���z���̗��p�҂̈��S���m�ۂ��Ȃ�������X�g�b�N���~���Ɋ��p�i���p���i�j�ł���悤�C���ɗv�]�������r���ݔ��̐ݒu�`���̊ɘa�ɂ��Č����s���Ă��Ă���C���ʁC���̐��ʂ�����ꂽ���Ƃ���C�V���ɔr���ݔ��̐ݒu��s�v�Ƃ��镔�������ɒlj�������̂ł���B
�Ȃ��ł����Ƀj�[�Y������̂����������{�ݓ��������悤�ŁC�p�u���b�N�R�����g�̕�W�ӌ����āC����Ɂu�ʕ\1�i���j���ȊO�̗p�r�v�u�����فv�u���p�فv�u�}���فv���Ώۗp�r�Ƃ��ċK�肳��܂����B
�����̔w�i�ɂ́C�������������������{�ݓ��ɗp�r�ύX���₷������C�Ƃ����Ӑ}������悤�ł��B
���C���������������ɏo���ꂽ�u�p�u���b�N�R�����g�̌����v���Q�l�ɂȂ�܂��B�����Ɠ����ɏo����Ă����Z�p�I�����͂���Ɋ�Â��ċL�q����Ă��܂��B
�i�Q�l�F�p�u���b�N�R�����g�Ƃ͍s���E�����̂Ɋւ��p��ŁC���{�̐������ĉߒ��ō�������ӌ������債�C���̈ӎv����ɔ��f�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��鐧�x�B�Ⴆ�s���@�ւ����߂�K�������肵�C�܂��͕ύX���邱�Ƃ��������Ă���ꍇ�ɁC�z�[���y�[�W�Ȃǂł��̑f�Ă����\���C��������ӌ�����B�ӌ����q�ׂ悤�Ƃ��鍑���́C�d�q���[����X�ւȂǒ�߂�ꂽ���@�ɂ��C�����܂łɈӌ����q�ׂ�B�j
�u�����̍��������v �iWeb�T�C�g���j
�g12������1436���͑�ꍆ�����l���ō\������܂��B�ǂ̍��ɊY�����Ă��r���ݔ��ݒu�`�����Ə�����܂��B���̑�l���ɂ̓C������j���������āC���̂�����ł����Ă��r���ݔ��ݒu�`�����Ə��������̂ŁC�����C���̎����V����������lj����Ă��܂��B���������C�n���C�j����1�����Ƒ���ɂ���C�ꂼ��n���C�j���C�z���ɂȂ��Ă��܂��B�܂�C3��18���ȍ~�͂���܂Łu�r�������l-�n-�i4�j�K�p�v�ȂǂƋL�ڂ��Ă������̂��C�u�r�������l-�j-�i4�j�K�p�v�Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B�����͌��z�Ɠ����Ɏ{�s�ς݂ŁC�o�ߑ[�u���͂���܂���B���ꂩ��\�����鎑���ɂ��ẮC�L�ڂ�ς��Ă����܂��傤�B
�lj����ꂽ�����͈ȉ��ł��B
��
���K���͔��K�̒���K�ŁC���Ɍf�����ɓK�����镔���i���Y��ɓK�����铖�Y�K�̕����i�ȉ��u�K�������v�Ƃ����B�j�ȊO�̌��z���̕����̑S�Ă��ߑ�126����2��1����ꍆ�����O���܂ł̂����ꂩ�C�O�e���Ɍf������̂̂����ꂩ�Ⴕ���̓C�y�уn����z�܂ł̂����ꂩ�ɊY������ꍇ���͓K�������ƓK�������ȊO�̌��z���̕����Ƃ����ω\���̏��Ⴕ���͕ǎႵ���͓����2���ɋK�肷��h�ΐݔ��ŋ�悳��Ă���ꍇ�Ɍ���B�j
�i1�j
���z��@�ʕ\���i���j���Ɍf����p�r�ȊO�̗p�r���͎��������{�ݓ��i��������҂̎g�p������̂������B�j�C�����فC���p�َႵ���͐}���ق̗p�r�ɋ�������̂ł��邱�ƁB
�i2�j
�i1�j�ɋK�肷��p�r�ɋ����镔���ɂ�����傽��p�r�ɋ������e�����ɉ��O�ւ̏o�����i���O�ւ̏o���C�o���R�j�[���͉��O�ւ̏o���ɋߐڂ����o���������B�ȉ������B�j�i���Y�e�����̊e�����瓖�Y���O�ւ̏o�����܂ŋy�ѓ��Y���O�ւ̏o�������瓹�܂ł̔���x�Ⴊ�Ȃ����̂Ɍ���B�j���̑����Y�e�����ɑ�����҂��e�Ղɓ��ɔ��邱�Ƃ��ł���o�����݂����Ă��邱���B
�Q�l�j�D
�u����������1436����l�����v�̊m�F�\���p�@�K�`�F�b�N�}�i2�K���ʐ}�j�ł̗��p�� |
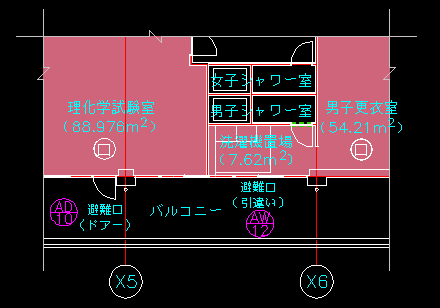 |
���p��ł��B�Q�l�܂łɁB
�^�����{�݂̔r�����C�v�ł��B�����̂܂܂̃T�b�V�ł͎��R�r�����̊m�ۂ�����Ȏ��ō�����1436����l�����𗘗p���Ă��܂��B
���K�p�������n�b�`���O���Ă���܂��B
�c�e�����ɉ��O�ւ̏o�����c�ɊY������o���i�����j
�E
�h�A�[
�E
���Ⴂ
���݂͂̕������̈ȉ������}�Ⴊ�K�v�ł��B
��j�D
�����ȍ�����1436����l����
�e�����ɉ��O�ւ̏o�����C���̑����Y�e�����ɑ�����҂��e�Ղɓ��ɔ��邱�Ƃ��ł���o�����݂����Ă��邱�ƁB
�Q�l�j�D
�ȉ��C������1436����l�i/���j�̊m�F�\���ł̗��p��T���v�����L��܂��B���̐}�Ƃ͕ʂł��B�����R�Ƀ_�E�����[�h���Ă݂Ă��������B
�i���̃t���[���́u�@�K�֘A�����̃_�E�����[�h�v���j�@�@
a1_150_houki_check_hanrei_yoko.dwg�@�@README�@�@�\����
DWF�@HTM
�@�K�`�F�b�N�}�}�� ���i��j
�^�����p��
a1_150_houki_check_hanrei_tate.dwg�@ �@README�@�@�\����
DWF�@HTM
�@�K�`�F�b�N�}�}�� �c�i��j
�^�����p�� |
�i���D�����lj��i1�j�i2�j�ɓK�����镔�������̊K�ɍ��݂��Ă���ꍇ�̈��������G�ł��B�ȉ��u�Q�l�j�D�v���Q�Ƃ��Ă��������B�j
�Q�l�j�D
Web�T�C�g����u�p�u���b�N�R�����g���ʌ���Q&A�����v
�p�u���b�N�R�����g���ʌ����ł́C�V�����̎�舵����l������������Ă��܂��B���ɏd�v�Ǝv����Q&A���ȉ��ɔ������܂��B
Q�F�Ώۗp�r�ɂ��āC�r���ݔ��̐ݒu��s�v�Ƃ���̂́C���z���S�̂��C���z���̕������B
A�F���z���̕����ł��B
Q�F����̊ɘa�̑Ώۂ͊������z���Ɍ��肳���̂��B
A�F�������z���Ɍ��炸�C�V�z�̌��z���ɂ��Ă��{�����̓K�p���\�ł��B
Q�F���������{�ݓ��̒�`�͌��z��@�{�s�ߑ�19���1���ɋK�肷����̂Ɠ������B
A�F�{�����ɂ�����u���������{�ݓ��v�́C�ߑ�19���1���ɋK�肷�鎙�������{�ݓ��������܂��B�������C�q�ǂ��E�q��Ďx���@�̎{�s���i����27�N4��1���j��́C�ߑ�115����3��1����1���ɋK�肷�鎙�������{�ݓ��������܂��B
Q�F�V�l�����@��5����2�ɋK�肳��Ă���u�V�l�����쓙���Ɓv�u�V�l�f�C�T�[�r�X���Ɓv�C�u�V�l�Z���������Ɓv�C�u���K�͑��@�\�^�����쎖�Ɓv�C�u�F�m�ǑΉ��^�V�l���������������Ɓv�C�u�����^�T�[�r�X�������Ɓv���s���{�݂́u���������{�ݓ��v�Ɋ܂܂��̂��C�܂܂�Ȃ��̂��m�ɂ��ꂽ���B
A�F�����̎{�݂ɂ��ẮC�`�ԁE�@�\�ɒ��ڂ��C���Ԃɉ����āu���������{�ݓ��v�Ɋ܂܂�邩�ۂ��f����̂��K���ł���ƍl���Ă���܂��B
Q�F���������{�ݓ��i��������҂̎g�p������̂������B�j�Ƃ́C��̓I�ɂǂ̂悤�ȗp�r���z�肳���̂��B
A�F���������{�ݓ��̂����C�ۈ珊��V�l�f�C�T�[�r�X�Z���^�[�C��q�ی�{�݁C�n�抈���x���Z���^�[���̒ʏ��{�݂�z�����Ă���܂��B
Q�F��h�ɂɂ��Ă��ɘa���C�����X�g�b�N�̊��p�ɂȂ��Ă����ׂ��łȂ����B
A�F�A�Q�̗p�r�ɋ����錚�z���́C�A�Q���̉Ђ̊o�m�E���̒x�ꂪ�z�肳��邽�߁C�{�����̓K�p�O�Ƃ��Ă��܂��B�Ȃ��C��h�ɂɔr���ݔ��̐ݒu�����߂���͉̂��זʐς�500�u����ꍇ�ȂǂɌ����Ă���_�ɂ����ӂ��������B
Q�F�����̖ʐϐ�������������͋K�肳��Ȃ��̂��B
A�F���O�̏o�����͋����̊e��������e�Ղɉ��O�ɔ��ł���ꏊ�ɐ݂�����ȂǁC����x�Ⴊ�Ȃ����̂ł���K�v������܂��B�ʐϐ����͂���܂��C����x�Ⴊ�Ȃ������̊e�������牮�O�̏o�����ւ̕��s�����́C�ڈ��Ƃ��ċ����̏��ʐ�100�u���x��z�肵10m���x�Ƃ��邱�����l�����܂��B
�܂��C���J�n�㑁���ɉ��O�̏o�����Ɏ��邱�Ƃ�z�肵�Ă��܂��̂ŁC���������͂���܂����B
Q�F����x�Ⴊ�Ȃ����̂̋�̓I�Ȋ�������Ăق����B
A�F�u����x�Ⴊ�Ȃ����́v�́C�Ⴆ�Ύ��̂悤�Ȃ��̂�z�����Ă��܂��B
�E�����̊e�������狏���̊O�ɏo��܂ł̕��s�����������x�ȉ��B
�i�ڈ��Ƃ��ċ��������ʐ�100�u���x��z�肵10m���x�j�ł���B
�E�������َ̍݊҂��˂�|���o�������̊J������ʂ������̊O�Ɏx��Ȃ��o����B
�E���O�ւ̏o�����瓹�ɒ��ڒʂ��邩�C���ɒʂ��镝��50�p�ȏ�̒ʘH���̑��̋�n���݂����Ă���B
�E�o���R�j�[���\���ɊO�C�ɊJ������Ă���C���Y�o���R�j�[����n������O�K�i�C���ׂ���C�^���b�v���̓��Y�����َ̍݊҂̓����܂������S�Ȕ��o�H�����m�ۂ���Ă��铙�B
Q�F�e�������L�����Ɩʂ��镔���Ɍ˂�݂��Ȃ����Ƃ��\�ł��邪�C���o�H�ɂȂ�L���⑼�̋����ɉ��𗬓������Ȃ��悤�ɁC�V��ɖh���ǂ̐ݒu���K�v�łȂ����B
A�F�K�������́C�L�����ւ̉��̗������������ꍇ�ł��傽��p�r�ɋ����鋏�����牮�O�Ɉ��S�ɔ��ł���\���ƂȂ��Ă��܂��̂ŁC�h���ǂ̐ݒu�͋��߂Ă��܂����B
Q�F���Y�p�r�ɋ�����S�Ă̋�������ɓK�����Ă��Ă��C�L���������R�r���ƂȂ��Ă��ėߑ�126����2�ɓK������ꍇ�ɂ́C���ω\���̏�����̖h�ΐݔ��ŋ�悳��Ă��Ȃ���C�{�����̓K�p�͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
A�F�K�������ɂ��āC�傽��p�r�ɋ�����e������������Ă���C�L�����̕������܂߁C�{�����̓K�p���\�ł��B���̏ꍇ�C�L�����ɔr���ݔ���݂��Ă��Ă��C��������悷��K�v�͂���܂����B
Q�F�����p�r�{�݂�1�K���������������{�݂ł���ꍇ�ɁC���������{�ݕ������{��ɓK������C1�K�̑��p�r�Ƃ̋��p�����̒ʘH���ɂ��Ĕr���ݔ��̐ݒu��s�v�Ƃł��邩�B
A�F���Y���p�����́C���̗p�r�ł��g�p������̂ł���C�r���ݔ��̐ݒu��s�v�Ƃ͂ł��܂���B�������C���̗p�r�������{�����̊�ɓK�����Ă���C���Y���p�����ɔr���ݔ���݂���K�v�͂���܂����B
Q�F���זʐ�500�u�ȉ��̌��z�����ΏۂƂȂ邩�B�܂��C�K�������Ɋ܂܂��L�����ɂ͔r���ݔ����Ȃ��Ƃ��C�{��̓K�p���\���B
A�F���זʐ�500�u�ȉ��̌��z�����r���ݔ��̐ݒu�����߂�����͖̂{�����̓K�p�ΏۂƂȂ�܂��B�܂��C�K�肷��p�r�ɋ����镔���ɂ�����傽��p�r�ɋ�����e���������������Ă���C���Y�p�r�����̘L�����ɔr���ݔ���ݒu�����ɁC�{��̓K�p���\�ł��B
Q�F�K�������ȊO�̌��z���̕������ߑ�126����2��1����1�������3���܂ł̂����ꂩ���͕���12�N���ݏȍ�����1436����1�������4���܂łɌf������̂̂����ꂩ�ɊY�����r���ݔ���v���Ȃ����̂ł���ꍇ�C�K�������ƓK�������ȊO�̕����̋��E�����ɋK����������̂��B
A�F���̏ꍇ�C���E�����ɓ��i�̗v���͂���܂����B
Q�F�����ƘL������̂ƂȂ����`�Ԃ̎{�݂̏ꍇ�C�L���������r���ݔ��͕s�v�ƂȂ�̂��B
A�F��ɓK������ꍇ�́C�����ƈ�̂ƂȂ����L���������܂߁C�r���ݔ��̐ݒu��v���Ȃ����ƂƂȂ�܂��B
Web�T�C�g���Q�l
�u�q�ǂ��E�q��Ďx���@�v�̎{�s���i����27�N4��1���j��́C���������{�ݓ��̋K����e���ς�镔���͗v�`�F�b�N�ł��B
�ȉ��C����lj����ꂽ�����̊T�v���킩��₷���L�ڂ��ꂽ�����ł��B���Q�l�܂łɁB
�����L�����N���_�E�����]�h�ł���PDF�t�@�C����8�y�]�W����10�y�]�W�ɂ���܂��B
�����N ��
�u�q�ǂ��E�q��Ďx���@���̎{�s�ɔ����c�ۘA�g�^�F�肱�ǂ����̌��z��@��̎戵�����ɂ��āi�Z�p�I�����j�v
�܂��C�q�ǂ��q��Ďx���@�ƌ��z��@�̊֘A�ɂ��Ă͂�����B
�����N ��
�u�q�ǂ��q��Ďx���@�Ɖ������z��@�̊֘A�ɂ��āv
���Ӂj�D�ɘa�̓K�p���镔���ɂ��Ă͋������̋�ʂ͂Ȃ��C�������������͊ɘa�ł���_�C����ɏA�Q�̗p�r������ꍇ�͊ɘa�̑ΏۊO�ƂȂ�_�ɂ����ӁB
�� 004�@�r���ݔ��̐ݒu��̍������i�r���K��̕ʓ��݂Ȃ��K�p�͈̔͂̊g���j�ɂ��ā@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
�����̎�|
�E
���s���x�ł́C�u�J�����̂Ȃ����ω\���̏��E�ǁv���́u�Չ����\��L����h�ΐݔ��v�ŋ�悳��Ă��錚�z���̕����ɂ��ẮC���݂ɉЂ̉e���i���E�K�X�̗����j���ɂ������Ƃ���C���ꂼ���ʂ̌��z���Ƃ݂Ȃ��āC�r���ݔ��̋K���K�p���邱�ƂƂ��Ă���B
�E
���̂��߁C�A�g���E������Đڑ����錚�z���̂悤�ɁC�e���ɂ����Ĕ������鉌���\���ɒ~�ςł���悤�ȋ�Ԃŋ�悳��Ă���ꍇ�ł����Ă�1���Ƃ��Ĉ����邱�ƂƂȂ��Ă���B
�������e
�ȉ��C�A�g���E���ŕʓ��Ƃ݂Ȃ���
| �A�g���E���ŕʓ��Ƃ݂Ȃ��� |
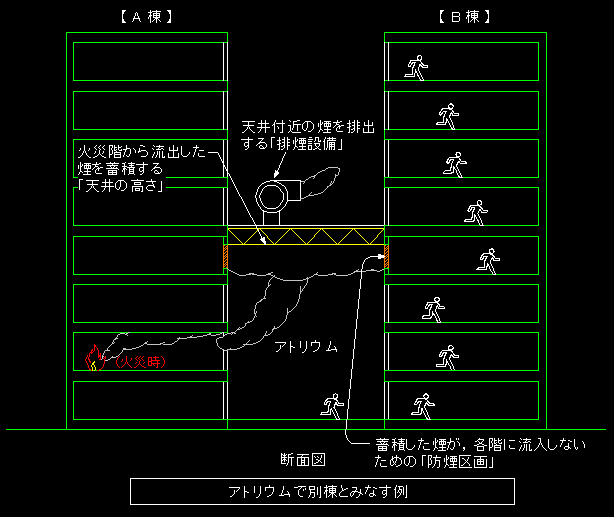 |
���z���́[���̕����yA���z�ʼn����������Ă��C�����yB���z�ɉ����i�����Ȃ��ꍇ�ɂ́C���ꂼ��ʂ̌��z���Ƃ��Ĕr���K���K�p�ł��邱�ƂƂ���B
��j�D�ʓ��Ƃ݂Ȃ��A�g���E�������̏����i�����K�莖���j
(1�j
�Д����̂����ꂪ���Ȃ��p�r�ɋ�������̂ł��邱��
�w���Ζh�~�x
(2�j �V��ƕǂ̓��������s�R�ޗ��ł��邱�� �w���Ζh�~�x
(3) �[��̓V�䍂����L���邱�� �w�~���x
(4�j �r���ݔ����݂����Ă��邱�� �w�r���x
(5�j �V��t�߂ɖh����悪�݂����Ă��邱�� �w�h���x ��
�ʂ̌��z���Ƃ݂Ȃ����ƂŁC�������Ƃɔr���K���K�p����C�ꍇ�ɂ���Ă͔r���ݔ���݂��Ȃ��Ă��悢������������P�[�X������B |
���������E�����K
��
M001�@���������Ɩ����K�ɂ���
���z��@�́u���������v�Ə��h�@�ɂ����颖����K�
���z��@�ł́C�����������ōl����B
���h�@�ł́C�������C�K�ōl����B
�w���z��@�ɂ����颖���������x
���z��@�ł��J������L���Ȃ������������������Ƃ������ƂɂȂ�B���p�̏Ɩ����u�C�r���݊��C���C�ݔ����Ƃ������e���֑[�u�����u���邱�Ƃ��`���t�����Ă���B
���z��@��̖��������Ɋւ���e��K��
| ���z��@��̖��������Ɋւ���e��K�� |
| �K������ |
�� |
���������̒�` |
���������ƂȂ����ꍇ�̋K�� |
| �̌� |
�@�Q�W��
�߂P�X���C�Q�O��
�i�߂P�P�U���̂Q��P����ꍆ�j |
�̌��Ɋւ��Ă͌����p�r�����肳��Ă�����̂́C�K�����̌����p�r�̋����ɂ͊J�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���C��֑[�u�͗�O�������F�߂��Ȃ��
�̌����K�v�Ȍ����p�r�F�Z��C�w�Z�C�a�@�C��h�ɁC���������{�ݓ�
�̌��̊�F�̌���L���ȕ����̊J�����i�����͈��ȏ�̋�n�ɖʂ��镔���j�͊e�����ʐς̂P/�T�`�P/�P�O�ȏ�Ƃ���
�̌���̖�������
�i�ߑ�P�P�U���̂Q��P����ꍆ�j
�ʐρi��20���̋K����v�Z�����̌��ɗL���ȕ����̖ʐςɌ���B�j�̍��v���C���Y�����̏��ʐς��P/�Q�O�ȏ��̂��́B
|
| ���C |
�@�Q�W���Q�� |
���C�ɗL���ȕ����̊J�����������ʐς̂P/�Q�O�����̂��́i���C��̖��������j |
�@�B���C�ݔ��Ƃ���B |
| �r�� |
�߂P�Q�U���̂Q
�߂P�P�U���̂Q��P���� |
�r����L���ȕ����̊J�����i�V�䂩��W�Ocm�ȓ��j�������ʐς̂P/�T�O�����̂���
�i�r����̖��������j |
�@�B�r���ݔ��Ƃ��邩���́C���ݏȍ����ɂ�蓯���ȏ�̂��̂Ƃ��� |
| ���p�Ɩ� |
�߂P�Q�U���̂S
�߂P�P�U���̂Q��P���ꍆ |
�̌���L���ȕ����̊J�����������ʐς̂P/�Q�O�����̂��� |
���p�Ɩ��̐ݒu |
| �������� |
�߂P�Q�W���̂R�̂Q |
���L���ꍆ�������ǂ��炩�̋���
�ꍆ
�T�O�u���鋏���ŁC�r����L���ȕ����̊J�����������ʐς̂P/�T�O�����̂���
��
�����x������K�v�Ƃ����Ƃ��̑��p�r���ނȂ������ō̌����m�ۂ���Ȃ����� |
�ǁC�V��̎d�グ�����s�R�ޗ��Ƃ���B |
| ��v�\���� |
�@�R�T���̂R
�߂P�P�P���P�� |
���L���ꍆ�������̂ǂ��炩�̋���
�i�߂P�P�P���P���j
�ꍆ
�̌���L���ȕ����̊J�����������ʐς̂P/�Q�O�����̂���
��
����L���ȊJ�����ŁC�傫�������V�Tcm�ȏ�C�����P.�Qm�ȏ�Ȃ����̖��́C�Pm�ȏ�̉~�����ڂł��Ȃ����́i����̖��������j
|
��������悷���v�\������ω\�����͕s�R�ޗ��Ƃ���
���j�D
�߂P�P�P������ |
| ���s���� |
�߂P�Q�O���P���̕\���i��j
�߂P�P�U���̂Q��P���P�� |
�̌���L���ȕ����̊J�����������ʐς̂P/�Q�O�����̂��� |
���s�����R�Om�ȓ��Ƃ��� |
�߂P�P�P������������Ă��܂��B
�iWeb�T�C�g��蔲���j
����݂��Ȃ������̂����ω\���Ƃ�����͈̂̔͂̍������ɂ��Ẳ����@�i��111���1���@�@��35����3�j
�����̔w�i�E�T�v
�E
�ߔN�̎Љ�̕ω���Z�p�I�m���̒~�ϓ��܂��C�Ў��ɉЂ̊g���h���C�َ݊҂����S�ɔ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����h�E���W�K��ɂ��āC���S���̊m�ۂ�O��Ƃ��C�����̋K��̍��������s���B
�����̔w�i
�E����݂��Ȃ������́C�Ў��̔����S�����l�����C�ǂ⏰�Ȃǂ̍������\�i�ω\���j�����߂Ă���B
�E�ߔN�C�ˌ��ďZ������y���K���i���������j���V�A�^�[���[���̂悤�ȑ���݂��Ȃ�������ݒu����j�[�Y�����܂��Ă�����̂́C�{�K��������݂��Ȃ������̐ݒu�̎x��ɂȂ��Ă����B
�������e
�E����݂��Ȃ������ł��C�Ў��ɑ����̔��\�ȏꍇ�i�����Е�m�ݔ����ݒu�����i�S�Ă̊K�j�C���ʐς����ȉ��j�ɂ́C���S�����m�ۂ���Ă������Ƃ���C���̕ǂ⏰�Ȃǂ��������\�i�ω\���j��s�v�Ƃ����B
�����j�D
�̌��ɂ́C�@��28���C�@��35���C�@35����3��3�̖@��������C����ɘa�����̂��w�@��35����3�x�݂̂ł��B����̊ɘa���g���Ă��C�c��2�̍̌��̖@���͊ɘa����Ă��Ȃ��Ƃ������ƁB
�Q�l�j�D�̌����������p�Ɩ���OK�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B
������
��P�P�P���i���z��@�{�s�߁j
�y�����̑��̊J������L���Ȃ��������z�@�@��4��
�ω\���A���ω\���A�h�\���A�h��擙�i��107���|��116���j
��P�P�P���@�@��35����3�i�@��87
���3
���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�j�̋K��ɂ�萭�߂Œ�߂鑋���̑��̊J������L���Ȃ������́C���̊e���̂����ꂩ�ɊY�����鑋���̑��̊J������L���Ȃ������i���K���͔��K�̒���K�Ⴕ���͒����K�̋������̑��̋����ł��āC���Y�����̏��ʐρC���Y�����̊e�������牮�O�ւ̏o���̈�Ɏ�����s�������тɌx��ݔ��̐ݒu�̏y�э\���Ɋւ�����x�Ⴊ�Ȃ����̂Ƃ��č��y��ʑ�b����߂��ɓK��������̂������B�j�Ƃ���B
��@ �ʐρi��20���̋K��ɂ��v�Z�����̌��ɗL���ȕ����̖ʐςɌ���B�j�̍��v���C���Y�����̏��ʐς�1/20�ȏ�̂���
��@
���ڊO�C�ɐڂ������L���ȍ\���̂��̂ŁC���C���̑傫�������a1m�ȏ�̉~�����ڂ��邱�Ƃ��ł�����̖��͂��̕��y�э������C���ꂼ��C75�p�ȏ�y��1.2m�ȏ�̂���
2�@
�ӂ��܁C��q���̑������J�����邱�Ƃ��ł�����̂Ŏd��ꂽ2���́C�O���̋K��̓K�p�ɂ��ẮC1���Ƃ݂Ȃ��B
��P�P�P������j�D
����̉����ŁC�ԕ����������lj��ɂȂ��Ă��܂��B�v��ƁC�����̓��e�ɓK���������������C�̌��̑���݂���K�v�͖����Ƃ������ƁB���K���͒���K�C�����K�Ɍ���ɘa�\�ƂȂ��Ă���B
�厖�Ȃ͈̂ȉ��̍����̓��e�i���y��ʑ�b����߂��ɓK��������́j�B
�ȉ��C������249���̉���}
| �@����݂��Ȃ����������@�@������249������} |
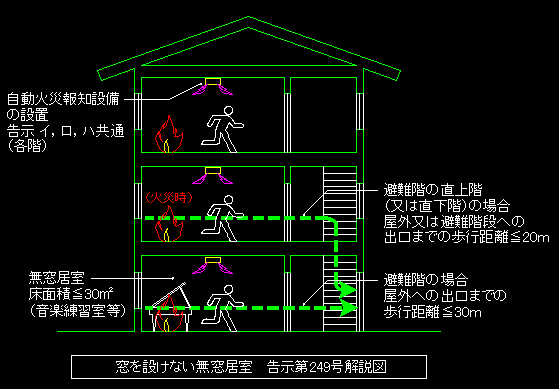
|
������249���@��v�\������ω\�����Ƃ��邱�Ƃ�v���Ȃ�����x�Ⴊ�Ȃ������̊���߂錏
���z��@�{�s��(�ȉ��u�߁v�Ƃ����B)��111���1���ɋK�肷�����x�Ⴊ�Ȃ������̊�́C���Ɍf������̂Ƃ���B
��@���̃C����n�܂ł������ꂩ�ɊY�����邱�ƁB
�C�@���ʐς�30�u�ȓ��̋���(�Q���C�h�������̑��̐l�̏A�Q�̗p�ɋ�������̂������B�ȉ������B)�ł��邱�ƁB
���@���K�̋����ŁC���Y�����̊e�������瓖�Y�K�ɂ��������O�ւ̏o���̈�Ɏ�����s������30���ȉ��̂��̂ł��邱�ƁB
�n�@���K�̒���K���͒����K�̋����ŁC���Y�����̊e����������K�ɂ����鉮�O�ւ̏o�����͗ߑ�123���2���ɋK�肷�����O�ɐ݂�����K�i�ɒʂ���o�����̈�Ɏ�����s������20���ȉ��̂����ł��邱�ƁB
��@��110����5�ɋK�肷���ɏ]�����x�u(�����Е�m�ݔ��Ɍ����B)��݂������z���̋����ł��邱���B
�ȏ�̍����ɓK����������C���������i�@��35����3�j�Ƃ��邱�Ƃ��ł����B
��������j�D
���̍����ɓK��������ׂɂ́C�u��v�u��v���K�������邱�ƁB
�K�����閳���������C���Y������������悷����v�\������ω\���Ƃ��邱�Ƃ�v���Ȃ����ƂƂ����B
�u��v�́e�����ꂩ�ɊY���f�͂����ꂩ1�I�����ēK��������悢�B
���� �C�C���C�n���ʂ��C�x��ݔ��i�����Е�m���j���ɘa���p���������i�e�K�j�ɐݒu���邱�ƁB
�x�u�̏ڍ��ɂ��Ắw��110����5�x�ɋK�肷����̂Ƃ���C���̒��ł������Е�m��Ɍ���Ƃ���C�w����198����ꍆ�x�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�x��ݔ��́C�Ў��ɑ����ɉЏ���`�B���C�َ݊҂̓����x�����������B
���ʐ�30�u�ȓ��́C�Ў��ɑ����ɔ��邱�Ƃ��\�ɂ���B
|
���ӂƂ܂Ƃ߁j�D
����̊ɘa�͎g���₷�����ǁC�Ƃɂ������ɂ��̌��̏����鎖�����Y��Ȃ��B
����C�u��v�̌x��ݔ��i�����Е�m��j�����ݒu����C�u��v�͂��Ȃ�ɂ��̂ŁC���Ɨ��p���₷���ł��傤�B
�w���h�@�ɂ����颖����K��x�@�@�i�����K�����\�@�T���v���t�@�C���_�E�����[�h�j
���h�@�ɂ����Ă͖����͂ǂ̂悤�ɍl�����Ă���̂��B
���h�@�ł́C�Г������������ꍇ�̂��̏��Ί�������є���̍�������������K��P���i�ȉ�������K��Ƃ����j�Ƃ��Ĉ����Ă���C���̓_��������������P���Ƃ��Ĉ����Ă������z��@�Ƃ̑傫�ȑ��ٓ_�ł���B
���h�@�������K�̊T�O�����h�@�{�s�ߑ�P�O���P����܍��Ţ���z���̒n��K�̂����C���㖔�͏��Ί�����L���ȊJ������L���Ȃ��K��Ƃ���Ă���C�L���ȊJ�����̐��@��`��\���������h�@�{�s�K����T���̂Q�Ɏ�����Ă���B
�ߑ�10���k���h�@�{�s�߁l
�y���Ί��Ɋւ����z
��10���@
���Ί햔�͊ȈՏ��Ηp��i�ȉ��u���Ί��v�Ƃ����B�j�́C���Ɍf����h�ΑΏە����͂��̕����ɐݒu������̂Ƃ���B
�i�r���ȗ��j
�܁@ �O�e���Ɍf����h�ΑΏە��ȊO�̕ʕ\��1�Ɍf���錚�z���̒n�K�i�n�����z���ɂ����ẮC���̊e�K�������B�ȉ������B�j�C�����K�i���z���̒n��K�̂����C�����ȗ߂Œ�߂���㖔�͏��Ί�����L���ȊJ������L���Ȃ��K�������B�ȉ������B�j����
3�K�ȏ�̊K�ŁC���ʐς�50�u�ȏ�̂���
�i�ȉ��ȗ��j
�i���㖔�͏��Ί�����L���ȊJ������L���Ȃ��K�j
�i��������K��j
�K����5����2 �@�ߑ�10���1����܍�
�̑����ȗ߂Œ�߂���㖔�͏��Ί�����L���ȊJ������L���Ȃ��K�́C�P�P�K�ȏ�̊K�ɂ��Ă����a�T�O�p�ȏ�̉~���������邱�Ƃ��ł���J�����̖ʐς̍��v�����Y�K�̏��ʐς��P/�R�O����K�i�ȉ��u���ʊK�v�Ƃ����B�j�ȊO�̊K�C�P�O�K�ȉ��̊K�ɂ��Ă����a�Pm�ȏ�̉~���������邱�Ƃ��ł���J�������͂��̕��y�э��������ꂼ���V�T�p�ȏ�y�тP.�Qm�ȏ�̊J�������Q�ȏ��L�������ʊK�i���j�ȊO�̊K�Ƃ���B
�Q �@�O���̊J�����́C���̊e���i11�K�ȏ�̊K�̊J�����ɂ��ẮC��������B�j�ɓK��������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�� �@���ʂ���J�����̉��[�܂ł̍����́C�P.�Qm�ȓ��ł��邱�ƁB
�� �@�J�����́C�����͓��ɒʂ��镝���Pm�ȏ��̒ʘH���̑��̋�n�ɖʂ������̂ł��邱�ƁB
�O �@�J�����́C�i�q���̑��̓�������e�Ղɔ��邱�Ƃ�W����\����L���Ȃ����̂ł���C���C�O������J�����C���͗e�Ղɔj�邱�Ƃɂ��i���ł�����̂ł��邱�ƁB
�l �@�J�����́C�J���̂��ߏ펞�ǍD�ȏ�ԂɈێ�����Ă�����̂ł��邱�ƁB
���j
�v��
���a�Pm�ȏ�̉~�����ڂ��邱�Ƃ��ł���J�������͂V�T�p�ȏ�y�тP.�Qm�ȏ�̊J�������Q�����ȏ��L���C���C���̊J�������i�v���X�j���a�T�O�p�ȏ�̉~�����ڂ��邱�Ƃ��ł���J�����̖ʐς̍��v�����̊K�̏��ʐς̂P/�R�O����K�i���ʊK�j
���z��@�ł��̌��C���C�����ꂼ��̖ړI�����J�����̐ݒu���̂��̂��`���Â����Ă���̂ɑ��C���h�@�ɂ����閳���K�̋K��́C�J�����̐ݒu���`���Â�����̂ł͂Ȃ��C���z�������h������C����ł̈��S����}����̔��f�v�f�Ƃ��ĊJ��������舵���Ă�����̂ł���B�܂�C�L���ȊJ�������ݒu����Ă���ɂ��������Ƃ͂Ȃ����C�ݒu����Ă��Ȃ��Ȃ���C���h������̍����������̂ŁC���̕����h�p�ݔ����̐ݒu����C��ʂ̊K��苭�����悤�Ƃ��������Ȃ̂ł���B
��1�j�D���Ί�
���Ί�̐ݒu�ōl���Ă݂�ƁC�Q�K���������̏ꍇ�C���ʊK�i�P/�R�O�̋K����m�ۂ̊K�j�ł���Ȃ�Ώ��Ί�̐ݒu�͕K�v�Ȃ����C�P�C�Q�K�Ƃ������K�ŁC���ʐς��e�X�T�O�u�ȏ�����C���ꂼ��̊K�Őݒu���`���Â�����B
��Q�j�D�������ΐ�
���l�ɉ������ΐ��̏ꍇ�C�������r���̏ꍇ(�������C�����ɂ��ɘa��K�p���Ȃ����̂Ƃ���)�C���ʊK�ł���P�K����R�K�܂ł��ׂĐݒu�͕s�v�����C�����K�Ȃ�ΑS�قɐݒu���K�v�ƂȂ��Ă���B
���Ί�Ɖ������ΐ��̐ݒu���������Ă��C���ꂾ���������K����������̂�����C�����ɖ������z�����ɂ���Ȃ��s�o�ςȂ��̂��C���킩�肢��������Ǝv���B
���h�@�ɂ����颖����K��Ɣ��肳����
�����K�ƂȂ�Ώ��h�p�ݔ��̖w�ǂ̎�ނŐݒu��ɔ����ȕω���������B
�������ΐ�ݔ��E�X�v�����N���[���ΐݔ��E���Ί��E�����Е�m�ݔ��E���x��ݔ��E�������h�p�ݔ��̐ݒu��ɂ����āC�����̗p�r�C�ʐρC�K���C���e�l�����Ɠ������炢��Ȋ�ƂȂ�B�ݔ��̐ݒu���������C�����K�ɂȂ�������Е�m�ݔ��̊��m��̎�ʂ����d�������m���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��C���낢��Ȑ������B���̐�����ɘa���邽�߂ɁC�P�K�Ȃǂɐݒu����傫���V���b�^�[�Ȃǂ��C�O������|���v�Ԃ̐����ɂ���ĊJ���邱�Ƃ��o���������V���b�^�[�ɂ��Ă��錚������������B
�Q�l�j�D�m�F�\���̐}�ʕ\�L���ɂ���
�����K����W�i���h�j
�E
����̊J�����ɂ͎{�����@�L���邱�ƁB
�E
�L�[�v�����ƌ���\��Y�t���邱�ƁB
�����K�����\�@�T���v���t�@�C���_�E�����[�h�@�i���̃t���[���́u�@�K�֘A�����̃_�E�����[�h�v���j
a1_150_houki_check_shick_musoukai.dwg�@�@���� ��
README�@�@�@�\��
�FDWF�@HTM�@
�i�ʃE�B���h�E�ŕ\���j�@
�@�K�`�F�b�N�}�@�V�b�N�n�E�X�����\�C�����K�����\
�i��j
�\�FExcel�����N�\�� �i.ver 2002�j
a1_150_houki_check_musoukai.xls�@
���h�@�ɂ�閳���K�̌����@�@�i��LDWG����N�����ĕۑ��������́B�@.ver 2002�j
�Q�l�j�D
a1_150_houki_check_shick.xls�@
�V�b�N�n�E�X�g�p���z�ޗ��\�@�@�i��LDWG����N�����ĕۑ��������́B�@.ver 2002�j
�F�]������X�^�C���t�@�C���i.ctb�j
�_�E�����[�h �FT_office_monochrome.ctb�@�@README
������K��̍ו����ӎ����@�i2009W�j
�����K�ȊO�̊K�̔���́C�K����T���̂Q�ɂ��ق��C�ו��ɂ��Ă͎��ɂ���舵�����ƁB
�P �J�����̈ʒu
�i�P�j �K����T���̂Q��Q����P���ɋK�肷��u���ʂ���J�����̉��[�܂ł̍����v�ɂ��ẮC���ɂ�邱�ƁB
�A ����͌����Ƃ��ĔF�߂Ȃ����C���̏����̂��ׂĂɓK������ꍇ�͂��̌���ł͂Ȃ��B
�i�A�j �s�R�ޗ��ő����C���C���łȍ\���ł��邱�ƁB
�i�C�j
�J�������݂����Ă���ǖʂƂ����Ԃ��Ȃ����ʂɌŒ肳��Ă��邱�ƁB
�i�E�j ������30cm�ȉ��C���s��30cm�ȏ�C���͊J�����̕��ȏ�ł��邱�ƁB
�i�G�j ����̏�[����J�����̉��[�܂�1.2���ȓ��ł��邱�ƁB
�i�I�j ����x�Ⴊ�Ȃ����ƁB
�C
�J�������e�ՂɊO�����Ƃ��ł��Ȃ��V���Ŏd���Ă���ꍇ�́C���[�����ʂ���1.2���ȓ��ɂ���J�����݂̂�L���J���Ƃ��Ď�舵�����ƁB
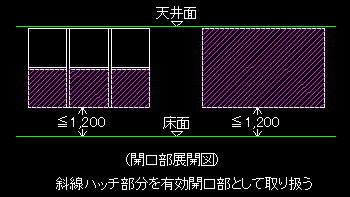
�i�Q�j �K����T���̂Q��Q����Q���ɋK�肷��u�ʘH���̑��̋�n�v�ɂ��āC���Ɍf�����n���́u�ʘH���̑�
�̋�n�v�Ƃ��Ď�舵�����Ƃ��ł���B
�A
�����͒n�������c�̓��̊Ǘ���������ŏ����ɂ킽���ċ�n�̏�Ԃ��ێ���������
�C
�����͓��ɒʂ��镝���P���ȏ�̒ʘH�ɒʂ��邱�Ƃ��ł���L��C���z���̉���C��C�o���R�j�[�C�����C
�K�i��̕����Ŕ��y�я��Ί������L���ɂł������
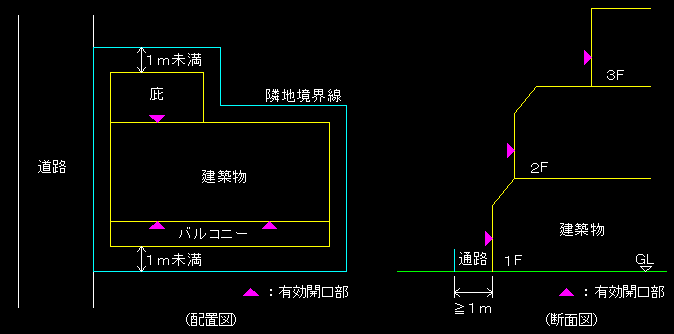
�E �P���ȓ��̋�n���͒ʘH�ɂ�����C�ւ����̑��̍H�앨�Ŕ��y�я��Ί����̖W���ɂȂ�Ȃ�����
�G �X�Βn�C�͐�~���̑����Ί������L���ɍs�������
�I ���͂������ň͂��Ă��钆�듙�ŁC���Y���납�瓹�ɒʂ���ʘH������C���̂��ׂĂɓK���������
�i�A�j �ʘH�̕����͂P���ȏ�ł��邱�ƁB
�i�C�j
����ɖʂ��镔���ȊO�̗L���O�ǂɒ��a�P���ȏ�̉~�����ڂ��邱�Ƃ��ł���J�������͂��̕��y�э�
�������ꂼ��75cm�ȏ�y��1.2���ȏ�̊J�������Q�ȏ゠�邱�ƁB
�i�E�j
����ɖʂ��镔���ȊO�̗L���O�ǂ̊J�����ŕK�v�ʐς̂Q���̂P�ȏ���m�ۂł��邱�ƁB
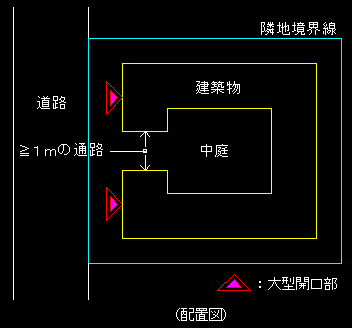
�i�R�j �K����T���̂Q��Q����S���ɋK�肷��u�J���̂��ߏ펞�ǍD�ȏ�ԁv�ɂ��āC���Ɍf�����Ԃ́C�펞
�ǍD�ȏ�ԂƂ��Ď�舵���B
�A �i�q�C���[�o�[�C�L�����C���������̑��̐ݔ��ɂ����y�я��Ί�����W���ɂȂ�Ȃ����́B
�C �J�����ƊԎd�ؕǓ��̊ԂɒʘH��݂��C�Ԏd�ؕǓ��ɏo������L���ɐ݂������̂ŁC���̂��ׂĂɓK����
�����
�i�A�j �ʘH�͒ʍs���͉^���݂̂ɋ�����C���C�R���������u����Ă��Ȃ����Ɠ��펞�ʍs�Ɏx��Ȃ����ƁB
�i�C�j
�ʘH�y�ъԎd�ؕǓ��̏o�����̕����͂����ނ˂P���ȏ�ł��邱�ƁB�i���̏ꍇ�C�ʘH�̕������ꏊ��
���قȂ�ꍇ�͂��̍ŏ��̂��̂Ƃ���B�j
�i�E�j
�Ԏd�ؕǓ��̏o�����ƊO�ǂ̓��Y�J�����Ƃ̕��s�����́C�����ނ�10���ȉ��ł��邱�ƁB
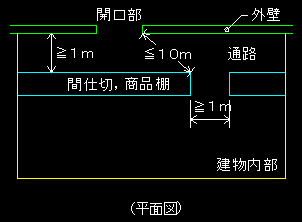
�Q �J�����̍\��
�K����T���̂Q��Q����R���ɋK�肷��u�O������J�����A���͗e�Ղɔj�邱�Ƃɂ��i���ł�����́v�Ƃ��āA���Ɍf����J������L���J�����Ƃ��Ď�舵�����Ƃ��ł���B
�i�P�j �K���X��
�\�|�P�Ɍf������́B�������A�����ȊO�̂��̂ł����Ă��A�O������̈ꕔ�j�ɂ��J���ł���ƔF�߂���ꍇ�́A���ۂɊJ�����镔����L���J���Ƃ��Ď�舵�����Ƃ��ł���B
�i�Q�j �V���b�^�[�t�J����
�A
���K�ɐ݂���ꂽ�蓮���y�ʃV���b�^�[�t�̊J�����i�V���b�^�[�̒ꕔ�Ɏ{���@�\��������̈ȊO�ɂ����ẮA���O���琅���ʼn����ł��鑕�u��������ꍇ�Ɍ���B�j
�C
�����Z��̉J�˂Ƃ��Đ݂���ꂽ���̂ŁA�J�����Ɍ���ߑ�126���̂V��T���ɒ�߂�\���̂��̖��͂���Ɠ����̏��h�����X�y�[�X���m�ۂ���A���A���O�����h��������ȍH���p���邱�ƂȂ��e�ՂɊJ���ł���蓮���y�ʃV���b�^�[�t�J�����i�i�h�r
�` �S�V�O�S�Œ�߂�X���b�g�̔���1.0mm�ȉ��̂��̂Ɍ���B�j
�E
�����m��̍쓮�ƘA�����ĉ�������蓮���y�ʃV���b�^�[�t�J�����i���d���t�Ɍ���B�j
�G
�����O����J���ł���d�����V���b�^�[�t�̊J�����i���d���t�Ɍ���B�j
�I
�����m��̍쓮�ƘA�����ĊJ������d�����V���b�^�[�t�̊J�����i���d���t�Ɍ���B�j
�J
�h�ЃZ���^�[�A�����Ǘ������̏펞�l������ꏊ���牓�u���u�ɂ��J���ł���d�����V���b�^�[�t�̊J�����i���d���t�Ɍ���B�j
�L
���O���琅���ɂ���ĊJ���ł��鑕�u��������d���V���b�^�[�t�̊J����
�i���j���d���́A���Ɣ��d�ݔ��A�~�d�r�ݔ����͔R���d�r�ݔ��ɂ����̂Ƃ��A���d����H�́A�ωΔz���Ƃ��邱�ƁB
�i�R�j �h�A
�A
�蓮���h�A�i�n���K�[���̂��̂��܂ށB�j�ʼn����O����e�ՂɊJ���ł�����̂������A�K���X������L����蓮���h�A�̂����A���Y�K���X��e�Ղɔj�邱�Ƃɂ������̎{���������ł�����̂��܂ށB
�C
�d�����h�A�ŁA���́i�A�j���́i�C�j�̂����ꂩ�ɊY���������
�i�A�j ���ʃK���X�Ŕ��U�o�ȉ��̂���
�i�C�j
��d���ł����Ă����d���̍쓮���͎蓮�ɂ��J���ł������
�i�S�j ��d��
�i�P�j����i�R�j�܂ł̊J�������g�ݍ��킳�ꂽ���́i�L���J���̎Z��ɂ��ẮA�J���ʐς̏��Ȃ����ōs���B�j�������A�ݒu�̏�����㖔�͏��Ί�����L���łȂ��ƔF�߂���̂������B
�\�|�P
�i �i�P�j �K���X�� �̎戵���j
�J�����̃K���X
�̎�� |
�K���X�̌��� |
�J�����̌`�� |
�� �� |
| ����L�� |
���ꖳ�� |
| ���ʃK���X |
6.0�o�ȉ� |
�����Ⴂ�� |
�� |
�� |
| �e�h�w |
�� |
�� |
| �S������K���X |
6.8�o�ȉ� |
�����Ⴂ�� |
�� |
�� |
| �e�h�w |
�~ |
�~ |
| 10.0�o�ȉ� |
�����Ⴂ�� |
�� |
�� |
| �e�h�w |
�~ |
�~ |
| �ԓ���K���X |
6.8�o�ȉ� |
�����Ⴂ�� |
�� |
�� |
| �e�h�w |
�~ |
�~ |
| 10.0�o�ȉ� |
�����Ⴂ�� |
�� |
�� |
| �e�h�w |
�~ |
�~ |
| �����K���X |
5.0�o�ȉ� |
�����Ⴂ�� |
�� |
�� |
| �e�h�w |
�� |
�� |
| �ϔM���K���X���P |
5.0�o�ȉ� |
�����Ⴂ�� |
�� |
�� |
| �e�h�w |
�� |
�� |
| ���킹�K���X |
���Q |
�����Ⴂ�� |
�� |
�� |
| �e�h�w |
�~ |
�~ |
| ���R |
�����Ⴂ�� |
�� |
�~ |
| �e�h�w |
�~ |
�~ |
| ���w�K���X |
�\������K���X���Ƃɖ{�\�i���킹�K���X�������ق��A�ԓ���K���X�y�ѓS������K���X�ɂ����ẮA����6.8mm�ȉ��̂��̂Ɍ���B�j�ɂ��]�����A�S�̂̔��f���s���B |
���P
���x�����ʃK���X�i����6.0mm
�ȉ��j�Ɠ����̂��̂Ɍ���B�i��F�ϔM�������K���X�i���i���u�t�@�C�A���C�g�v�j�j
���Q
�@ �t���[�g�K���X�i����6.0mm
�ȉ��j�{�o�u�a�i�|���r�j���u�`���[���j�i30mil�i����0.76mm�j
�ȉ��j�{�t���[�g�K���X�i����6.0mm
�ȉ��j�̍��킹�K���X
�A �ԓ��K���X�i����6.8mm
�ȉ��j�{�o�u�a�i�|���r�j���u�`���[���j�i30mil�i����0.76mm�j��
���j�{�t���[�g�K���X�i����5.0mm �ȉ��j�̍��킹�K���X
���R
�@ �t���[�g�K���X�i����5.0mm
�ȉ��j�{�o�u�a�i�|���r�j���u�`���[���j�i60mil�i����1.52mm�j
�ȉ��j�{�t���[�g�K���X�i����5.0mm
�ȉ��j�̍��킹�K���X
�A �ԓ��K���X�i����6.8mm
�ȉ��j�{�o�u�a�i�|���r�j���u�`���[���j�i60mil�i����1.52mm�j��
���j�{�t���[�g�K���X�i����6.0mm �ȉ��j�̍��킹�K���X
�B �t���[�g�K���X�i����3.0mm�ȉ��j�{�o�u�a�i�|���r�j���u�`���[���j�i60mil�i����1.52mm�j
�ȉ��j�{�^�K���X�i����4.0mm�ȉ��j�̍��킹�K���X
�m�}��n
�� �c
�J�����S�̂�L���J�����Ƃ��ĎZ��ɉ����邱�Ƃ̂ł������
�� �c �K���X���ꕔ�j�A�O������J���ł��镔���i�����Ⴂ�˂̏ꍇ�͊T��1/2�i���ۂɊJ���ł��镔���j�j��L���J�����Ƃ��ĎZ��ɉ����邱�Ƃ̂ł�����́i�N���Z���g��o�[�n���h�����̂Ɍ��t���ƂȂ��Ă��铙�̓���Ȃ���
�ɂ��ẮA�ʂɔ��f���邱�Ɓj�B
�~ �c
�L���J�����Ƃ��Ĉ����Ȃ�����
�i���P�j
�@
�u����L��v�Ƃ́A���K���͊O���o���R�j�[�A����L�ꓙ�j���Ƃ̂ł��鑫�ꂪ�݂����Ă����
�̂������B�܂��A�o���R�j�[�Ƃ́A����ߑ�126���̂V�ɒ�߂�\���̂��̖��͂���Ɠ����̂��̂������B
�A
�u�����Ⴂ�ˁv�Ƃ́A�ЊJ���A�J���˂��܂߁A�ʏ�͕���������J���ł��A���A���Y�K���X���ꕔ�j
�邱�Ƃɂ��A�O������J�����邱�Ƃ��ł�����̂������B
�B �u�e�h�w
�v �͛ƂߎE�����������B
�i���Q�j����ɂ���
�� ��́C���p�i�����ɑ���J�����̏ꍇ�C�ꕔ�قȂ�̂Œ��ӁB
��D�����K���X5.0�o�ȉ��̂e�h�w
�� �~ �C�~�@�Ȃ�
���C�����s��������h�@�ւɂ���Č������ꗥ�ł͂Ȃ��̂Ŏ��O�̊m�F���Ă������ƁB
�\�|�Q�@�L���J����
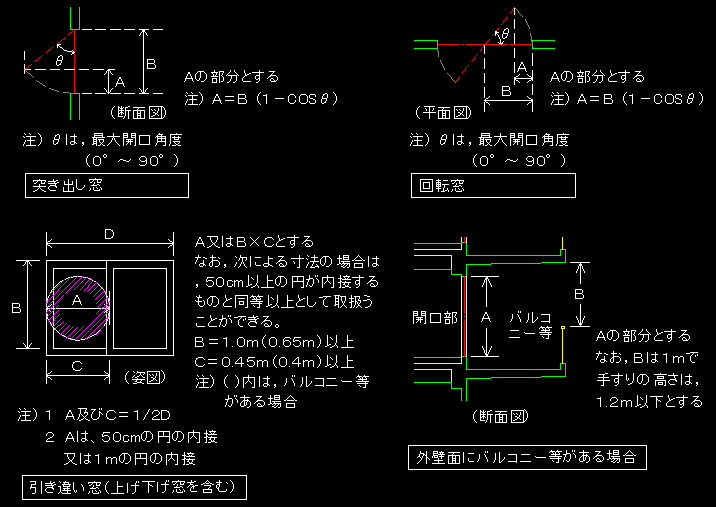
�R ���̑�
(1)
����K�����O��ԓ��Ŋu�Ă��Ă���ꍇ���͊J�����̂Ȃ��ω\���̕ǂŋ�悳��Ă���ꍇ�ɂ����ẮA
�u�Ă�ꂽ�������͋�悳�ꂽ�������Ƃɖ����K�̔�����s�����ƁB
(2)
�����K�̔���́A�J���������ׂĕ�������Ԃōs�����ƁB
(3) ��S���ʐρE�K�̎戵��(1)�ɂ��A�\���ɊO�C�ɊJ������Ă��镔���ŁA���A�����I�p�r�ɊY�����镔
���ɂ��ẮA���ʐς̎Z���͓��Y�������Z�����čs���Ƃ���Ă��邪�A�����K�̔�����s����ł͂����
���Ȃ����̂Ƃ���B
�i���j�|�[�`�����̖ʐς`�́A�\���O�C�ɊJ������Ă��邪�A�����ԎԌɂƂ��Ă̗p�r��L����ƔF�߂�
��邽�߁A���ʐς̎Z���͎Z�������B���������Č��z���̏��ʐς͑q�ɕ����̖ʐςa�ƍ��Z��
�āi�`�{�a�j�ƂȂ邪�A�����K�̔����́A�|�[�`���͊O�����Ƃ��Ď�舵���A���ʐςa�̂P�^
30�̊J�����̗L���ɂ�蔻�f������̂Ƃ���B
(4)
���������̑����镔���̏��ʐϋy�ъJ�����̎戵���́A���ɂ�邱�ƁB
�A ���ʐς̎Z��́A���Y���������镔���Ƃ���B
�C
�J�����̖ʐς̎Z��́A���������镔���̊O�NJJ�����̍��v�Ƃ���
�����Ƃ��i�����炢�j
�i�@�Q���P���S���j
�����̒�`�́C����Z�C�����C��ƁC�W��C��y���̑������ɗނ���ړI�̂��ߌp���I�Ɏg�p���鎺��Ƃ���Ă���B����̐l���p���I�Ɏg�p����ꍇ�����łȂ��C����̕�����s����̐l������ւ藧���ւ�p���I�Ɏg�p����ꍇ�ࢌp���I�Ɏg�p���飂Ɋ܂܂��
| �����Ƃ݂Ȃ������̗̂� |
�Z�� |
�H���C���ԁC���ږ�C�Q���C���ցC�~�[�i�����݂̂ŁC���ʐς��������Ɨ��������̂͗߂T�́i���{�ݓ��j�̓K�p�ɂ����Ĕ��j�C�Ǝ����� |
| ������ |
�������C���ڎ��C�������C��c���C�h������ |
| �X�� |
����C�������C�i�����C�������� |
| �H�� |
��Ə��C�H���C�������C�x�e���� |
| �a�@ |
�a���C�f�@���C�Ō�w���C��t���C��p���C�ҍ����� |
| ���O���� |
�E�ߎ��C������ |
| �����Ƃ݂Ȃ���Ȃ����̗̂� |
���ցC�L���C�K�i�C�֏��C���ʏ��C�������C�����C�@�B���C�ԌɁC�X�ߎ��C�l�����C�q�ɁC�[�ˁC���u�� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �u�ڎ��v�֖߂�