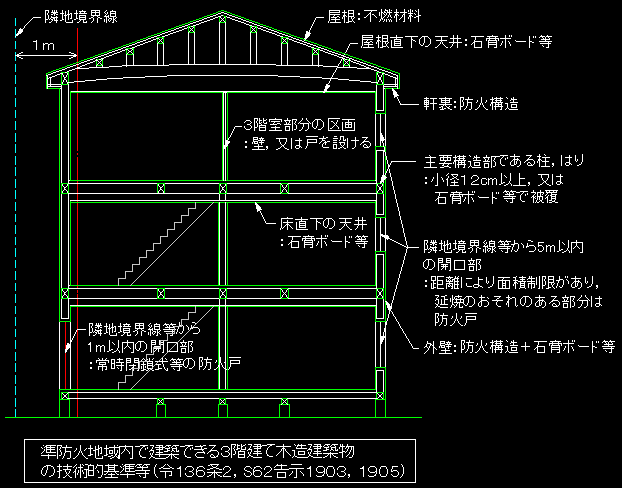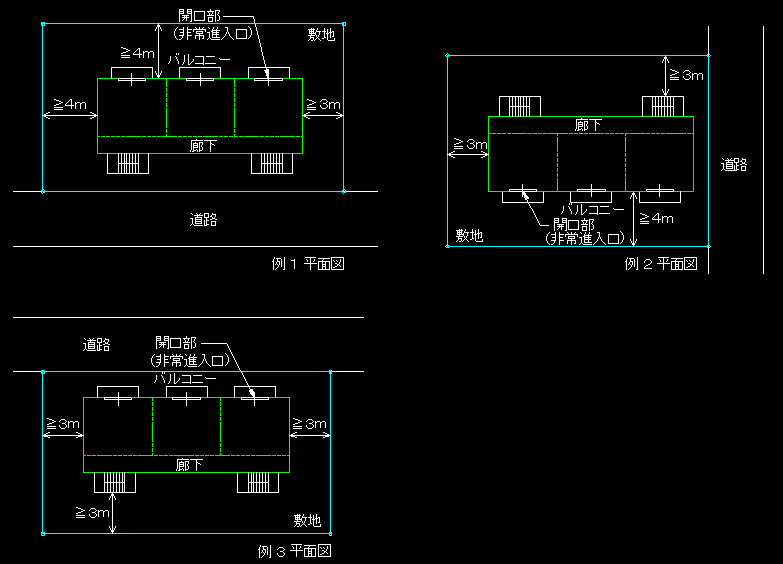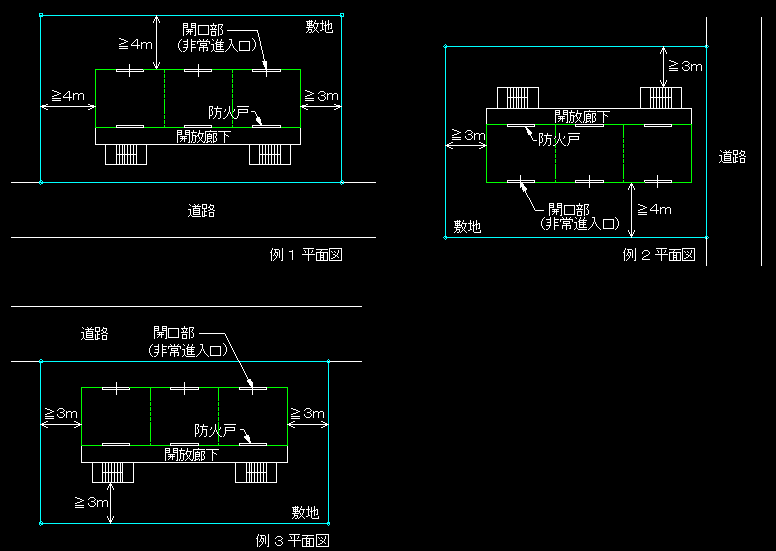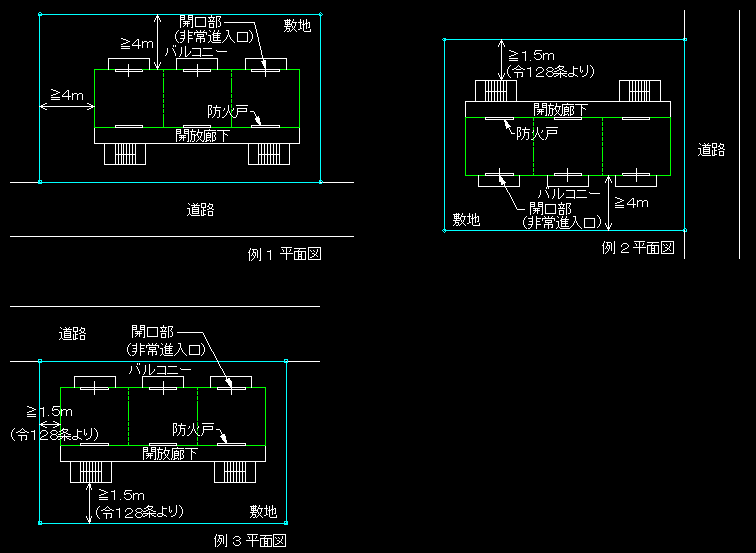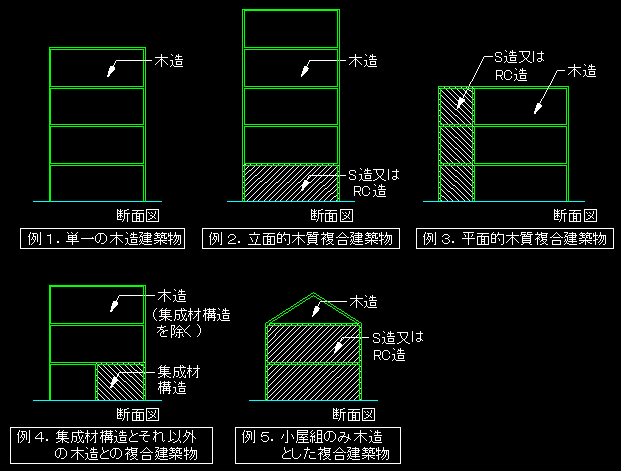「建築基準法及び関連法解説」
全ページ
→
遠山英雄都市建築設計事務所 - HOMEへ
__________________________________________________
木造3階建て及び木材で建てられる構造と規模
「 目 次
」
■ 001 木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物/木造3階建て共同住宅
法律改正
(法第62条~第64条/法第20条/法第27条)
準防火地域内でも建築可能な3階建て木造建築物
(令136条の2,他)
準防火地域内の建築規制
(令136条の2,他)
■ 002 準防火地域内で建築できる3階建て木造建築物の技術墓準
準防火地域内で建築できる3階建て木造建築物の技術墓準
(令136条の2,S62告示1903号,1905号)
準防火地域内の3階建木造建築物の基準
(令136条の2,S62告示1903
号,1905号)
※
地盤の地耐力について (2024.03.22追記)
参考).防火地域の建築規制
■ 003 木材で建てられる構造と規模
木造の準耐火建築物
耐火性能検証法によりもっと木造で建てられる
■ 004 木造3階建て共同住宅
(令115条の2の2第1号~第5号)
木造3階建て共同住宅
耐火建築物としなくてもよい木造3階建て共同住宅(タイプ別)
● バルコニー設置型
● 開放廊下設置型
●
バルコニー+開放廊下設置型
参考).木造耐火構造
耐火1時間の大臣認定を取得した木造の主な形態の例
木造3階建て 建築基準法改正 [法第27条の改正] (「国土交通省.htm」より抜粋)
(小規模な建築物の主要構造部規制の合理化
/ 耐火要件の緩和)
■ 001 木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物/木造3階建て共同住宅 (2007W)
法律改正
(法第62条~第64条/法第20条/法第27条)
かつては準防火地域では建てられなかった木造3階建て住宅も,1987年(昭和62年_同年施行)の法律改正で建てられるようになった。建てる場合は,一定の防・耐火上必要な建築基準を守ることが必要となる (建築基準法第62条~第64条)。
延焼を防ぐための高い耐火性能や,構造計算(建築基準法第20条)を義務づけるなど2階建てに比べて厳しい耐震性能が求められる。1階をビルトイン式の車庫にした間口の狭いタイプは構造的に問題があるケースもあるので注意が必要。なお,防火地域と準防火地域以外(平成10年の改正(平成11年施行)により防火地域以外)では木造3階建て共同住宅(通称木三共)も92年(平成4年_平成5年施行)から建築可能になった。ただし,木三共は木造3階戸建て住宅の基準よりもさらに厳しい防耐火上必要な建築基準を守ることが必要となる(建築基準法第27条)。施工者についての規制はないので,近所の大工さんでも建てられる。
また,平成16年4月までに,枠組壁工法建築物の主要構造部の全ての部位において耐火構造の国土交通大臣の認定を受けたことから枠組壁工法の耐火建築物の建設が可能となり,防火地域における建設や4階建て以上の建設の可能性が拡大された。
また,丸太組構法建築物については,昭和61年の丸太組構法の技術基準告示(同年施行)及び平成14年の告示改正により,この基準に適合する建築物について建設が可能となった。
また,木造3階に類似したものに「小屋裏3階」がありますが,これは3階建てとは異なり,二階の上部にある屋根小屋組みの空間を利用するために内装を施し,昇降用道具を用意したもので,人間が居住する目的に使用することは出来ず,納戸・物置としての空間利用が認められています。
準防火地域内でも建築可能な3階建て木造建築物
(令136条の2,他) (2006H)
従来,3階建て中規模建築物については耐火・簡易耐火建築物としなければならなかったが,昭和62年の改正で一定の構造基準の木造建築物(※)が建築可能となった。もちろん木造を用いた法2条9号の3イの準耐火建築物でも建築は可能である。
準防火地域内の建築規制
|
準防火地域内の建築規制
|
| 対象 |
構造制限 |
| ① |
地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物 |
[適用除外]
卸売市場の上屋,機械製作工場等で主要構造部が不燃材料で造られたもの等
|
耐火建築物 |
| ② |
延べ面積が500㎡を超え,1,500㎡以下の建築物 |
耐火建築物又は準耐火建築物 |
| ③ |
地階を除く階数3の建築物 |
耐火建築物,準耐火建築物又は一定の技術基準(令136条の2)に適合する木造建築物等 |
| ④ |
木造建築物等 |
--- |
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造とする |
| ⑤ |
④に付属する高さ2mを超える門・へい |
--- |
延焼のおそれのある部分を不燃材料で造るか又は覆う |
■ 002 準防火地域内で建築できる3階建て木造建築物の技術墓準 (2006H)
準防火地域内で建築できる3階建て木造建築物の技術墓準
(令136条の2,S62告示1903
号,1905号)
1) 隣地境界線等から水平距離1m以下の外壁の開口部には換気孔又は便所・浴室等(居室及び火気使用室を除く)に設ける換気用窓で開口面積0.2㎡以内のものを除き,常時閉鎖式,煙・熱感知器・温度ヒューズ連動閉鎖式又ははめ殺し防火戸を設ける。
2) 隣地境界線又は道路中心線からの水平距離5m以下の部分にある外壁の開口部は,隣地境界線又は道路中心線からの水平距離に応じて開口部の面積を制限する。
| 5m以内の開口部の面積制限(S62告示1903号) |
(注意事項)
・開口部の許容面積は各外壁面ごとに考える(各外壁面ごとに1~3階の合計とする)
・常時閉鎖式,煙・熱感知器・温度ヒューズ連動閉鎖式又ははめ殺し防火戸を設けた開口部以外の開口部は,その1.5倍の面積を有すると見なす
・1面の外壁の長さが10mをこえる建築物は10m以内ごとに開口部の許容面積を考えてよい
・道路幅員又は同一敷地内の他の建築物(延べ面積の合計≦500㎡である場合を除)の外壁との水平距離が6mをこえる場合は,道路中心線又は外壁間の中心線をその水平距離(m)÷2-3mの位置と見なす
|
| 隣地境界線からの水平距離(L) |
開口部の許容面積 |
| L≦1m |
9㎡ |
| 1m<L≦2m |
16㎡ |
| 2m<L≦3m |
25㎡ |
| 3m<L≦4m |
36㎡ |
| 4m<L≦5m |
49㎡ |
3) 外壁の構造
外壁の屋内側に厚さ12mm以上の石こうボード等の防火被覆を設けるほか,防火被覆の取り合い等の部分を外壁の内部に炎が入らない構造とする。
4) 主要構造部である柱及びはりの構造
準耐火構造又は原則としてその小径を12cm以上とする。
5) 床又はその直下の天井の構造
床の裏側に12mm以上の石こうボード等の防火被覆を設ける(ただし最下階の床は除く)
6)
屋根又はその直下の天井の構造
屋根の裏側に12mm十9mm以上の石こうボード等の防火被覆を設ける(天井の場合も上記と同じ構造)。
7) 3階部分の区画
3階の室の部分とその他の部分とは,壁又は戸(ふすま,障子等は除く)で区画する。
準防火地域内の3階建木造建築物の基準
(令136条の2,S62告示1903
号,1905号) (2006H)
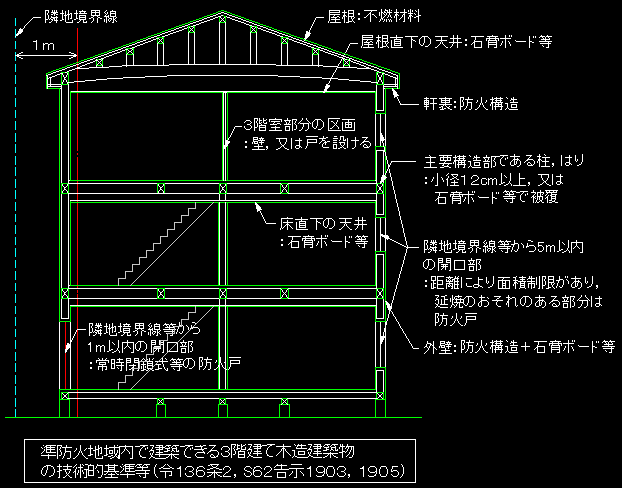
※
地盤の地耐力について (2024.03.22追記)
3階建て木造建築物の地耐力は40kN/㎡≒4.08トン/㎡(4.08t/㎡)が必要だといわれています。N値に換算すると約「4」です。2階建ては,30kN/㎡≒3.06トン/㎡(N値「3」)です
地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(=地耐力)は,「kN/㎡(1㎡あたりキロニュートン)」で表されます。告示1347号他,詳細を以下に記してあります。
左フレームINDEXの「耐震基準の改正の変遷,他」
→ 「建築物に必要な地盤の地耐力(許容応力度)について」
参考).防火地域の建築規制 (2006H)
|
防火地域内の建築規制
|
| 対象 |
構造制限 |
| ① 階数3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物 |
ただし③に該当するものを除く |
耐火建築物 |
| ②
その他の建築物 |
耐火建築物又は準耐火建築物 |
③
1)50㎡以内の平屋建の付属建築物で外壁及び軒裏が防火構造のもの
2)卸売市場の上屋,機械製作工場等で主要構造部が不燃材料で造られたもの等
3)高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造られたもの等
4)高さ2m以下の門又は塀 |
制限なし |
注).防火地域の看板等の規制
防火地域内の看板,広告塔,装飾塔その他類似の工作物で,次のものはその主要な部分を不燃材料で造るか,あるいは覆わなければならない。
① 建築物の屋上に設けるもの
② 高さ3mを超えるもの
■
003 木材で建てられる構造と規模
(2007W)
建築基準の性能規定化により,火災が終了するまで倒壊や延焼を起こさないことが耐火性能検証法により確かめられれば,どのような地域・用途・規模であっても,木造で建てられるようになりました。
木造の準耐火建築物
柱など,表面が燃えても構造耐力上支障のない太さとし(燃えしろをとり),壁,床,はり,屋根などに防火被覆を設けたり,開口部に防火戸等を設けた建築物をいいます。準耐火構造では,床や階段のけたや踏板に,図のような木材を使うことができます。
以上は,火災による45分間の加熱の間,構造耐力上支障のないものですが,軒高9m,棟高13mを超える建築物や,木造3階建て共同住宅では60分間の加熱に耐えることが必要です。(1時間準耐火)
準耐火構造の例
(図省略)
準耐火建築物の例
店舗(レストランなど)
平屋建てまたは2階の延べ面積が500平方メートル未満の2階建ての場合には,木造で建てられます。平屋建てまたは2階建てで,床面積が3,000平方メートル以下の場合には,準耐火建築物であれば木造で建てられます。
事務所
一戸建て住宅,長屋住宅,事務所については,延べ面積が3,000平方メートル以下で,3階建て以下の場合には,一定の防火上の基準を満たせば木造で建てられます。
木造3階建て共同住宅(団地など)
防火地域以外では,一定の防火上の基準(1時間準耐火構造等)を満たせば,特に検証をしなくても建てられます。
※従来より防火・準防火地域以外の区域では木造で建てられましたが,平成11年5月から,準防火地域内においても建てられるようになっています。
民宿
農業や農村生活を体験できるグリーン・ツーリズムの宿。平屋建てまたは2階建てで,2階の延べ面積が300平方メートル未満の場合には,木造で建てられます。「その他の地域」では,茅葺き屋根とすることも可能です。これを上回っても,平屋建てまたは2階建てで,延べ面積3,000平方メートル以下の場合には,準耐火建築物であれば木造で建てられます。
学校
平屋建てまたは2階建てで,延べ面積が2,000平方メートル未満の場合には,木造で建てられます。平屋建てまたは2階建てで,延べ面積が3,000平方メートル以下の場合には,準耐火建築物であれば木造で建てられます。
耐火性能検証法によりもっと木造で建てられる
政令,告示に基づく技術基準により,建築物での火災を予測し,主要構造部が火災終了まで耐えることを検証する方法です。
|
火災継続時間より保有耐火時間が長いことを確認
|
火災の継続時間
可燃物の量,開口部の大きさ等から火災が発生するまでの予測時間を計算 |
< |
主要構造部の保有耐火時間
主要構造部が火災に対して耐えることができる時間を,構造方法や火災の温度等に応じて計算 |
検証法により木造建築物の設計を行う場合は,火災による温度上昇の影響を受けやすい部分は,不燃材料等で覆うなどの措置が必要であると考えられます。また,天上を高くしたり,大きい空間とすることで,火災時に熱がこもりにくくする場合などは,はりを木材のあらわしで用いることも可能と考えられます。
この他,主要構造部を耐火構造にしようとする場合,例えば,構造部材に集成材等を用い,これに耐火被覆,木製仕上げを行なう,あるいは,これは木造ではありませんが,鉄骨等に木製の厚板で被覆し,内装材として用いることで,耐火構造としての性能を確保するとともに木の質感を出す方法が考えられます。
耐火性能検証法による木造耐火建築物の例
・ 体育館,ドームなど
なお,従来より以下のように,防火上の地域区分,建築物の用途,規模に応じて,一定の基準を満たせば,特に検証をしなくても木造で建てられます。
防火地域
準耐火建築物であれば,2階建て以下で,延べ面積が100平方メートル以下のものを木造で建てられます。
準防火地域
3階建て以下(地階を含まない)で,延べ面積が500平方メートル以下のものを木造で建てられます。なお,3階建ての場合は,柱やはり等を,通常の火災によって建築物が容易に倒壊しないような措置が必要となります。準耐火建築物であれば,3階建て以下で,延べ面積が1,500平方メートル以下のものを木造で建てられます。
22条区域
延べ面積が3,000平方メートル以下のものは構造上の制限なく建てられます。なお,屋根は飛び火に対して燃えない材料(木材も認定を得れば可能)などで葺くこと,外壁で延焼のおそれのある部分は,外装側を土塗り壁(裏返し塗りのないもの)などとし,内装側にせっこうボードを張ることが必要となります。
その他の地域
22条区域と同様,延べ面積が3,000平方メートル以下のものは構造上の制限なく木造で建てられます。
学校,病院,共同住宅などの用途
劇場,病院,百貨店,ホテル,共同住宅のように不特定多数の人が利用したり,就寝に使用されたりする建築物(特殊建築物)であっても,一定の規模や階数以下のものは準耐火建築物等にすることで,木造で建てられます。それ以上の規模の特殊建築物であっても,耐火性能を検証することにより木造で建てられます。
■ 004 木造3階建て共同住宅
(令115条の2の2第1号~第5号) (2006H)
木造3階建て共同住宅
共同住宅は法別表第1い)欄(2)に該当するので,3階以上にある場合は耐火建築物としなければならない。ただし,地階を除く階数が3で,3階を下宿,共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものについては,防火地域以外の区域に限り,次の①~④のもとに準耐火建築物とすることができる(耐火建築物にしなくてもよいということ)。通称,木三共(もくさんきょう)と呼ばれている。ただし準防火地域にあるものは⑤も満たすこと(法27条ただし書き,令115条の2の2)。
①.令115条の2の2第1号(主要構造部)
主要構造部の耐火性能を1時間準耐火構造とすること
②.同条2号(バルコニー等)
各宿泊室等に原則として避難上有効なバルコニ等を設置すること
③.同条3号(非常用の進入口,通路等)
3階の各宿泊室等の開口部(非常用の進入口の窓と同等のもの)が道に通ずる幅員4m以上の通路等に面していること
④.同条4号(周囲の空地)
建築物の周囲に原則として幅員3m以上の通路が設けられていること
⑤.同条5号(3階の開口部)
3階の各宿泊室等の外壁の開口部等に原則として防火設備(両面20分〉を設けること
耐火建築物としなくてもよい木造3階建て共同住宅(タイプ別) (2006H)
(防火,準防火地域以外の3階建て共同住宅(特殊建築物)等の技術的基準等のパターン例(令115条の2の2第1項第一~五号))
● バルコニー設置型
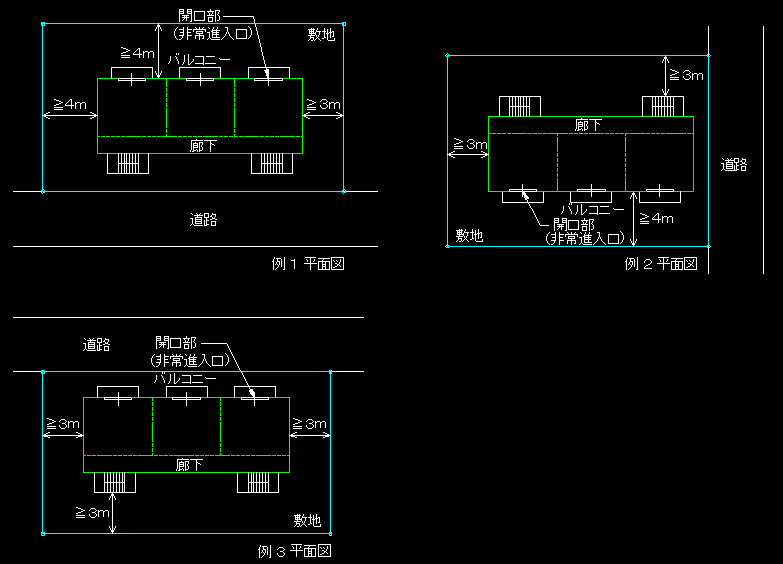
● 開放廊下設置型
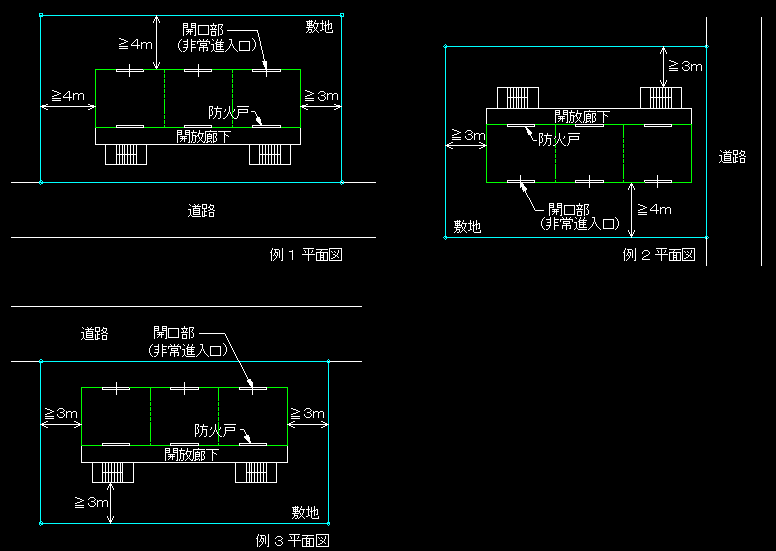
●
バルコニー+開放廊下設置型 (注.開口部からの上階燃焼を防止する庇,バルコニー等の設置のあるものとする)
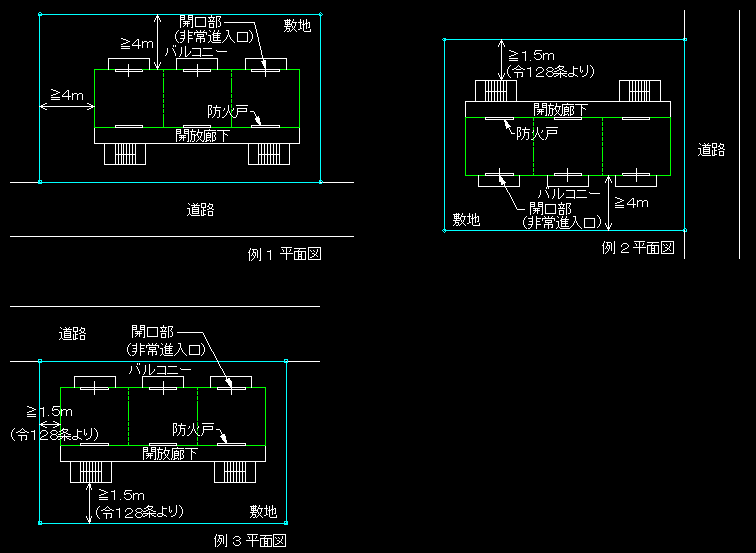
参考).木造耐火構造 (2006H)
ここ数年,枠組壁工法による耐火建築物をはじめとして,木質系耐火建築物の開発が進んでいるので注目したい。従来,木造建築物は1時間準耐火建築物までが限界であったが,実験的検証により耐火性能の確認が進み,耐火構造として主要構造部の各部位ごとの大臣認定の取得が可能となった。これにより単一の木造構成(在来軸組工法,枠組壁工法,木質系プレハブ工法)だけでなく,木造と非木造(RC造,S造,集成材構造など)を組み合わせた新しい複合形態の耐火建築物も実現可能となった。
(枠組壁工法耐火建築物を設計・施工する際には,(社)日本ッーバイフォー協会と事前打合わせをしておきたい。また,参考文献として同会発行『枠組壁工法による木質複合建築物設計の手引き』がある。なお乾式材料のみの対応であったツーバイフォー工法に,湿式外壁の構造(1時間)が平成17年7月に新たに認定され,外壁材として使用が可能となっている。)
以下,耐火1時間の大臣認定を取得した木造の主な形態の例 (2006H)
| 耐火1時間の大臣認定を取得した木造の主な形態の例 (2006H)
|
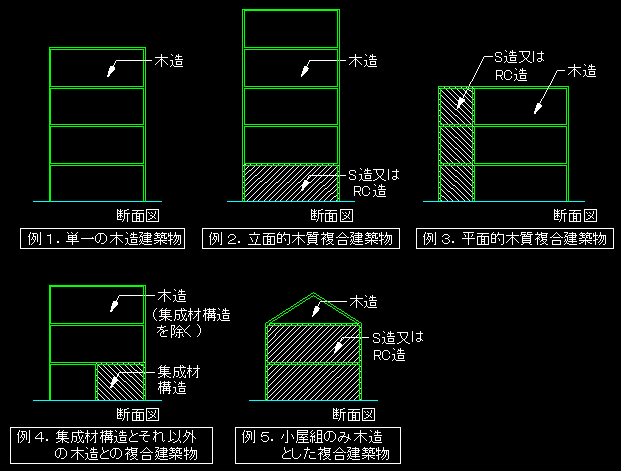
|
例 1.単一の木造建築物
木造の4階建て
例 2.立面的木質複合建築物
1階 :S造又はRC造
2~5階 :木造(4階建て)
例 3.平面的木質複合建築物
3階建てで,一部木造3層,一部S造又はRC造3層
例 4.集成材構造とそれ以外の木造との複合建築物
3階建てで,1階の一部集成材構造,1階の一部及び2,3階木造(集成材構造を除く
)
例 5.小屋組のみ木造とした複合建築物
1,2階 :S造又はRC造
小屋組み(勾配屋根) :木造
|
木造3階建て 建築基準法改正 [法第27条の改正] (「国土交通省.htm」より抜粋)
(小規模な建築物の主要構造部規制の合理化
/ 耐火要件の緩和)
木造3階建て共同住宅(木三共)は法改正によって建てやすくなりました。
2019年の建築基準法第27条の改正によって,緩和条件を満たせば200㎡未満の木造3階建て共同住宅を建築する場合には耐火要件を満たす必要なく建築することが可能となりました。
ただし,耐火要件を緩和させるためには自動火災報知器の設置や,階段の安全装置の設置が必要です。
(詳細 → 「防火区画 ・
防火上主要な間仕切り」(別のウィンドウで表示)
→ 「※ 必見).第27条の改正」を参照してください。)
1. 法改正による木造3階建て共同住宅の変更点
建築基準法第27条改正の大きなポイントは,3階建てで延べ床面積が200㎡未満の場合,耐火建築物以外で設計・建築ができるようになった点です。
本来,木造3階建て共同住宅は特殊な建築物です。準耐火建築物(壁や柱などの主要構造部のみ耐火被覆工事)として建築するためには,厳しい4つの建築基準をクリアする必要がありました。
それが今回の法改正では,建設予定地の延べ床面積が200㎡未満の小規模な土地であれば,緩和規定を満たすことで従来の4つの基準すべてをクリアしていなくても建築可能になったのです。
参考:建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について
| 国土交通省
しかし,延べ床面積が200㎡以上の木造3階建て共同住宅を建てる場合は,従来通り1時間準耐火構造とするための建築基準を満たす必要があることには変わりないので注意が必要です。
2. 木造3階建て共同住宅の建築基準
木造3階建て共同住宅は,木造3階建て共同住宅が1時間準耐火建築物として認められるために必要な基準は,以下の4つです。
「木三共」の4つの設計基準
・ 1時間準耐火構造にする
・ 避難に有効なバルコニーの設置
・ 敷地内に通路を設ける
・ 防火設備を設ける
これら4つの建築基準を一つでも満たさなければ,木造3階建て共同住宅は1時間準耐火建築物として認められません。
とはいえ,2019年の法改正により「避難上有効なバルコニー」「建物周囲の幅3mの通路」は緩和された条件を満たせば問題ないことになりました。それぞれの緩和条件を正しく理解しましょう。
2.1. 基準①:「1時間準耐火構造」にすること
木造3階建て共同住宅は準耐火構造であることが求められます。木造三階建て共同住宅では,火災から1時間の間は建物の構造を保つ必要があり,これを1時間準耐火建築物といいます。
1時間準耐火構造とするためには,主要構造部である壁,柱,梁 屋根の軒裏は耐火被覆工事を行い耐火性能を高めなければなりません。
非損傷性が,火災発生から1時間以上であることも条件です。加えて,外壁の遮炎性も1時間以上であることが求められます。
ちなみに,通常の準耐火構造では遮炎性は45分以上です。木造3階建て共同住宅の場合は,建物規模や避難人数が加味されるため,さらに長く1時間以上に設定されています。
2.2. 基準②:避難に有効なバルコニーを設置すること
火災が起きた際の避難経路として避難可能なバルコニーを取りつける必要があります。部屋の出入り口とバルコニーの2方向の避難経路の確保が必要です。
さらに廊下と階段部分には,常時外気を開放し,排炎有効となる開口部を設けることも,木造3階建て共同住宅の建築ルールとなります。しかし,以下の条件を満たした場合は「避難上有効なバルコニー」の設置は不要です。
「避難上有効なバルコニー」の建築基準を満たすための緩和条件
・ 各住戸から地上に通じる廊下,階段が直接外気に開放されていること
・ 各住戸の廊下,階段に面する窓・扉が防火設備であること
2.3. 基準③:敷地内で建物の外側に幅3m以上の通路を設けること
敷地内には原則幅員3m以上の敷地内通路を設ける必要があります。しかし,敷地内に幅3m以上の通路を設ける場合,建物の面積がかなり限られてしまいます。そこで,以下の条件を満たせば「幅員3mの敷地内通路」を緩和できることになりました。
「建物周囲の幅3mの通路」の建築基準を満たすための緩和条件
・ 宿泊室などに避難上有効なバルコニーなどを設けている
・ 宿泊室などから地上に通じる主な廊下や階段,その他の通路が直接外気に開放されている
・ 宿泊室などの通路に面する開口部に遮炎性能を持つ防火設備を設けている
・ 外壁の開口部の上部に遮炎性能のあるひさしなどが防火上有効に設けられている
なお,「避難上有効なバルコニー」と認められるためには,以下の条件があります。これら4つの条件を一つでもクリアできない場合は,敷地内通路が必須となります。
・ バルコニーの床面は耐火被覆工事がなされていること(1時間準耐火構造)
・ 避難設備(ハッチなど)の設置
・ 避難設備から建物外へ通じる道路への経路幅員が90cm確保されている
・ バルコニーへ出るための出入り口が高さ1.8m・幅75cm以上であり,床から15cm以下である
疑問).
どういうこと?バルコニーは緩和条件を満たせば設置しなくてもいいのでは?
バルコニーか通路のどちらかで避難経路を確保する必要があるということでは?
回答).
基準②と基準③の緩和条件を照らし合わせるとわかりますが,基準②の緩和条件を満たせば避難上有効なバルコニーの設置をしなくてもいいというわけではなく,その場合建物周囲の幅3mの通路の確保が必要だということです。
逆に言うと,避難上有効なバルコニーが設置できれば幅3mの通路は確保できなくても準耐火基準の建物として認められるということです。これは施工会社の担当者の方も理解が難しいような箇所でしょう。
2.4. 基準④:3階住戸の外壁の開口部に防火設備を設置すること
建設予定地が防火地域,あるいは準防火地域の場合は建物の3階部分には防火設備が必要です。3階の宿泊室や外壁の開口部,宿泊室以外の部分に面する開口部に,遮炎性のある防火設備の設置が必要であることは覚えておきましょう。
次の条件のうちいずれかを満たす場合は,例外として3階部分の防火設備は不要です。
・ 開口部から90cm未満の部分に宿泊室など以外の部分の開口部を設けない
・ 宿泊室以外の部分の開口部と50cm以上突出したひさし,そで壁などを設けている
例外の条件を満たさない限り,基本的には防火設備の設置が必要となります。
まとめ!
2019年以降は,建築基準法が改正され,木造3階建て共同住宅は防火地域でないことなどの基準を満たせば準耐火建築物として建築することができるようになりました。
参考:建築基準法 第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
以下,補足です。
例えば,階数3の住宅をグループホームや保育所などの特殊建築物へと用途変更する場合,従来は耐火建築物への改修しか選択肢はありませんでした。今回の改正により,200㎡未満の小規模建築物は条件を満たせば耐火要求が免除されています。法27条の改正の主な目的は,『既存の戸建住宅等の活用』です。他,就寝用途・医療福祉系の特殊建築物の病院,診療所(患者の収容施設があるもの),ホテル,旅館,下宿,共同住宅,寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるもの)も同様に条件を満たせば耐火要求が免除されます。
これまで,"建築基準法の別表第1に該当する特殊建築物"は,「階数3以上になると耐火建築物としなければならない」というのが,おおまかな考え方でした。(※木三共(木造3階建て共同住宅)など例外あり)
今回の法改正によって,『小規模な建築物であれば耐火構造が免除』という選択肢が増えたのが,とてつもなく大きなポイントです。
現行の竪穴区画は残しつつ,少し基準を緩和した『小規模建築物における竪穴区画』が追加されています(詳細省略)。
「目次」へ戻る