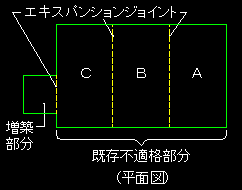|
�����s�K�i���z���̓K�p�ɂ���
|
|
�������z��
|
�@ |
| �� |
|
���z��@�̉������ɂ��K������
|
| �� |
| ���������z���ɂ��āC�K�����Ă��Ȃ������Ɍ���C��F���z���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��C�V�����K���K�p���O������������s�K�i���z���Ƃ��đ���
|
| �� |
|
�������{�H��̍H�����{
|
�� �� �� �� |
�� ��K�͂łȂ��C�U�E�͗l�ւ�����ꍇ
�� �H�������Ȃ��ꍇ
|
| �� |
�@ |
�� |
| �� �����z�C��K�͏C�U�E�͗l�ւ�����ꍇ
|
���������K�p���O
|
| �� |
�@ |
|
�����C�����S�̂����s�K��ɑ����ɉ��C
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�ɘa�K��i�@�W�U���̂V�j |
�@���@�ɘa�K��
�@�@�@�@�@�i�@�W�U���̂W�j |
| �� |
�� |
�� |
|
�K�p���O�i�P���j |
�����K�p�i�Q���j |
�����K�p�i�R���j |
�i�K���C |
���͈͓̔��̑��z��������ꍇ�͓K�p�Ȃ�
�i�\�F�q��q�̊����s�K�i���z���̐����̊ɘa�r�j |
�G�L�X�p���W���C���g���ō\���I�ɕ�������Ă��鑝�z���Ɨ������ɓK�p
�i�\�F�q��q�̕����K�p���s���ꍇ�̊e�K��̓K�p�i�Ɨ��������Ƃɂ��K�p�j�r�j |
�����P�ʁC�ݔ��P�ʂœK�p
�i�\�F�q��q�̕����K�p���s���ꍇ�̊e�K��̓K�p�i�������Ƃɂ��K�p�j�r�j |
����s�����̑S�̌v��F�����K�v������ |
|
�����s�K�i���z���̐����̊ɘa�i�߂P�R�V���̂Q�`�P�Q�j |
|
�Ώۍ��� |
�ɘa���� |
| �߁C�R�V���̂Q�i���P�j |
�P�D�\���ϗ͊W�i�@�Q�O���j
���������C�����w���z���C�@�W�U���̂V��Q���̋K��ɂ��@�Q�O���̋K����Ȃ������������ |
�@
�����z�����̏��ʐς̍��v������̉��זʐς̂P/�Q�ȉ��ŁC���C�����z��̍\�����@�����̂����ꂩ�ɊY�����邱��
�C�D�ϋv�����W�K��ɓK�����C���C���d�C�ωd�C�ϐ�C�����C�y���C�����C�n�k���̑��̐U���E�Ռ��ɂ��C�|��C����C�����ӂ��ޓ����E�����Ȃ��Ƃ��đ�b����߂��ɓK������\�����@�iH�P�V�����T�U�U����P�j
���D�߂R�͂P�߂���V�߂̂Q�܂łP�i�߂R�U���C�߂R�W���Q�`�S���������j�̋K��ɓK�����C���C���̊�b�̕⋭�ɂ��đ�b����߂��ɓK������\�����@�i�@�U���P���S�����z���Ɍ�����.�j�iH�P�V�����T�U�U����Q�i���Q�j�j
�A
�����z�����̏��ʐς̍��v���C����̉��זʐς̂T%�ȉ����T�O�u�ȉ��̏ꍇ�͎��̂�����ɂ��K�����邱��
�E�����z�������߂R�́C�@�S�O�����i�\���ϗ͂Ɋւ��鐧���j�ɓK�����邱��
�E�G�L�X�p���W���C���g����p���邱�Ƃɂ�葝���z�����ȊO�̍\���ϗ͏�̊댯�������債�Ȃ����� |
| �߂P�R�V���̂R |
�Q�D�h�Εǁi�@�Q�U���j |
�@
����Ȍ�̑����z�����̏��ʐς̍��v�͂T�O�u�ȓ��ł��邱�� |
| �߂P�R�V���̂S |
�R�D���ꌚ�z���̍\������
�i�@�Q�V���j |
�@
����Ȍ�̑����z�����̏��ʐς̍��v�͂T�O�u�ȓ��ł��邱��
�����z�ɂ����Ă͌���̋q�ȁC�a�@�̕a���C�w�Z�̋������傽��p�r�̕����ȊO�Ɍ��� |
| �߂P�R�V���̂T |
�S�D�������̊E�ǁi�@�R�O���j |
�@
���z��̉��זʐς́C����̂P.�T�{�ȓ��ł��邱��
�A ���z�����̏��ʐς́C����̉��זʐς̂P/�Q�ȓ��ł��邱�� |
| �߂P�R�V���̂U |
�T�D���p�G���x�[�^�[ |
�@
���z�����̍����͂R�Pm�ȉ��Ƃ���
�A ���z�����̏��ʐς̍��v�́C����̉��זʐς̂P/�Q�ȓ��ł��邱��
�B ���z�����̏��ʐς́C����̉��זʐς̂P/�T�ȓ��ł��邱��
�C ���z�����̍����́C����̍����ȉ��Ƃ��� |
| �߂P�R�V���̂V |
�U�D�p�r�n��
�i�@�S�W���P���`�P�Q���j |
�@�����z�͊���̕~�n���ł���C���C�����z��̗e�ϗ��i�@�T�Q���P�C�Q�C�V���j�C������������̕~�n�ʐςɑ��ēK�����Ă��邱��
�A ���z��̏��ʐς̍��v���C����̂P.�Q�{�ȓ��ł��邱��
�B ���z��̕s�K�i�����̏��ʐς̍��v�́C����̂P.�Q�{�ȓ��ł��邱��
�C
���z��̌����@�̏o�́C�@�B�̑䐔�C�e�퓙�̗e�ʂ́C����̂P.�Q�{�ȓ��ł��邱��
�D
�p�r�̕ύX�i�߂P�R�V���̂P�W�C�Q���͈͓̔��̂��̂������j��Ȃ����� |
| �߂P�R�V���̂W |
�V�D�e�ϗ��i�@�T�Q���P���C�Q���C�V���C�U�O���P���j |
�@
�����z�����͎����ԎԌɋy�ю��]�ԎԌɏ�̗p�r�Ɍ���
�A
���z�O�̎����ԎԌɓ��ȊO�̏��ʐς̍��v�́C����ȓ��ł��邱��
�B
�����z��̎����ԎԌɓ��̏��ʐς̍��v�́C�����z��̏��ʐς̍��v�̂P/�T�ȓ��ł��邱��
�����s�K�i���z���̑����z�ɂ�����e�ϗ��Z��
�e�ϗ��̋K��i�@��52���1���C��2���������͑�7���܂��͖@60���1���i���z���̍����ɂ����镔���������B�j�j���K�p���O�Ƃ��������s�K�i���z���ɑ����z���s���ꍇ�C�����ԎԌɓ������C���~�q�ɕ������ɂ��Ă͈��͈͓̔��ŁC�G���ׁ[�^�[�̏��~�H�̕����͏��ʐςɊW�Ȃ��C�e�ϗ��Z��ɂ����鉄�זʐςɎZ�����Ȃ��B
�ڍׁu�����s�K�i���z���ɂ����đ����z���F�߂���͈��v�͈ȉ����Q�Ƃ��Ă��������B
�e�ϗ��Ɖ����ʐ�
�� �h�Ў{�݂�L���錚�z�����̗e�ϗ��Z��
�i�����@�j
�i�ʂ̃E�B���h�E�ŕ\���j
|
| �߂P�R�V���̂X |
�W�D���x���p�n��
�s�s�Đ����ʒn��i�@�T�X���P���C�U�O���̂Q�C�P���j |
�@
�e�ϗ��̍Œ���x���͌��z�ʐς̊ɘa�̏ꍇ
���L�C�`�j�Ƃ���
�A �e�ϗ��̍ō����x�y�ь��z�ʐς̊ɘa�̏ꍇ
���L�C�`��y�тQ�̇@�`�B�Ƃ���B
�B �e�ϗ��̍ō����x�̊ɘa�̏ꍇ
�Q�̇@�`�B�Ƃ���B
�C.���z��̌��z�ʐρC���זʐς́C����̂P.�T�{�ȓ��ł��邱��
��.���z��̌��z�ʐς́C���z�ʐς̍Œ���x�̂Q/�R�ȓ��ł��邱��
�n.���z��̗e�ϗ��́C�e�ϗ��̍Œ���x�̂Q/�R�ȓ��ł��邱��
�j.���z�����̏��ʐς́C����̉��זʐς̂P/�Q�ȓ��ł��邱�� |
| �߂P�R�V���̂P�O |
�X�D�h�Βn��C����h�ЊX�搮���n��i�@�U�P���C�U�V���̂Q�C�P���j |
�@
�����z�����̏��ʐς̍��v�͂T�O�u�ȉ��C�����C����̉��זʐς̍��v�ȓ��ł��邱��
�A
���z��̊K���͂Q�ȉ��ŁC���C���זʐς��T�O�O�u�ȓ��ł��邱��
�B �����z�����̊O�ǁC�����́C�h�\���Ƃ��邱��
���ؑ����z���ɂ����Ă͊������z�����̂��̂��C�O�Njy�ь������h�\���ł�����̂Ɍ��� |
| �߂P�R�V���̂P�P |
�P�O�D���h�Βn��
�i�@�U�Q���P���j |
�@
����Ȍ�̑����z�����̏��ʐς̍��v�͂T�O�u�ȓ��ł��邱��
�A ���z��ɂ�����K���͂Q�ȉ��ł��邱��
�B �����z�����̊O�ǁC�����́C�h�\���Ƃ��邱��
���h�Βn��ɓ����B |
| �߂P�R�V���̂P�Q |
�P�P�D��K�͂̏C�U�C�͗l�� |
�@
�@�Q�O���ɂ��ẮC�����w���z���C�@�W�U���̂V��Q���̋K��ɂ惊�@�Q�O���̋K����Ȃ������������C���Y���z���̍\���ϗ͏�̊댯�������債�Ȃ�����
�A
�@�Q�U��Q�V��R�O��R�S���Q����S�V��T�P��T�Q���P�C�Q�C�V����T�R���P�C�Q����T�S���P����T�T���P���C�T�U���P����T�U���̂Q�C�P����T�V���̂S�C�P����T�V���̂T�C�P����T�W��T�X���P�C�Q����U�O���P�C�Q���B�U�O���̂Q��P�C�Q���B�U�P��U�Q���P���B�U�V���̂Q��P�C�T�`�V���B�U�W���P�C�Q���ɂ��Ă͊ɘa�����Ȃ��Ŋɘa�i���ӁF�W�c�K��̂����ړ��`���i�@�S�R���j�⓹�H�����z���i�S�S���j�͑k�y�K�p�������j�B
�B�@�S�W������P������P�Q���ɂ��ẮC�p�r�ύX�i�߂P�R�V���̂P�W��Q���͈͓̔��̂��̂�
�����j��Ȃ����� |