■ 001 都市計画法の定義/土地の区画形質の変更
都市計画法第4条 全文
【定義】
第4条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
2 この法律において‥‥(省略)
~(省略)
12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
~(省略)
16(省略)
開発行為の定義の解釈基準 1
「開発行為」について
12項に規定する開発行為とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。ここでいう「主として」に該当するか否かは,土地の区画形質の変更を行う主たる目的が,建築物を建築すること又は特定工作物を建設することにあるということであり,土地の利用目的,物理的形状等から一体と認められる土地について,その主たる目的が建築物の建築又は特定工作物の建設に係るものでないと認められる土地の区画形質の変更そのものは,開発行為には該当しない。
「建築又は特定工作物」について
12項に規定する建築物とは建築基準法上の建築物をいい,特定工作物とは,コンクリートプラント,アスファルトプラント,ゴルフコース,1ha以上の野球場,陸上競技場などである。
「土地の区画形質の変更」について
12項に規定する「土地の区画形質の変更」とは,都市計画法における開発許可の対象となる宅地造成等のことだが,土地の形状又は性状に変更をもたらす行為のことで,「区画の変更」,「形の変更」,「質の変更」のいずれかに該当する場合をいう。宅地造成だけでなく,道路の新設などを伴う土地区画の変更,農地から宅地への変更などを含む広い概念である。ただし,建築確認をうけた建築工事と一体と認められる基礎打ち及び土地の掘削や,単に土地登記簿上で土地を合筆もしくは分筆すること,所有権等の権利境界線の変更は「区画の変更」には該当しないものとする。
(「土地の区画形質の変更」の具体的な定義は,各自治体の「開発指導要綱」で定められている場合が多い。また各自治体の条例で定める場合もある。)
1)土地の「区画の変更」
土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・改廃移動することにより,土地の「区画」を変更すること。
2)土地の「形の変更」
宅地造成工事等による土地の盛土・切土,整地等による土地の形状を変更すること。
3)土地の「質の変更」
宅地以外の土地(農地・山林など)を,宅地にすること。
1)の「区画の変更」について
「区画の変更」とは,「従来の敷地」の境界を変更することをいう。「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為」も,区画の変更が生じるものとする。
① 「従来の敷地」とは,次のいずれかに該当する土地をいう。
ア) 現に建築物が存在する土地( 仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く。)
イ) 土地全部事項証明書の地目が「宅地」である土地で,現在,農地や山林として利用されていない土地
ウ) 固定資産税台帳の地目が,「宅地」である土地で,現在,農地や山林として利用されていない土地
エ) 従前,建築物の敷地として利用されていた土地で,現在まで,農地や山林として利用されていない土地(線引き前に建築物を除却したものを除く。)
オ) 建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際,道路と一体的に造成された土地
カ) 建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地(緑地,未利用地等は除く。) で,次のいずれかに該当するもの
(a) 都市計画法に基づく開発行為の許可を受け,工事の完了公告がなされた土地
(b) 旧宅地造成事業に関する法律によって認可を受け,工事の完了公告がなされた土地
(c) 都市計画法第29条第1項第3号,第4号,第6号,第7号又は第8号に該当する開発行為が終了した土地
(d) 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の認可を受けた土地で,仮換地の指定後,使用収益の開始及び停止が行われた土地
② 「従来」とは,いずれも過去の建築確認通知書,開発許可書,土地全部事項証明書,土地の公図及び,建物全部事項証明書等の経緯により判断するものとする。
③ 「土地の単なる分合筆や,所有権等の権利境界線の変更」とは主として建築物の建築又は,特定工作物の建設用に供することを目的とせず,単に土地の分合筆を行う行為や,単に土地所有権の権利境界を変更(いわゆる「権利区画の変更」) する行為は,「区画の変更」には該当しないものとする。
ただし,「権利区画の変更」後,土地利用形態・物理的形状からみて他の土地とは独立した機能を有するひとまとまりの土地の区域(従来の敷地の境界) に変更が生じる場合は,その時点(建築物の建築又は,特定工作物の建設を行う時点) で「区画の変更」が発生するものとする。
④ 「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為」とは建築物等の建築に際し,土地の「形」・「質」の変更を伴わず,公共施設(道路,公園,排水施設等)の整備を必要としないものを,「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為」と判断し,開発行為に該当しないものとして取り扱うものとする。
⑤ 「区画の変更」の具体例は次のとおりとする。
ア) 既存建築物の建替えにより,建築区画が変更される場合
イ) 従来の敷地内において,道路・水路・その他の公共施設の新設,拡幅,付け替え,廃止をする場合
ウ) 従来の敷地の権利者が,その敷地内に複数の用途上可分の建築物を建築する場合
エ) 従来の敷地の権利者が,建築物の建築を目的として,第三者への所有権等の移転等により,土地を複数の建築区画に分割する場合
オ) 従来の敷地を拡張する場合
2)の「形の変更」について
「形の変更」とは,建築物の建築又は,特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の切土,盛土により土地の現状を変更する宅地の整備をいう。
従って,土地利用をするにあたり,整地として認められるものを除き,原則,切土,盛土を伴なえば「形」の変更に該当するものとする。
「形」の変更は,以下に示す各項のいずれかに該当するものとする。
① 切土を行う高さが2.0m以上の場合
② 盛土を行う高さが1.0m以上の場合
③ 一体的な切土・盛土を行う高さが2.0m以上の場合
④ 0.5m以上の切土又は盛土を行う土地の合計面積が,開発区域の過半以上若しくは,施行範囲500㎡以上の場合
なお,建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち,土地の掘削等の行為,さらに特定工作物の建設行為そのものに属する土地の形状の変更は,「形の変更」に該当しないものとする。
注意).「形の変更」については各自治体の「開発指導要綱」や各自治体の条例で定める場合がある。
①の2.0m以上 : 東京都→1.0m以上(切土,盛土共)
④の0.5m以上 : 鎌倉市→0.3m以上が500㎡以上 / 横浜市→0m以上(高さに関係なく)が500㎡以上
■ 002 都「土地の区画形質の変更」事例図解
「形の変更」の事例 (一定規模以上の土地の区画形質の変更)
切土1
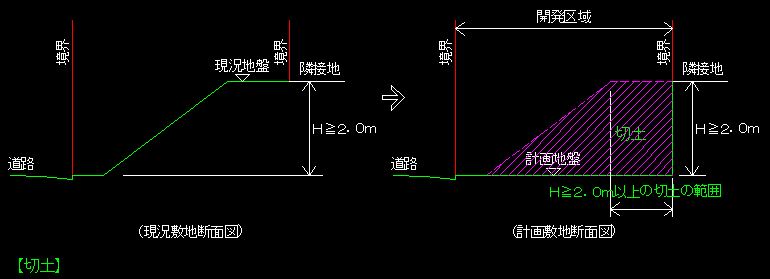
注意).H≧2.0mについて
東京都→1.0m以上(切土,盛土共)
鎌倉市→0.3m以上が500㎡以上
横浜市→0m以上(高さに関係なく)が500㎡以上
切土2
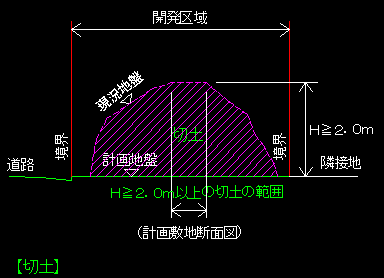
注意).H≧2.0mについて
東京都→1.0m以上(切土,盛土共)
鎌倉市→0.3m以上が500㎡以上
横浜市→0m以上(高さに関係なく)が500㎡以上
盛土1
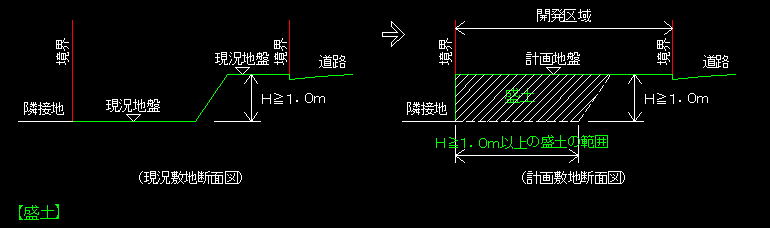
注意).H≧1.0mについて
鎌倉市→0.3m以上が500㎡以上
横浜市→0m以上(高さに関係なく)が500㎡以上
盛土2
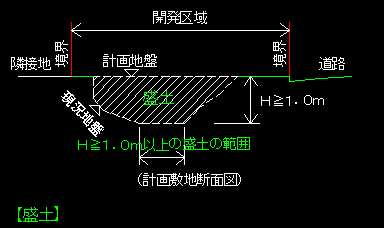
注意).H≧1.0mについて
鎌倉市→0.3m以上が500㎡以上
横浜市→0m以上(高さに関係なく)が500㎡以上
一体的な切土・盛土 1
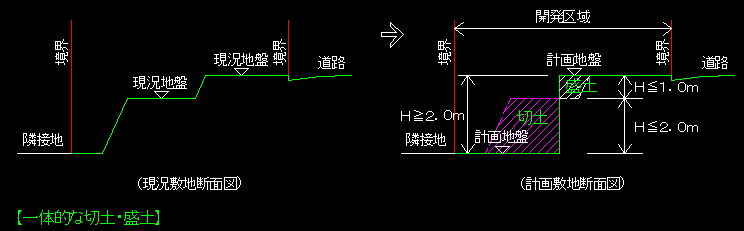
注意).H≧2.0mについて
鎌倉市→0.3m以上が500㎡以上
一体的な切土・盛土 2
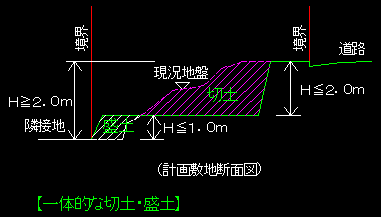
注意).H≧2.0mについて
鎌倉市→0.3m以上が500㎡以上
一体的な切土・盛土 3 (横浜市の基準)
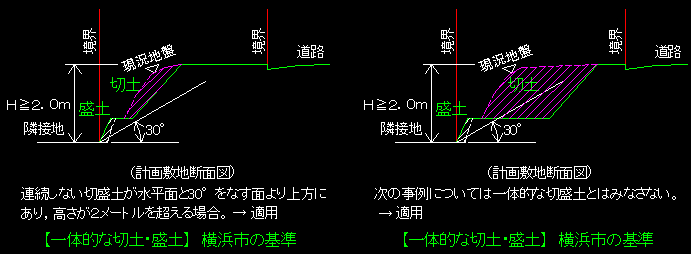
H≧0.5mの切土の施行範囲が500 ㎡以上,又は開発区域の過半以上
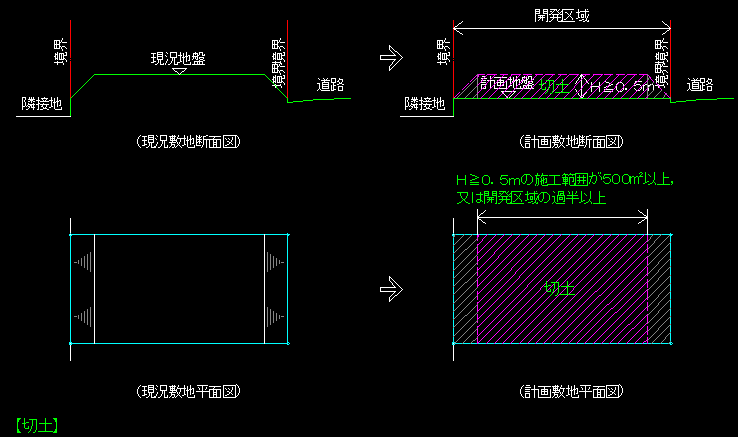
注意).H≧0.5mについて
鎌倉市→0.3m以上
横浜市→0m以上(高さに関係なく)
H≧0.5mの盛土の施行範囲が500 ㎡以上,又は開発区域の過半以上
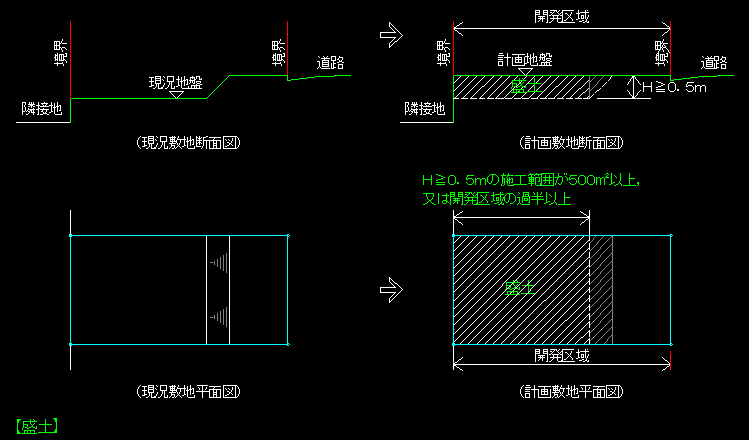
注意).H≧0.5mについて
鎌倉市→0.3m以上
横浜市→0m以上(高さに関係なく)
H≧0.5mの切土・盛土の施行範囲が500 ㎡以上,又は開発区域の過半以上
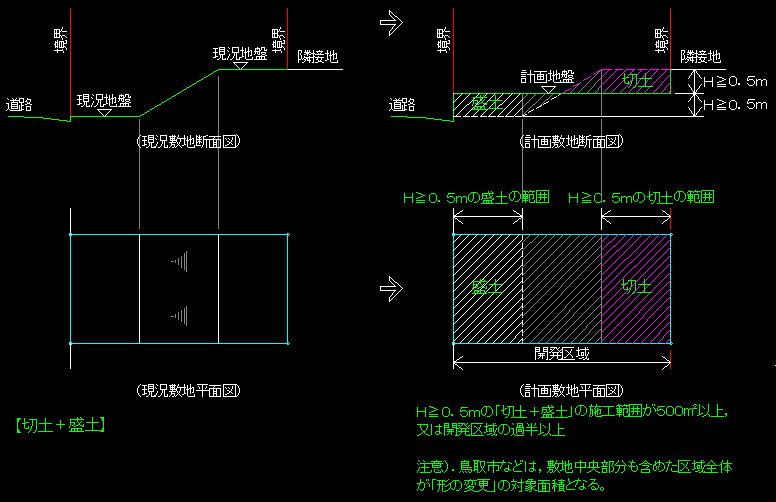
注意).H≧0.5mについて
鎌倉市→0.3m以上
横浜市→0m以上(高さに関係なく)
鳥取市→H≦0.5m部分(敷地中央)も含めた区域全体が「形の変更」の対象面積となる
「質の変更」の事例 (一定規模以上の土地の区画形質の変更)
例 1
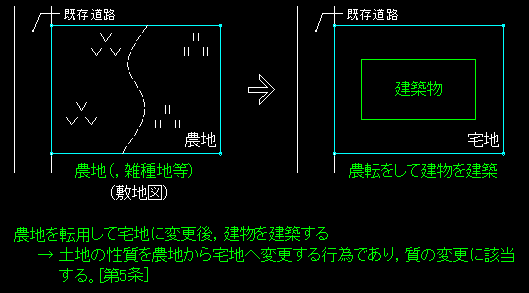
例 2
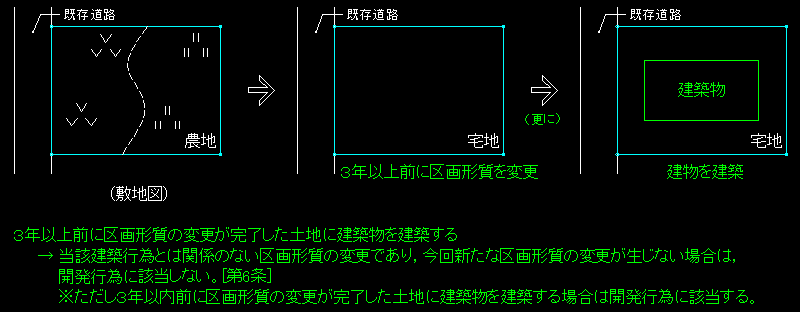
例 3
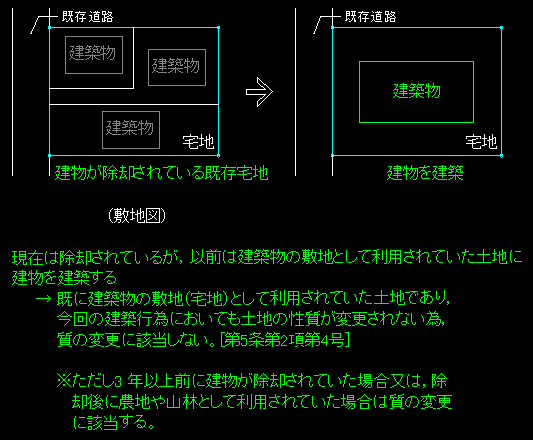
「区画の変更」 の事例 その1 (一定規模以上の土地の区画形質の変更)
例 1
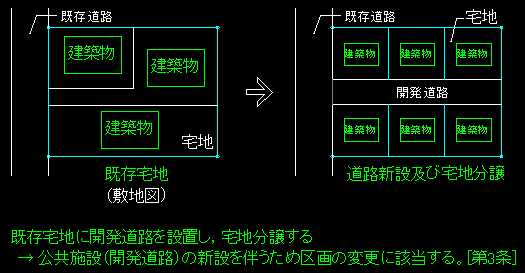
例 2
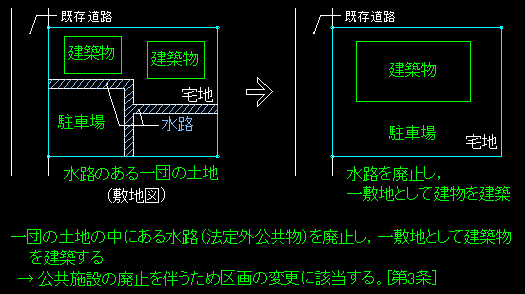
例 3
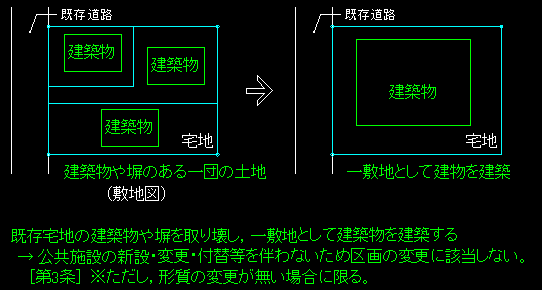
例 4
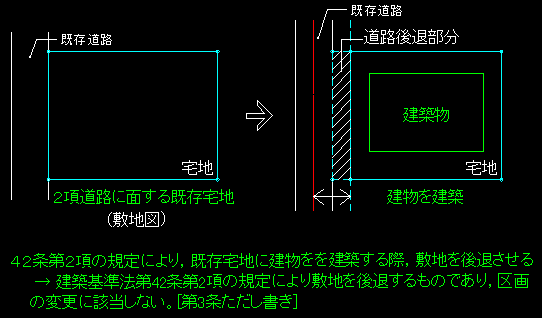
例 5 (横浜市の基準例)
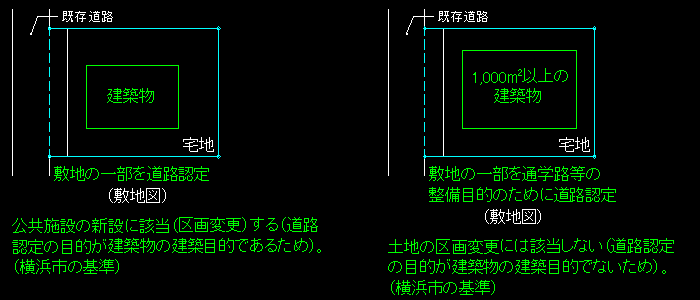
例 6 (横浜市の基準例)
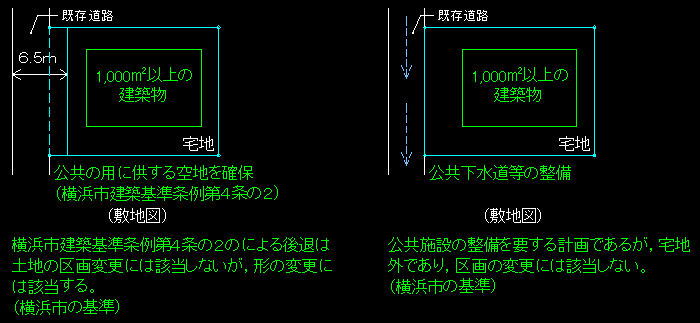
「区画の変更」 の事例 その2 (一定規模以上の土地の区画形質の変更)
例 1
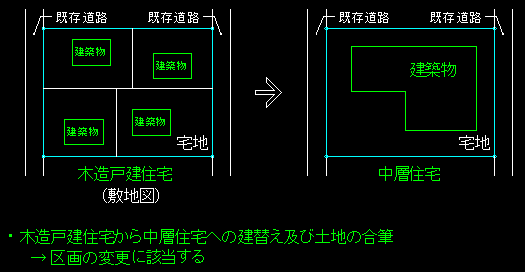
・ 敷地及び建築物の権利の変更に係わらず,建築物の利用形態に着目すると,建築区画に変更があるため,区画の変更に 該当する。
例 2
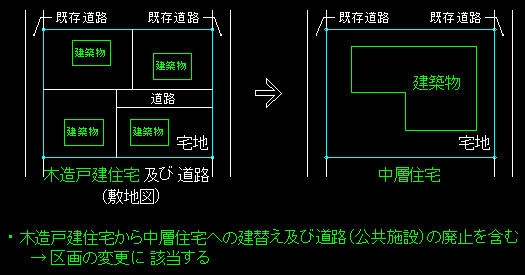
・ 敷地及び建築物の権利の変更に係わらず,建築物の利用形態に着目すると,建築区画に変更があるため,区画の変更に 該当する。
例 3 (横浜市の基準例)
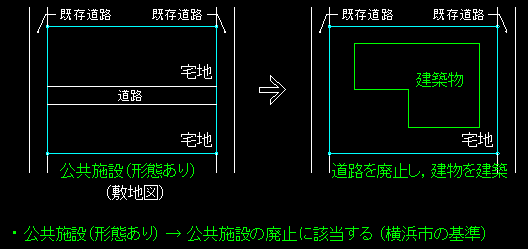
例 4 (横浜市の基準例)
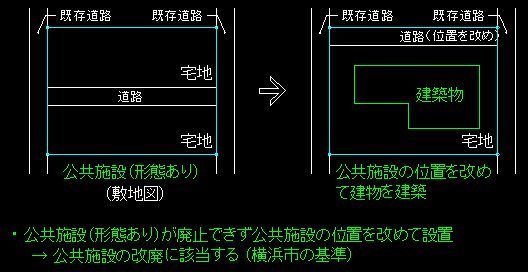
例 5
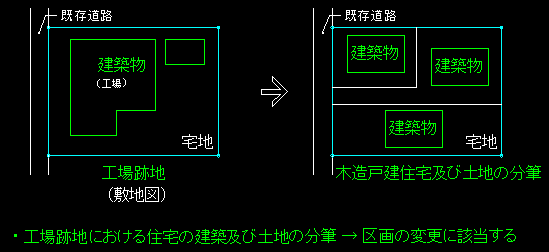
・ 敷地及び建築物の権利の変更に係わらず,建築物の利用形態に着目すると,建築区画に変更があるため,区画の変更に 該当する。
例 6
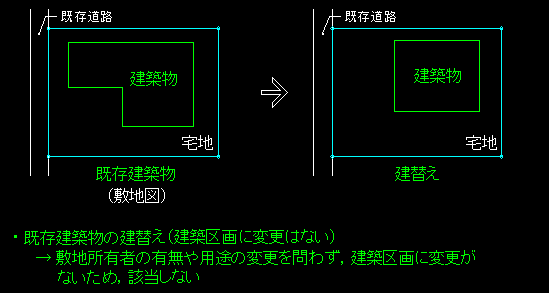
例 7 (欠番)
例 8 (欠番)
例 9
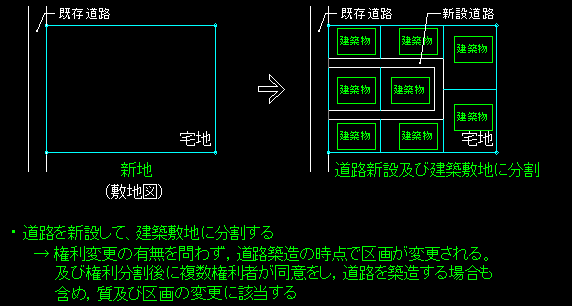
例 10
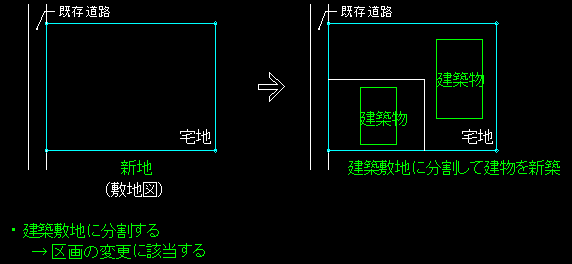
例 11 (横浜市の基準例)
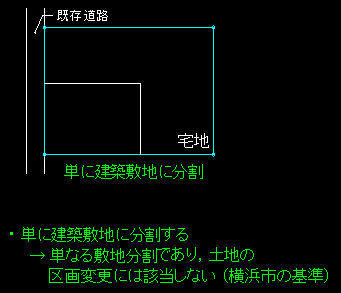
例 12
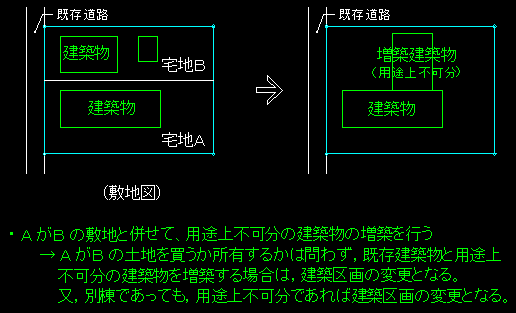
例 13 (横浜市の基準例)
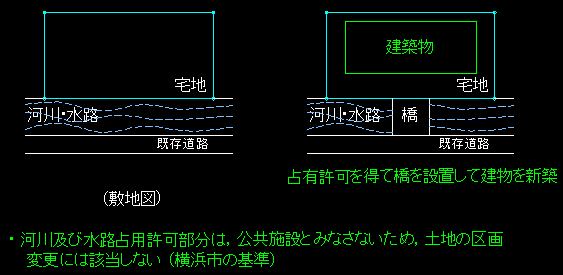
■ 003 「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」について
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」について
土地の物理的形状,計画的利用目的等からみて一体性が認められる「土地の区画形質の変更」を行う主たる目的が,建築物の建築敷地又は特定工作物の建設用地に供することにある場合( 以下,「建築目的」という。) をいう。
「土地の区画形質の変更」を行う目的は,行為者の主観的な態様(内心の有り様) にとらわれず,一体性が認められる「土地の区画形質の変更」に挙げられる諸事由を総合的,客観的に判断するものとする。
① 「主として」について
その主たる目的が『建築目的』である場合,一体性が認められる範囲(区域) 内の行為は,道路の新設や排水施設の整備等であっても,それが主として『建築目的』であれば,開発行為に該当するものとする。
ただし,一体性が認められる範囲(区域) 内に,建築物を建築する部分が存していても,全体として,主たる目的から『建築目的』でないとされる場合は,当該建築物を建築する部分の行為も開発行為に該当しないものとする。
② 「建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する」場合について
建築物の建築行為,特定工作物の建設行為そのものとは別の,これらに先行する行為が開発行為に該当し,建築行為又は建設行為そのものに属する土地の形状の変更は,開発行為に該当しないものとする。
したがって,擁壁を設置する行為は,建築確認を受けている擁壁であっても,建築物を建築する敷地を造成するものであれば開発行為とする。
一方,伐採や抜根,既存建築物の除去,塀・垣・さく等の除却や設置,建築物の建築等と不可分な一体的な工事と認められる基礎打ちや土地の掘削等は,開発行為に該当しないものとする。
また,建築行為及び建設行為の主体は,特に限定されておらず,必ずしも「土地の区画形質の変更」を行うもの自身が建築又は建設する場合に限らず,宅地のみを分譲する者が行う造成工事も開発行為に該当するものとする。
例えば,「建築目的」でない「区画形質の変更」後に「建築目的」で利用する場合は,開発行為とする。
具体的な事例としては,宅地である土地の区画を変更した上で,いったん屋外駐車場として利用した後に,新たに共同住宅等の建築を行う場合が該当する。これは,時間的なずれが生じているものの,駐車場へ土地利用を変更する前の状態が「従来の敷地」であると判断されることより,開発行為に該当すると判断するものである。
③ 「建築目的」の有無について
「建築目的」の有無は,「山林現況分譲」,「菜園分譲」,「現況有姿分譲」,「建築不可」等の文言により形式的に判断されるものではなく,土地の区画割り,区画街路の状況,等諸般の事由を総合的に勘案し,客観的に判断するものとする。
尚,建築目的の判断については,以下に示す各事項によるものとする。
「建築目的」の判断について
ア) 土地の区画割り
土地が戸建て住宅等の建築に適した形状,面積に分割されていること。
イ) 区画街路
区画街路が整備され,又はその整備が予定され,宅地としての利用が可能となっていること。
ウ) 擁壁
住宅建設を可能とする擁壁が設置され,又はその設置が予定されていること。
エ) 販売価格
近隣の土地と比較してより宅地の価格に近いものといえること。
オ) 利便施設
上下水道,電気供給施設等の整備がなされ,若しくは近い将来整備されるような説明がなされ,又は附近に物品販売施設,学校その他の公益施設があり,生活上不便をきたさないような説明がなされていること。
カ) 交通関係
交通関係が通勤等に便利であるとの説明がなされていること。
キ) 附近の状況
附近で宅地開発,団地建設等が行われている,団地等がある,工場等の職場がある等の説明がなされていること。
ク) 名称
対象地に住宅団地と誤認するような名称が付されていること。
■ 004 開発許可/許可を要しない開発行為の規模/開発行為の許可を要しない通常の管理行為,軽易な行為その他の行為
開発許可
都市計画法第29条 全文
【開発行為の許可】
第29条都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は,あらかじめ,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市,同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあっては,当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる開発行為については,この限りでない。
開発行為 ⇒ 法第4条第12項 「定義」
国土交通省令で定める ⇒ 規第16条 「開発許可の申請」
一 市街化区域,区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で,その規模が,それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
政令 ⇒ 令第19条 「許可を要しない開発行為の規模」
二 市街化調整区域,区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で,農業,林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
政令 ⇒ 令第20条 「第29条第1項第二号及び第2項第一号の政令で定める建築 ... 」
三 駅舎その他の鉄道の施設,図書館,公民館,変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
政令 ⇒ 令第21条 「適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支 ... 」
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて,まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
政令 ⇒ 令第22条 「開発行為の許可を要しない通常の管理行為,軽易な行為 ... 」
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において,それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は,あらかじめ,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる開発行為については,この限りでない。
政令 ⇒ 令第22条の2 「法第29条第2項の政令で定める規模」
国土交通省令で定める ⇒ 規第16条 「開発許可の申請」
一 農業,林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
政令 ⇒ 令第20条 「第29条第1項第二号及び第2項第一号の政令で定める建築 ... 」
二 前項第三号,第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3 開発区域が,市街化区域,区域区分が定められていない都市計画区域,準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1項第一号及び前項の規定の適用については,政令で定める。
政令 ⇒ 令第22条の3 「開発区域が2以上の区域にわたる場合の開発行為の許可 ... 」
都市計画法29条解説
都市計画法29条の規定により,開発行為をしようとする者は,あらかじめ,都道府県知事(指定都市,中核市,特例市にあっては,当該市の長)の許可を受けなければならない。
ただし,下記の場合等には開発許可は不要である。
1.一定の面積に達しない開発行為(都市計画法29条1項1号)。「一定の面積」とは,東京都の特別区・既成市街地・近郊整備地帯などでは500平方メートル未満,市街化区域では1,000平方メートル未満,区域区分が定められていない都市計画区域では3,000平方メートル未満,準都市計画区域では3,000平方メートル未満である(同法施行令19条)。
2.市街化調整区域,区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で,農業,林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(同法29条1項2号)。
3.駅舎その他の鉄道の施設,社会福祉施設,医療施設,学校教育法 による学校(大学,専修学校及び各種学校を除く。),公民館,変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 (同法29条1項3号)。
4.国・都道府県・一定の市町村が行う開発行為(同法29条1項4号)。
5.都市計画事業の施行として行う開発行為(同法29条1項5号)。
6.土地区画整理事業の施行として行う開発行為(同法29条1項6号)。
7.市街地再開発事業の施行として行う開発行為(同法29条1項7号)。
8.住宅街区整備事業の施行として行う開発行為(同法29条1項8号)。
9.防災街区整備事業の施行として行う開発行為(同法29条1項9号)。
10.公有水面埋立法2条1項の免許を受けた埋立地であつて,まだ同法22条2項の告示がないものにおいて行う開発行為(都市計画法29条1項10号)。
11.非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 (同法29条1項11号)。
12.通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの(同法29条1項12号)。
都市計画法施行令第19条 全文
【許可を要しない開発行為の規模】
第19条 法第29条第1項第一号の政令で定める規模は,次の表の第1欄に掲げる区域ごとに,それぞれ同表の第2欄に掲げる規模とする。ただし,同表の第3欄に掲げる場合には,都道府県(指定都市等(法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第33条第6項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあっては,当該指定都市等又は事務処理市町村。第22条の3,第23条の3及び第36条において同じ。)は,条例で,区域を限り,同表の第4欄に掲げる範囲内で,その規模を別に定めることができる。