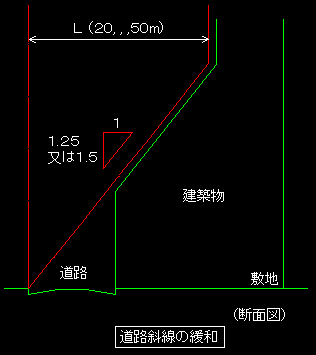
「建築基準法及び関連法解説」
全ページ
→
遠山英雄都市建築設計事務所 - HOMEへ
__________________________________________________
斜線制限
「 目 次
」
道路斜線
● 法56条 【建築物の各部分の高さ】
法56条第1項第一号
■ do_001 道路斜線制限とその適用範囲
(距離L)
道路斜線制限とその適用範囲
(距離L) (法56条第1項第一号,別表第3(い)欄,(ろ)欄及び(は)欄)
建物のセットバックと道路斜線
(法第56条第2項)
計画道路等を前面道路とみなす場合
(法56条6項,令131条
→ 令131条の2)
「2以上の道路がある場合」の建築物のセットバックがない場合の適用範囲の考え方
(法56条第1項第一号,令132条)
「2以上の道路がある場合」の建築物のセットバックがある場合の適用範囲の考え方
(法56条第1項第一号,令132条)
公園等がある場合の適用範囲の考え方及び川+2面道路がある場合の考え方
(法56条第1項第一号,同条第2項,令132条,134条)
■ do_002 敷地の地盤面と道路面に高低差がある場合
(
第135条の2)
■ do_003 敷地の地盤面に3m以上の高低差がある場合
(令2条第2項)
■ do_004 後退距離内に含まれるもの(建築できるもの)
後退距離内に含まれるもの(=在っても良い=建築できるもの)
(令130条の12第一号,第二号/法56条第2項及び第4項)
後退距離に含まれる物置等
建築設備である受水槽等について
後退距離に含まれるポーチ等
後退距離に含まれる物置,ポーチ等
セットバックの算定において除かれる部分(門,塀等)
(令130条の12第1項第三号,法56条第2項及び第4項)
道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の後退距離
(令130条の12第1項第三号,法56条第2項及び第4項)
建築物セットバックによる緩和の問題点と解釈
(令130条の12,法56条第2項)
擁壁がある場合の道路斜線 (高低差H=1.4の場合)
道路面と敷地の地盤面に1m以上の高低差がある場合
後退距離内に含まれる部分(建築できるもの)
(令130条の12第1項第六号,法56条第2項及び第4項)
前面道路の路面中心からの高さが1.2m以下の建築物の部分
境界線に沿って設ける門,塀
その他,セットバックの算定において除かれる部分
(令130条の12第1項第五号,法56条第2項及び第4項)
■ do_005 道路斜線適用範囲
基準容積率による道路斜線適用範囲
(法56条第1項第一号)
容積率加重平均と道路斜線適用範囲
(法52条7項,法56条第1項第一号)
建築物の敷地が2以上の地域又は区域に渡る場合
基本的な道路斜線適用範囲
(法52条7項,法56条第1項第一号)
建築物の敷地が2以上の地域又は区域に渡る場合
例1~4
■ do_006 住居系用途地域の斜線勾配
(法56条第3項,4項)
住居系用途地域の斜線勾配の場合
4項適用の場合と3項適用の場合の比較
■ do_007 道路斜線制限の「前面道路」の定義
(令132条)
■ do_008 道路斜線制限の基本
道路斜線制限の基本 (
「東京の街づくり情報」より )
道路に隅切りがあるケース
道路斜線の回り込みの考え方 (東京都,大阪市の採用例)
入り隅敷地の角度による回り込み(2W1)の考え方1~6
■ do_009 複数の道路がある敷地の道路斜線制限の緩和
(法56条第6項,令132条)
2以上の前面道路がある場合
4面道路がある敷地の緩和の原則
狭い幅員道路への回り込みの範囲
道路の隅切部分の取り扱い
道路の回り込みの基点の取扱い
L形の前面道路の場合 例1,2
(令132条) (2009JCBAより
)
T字形の前面道路の場合 例1,2 (2008横浜市pdf/2009JCBAより)
広い道路と狭い道路が斜めに接続している場合の取り扱い
例①,②
広い道路と狭い道路が斜めに接続している場合の取り扱い 別解釈③~⑤
広い道路と狭い道路が斜めに接続(120°以下,120°越え)している場合の取り扱い (2008横浜市pdfより)
2つの道路の場合の取り扱い(挟まれた敷地
例1) (2008横浜市pdfより)
2つの道路の場合の取り扱い(挟まれた敷地
例2) (2008横浜市pdfより)
入り隅前面道路の場合/入り隅前面道路の後退距離の取扱い
(横浜市pdf./大阪市/2009JCBAより)/
(横浜市pdf.より)
行き止り道路の場合(両側敷地あり,なし)
(横浜市pdf./2009JCBAより)
行止まり道路(両側敷地あり,なし)及び入隅敷地の後退距離の取り扱い
(横浜市pdf./2009JCBAより)
幅員が極端に異なる前面道路の取り扱いとセットバックの緩和
前面道路幅員が極端に異なる場合の取り扱い
前面道路幅員が1つでその幅員が異なる場合の取扱い (2008横浜市pdfより)
2以上の前面道路による緩和 例1,2 (2009JCBAより)
前面道路幅員がV字状の場合の取り扱い 例 (2008横浜市pdfより)
路地状敷地の道路斜線制限 例1 (横浜市pdf/2009JCBAより)
路地状敷地の道路斜線制限 例2 (「東京の街づくり」より)
敷地が隣地(宅地)を挟む場合の道路斜線の適用 (2008横浜市pdfより)
■ do_010 道路の反対側に公園等がある場合
(法56条6項,令134条)
前面道路の反対側に公園等がある場合の取り扱い 例 (2008横浜市pdfより)
前面道路の反対側に一部に公園がある場合 (2008横浜市pdfより)
隣地斜線
● 法56条
【建築物の各部分の高さ】
法56条第1項第二号
■ ri_001 隣地斜線の基本及びセットバックの場合
(法56条,令135条の3)
隣地斜線の基本及びセットバックの場合
壁面のセットバック緩和の考え方
敷地が公園,広場等に接する場合
(法56条6項,令135条の3第1項1号)
■ ri_001 敷地の地盤面が隣地と高低差がある場合
北側斜線
● 法56条 【建築物の各部分の高さ】
法56条第1項第三号
■ ki_001 北側斜線の原則/緩和規定
北側斜線の原則
一般的な緩和規定
① 敷地の北側に水面,線路敷等がある場合
(法56条6項,令135条の4第1項一号)
② 敷地の地盤面が北側隣地地盤面より1m以上低い場合
(法56条6項,令135条の4第1項二号,2項)
■ ki_001 敷地が2以上の地域等にわたる場合
(法56条5項)
●
法58条 【高度地区】
■ ko_001 高度地区の形態制限
(横浜市,東京都)
(法58条)
高度斜線制限
道路斜線
● 法56条
【建築物の各部分の高さ】
法56条第1項第一号
■ do_001 道路斜線制限とその適用範囲
(距離L)
道路斜線制限とその適用範囲
(距離L) (法56条第1項第一号,別表第3(い)欄,(ろ)欄及び(は)欄)
法56条第1項第一号
第56条 建築物の各部分の高さは,次に掲げるもの以下としなければならない。
一
別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域,地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ,前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては,当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に,同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
別表第3 ⇒ 法別表第3
「前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制
... 」
容積率 ⇒ 法第52条 「容積率」
適用範囲の距離L(20~50m)は基準容積率(別表第3(い)欄及び(ろ)欄)に応じて(は)欄に定められる。
L
以上の距離にある建築物の部分については,道路斜線制限は適用されない。
| 道路斜線制限とその適用範囲 (距離L) |
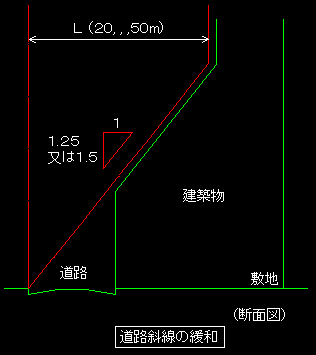 |
建物のセットバックと道路斜線 (法第56条第2項)
第56条第2項
2
前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については,同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは,「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
政令 ⇒ 令第130条の12
「前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制
... 」
| 建物のセットバックと道路斜線 |
|
後退距離(L)は,建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものとする。 後退距離に応じて道路斜線の適用範囲(L)も移動する。 |
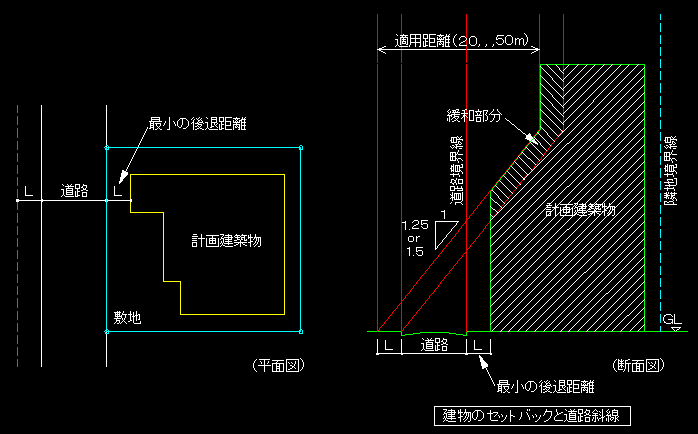 |
計画道路等を前面道路とみなす場合 (法56条6項,令131条
→ 令131条の2)
| 計画道路等を前面道路とみなす場合 |
都市計画道路,地区計画等の予定道路,壁面線又は位置の制限の規定による道路がある場合で行政庁が認めた場合,また土地区画整理事業を施した地区で行政庁が指定した道路は前面道路とみなされる。(令131条の2) |
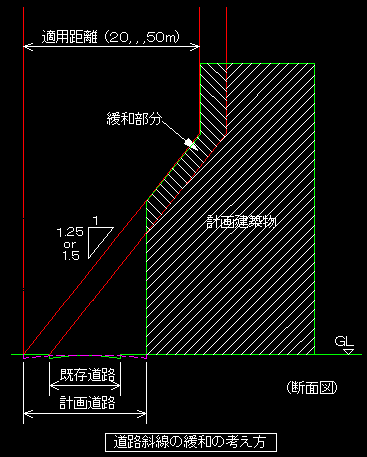 |
「2以上の道路がある場合」の建築物のセットバックがない場合の適用範囲の考え方
(法56条第1項第一号,令132条) (2006H)
| 建築物のセットバックがない場合の適用範囲の考え方 | |
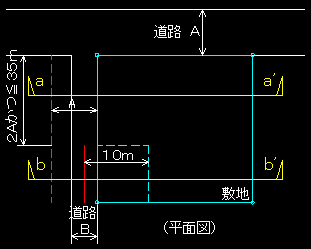
|
|
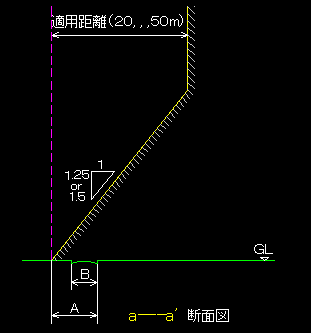
|
 |
「2以上の道路がある場合」の建築物のセットバックがある場合の適用範囲の考え方
(法56条第1項第一号,令132条) (2006H)
| 建築物のセットバックがある場合の適用範囲の考え方 | |
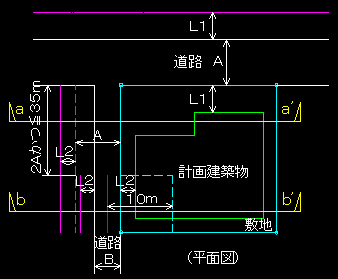 |
|
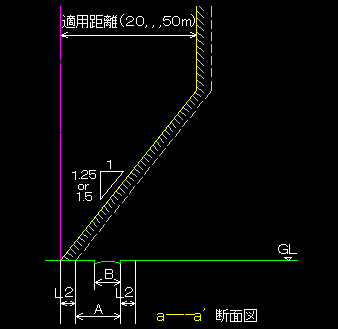
|
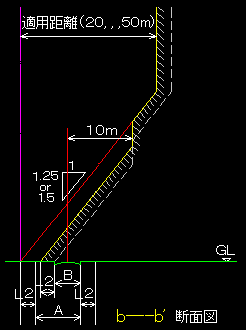 |
公園等がある場合の適用範囲の考え方及び川+2面道路がある場合の考え方
(法56条第1項第一号,同条第2項,令132条,134条) (2006H)
| 公園等がある場合の適用範囲の考え方 | 川+2面道路がある場合の考え方 (建築物のセットバックがない場合) |
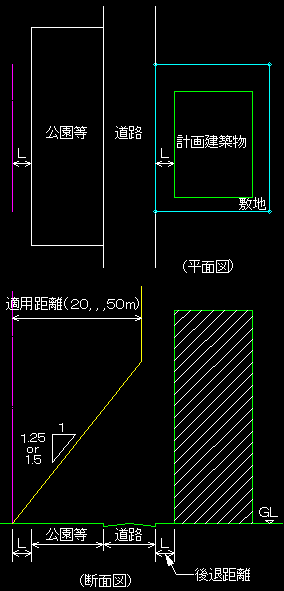 |
たとえB<Cでも,C<Aなので斜線ハッチ部分のみC道路の適用を受け,その他はAの幅の斜線制限を受ける。 川若しくは海の他,公園,広場,その他これに類するものの場合も同様。 |
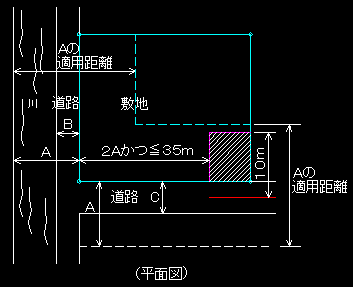 |
■ do_002 敷地の地盤面と道路面に高低差がある場合
(第135条の2)
【道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合】
第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては,その前面道路は,敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は,地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては,同項の規定にかかわらず,規則で,前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
敷地の地盤面が道路面より1m以上高い場合及び敷地の地盤面が道路面より低い場合 (2006H)
| 敷地の地盤面が道路面より1m以上高い場合 | 敷地の地盤面が道路面より低い場合 この場合は,当然,道路の高さからの斜線となる。 |
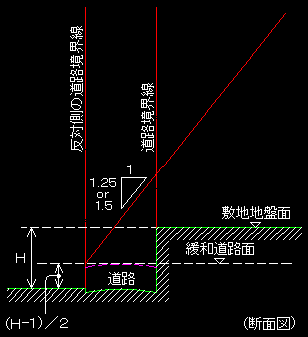 |
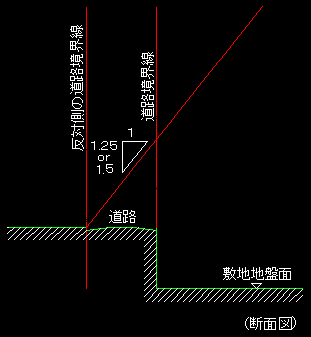 |
■ do_003 敷地の地盤面に3m以上の高低差がある場合
(令2条第2項) (2006H)
| 敷地の地盤面に3m以上の高低差がある場合 |
|
敷地に地盤面が複数ある場合 道路斜線制限は,建築物の各部分の高さを制限しており,複数の地盤面がある場合は,それぞれの地盤面ごとに適用する。 |
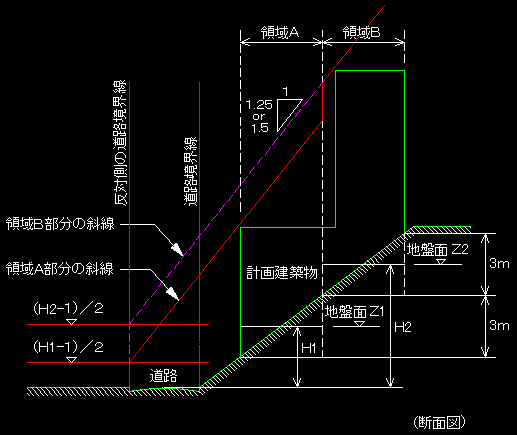 |
■ do_004 後退距離内に含まれるもの(建築できるもの)
後退距離内に含まれるもの(=在っても良い=建築できるもの) (2006H)
(令130条の12第一号,第二号/法56条第2項及び第4項)
| 後退距離に含まれる物置等 | |
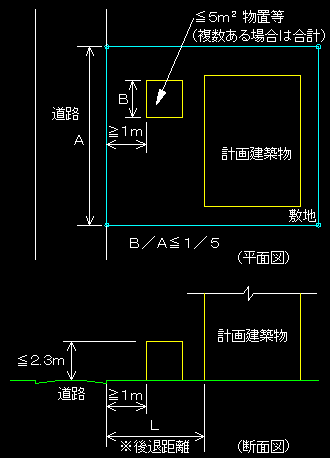 |
セットバックの算定において除かれる部分 物置,自転車置場その他これらに類する用途に供するもので次の要件を満たす建築物の部分 イ 軒の高さが前面道路の路面の中心から2.3m以下であり,かつ,床面積の合計が5㎡以内であること。 ロ 間口率(当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを,敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値)が1/5以下であること。 ハ 前面道路の境界線から1m以上後退していること(建建築物の壁,柱等の面で測定)。 |
建築設備である受水槽等について
(令130条の12第一号) (2009JCBAより
)
建築設備である受水槽等については,建築物に該当することから,後退距離の算定の対象となるが,「物置その他これに類する用途に供する建築物」として,令130条の12第
1号の要件に該当するものであれば,後退距離L内に建築が可能となる。
なお,受水導等の位置に建築物に該当しない機械式駐車場等がある場合は,工作物であるため後退距離の算定の対象外(除く)となる。
後退距離に含まれるポーチ等 (2006H)
(令130条の12第二号,法56条第2項及び第4項)
| 後退距離に含まれるポーチ等 | |
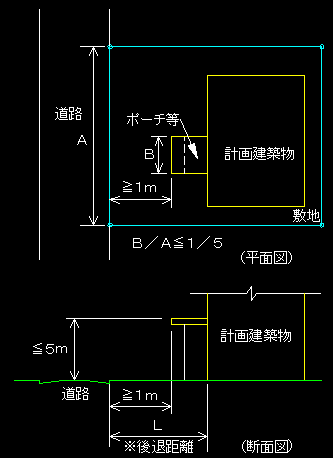 |
ポーチその他これらに類するもので,次の要件を満たすもの イ 高さが前面道路の路面の中心から5m以下であること。 建築物の部分 ロ 間口率(当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを,敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値)が1/5以下であること。 ハ 前面道路の境界線から1m以上後退していること(建建築物の壁,柱等の面で測定)。 |
後退距離に含まれる物置,ポーチ等 (2006H)
(令130条の12第一号,二号/法56条第2項及び第4項)
| 後退距離に含まれる物置,ポーチ等 | |
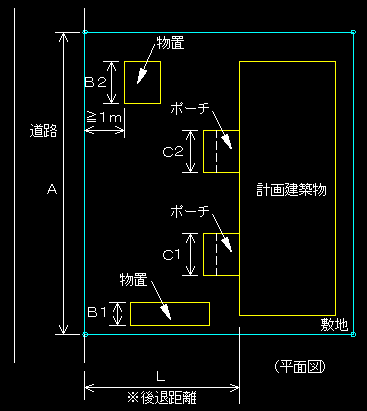 |
複数の物置等の後退距離の考え方 敷地内に要件を満たす物置,ポーチ等が複数ある場合の間口率の算定(令130条の12第1号,2号)については,図のように敷地地単位で算定する。 一号(物置その他)の間口率: (B1+B2)÷A ≦1/5 二号(ポーチその他)の間口率: (C1+C2)÷A ≦1/5 |
セットバックの算定において後退距離に含まれる部分(門,塀等)
(令130条の12第1項第三号,法56条第2項及び第4項)
| セットバックの算定において除かれる部分(門,塀等) | |
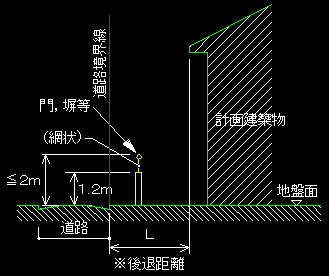 |
道路に沿って設られる前面道路の路面の中心からの 高さが2m以下の門,塀,前面道路の路面の中心から の高さが1.2mを超える部分網状その他これに類する もの(原則)。 |
道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の後退距離 (2006H)
(令130条の12第1項第三号,法56条第2項及び第4項)
|
道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の後退距離 例
道路と敷地に高低差がある場合の注意点 道路と敷地に2mを超える高低差がある場合は,「路面の中心からの高さが2m以下」という条件高さをオーバーしてしまい,大小に限らず門,塀を設けると原則,後退距離(L)は例1のような取扱いとなる。ただし,例2のような落下防止のためのネットフェンス等は,行政庁によって支障ないものとして扱っている場合もある。 |
|
|
例1
塀があるため原則,Lしか後退距離としてみなされない。 |
例2 ネットフェンスが設けられていても,Lを後退距離とみなす。(ただし,行政庁に確認のこと) |
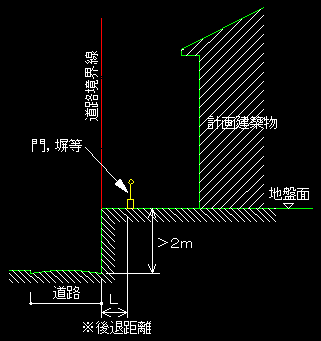 |
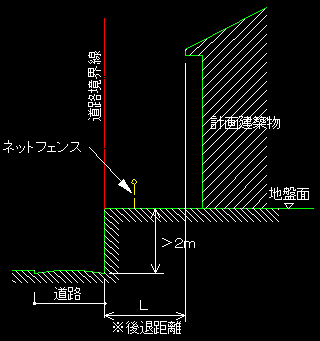 |
建築物セットバックによる緩和の問題点と解釈 (2002K
)
建築物が前面道路の境界線から後退した場合,「前面道路の反対側の境界線」は「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(中略)に相当する距離だけ外側の線」と読み替えられ道路斜線制限が緩和される(法56条2項)。また,この後退部分には,地盤面下の建築物の部分のほか,一定規模の「物置その他これらに類するもの」「ポーチ」「塀」などが設けられる(令130条の12)。
ここで問題となるのは,2段式機械駐車場等の「作物,建築設備,擁壁の上の柵等を設置することが可能かどうかである。この緩和の趣旨は道路から建築物を後退させることにより,当該建築物が道路に及ぼす影響を少なくするものであり,この後退部分に建築物とならない工作物を築造することは可能であろう。
建築設備の屋外単独設置の場合は,物置その他これらに類するもので緩和するのが妥当であり,設置可能であろう(令130条の12第一号)。
また,擁壁の柵等については,擁壁と道路の高低差の緩和を行った面からの高さで設置可能な規模(令130条の12第三号)であれば設置可能であろ(下図)。
尚,各内容については,事前に特定行政庁に確認されたい。
擁壁がある場合の道路斜線
(高低差H=1.4の場合) (2002K
)
| 擁壁がある場合の道路斜線 (高低差H=1.4の場合) | |
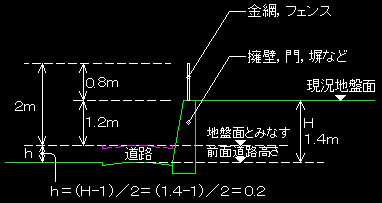 |
敷地に高低差Hがある場合,H≧1mであれば地盤面はh=(H-1)/2m緩和される(令135条の4第二号)。 その場合に令130条の12第三号による,門,塀の緩和を適用すると,高低差H≦1.4m以下であれば緩和対象となる。 |
道路面と敷地の地盤面に1m以上の高低差がある場合 (2008横浜市pdfより
)
| 道路面と敷地の地盤面に1m以上の高低差がある場合 | |
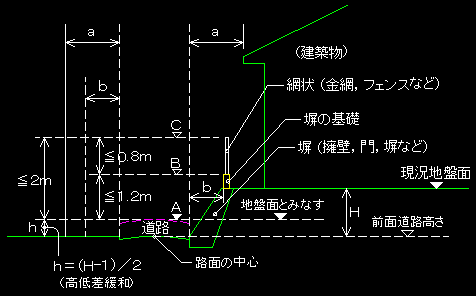 |
1.図に示す塀の高さは,令第2条第1項第六号イ及び令第135条の2により,A点からC点までとなる。 2.A点からB点までは,透過性のない塀の一部とみなす。 3.法第56条第2項による後退距離がaとなるものは,A点からC点までの高さが2m以下で,かつA点からB点までの高さが1.2m以下でB点か高さC点までの部分が「網状その他これに類する形状」とした場合です。 これ以外の場合は,後退距離はbとなる。 なお,擁壁の天端に生け垣のみの設置であれば後退距離はaとなる。また,令第135条の2第2項に基づき規則が定められている場合はこれによる。 (建建企第392号 建築局長 平成17年3月31日改正) |
参考).
建築基準法の一部を改正する法律等の施行について
(昭和62年12月3日住指発第395号)
建築基準法の一部を改止する法律等の施行について
(昭和62年12月3日住指発第396号,住街発第110号)
後退距離内に含まれる部分(建築できるもの)
(令130条の12第1項第六号,法56条第2項及び第4項)
前面道路の路面中心からの高さが1.2m以下の建築物の部分 (2002K
)
|
セットバックの算定において除かれる部分 ※前面道路の路面中心からの高さが1.2m以下の建築物の部分 |
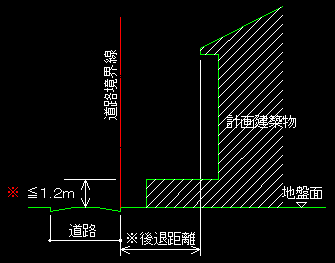 |
後退距離内に含まれるもの(建築できるもの)
(令130条の12第1項第四号,法56条第2項及び第4項)
境界線に沿って設ける門,塀 (2002K
)
|
セットバックの算定において除かれる部分 境界線に沿って設ける門,塀 |
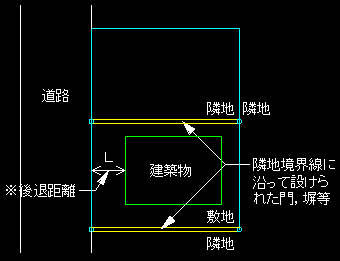 |
後退距離内に含まれるもの(建築できるもの)
(令130条の12第1項第五号,法56条第2項及び第4項)
その他,セットバックの算定において除かれる部分 (2002K
)
歩廊,渡り廊下その他これに類する建築物の部分で行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めた建築物の部分。
行政庁の規則で定めるものの例としては,具体的には「がんぎ(多雪区域にみられる家屋の一部やひさしを道路側に伸ばし,積雪を防ぐことを目的としたアーケード状のもの)」や道路上に設けられた公共歩廊等と接続する部分等が考えられる。
■ do_005 道路斜線適用範囲
基準容積率による道路斜線適用範囲
(法56条第1項第一号)
| 基準容積率による道路斜線適用範囲((L)の求め方 | |
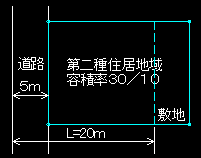 |
※ 基準容積率は 5m×4/10=200% 基準容積率は法別表3の(ろ)の10分の20以下の場合となり,よって道路斜線の適用距離は同表(は)の20mとなる。 |
容積率加重平均と道路斜線適用範囲
(法52条7項,法56条第1項第一号)
建築物の敷地が2以上の地域又は区域に渡る場合 (2006H)
| 容積率加重平均と道路斜線適用範囲 例 1 | 容積率加重平均と道路斜線適用範囲 例 2 | ||
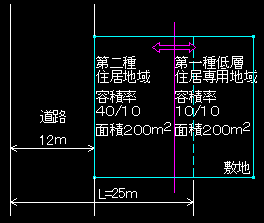 |
※ 基準容積率は =(400%×200㎡ +100%×200㎡)/400㎡ =250% 基準容積率は法別表3の(ろ)の10分の20~10分の30以下の場合となり,よって道路斜線の適用距離は同表(は)の25mとなる。 |
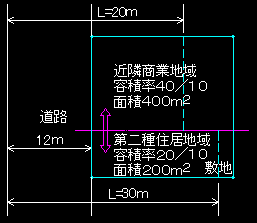 |
※ 基準容積率は =(400%×400㎡ +200%×200㎡)/600㎡ =333% よって道路斜線の適用距離は近隣商業地域においては法別表3の(は)の20mとなり,第二種住居地域においては同表の(は)の30mとなる。 |
基本的な道路斜線適用範囲
(法52条7項,法56条第1項第一号)
建築物の敷地が2以上の地域又は区域に渡る場合 (2006H)
| 基本的な道路斜線適用範囲 基準容積率350%の場合の 例 1 |
|
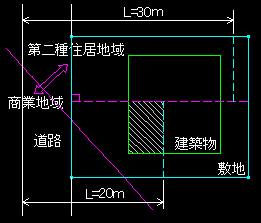 |
※ 適用範囲 商業地域:20m 第二種住居地域:30m ← 網掛け部分は商業地域の適用範囲内(20m)で道路斜線制限がなされる。 |
| 敷地が2以上の異なる用途地域にまたがる場合は,前面道路に面する方向の各断面内において,前面道路に接する地域または区域の適用距離が,前面道路に接しない地域または区域にも適用される。よってこの適用方式により,上図の場合,前面道路に接しない第2種住居地域の網掛け部分が,前面道路に接する商業地域の適用距離内(20m)で道路斜線制限がされることになる。 | |
基本的な道路斜線適用範囲(法52条7項,法56条第1項第一号)
建築物の敷地が2以上の地域又は区域に渡る場合 (2006H)
| 基本的な道路斜線適用範囲 基準容積率350%の場合の 例 2 |
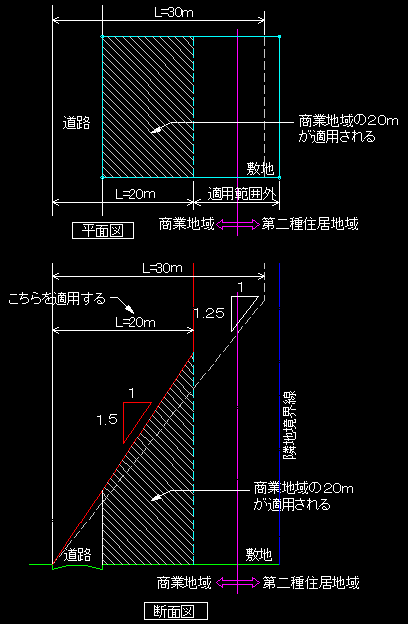 |
基本的な道路斜線適用範囲(法52条7項,法56条第1項第一号)
建築物の敷地が2以上の地域又は区域に渡る場合 (2006H)
| 基本的な道路斜線適用範囲 基準容積率350%の場合の 例 3 |
||
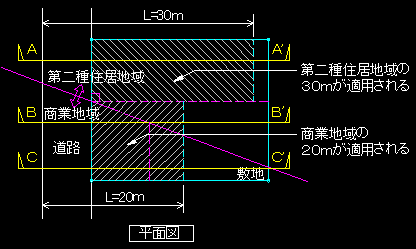 |
||
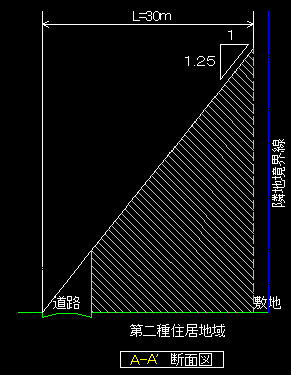 |
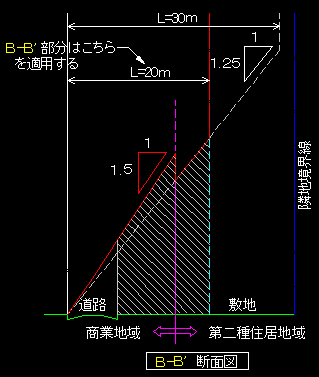 |
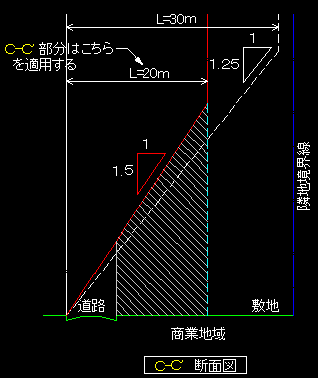 |
基本的な道路斜線適用範囲(法52条7項,法56条第1項第一号)
建築物の敷地が2以上の地域又は区域に渡る場合 (2006H)
| 基本的な道路斜線適用範囲の応用編 基準容積率350%とした場合の 例 4 |
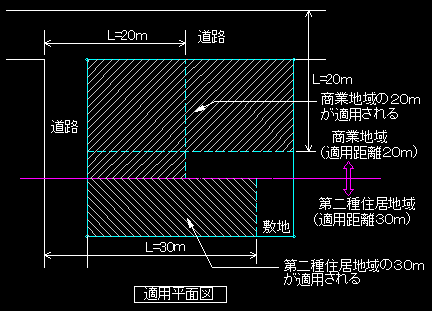 |
■ do_006 住居系用途地域の斜線勾配
住居系用途地域の斜線勾配の場合
(法56条第3項,4項)
第一種・二種中高層住居専用地域及び第一種・二種・準住居地域の前面道路が12m以上である場合は,前面道路の反対側からの水平距離が前面道路の幅員の1.25倍より大きい部分では斜線勾配を1.5とする。
| 住居系用途地域の斜線勾配 第一種・第二種中高層住居専用地域,第一種・第二種・準住居専用地域での前面道路幅員12m以上の斜線制限 |
|
| 建築物がセットバックしない場合 | 建築物がセットバックした場合 |
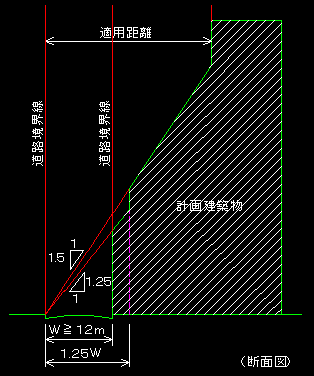 |
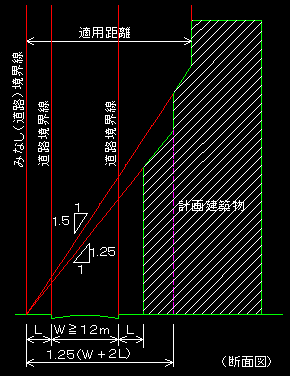 |
4項適用の場合と3項適用の場合の比較
(法56条第3項,4項) (1995K
)
| 住居系用途地域の斜線勾配 第一種・第二種中高層住居専用地域,第一種・第二種・準住居専用地域での前面道路幅員12m以上の斜線制限 4項適用の場合と3項適用の場合の比較 |
|
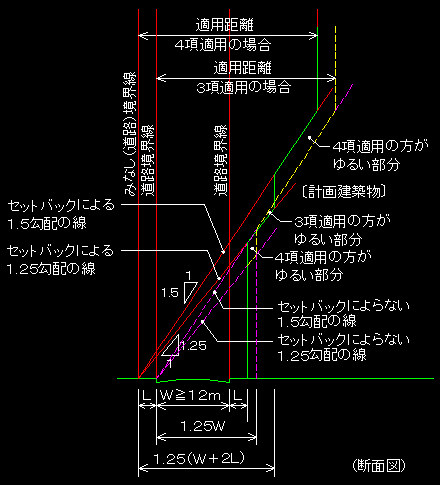 |
住居系地域で前面道路幅員が12m以上の場合 この規定は,1995年5月25日に施行された最新の規定である。 第1・2種中高層住居専用地域,第1・2種住居地域または準住居地域内,すなわち住居系の用途地域において前面道路の幅員が12m以上の場合,前面道路の反対側の境界線から水平距離が前面道路の幅員の1.25倍以上の区域では道路斜線は1.5勾配となる(法56条第3項)。 また,前面道路から後退した場合は,法56条第2項に規定するセットバック規定と同様の緩和措置が設けられており,この緩和措置は,建築主の判断により,その適用が選択できる(法56条第4項)。これは,セットバックによる道路斜線より,セットバックによらない道路斜線の方が,制限が緩やかになる部分があるためである。この選択は,3項あるいは4項の適用のどちらかを道路斜線のすべてにおいて適 用する場合のもので,部分により有利な道路斜線を適用することはできない。 また,セットバックによらない道路斜線を適用した場合においては,セットバックしている建築物であっても,道路斜線の適用距離の始点は,前面道路の反対側の境界線となる。 この緩和に関しては,後退による1.25勾配の線,後退によらない1.5勾配の線,さらに道路斜線の適用距離の問題が絡むため,非常に複雑である。したがって,セットバックによる道路斜線を適用した方が有利か否かは,一概に決めつけることはできない。しかし,一般的には,セットバックの大きい建築物については,セットバックによる道路斜線を適用する方が有利となる。また,指定容積率が小さい場合は,これが大きい場合と比較して,適用距離の関係からセットバックが小さくともセットバックによる道路傾斜を適用することが有利となる場合が早く現れる。 |
■ do_007 道路斜線制限の「前面道路」の定義
(1) 道路斜線制限の「前面道路」の定義
(令132条) (2002K
)
間題点と解釈
道路斜線制限においては,2以上の前面道路がある場合,広い幅員の道路を前面道路として斜線制限が緩和される(令132条)。
しかし,敷地の接道長さが短いと,幅員の広い道路からの消防活動が十分にできないなどの理由から,容積率の算定や道路斜線制限について前面道路とみなさないという特定行政庁も多い。
前面道路の解釈として,非常用の進人口の設置を要する4m以上の幅員を必要とすることや,あるいは条例等で定める数値以上の接道長さを必要とすることも無理な解釈とはいえないであろう。したがって計画にあたっては,事前に所定の特定行政庁で確認されたい。
| 幅員の大きな道路に接する長さが短い例1,2 | |
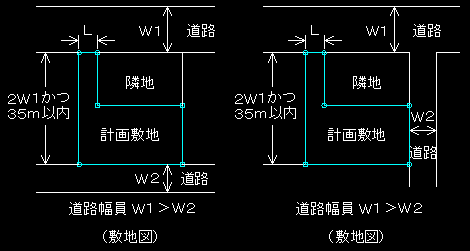 |
Lの幅員により前面道路として取り扱うか判断することになる。 L≧2mとするのが一般的である。 |
| 幅員の大きな道路に接する長さL≧2mの例 | |
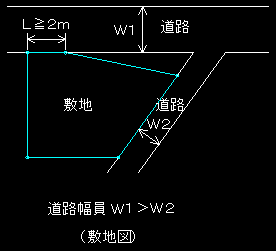 |
一般的な前面道路としての幅員 : W1 |
■ do_008 道路斜線制限の基本
道路斜線制限の基本 (
「東京の街づくり情報」より )
| 道路斜線制限の基本 ケース1~8 |
道路高さ制限による建築物の高さの限度は,道路境界線(敷地と道路の境界線)の形には関係なく,「前面道路の反対側の境界線」に水平な等高線を描くことになる。 したがって,下図のどのケースでも道路高さ制限による建築物の高さの限度は,敷地や道路の形にとらわれる必要はなく,図のように単純に「前面道路の反対側の境界線」に水平な等高線を描けばよいことになる。 ケース1は基本中の基本ケース2からケース4までは前面道路の反対側の境界線は直線であり,ケース1の応用問題。道路境界線の形にとらわれてはならない。ケース5とケース6は,前面道路の反対側の境界線が出隅になっているケース。前面道路の反対側の境界線の頂点からは平行線の代わりに同心円型の等高線が発生している。 ケース7とケース8は前面道路の反対側の境界線が入隅になっているケース。この場合の道路高さ制限は平行線が折り重なることになり,折り重なる範囲では厳しい方の制限が働く。 |
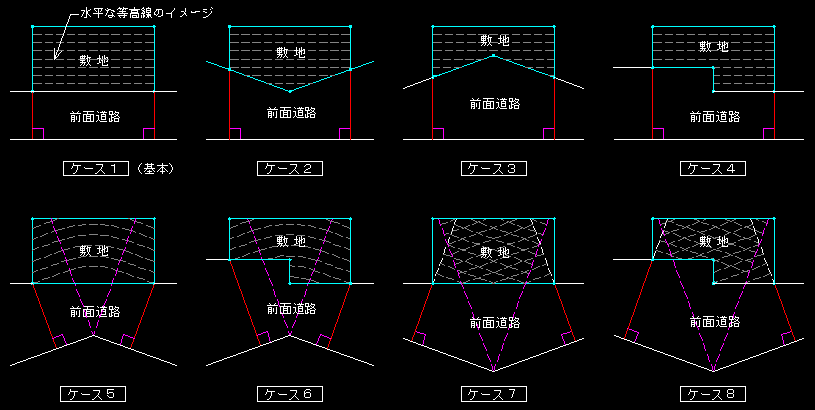 |
| 道路に隅切りがあるケース | |
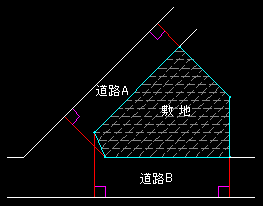 |
敷地,道路,道路高さ制限の関係 応用編道路Aと道路Bに分けて敷地に対する高さの等高線をイメージする。隅切りがあっても心配することはない。基本通りに等高線を描く。 |
| 入り隅敷地の角度による回り込み(2W1)の考え方1~4 |
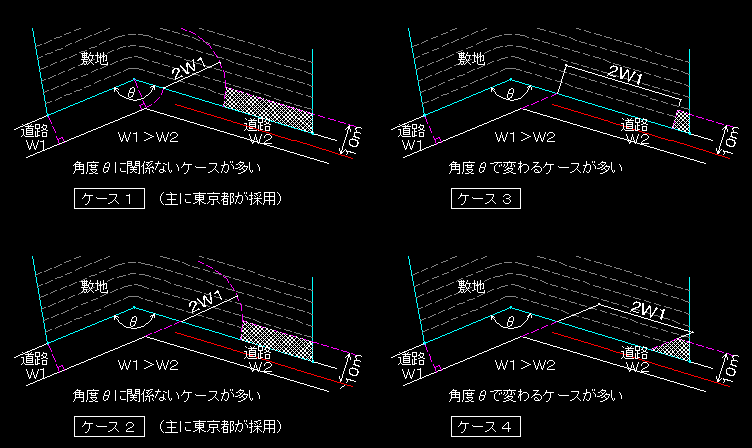 |
| 入り隅敷地の角度による回り込み(2W1)の考え方5,6 |
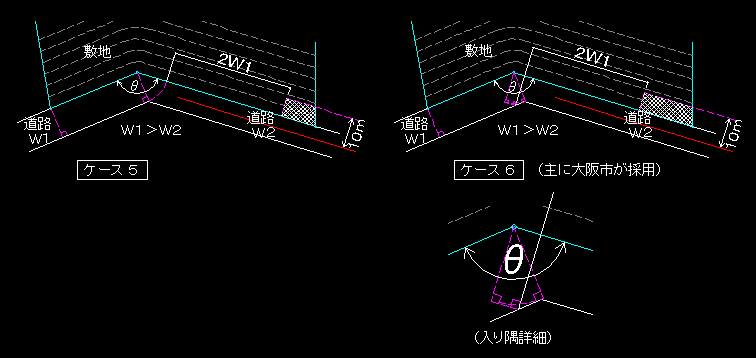 |
■ do_009 複数の道路がある敷地の道路斜線制限の緩和
(法56条第6項,令132条)
複数の道路がある敷地の道路斜線制限の緩和
【2以上の前面道路がある場合】
第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては,幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で,かつ,35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については,すベての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち,2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあっては,10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で,かつ,35m以内の区域については,これらの前面道路のみを前面道路とし,これらの前面道路のうち,幅員の小さい前面道路は,幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については,その接する前面道路のみを前面道路とする。
2以上の前面道路がある場合(法56条第6項,令132条)
| 2面道路の緩和の原則 | 2面道路がある敷地の緩和の原則(住居系地域の場合) |
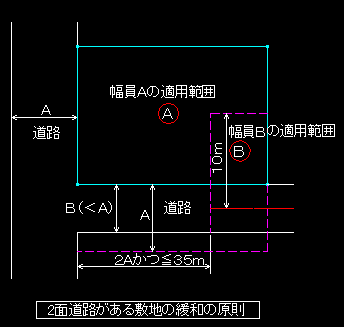 |
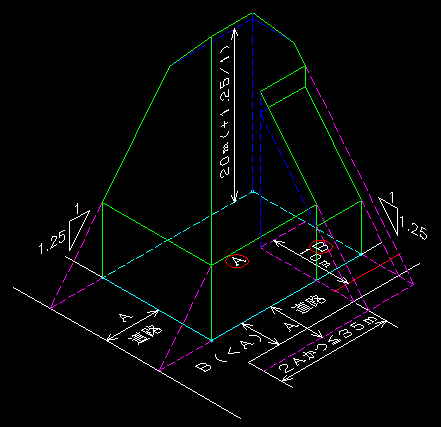 |
| 4面道路がある敷地の緩和の原則 |
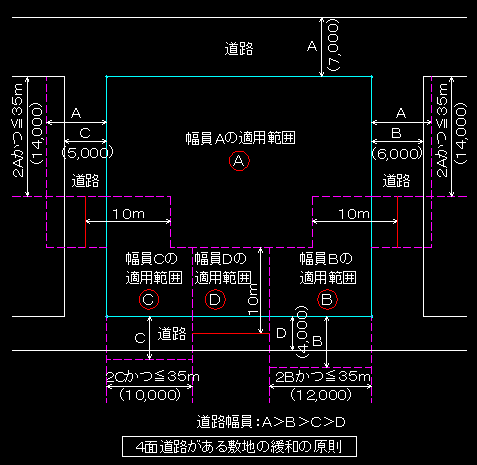 |
| 道路の隅切部分の取り扱い | |
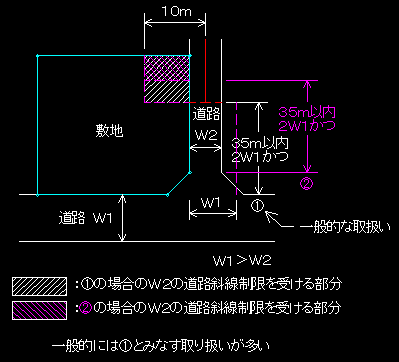 |
敷地が広い幅員の道路と狭い幅員の道路に面する場合,広い幅員の道路が回り込む基点をどこにするかで解釈が分かれる場合がある。 一般的に,隅切部分は狭い幅員の道路の部分とみなし,広い幅員の道路の部分とはみなさない取扱いが多い。 しかし,隅切の状態により,たとえば,その隅切部分の管理者などにより判断して,広い幅員の道路の回り込む基点を決める場合もあるだろう。 |
道路の回り込みの基点の取扱い
L形の前面道路の場合
例1,2 (令132条) (2009JCBAより
)
| L形の前面道路の回り込みの基点 例1 | L形の前面道路の回り込みの基点 例2 |
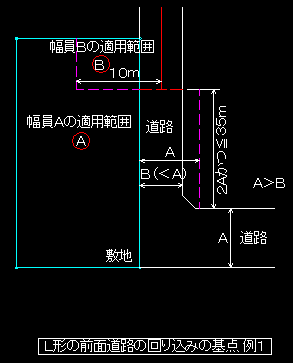 |
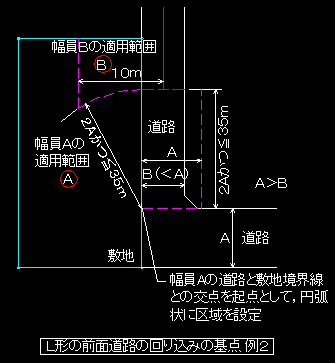 |
T字形の前面道路の場合
例1,2 (2008横浜市pdf/2009JCBAより)
| T字形の前面道路の場合 例1 (2008横浜市pdfより) | T字形の前面道路の場合 例2 (2009JCBAより) |
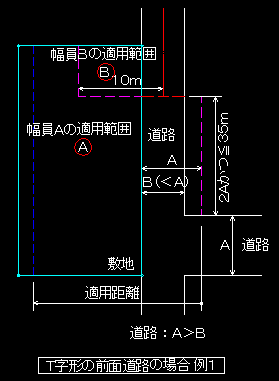 |
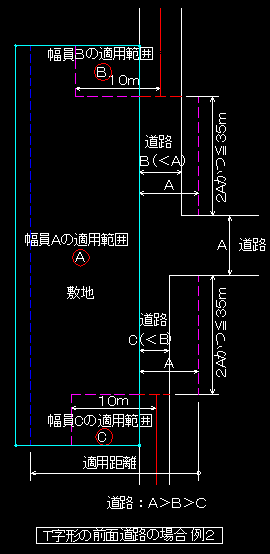 |
広い道路と狭い道路が斜めに接続している場合の取り扱い 例①,② (2002K
)
| 広い道路と狭い道路が斜めに接続している場合の取り扱い 例①,② | |
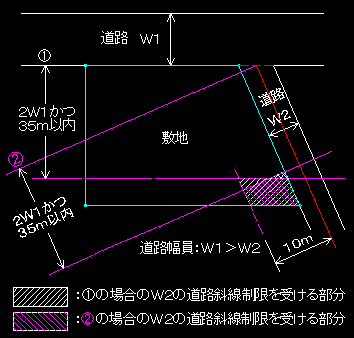 |
幅員の広い道路に狭い道路が斜めに接続されており,その狭い道路に沿っている敷地の場合,広い幅員の道路が回り込む基点と範囲をどこにするかは,従来から解釈が分かれるところだ。この場合,令132条の規定は「幅員の広い道路の2倍」,かつ「35m以内の区域」については広い道路による道路斜線制限の「影響範囲とする区域」とするとの趣旨と考えられるので,回り込める範囲は,広い幅員の道路の境界線からの垂直距離(①)をとるのが妥当であろう。 |
広い道路と狭い道路が斜めに接続している場合の取り扱い 例③~⑤ (2002K
)
別解釈
| 広い道路と狭い道路が斜めに接続している場合の取り扱い 例③ 別解釈 |
広い道路と狭い道路が斜めに接続している場合の取り扱い 例④ 別解釈 |
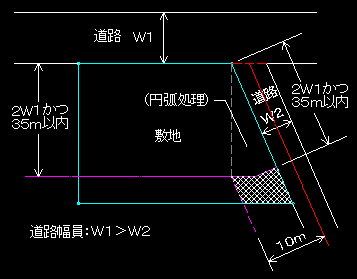 |
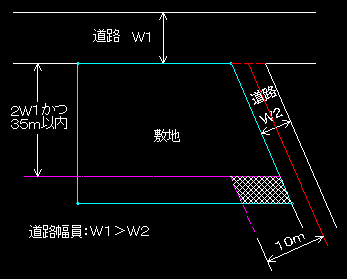 |
| 広い道路と狭い道路が斜めに接続している場合の取り扱い 例⑤ 別解釈 |
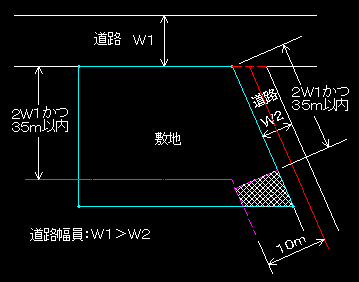 |
広い道路と狭い道路が斜めに接続(120°以下,120°越え)している場合の取り扱い (2008横浜市pdfより)
おさらい 一の道路の扱い
道路が交差し、又は折れ曲がる場合において、前面道路の中心線の敷地側から見た角度が120
度を超える場合にあっては、その道路は一の道路として取り扱う。
(令144条の4第一項第二号)
| 広い道路と狭い道路が斜めに接続(120°以下)している場合 | 広い道路と狭い道路が斜めに接続(120°超え)している場合 |
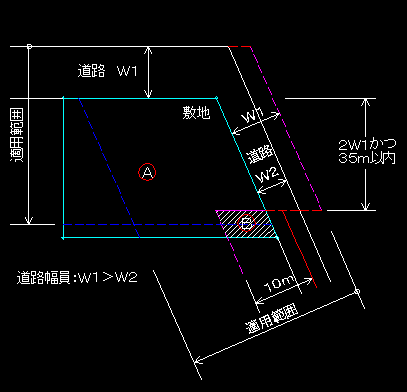 |
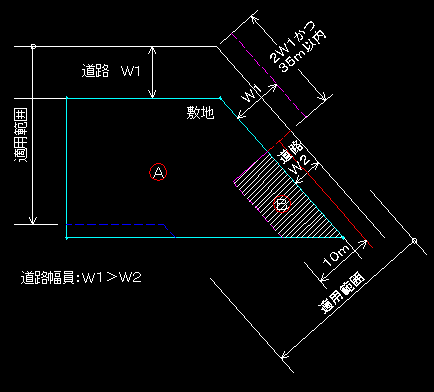 |
2つの道路の場合の取り扱い(挟まれた敷地 例1) (2008横浜市pdfより)
| 2つの道路の場合の取り扱い(挟まれた敷地例1) | |
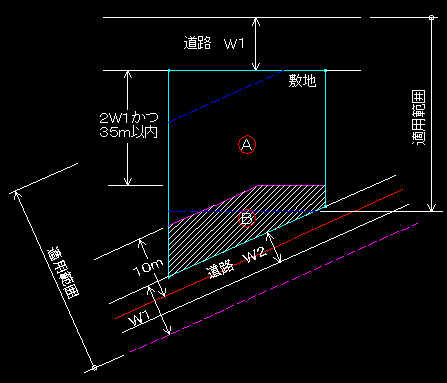 |
W1>W2の場合で,L≧2mならば,Aのエリアは,幅員W1の道路及び幅員W2の道路の幅員がW1あるものとみなした斜線制限を,Bのエリアは,幅員W2の道路斜線制限を受けるものとする。 後退距離の取り扱い 幅員W1及び幅員Wそれぞれの道路ごとに最小距離であるa及びbをを適用するものとする。 |
2つの道路の場合の取り扱い(挟まれた敷地例2) (2008横浜市pdfより)
| 2つの道路の場合の取り扱い(挟まれた敷地例2) |
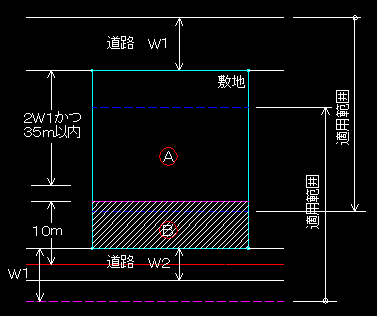 |
入り隅前面道路の場合 (横浜市pdf./大阪市/2009JCBAより) /
入り隅前面道路の後退距離の取扱い (横浜市pdf.より)
| 入り隅前面道路の場合 (横浜市pdf./大阪市 より) | 入り隅前面道路の後退距離の取扱い (横浜市pdf.より) |
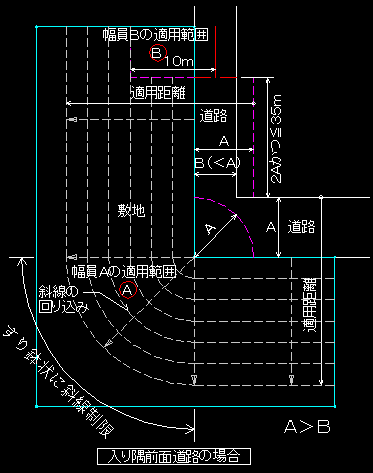 |
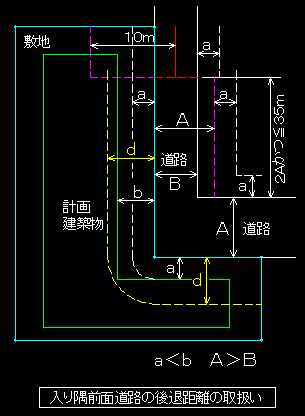 |
| 後退距離の取扱い あくまでも1本の道路であることから,後退距離としては,道路との最小幅(a)を一律に適用する。 |
|
| 例えば 幅員Aの道路に対するd離れた線上のhの制限は h = (A+d+a)×1.25(又は1.5) |
|
| 天空率算定における適合建築物の設定 入隅敷地においては,適合建築物は令第132条の規定による区域ごとに敷地を区域区分するが,あくまでも1本の道路であることから,後退距離としては,道路との最小幅(a)を適用して適合建築物を設定する。 |
行き止り道路の場合(両側敷地あり,なし) (横浜市pdf./2009JCBAより)
| 行き止り道路の道路斜線 行き止り道路の先端部に位置する敷地の斜線制限については図のように道路先端部において当該道路と同じ幅員(W)の道路が回転するものとみなして反対側の境界線を設定する。 |
|
| 行き止り道路の道路斜線(両側敷地あり) (横浜市pdf.より) | 行き止り道路の道路斜線(両側敷地なし) (2009JCBAより) |
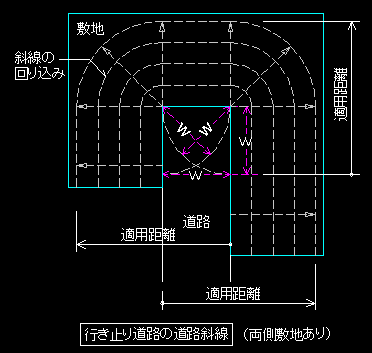 |
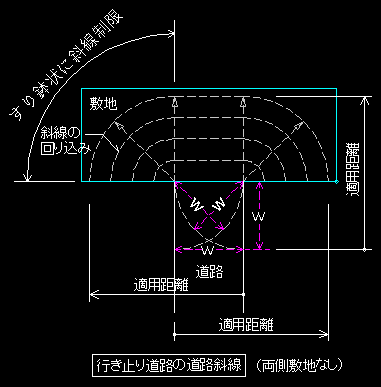 |
特殊な敷地等における後退距離(道路斜線制限)
行止まり道路(両側敷地あり,なし)及び入隅敷地の後退距離の取り扱い (横浜市pdf./2009JCBAより)
| 行止まり道路及び入隅敷地の後退距離の取り扱い | |
| 行き止り道路の道路斜線(両側敷地あり) (横浜市pdf./2009JCBAより) |
行き止り道路の道路斜線(両側敷地なし) (2009JCBAより) |
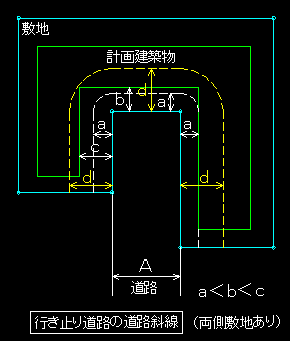 |
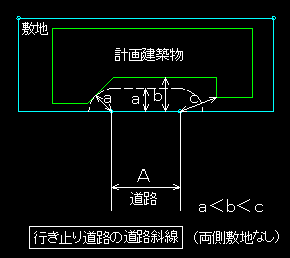 |
| 後退距離の取扱い あくまでも1本の道路であることから,後退距離としては,道路との最小幅(a)を一律に適用する。 |
|
| 例えば d離れた線上のhの制限は h = (A+d+a)×1.25(又は1.5) |
|
| 天空率算定における適合建築物の設定 入隅敷地においては,適合建築物は令第132条の規定による区域ごとに敷地を区域区分するが,あくまでも1本の道路であることから,後退距離としては,道路との最小幅(a)を適用して適合建築物を設定する。 |
|
幅員が極端に異なる前面道路の取り扱いとセットバックの緩和
敷地の前面で道路の幅員が極端に異なる場合,①幅員の広い道路および幅員の狭い道路を,一つの前面道路とみなし,令132条の緩和は適用しない,②幅員の広い道路と幅員の狭い道路を二つの前面道路とみなし,令132条の緩和を適用する,③道路の反対側の境界線が直線のほうの敷地は一つの前面道路に接するとみなして令132条の規定の緩和は適用せず,道路の反対側の境界線が屈曲しているほうの敷地については,二つの前面道路に接するとみなし,令132条の緩和を適用する,の三つの取扱いが考えられる。
これらの取扱いについては,道路管理者や,幅員が極端に異なる場合などによって解釈が異なるが,一般的には①の取扱いを適用している特定行政庁が多いと思われる。しかし本来,令132条は建築物が不合理なものとならないように措置されたものと考えられる。
したがって,一つの敷地内で極端な高さ制限の相違が生ずる取扱いは適当でないとの考えから③の取扱いをしている特定行政庁もある(下図)。また,セットバックの緩和距離は壁,バルコニーなどで前面道路ごとに最も近い部分で測定する。
前面道路幅員が極端に異なる場合の取り扱い (2002K)
| 前面道路幅員が極端に異なる場合の取り扱い | |
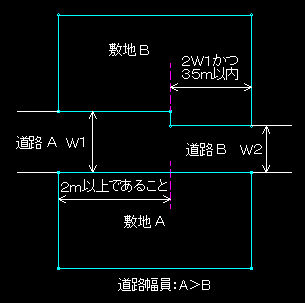 |
敷地 B 道路の反対側の境界線が直線の場合は,一つの前面道路に接するとみなし,回り込みの緩和は適用しない。 |
敷地 A 道路の反対側の境界線が屈曲している場合は,二つの前面道路に接するとみなし,回り込みの緩和は適用する。 一般的な広い前面道路としての幅員 : W1 一般的な狭い前面道路としての幅員 : W2 |
|
前面道路幅員が1つでその幅員が異なる場合の取扱い (2008横浜市pdfより)
| 前面道路幅員が1つでその幅員が異なる場合の取扱い 例 | |
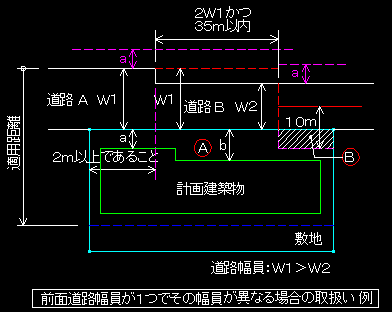 |
一般的な前面道路としての幅員 : W1 後退距離の取り扱い 一の道路なので,建築物の後退距離の最小距離はaとなり,aを一律に適用するものとする。 |
| 2以上の前面道路による緩和
例1,2 (2009JCBAより) 一般的な前面道路としての幅員 : a |
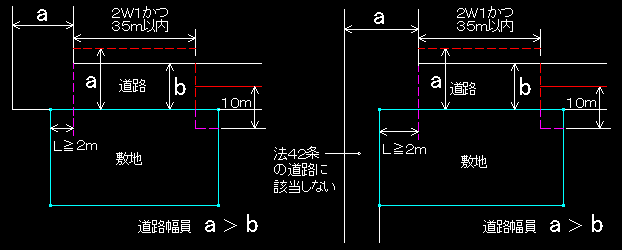 |
| 前面道路幅員がV字状の場合の取り扱い
例 (2008横浜市pdfより) 一般的な前面道路としての幅員 :W1 |
|
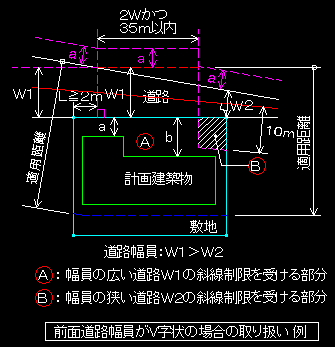 |
間題点と解釈 前面道路幅員がV字状の場合の取り扱い最大幅員の前面道路の幅員がV字状の場合,他の前面道路に回り込める幅員の数値はどの値を採用するかという問題である。この場合,法43条1項の規定から,接道部分の幅員の最大の位置から最低接道長さ2mの位置の数値(※)として扱っている特定行政庁(横浜市,JCBAなど)が多い。 L≧2mの場合,幅員W1の前面道路があるとして回り込みを認めるのが一般的である。 ※ 道路境界線からの垂直距離 後退距離の取り扱い 一の道路なので,建築物の後退距離の最小距離はaとなり,aを一律に適用するものとする。 前面道路の反対側の境界線は,その境界線に垂直にaの距離だけ外側にあるものとする。 |
※
参考).W1の距離の測り方についての別解釈
・ 道路中心線への垂直線上の距離
・ 反対側の道路境界線への垂直線上の距離
路地状敷地の道路斜線制限 例1 (横浜市pdf/2009JCBAより)
| 路地状敷地の道路斜線制限 例1 | |
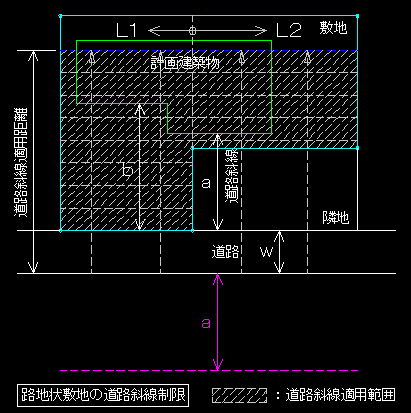 |
道路と敷地の間に他の敷地がある場合 L2の部分はL1の部分と同様に道路斜線制限を適用する。 【解説】L2の部分については,街区の形態を整えるため,また,形式的な敷地分割による脱法的行為を防ぐため,道路と敷地との間の空地が同一敷地である場合と同じ道路斜線制限を適用するのが妥当と考えられる。 後退距離の取り扱い 1つの道路なので,建築物の後退距離の最小距離はaとなり,aを一律に適用するものとする。 |
| 路地状敷地の道路斜線制限 例2 | |
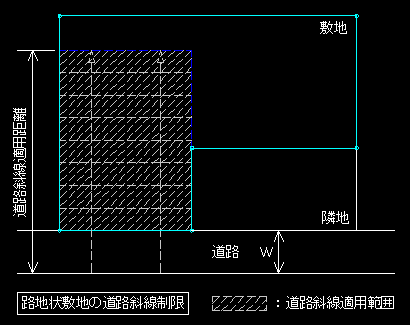 |
路地状敷地の道路斜線(東京都方式) 路地状敷地の道路斜線制限は前面道路に面する範囲で適用される。その他の部分は隣地斜線制限が適用される。 参考). 路地状敷地の天空率 道路斜線の円弧処理は入り角部分敷地における2方向の道路斜線を連続させることを目的とするものである。したがって,道路斜線を隣地斜線の適用部分に回りこませることは考慮しない。 |
敷地が隣地(宅地)を挟む場合の道路斜線の適用 (2008横浜市pdfより)
| 敷地が隣地(宅地)を挟む場合の道路斜線の適用 | |
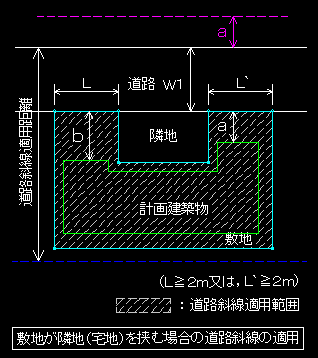 |
1つの道路に対して敷地が隣地(宅地)を挟む場合の道路斜線の適用について 敷地全体が,道路斜線制限を受ける。 |
■ do_010 前面道路の反対側に公園等がある場合
(法56条6項,令134条)
前面道路の反対側に公園等がある場合の取り扱い 例 (2008横浜市pdfより)
| 前面道路の反対側に公園がある場合の取り扱い 例 | |
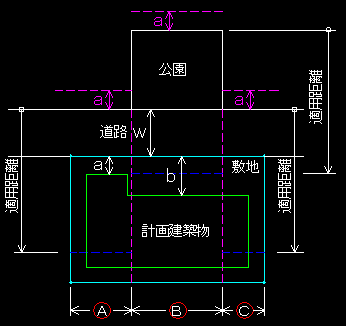 |
令134条を適用し,(領域Bが,公園緩和を受ける)令132条の規定は適用しないものとする。 後退距離の取り扱い 1つの道路なので,建築物の後退距離の最小距離はaとなり,aを一律に適用するものとする。 |
「公園」等による緩和(法56条6項,令134条)
間題点と解釈
a.「公園,水面等」による緩和道路斜線制限においては,前面道路の反対側に「公園,広場,水面,その他これらに類するもの」がある場合,前面道路の反対側の境界線は,これら公園等の反対側の境界線にあるものとみなす。また2以上の前面道路の反対側に公園等がある場合,さらに緩和される(法56条6項,令134条)。
また,隣地斜線制限においては,隣地が「公園,広場,水面その他これらに類するもの」がある場合,隣地境界線は,これら公園等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす(法56条6項,令135条の3第1項一号)。また,北側斜線制限においては,①北側の前面道路の反対側に水面等の空地がある場合,②北側で水面等の空地に接する場合,北側斜線の境界線は,水面等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす(法56条6項,令135条の4第1項一号)。ここでは水面等に,公園・広場は含まない。
一般的に法上の「公園」とは,都市公園法に規定されている「都市公園」を指し,将来の担保性が重要である。公園に類似するものとして「緑地」「広場」「緑道」「遊歩道」などがあるが,いずれも担保性が問題となる。なお,隣地斜線制限の公園については,都市公園法施行令2条1項一号の都市公園は除かれる(令135条の3第1項一号)。
b.公園等に面する場合の難しい取扱い
公園等に面する取扱いで難しいのが,前面道路の反対側の,一部が公園等となっている場合である。このような場合,公園等の部分に接する敷地の道路斜線制限は,令134条1項の規定により公園の反対側の境界線から適用されるのは論議の余地がない。問題は,公園に面していない敷地部分の道路斜線制限の扱いである。①道路の反対側の境界線から適用する,②令134条2項の規定により公園の反対側の境界線から適用する,の二つの解釈がある。
この場合,敷地の前面道路は一つに見えるが,実際は公園の部分が,面する道路と面しない道路はまったく条件が異なっており,令132条等の緩和の規定の設けられた趣旨にもとづいて,前面道路は,二つあると解釈し,その敷地の公園に面していない部分の道路斜線制限についても,令134条2項の規定により公園の反対側の境界線から適用するのが妥当であろう(図8)。
前面道路の反対側に一部に公園がある場合 (2008横浜市pdfより)
| 前面道路の反対側に一部に公園がある場合の取り扱い | |
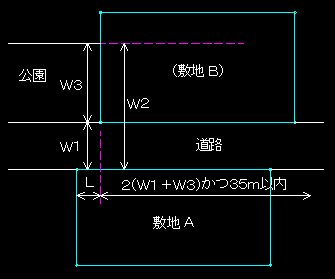 |
敷地Aについては,L≧2mの場合,公園を含めた幅員W2(=W1+W3)とW1の2以上の前面道路があるとみなすのが妥当であろう。 敷地Bについては,緩和はない。 |
水路等を隔てて道路がある場合の道路斜線の適用について(省略)
隣地斜線
● 法56条 【建築物の各部分の高さ】
法56条第1項第二号
二
当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあっては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあっては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあっては31mを加えたもの
関連 ⇒ 令第135条の3
「隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の
... 」
■
ri_001 隣地斜線の基本及びセットバックの場合
隣地斜線の基本及びセットバックの場合
| 隣地斜線の基本 | 20m又は30mを超える部分をセットバック させた場合の隣地斜線の緩和 |
20m又は30mを超える部分をセットバック させた場合の隣地斜線の緩和 庇等がある場合 (法56条第1項第二号) |
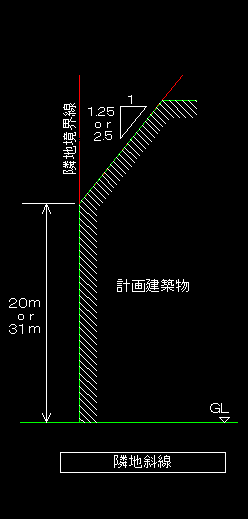 |
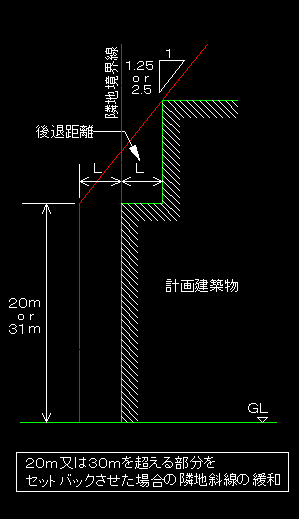 |
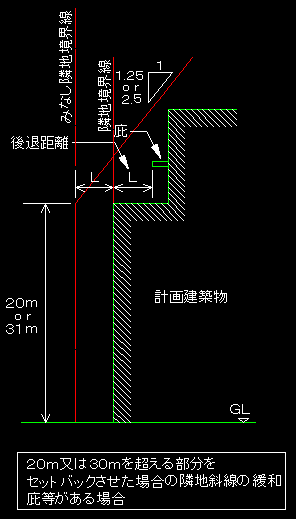 |
| ひさし等の後退距離の考え方 バルコニー,ひさし,出窓等があった場合はその先端から隣地境界線までの水平距離とする。 |
壁面のセットバック緩和の考え方 (2006H)
① 後退距離の算定は,建築物の高さ20m又は31mを超える部分における壁面と隣地境界線までの間の距離である。
② 適用に当たっては,建築物の高さ20m又は31mを超える建築物の部分から隣地境界線までの最小の水平距離で算出する。
| 最小の水平距離の考え方ケース1 | 最小の水平距離の考え方ケース2 |
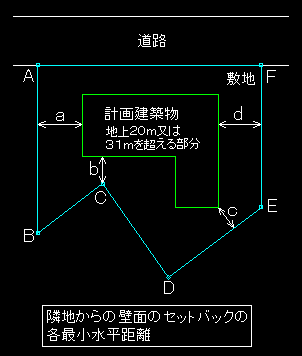 |
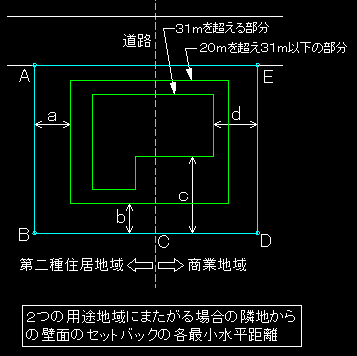 |
| 各最小の水平距離 辺AB:a/辺BC:b/辺CD:b/辺DE:c/辺EF:d |
各最小の水平距離 第二種住居地域内辺 AB:a/辺BC:b 商業地域内 辺CD:c/辺DE:d |
敷地が公園,広場等に接する場合(法56条6項,令135条の3第1項1号) (2006H)
敷地が公園(都市公園法施行令2条1項1号による都市公園(街区公園)を除く),広場,水面等に接する場合は,隣地境界線はこれら空地の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
| 水路等に面する場合の隣地斜線 | 水路等に面する場合の隣地斜線 20m又は30mを超える部分をセットバックさせた場合の緩和 |
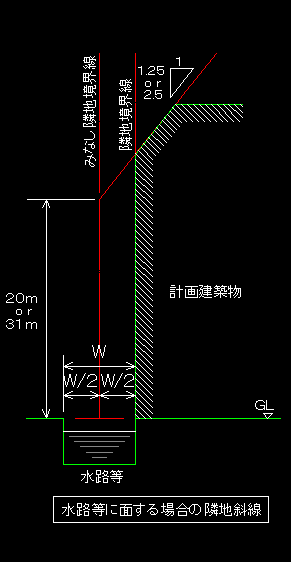 |
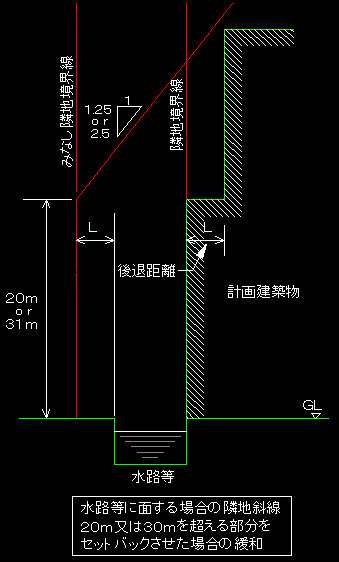 |
| ※ 水路,川若しくは海の他,公園,広場,その他これに類するものの場合も同様 | |
■ ri_002 敷地の地盤面が隣地と高低差がある場合
敷地の地盤面が隣地と高低差がある場合 (2006H)
|
敷地の地盤面が隣地の 地盤面より1m以上低い場合 |
敷地の地盤面が隣地の 地盤面より高い場合 |
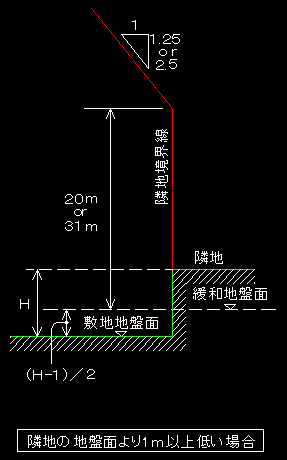
|
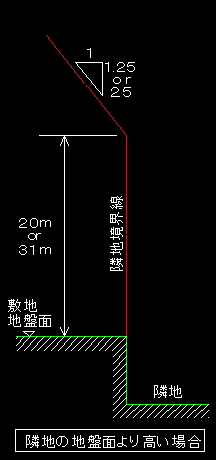
|
北側斜線
● 法56条 【建築物の各部分の高さ】
法56条第1項第三号
三 第1種低層住居専用地域若しくは第2種低層住居専用地域内又は第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(一),(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては,当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに,第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物にあっては5mを,第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあっては10mを加えたもの
■ ki_001 北側斜線の原則/緩和規定
北側斜線の原則 (2006H)
| 北側斜線の原則 水平距離 「L 」のとり方 :赤の矢印 | |
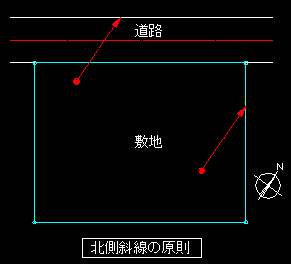 |
北側前面道路の反対側又は北側隣地境界線までの真北方向の水平距離をLとする。 なお,北側斜線制限についてはPH階の緩和なし。 |
参考).
法58条の高度地区の高度斜線(真北方向からの規制)の場合
北側が道路の場合,横浜市は道路中心線からの高度斜線となる。
一般的な緩和規定
①
敷地の北側に水面,線路敷等がある場合(法56条6項,令135条の4第1項一号) (2006H)
| 北側が水路等の場合の北側斜線 | 北側が道路+水路等の場合の北側斜線 |
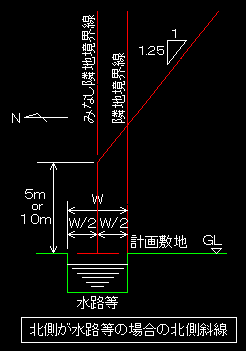 |
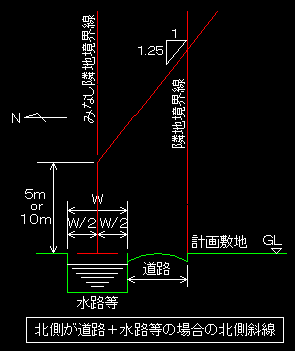 |
| ※ 水路,川若しくは海の他,公園,広場,その他これに類するものの場合も同様 | |
② 敷地の地盤面が北側隣地地盤面より1m以上低い場合(法56条6項,令135条の4第1項二号,2項) (2006H)
| 敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合 | |
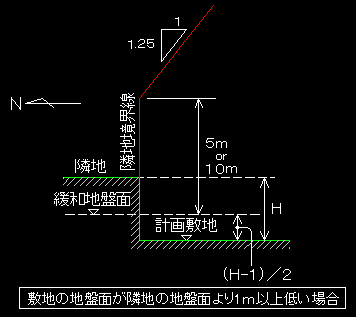 |
なお,北側隣地に建築物がない場合の北側隣地地盤面は平均地表面をいう。 |
|
※ 隣地の地盤面について 建築物がない場合の隣地の平均地表面のとり方 問題点 イ.敷地に相当する範囲のとり方 ロ.地盤のレベルの測定(他人の土地のため) ハ.将来ともその高さが担保されるのか 以上のような問題点があるため,実際の適用に当たっては,土地の造成等により現にその位置が確定している場合あるいはそれに近い状態でないと難しいと思われる。 |
|
■ ki_002 敷地が2以上の地域等にわたる場合
北側斜線制限
敷地が2以上の地域等にわたる場合(法56条5項) (1995K)
建築物の敷地が2以上の地域等にわたる場合,建築物の各部分の高さはその部分の属するそれぞれの地域等の制限を受ける(法56条5項)。
|
敷地が2以上の地域にわたる場合 低層住居専用地域が北側の例 |
敷地が2以上の地域にわたる場合 中高層住居専用地域が北側の例 |
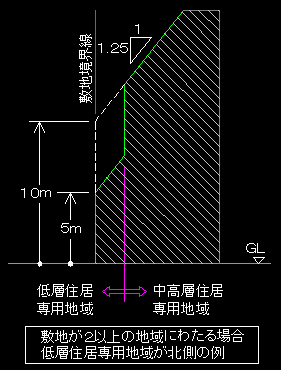 |
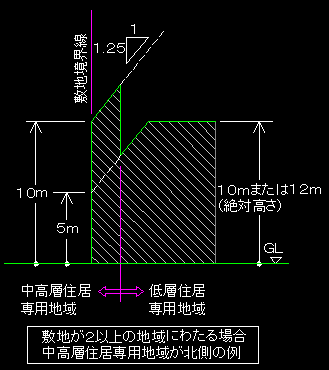 |
● 法58条 【高度地区】
法58条 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するも
のでなければならない。
注意).法第56条第7項の天空率制度との関連について
天空率制度は従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)となる法第56条に新たに第7項として設けられましたが,第7項第1項第一号(道路斜線),同項第二号(隣地斜線)及び同項第三号(北側斜線)が対象となります。法第58条の高度地区による斜線制限は対象になりません。同地区の計画建築物は高度地区規制に適合させなければなりません。
参考). 高度地区 横浜市,東京都
■ ko_001 高度地区の形態制限
高度地区の形態制限 (2007W)
例 :横浜市,東京都
高度斜線は真北方向からの規制です。(磁北ではありません)。北側の敷地境界からの規制ですが,北側に道路がある
場合は道路の反対側の境界からとなります。(横浜市だけは道路中心から)
高度斜線制限は法58条によるものであり,法56条の7の天空率計算によって緩和をうけることはできませんのでご注意下さい。
以下,横浜市 横浜国際港都建設計画高度地区 (平成23年10月14日
横浜市告示第506号)
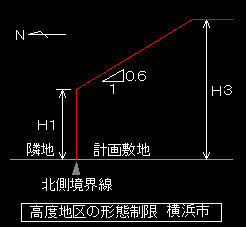
| 特定行政庁 | 高度地区種別 | H1 | H3 |
適用地域 |
備考 |
| 横浜市 | 第1種高度地区 | 5 | 10 | 第1種低層住居専用,第2種低層住居専用(150/60の地域を除く) | 北側が道路の場合,道路中心線からの高度斜線がかかります |
| 第2種高度地区 | 5 | 12 | 第1種低層住居専用,第2種低層住居専用(150/60の地域) | ||
| 第3種高度地区 | 7 | 15 | 第1種中高層住居専用,第2種中高層住居専用 | ||
| 第4種高度地区 | 7.5 | 20 | 第1種住居,第2種住居,準住居 | ||
| 第5種高度地区 | 10 | 20 | 近隣商業(200/80の地域) 準工業(200/60の地域) |
||
| 第6種高度地区 | -- | 20 | 近隣商業(300/80,400/80の地域) 商業地域(400/80の地域) |
||
| 第7種高度地区 | -- | 31 | 商業地域 準工業(200/60,400/60の地域) 工業地域(200/60の地域) |
・
敷地の北側に道路,水面,線路敷その他これらに類するもの(広場及び公園を除く)が接する場合は制限の緩和があります。
(取扱いの基準があります。)
・
高度地区には,他に最低限高度地区が指定されている地区もあります。
(最低限第1種は14m,最低限第2種は12m,最低限第3種は7mとする。)
・ 最低限第1種,最低限第2種高度地区の制限を受ける建築物については,最高限高度地区(第7種高度地区,高さ制限31m)の適用は除外されます。
・
最低限第3種高度地区の制限を受ける建築物については,最高限高度地区も同時に制限がかかります。
・
建築物の敷地が2以上の高度地区または高度地区の内外にわたる場合の北側斜線は,北側の敷地境界線が属する高度地区に関する制限によるものとします。
・ 工業地域内の最高限第5種高度地区の制限を受ける建築物で,住宅等の用途以外の建築物又は建築物の部分については,高さ31mまで建てることができます。
参考). 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917) より
横浜国際港都建設計画高度地区(抜粋) (平成23 年10 月14
日 横浜市告示第506 号)
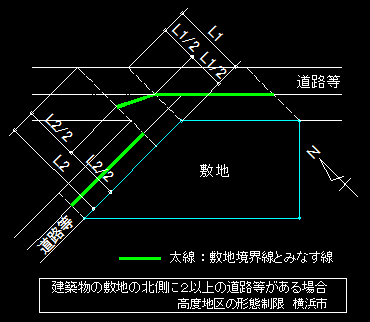 k_shasen_ko_01.gif |
建築物の敷地の北側に2以上の道路等がある場合 当該敷地の道路等に接する敷地境界線は、図のとおり、道路等の真北方向の幅の1/2 だけ外側にあるものとみなします。 |
| 建築物の敷地の北側にある道路等の終端部における場合 建築物の敷地の北側の敷地境界線に道路等の終端部が接する場合は, 当該敷地の道路等に接する敷地境界線は、図のとおり、道路等の真北方向の幅の1/2 だけ外側にあるものとみなします。 |
||
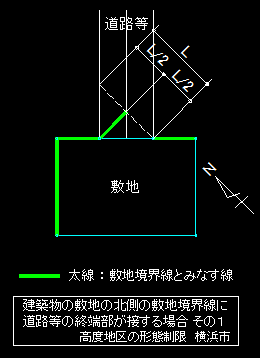 k_shasen_ko_02.gif |
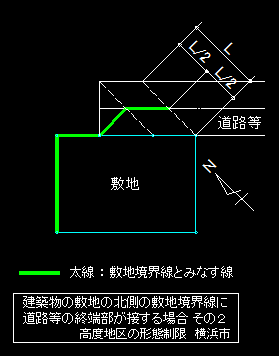 k_shasen_ko_03.gif |
|
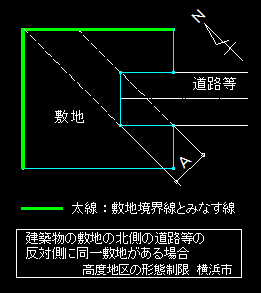 k_shasen_ko_04.gif |
建築物の敷地の北側の道路等の反対側に同一敷地がある場合 A区間の当該敷地の道路等に接する敷地境界線は、図のとおり、同一敷地の北側の敷地境界線にあるものとみなします。 |
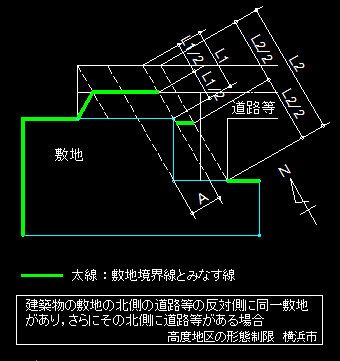 k_shasen_ko_05.gif |
建築物の敷地の北側の道路等の反対側に同一敷地があり,さらにその北側に道路等がある場合 A区間の当該敷地の道路等に接する敷地境界線は、図のとおり、同一敷地の北側の敷地境界線から、道路等の真北方向の幅の1/2 だけ外側にあるものとみなします。 |
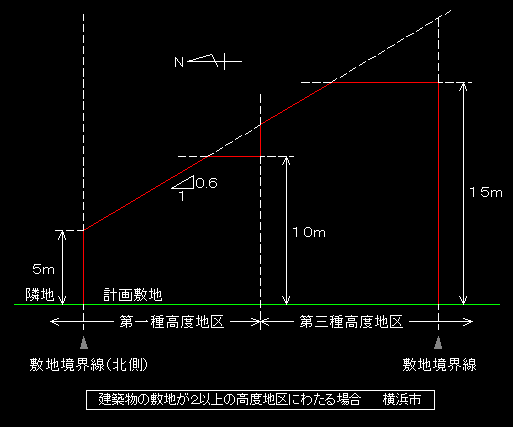 k_shasen_ko_06.gif |
高度地区の境界線がある場合の北側斜線 建築物の敷地が2以上の高度地区にわたる場合 北側斜線については、北側の敷地境界線が属する高度地区(第一種)に関する制限によるものとなります。建築物の最高高さについては、当該部分が属するそれぞれの高度地区(第一種,第三種)によるものとなります。 |
 k_shasen_ko_07.gif |
高度地区の境界線がある場合の北側斜線 建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合 北側斜線については、北側の敷地境界線が属する高度地区(第一種)に関する制限によるものとなります。建築物の最高高さについては、当該部分が属するそれぞれの高度地区(第一種,高度地区外)によるものとなります。 なお、高度地区外においても、市街化調整区域の許可基準等で高度地区を準用した高さ制限が適用されることがありますのでご注意ください。 |
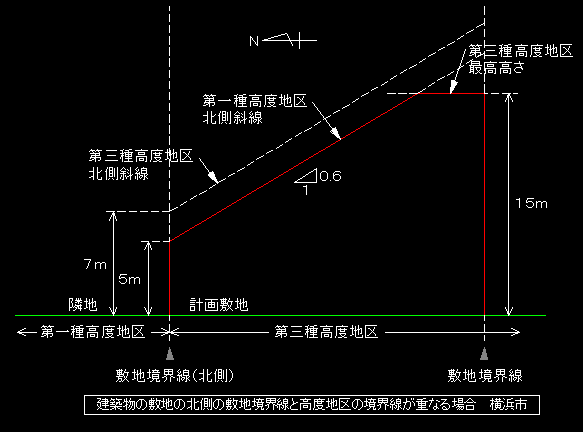 k_shasen_ko_08.gif |
建築物の敷地の北側の敷地境界線と高度地区の境界線が重なる場合 北側斜線については、両方の高度地区によるものとなるので、厳しい方の制限(第一種)が適用されることになります。建築物の最高高さについては、当該部分が属する高度地区(第三種)によるものとなります。 |
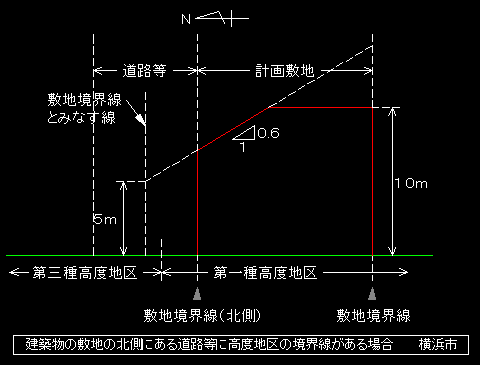 k_shasen_ko_09.gif |
建築物の敷地の北側にある道路等に高度地区の境界線がある場合 北側斜線については、北側の敷地境界線が属する高度地区(第一種)に関する制限によるものとなります。建築物の最高高さについては、当該部分が属する高度地区(第一種)によるものとなります。当該敷地の道路等に接する敷地境界線は、図のとおり、道路等の真北方向の幅の1/2 だけ外側にあるものとみなします。 ※制限の適用 道路が属する高度地区(第三種)ではなく,北側の境界線が属する高度地区(第一種)に関する制限が適用される。 第一種高度地区 5m+0.6/1 ≧10m |
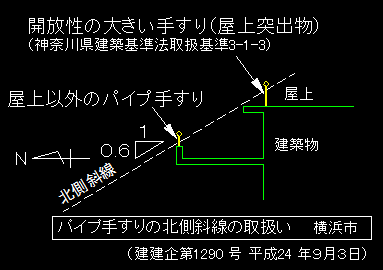 k_shasen_ko_10.gif |
パイプ手すりの北側斜線の取扱いについて 高度地区の制限において、屋上以外のバルコニー等の手すりが、パイプ、金網等の見透しのきく形状で、日照、通風の確保ができるものである場合にあっては、建築物の高さに算入しません。ただし、ガラス状のものやパンチングメタルは、日照・通風の観点から、建築物の高さに算入します。 なお、屋上のものについてはとなり、神奈川県建築基準法取扱基準3-1-3 により取り扱います。 |
以下,東京都
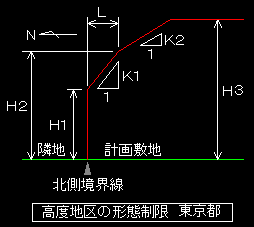
| 特定行政庁 | 高度地区種別 | H1 | K1 | L | H2 | K2 | H3 | 適用地域 | 備考 |
| 東京都 | 第1種高度地区 | 5 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | 都市計画による | |
| 25m第1種高度地区 | 5 | 0.6 | -- | -- | -- | 25 | |||
| 30m第1種高度地区 | 5 | 0.6 | -- | -- | -- | 30 | |||
| 31m第1種高度地区 | 5 | 0.6 | -- | -- | -- | 31 | |||
| 第2種高度地区 | 5 | 1.25 | 8 | 15 | 0.6 | -- | |||
| 10m第2種高度地区 | 5 | 1.25 | 8 | 15 | 0.6 | 10 | |||
| 12m第2種高度地区 | 5 | 1.25 | -- | -- | -- | 12 | |||
| 16m第2種高度地区 | 5 | 1.25 | 8 | 15 | 0.6 | 16 | |||
| 25m第2種高度地区 | 5 | 1.25 | 8 | 15 | 0.6 | 25 | |||
| 31m第2種高度地区 | 5 | 1.25 | 8 | 15 | 0.6 | 31 | |||
| 45m第2種高度地区 | 5 | 1.25 | 8 | 15 | 0.6 | 45 | |||
| 第3種高度地区 | 10 | 1.25 | 8 | 20 | 0.6 | -- | |||
| 12m第3種高度地区 | 10 | 1.25 | -- | -- | -- | 12 | |||
| 17m第3種高度地区 | 10 | 1.25 | -- | -- | -- | 17 | |||
| 20m第3種高度地区 | 10 | 1.25 | 8 | 20 | 0.6 | 20 | |||
| 22m第3種高度地区 | 10 | 1.25 | 8 | 20 | 0.6 | 22 | |||
| 25m第3種高度地区 | 10 | 1.25 | 8 | 20 | 0.6 | 25 | |||
| 35m第3種高度地区 | 10 | 1.25 | 8 | 20 | 0.6 | 35 | |||
| 45m第3種高度地区 | 10 | 1.25 | 8 | 20 | 0.6 | 45 | |||
| 31m高度地区 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 |