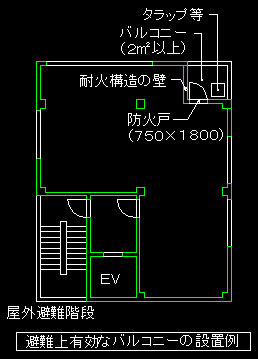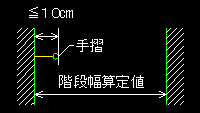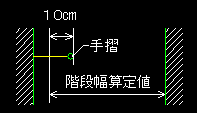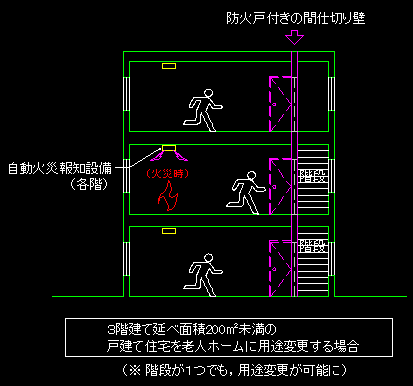�u���z��@�y�ъ֘A�@����v
�S�y�[�W
��
���R�p�Y�s�s���z�v������ - HOME��
�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�K�i
�u �� ��
�v
�� 001�@�K�i���ւ̏d�������̊ɘa
�@�@�@�@�@�@
�i�P�j����L���ȃo���R�j�[�̊
�i2006H�j
�@�@�@�@�@�@
�i�Q�j���O�ʘH�̊ �i2006H�j
�� 002�@�K�i�̕��̎Z��
�i����j
�� 002-2�@�K�i�ɌW��K���̍�����
�u�߂Q�R�������v�@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
�� 002-3�@2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����K�͌��z���͈̔͂̍�����
�u�ߑ�121�������v�@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
�� 003�@���O�ɐ݂��钼�ʊK�i��ؑ��Ƃ���ꍇ�̖h���[�u�̖��m���@�i2023W�j
�@�@�@�@�@�@2022�N�i�ߘa4�j
�� 001�@
�K�i���ւ̏d�������̊ɘa �i����L���ȃo���R�j�[�C���O�ʘH���ɂ��āj
�i2006H�j
��121���3���̊ɘa�K��
��121���3��
�E�E�E�E�E�E�������C�����̊e��������C���Y�d����Ԃ��o�R���Ȃ��ŁC����L���ȃo���R�j�[�C���O�ʘH���̑������ɗނ�����̂ɔ��邱�Ƃ��ł���ꍇ�́C���̌���łȂ��B
���̏ꍇ�C�K�肷����s�����̐��l��1/2���Ă��ǂ��B
����L���ȃo���R�j�[�C���O�ʘH���ɂ���
�i2006H�j
�\���ɂ��Ă͏�̖��L������Ă��Ȃ��B���f�̖ڈ��Ƃ��Ď��̍\���̃o���R�j�[�C���O�ʘH�������L���ȣ��Ƃ��Ĉ�ʓI�ƂȂ��Ă��邪�C�s�����ɂ���Ă͕~�n���̒ʘH��������������Ă���Ƃ��������̂Œ��ӂ̂��ƁB�Ȃ��C���Ă̂�����̂��镔���ɂ��ݒu�͉\�ł���
�i�P�j����L���ȃo���R�j�[�̊ �i2006H�j
�@
�o���R�j�[�̈ʒu�́C���ʊK�i�̈ʒu�Ƃ����ނˑΏ̂̈ʒu�Ƃ��C���C���̊K�̊e�����Ɨe�ՂɘA��������̂Ƃ��邱�ƁB
�A �o���R�j�[�́C���̂P�ȏ�̑��ʂ����H�����͕����V�Tcm�ȏ�̕~�n���̒ʘH�ɖʂ��C���C���S�ɔ��ł���ݔ��i���^���b�v���̐ݒu�j��L���邱�ơ
�B
�o���R�j�[�̖ʐς́C�Q�u�ȏ�i���Y�o���R�j�[������S�ɔ���ݔ��̕����������j�Ƃ��C���s���̐��@�͂V�Tcm�ȏ�Ƃ���B
�C
�o���R�j�[�i�����Z��̏Z�˓��Ő�p������̂������j�̊e��������Qm�ȓ��ɂ��铖�Y���z���̊O�ǂ͑ω\���i���ωΌ��z���ɂ����Ă͏��ω\���r�Ƃ��C���̕����ɊJ����������ꍇ�͓���h�ΐݔ��܂��͖h�ΐݔ��i���ʎՉ��Q�O���j��݂��邱�ơ
�D ��������o���R�j�[�ɒʂ���o�����̌˂̕��͂V�Tcm�ȏ�C�����͂Pm�W�Ocm�ȏ�C
���[�̏��ʂ���̍����͂P�Tcm�ȉ��Ƃ���
�E �o���R�j�[�͈�\���O�C�ɊJ������Ă��邱�ơ
�F
�o���R�j�[�̏��͑ω\���C���ω\�����̑������Ɠ����ȏ�̑ωΐ��\��L������̂Ƃ��C���C�\���ϗ͏���S�Ȃ��̂Ƃ��邱�ƁB
����L���ȃo���R�j�[�̐ݒu��
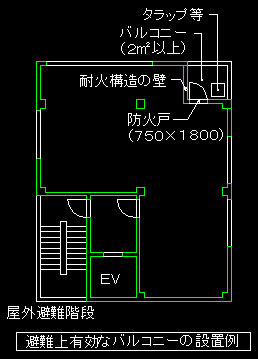
�i�Q�j���O�ʘH�̊ �i2006H�j
�@
���Y�K�̊O�ǖʂɉ����Đ݂����C���C���ʊK�i�̈ʒu�Ƃ����ނˑΏ̂̈ʒu�ʼn����ƘA��������̂ł��邱�ơ
�A ���Y�K�̊e�����Ɨe�ՂɘA��������̂ł��邱�ƁB
�B ���U�Ocm�ȏ�ŁC�肷�肻�̑����S�ɒʍs�ł��邽�߂̑[�u���u�������̂ł��邱�ƁB
�C
�ʘH�̈�[�́C���ʊK�i�ɘA�����C���[�̓^���b�v���̑��̔���L���Ȏ�i�ɂ����S�ȏꏊ�ɒʂ�����̂ł��邱�ơ�������C���ʊK�i�ɘA�����邱�Ƃ�����ł�ނȂ��ꍇ�ɂ����ẮC���[�ɔ���L���Ȏ�i��݂������̂ł��邱�ƁB
�D
���������Ƃ̋�ԁC�o�����̌ˋy�э\���ɂ��ẮC�o���R�j�[�ɂ�����ꍇ�Ɠ��l�̂��̂ł��邱�ơ�������C�o�����̌˂̕��͂U�Ocm�ȏ�Ƃ��C�����̑��̊J�����͔���x��̂Ȃ��ʒu�ɐ݂��邱�ƁB
��120���2���̊ɘa�K��
2�@
��v�\���������ω\���ł��邩���͕s�R�ޗ��ő����Ă��錚�z���̋����ŁC���Y�����y�т��ꂩ��n��ɒʂ���傽��L���C�K�i���̑��̒ʘH�����i���ʂ���̍�����1.2m�ȉ��̕����������B�j�y���V���i�V��̂Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮC�����j�̎����ɖʂ��镔���i��艏�C���䂻�̑������ɗނ��镔���������B�j�̎d�グ�����s�R�ޗ��ł������̂ɂ��ẮC�O���̕\�̐��l��10�����������l���̕\�̐��l�Ƃ���B�������C15�K�ȏ�̊K�̋����ɂ��ẮC���̌���łȂ��B
�� 002�@�K�i�̕��̎Z��
�i����j
�K�i���C�萠�@�i�@�R�U���C�߂Q�R���R���C�߂Q�T���j
�߂Q�R���R��
�R�@ �K�i�y�т��̗x����肷���y�ъK�i�̏��~�����S�ɍs�����߂̐ݔ��ł��̍������T�O�p�ȉ��̂��́i�ȉ��̍��ɂ����āu�肷�蓙�v�Ƃ����B�j���݂���ꂽ�ꍇ�ɂ������1���̊K�i�y�т��̗x��̕��́C�肷�蓙�̕����P�O�p�����x�Ƃ��āC�Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ��ĎZ�肷���B
�߂Q�T���Q��
�Q�@ �K�i�y�т��̗x��������i�肷�肪�݂���ꂽ���������B�j�ɂ́A���ǖ��͂���ɑ��������݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����
����̉���Ŏ肷��y�ъK�i�̏��~�����S�ɍs�����߂̐ݔ����݂���ꂽ�ꍇ�C�߂Q�R���R���ɂ���K�i���̎Z�����ł���悤�ɂȂ����B���C�肷��̐ݒu�ɂ��ď]���͊K�i��x��̗����ɑ��Ǔ�������Ύ肷��͐ݒu���Ȃ��Ă悩�������C����̉����ŏ��Ȃ��Ƃ��Б��ɂ͎肷���݂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�C�߂Q�T���Q���ł͗����ɑ��Ǔ���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B
�K�i�̕��̎Z��
�i����
�߂Q�R���R���j
| �肷��̓ˏo�����P�O�p�ȉ��̏ꍇ |
�肷��̓ˏo�����P�O�p����ꍇ |
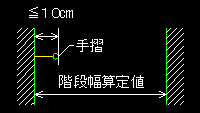 |
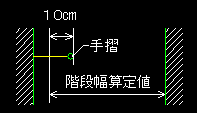 |
�� 002-2�@�K�i�ɌW��K���̍�����
�u�߂Q�R�������v�@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
�����@
�K�i�ɌW��K���̍�����
���z �F�����Q�U�N�U���S���@ �{�s�� �F��N�ȓ��̗\��@���@�����Q�U�N�V���P���������i�����E�B���h�E�ňړ��j���{�s����Ă��܂��B
�����y��ʏȍ����掵�S�㍆
�ȉ��C���y��ʏ�PDF���
�� �w�i
�ߔN�A�l���̌������ɂ��A�g�p����Ă��Ȃ������̌��z�������C���āA���̗p�r�Ɋ��p����Љ�j�[�Y�����܂���
���邪�A���z��ɓK������悤�K�i���������C���邽�߂Ɍ��z���̑��̕����ɋy�ԑ�K�͂ȉ��C���K�v�ɂȂ��
��������A�������z�X�g�b�N�̊��p������ƂȂ��Ă���B
�y��̗��z
���q���̐i�W�ɂ��w�Z���p���ɂ��A�����w�Z�Z�ɂ�������т̍Z�ɂƂ��Ċ��p�B
�y�Q�l�z�\�����v���ʋ��̑�21����Ăɑ��鐭�{�̑Ή����j�i����24�N8��21���\�����v���ʋ�搄�i�{�����\�j
�s���w�Z�ɂ����鎙���p�K�i�̊�̍������t
���w�Z�ɂ����鎙���p�K�i�̊�̍������ɂ��āC�K�v�Ȉ��S���m�ە������Ɋւ��Č������C���_��ƂƂ��ɁA���_����A���₩�ɑ[�u���u����B
��
���s�ƍ������̓��e
�܂����A���݊O���₷��Ⴂ���̂Ԃ���ɂ��l�̓]�|�E�]����h���A���~����
���S���m�ۂ��邽�߁A�K�i�̎�ʓ��ɉ����āA�K�i�y�т��̗x���̕����тɊK�i��
�������y�ѓ��ʂ̐��@���K��B�y���z��@�{�s�ߑ�23���1���z
��
���p�҂����S�ɏ��~�ł�����̂Ƃ��č��y��ʑ�b����߂��\�����@��
�p����K�i�ɂ��ẮA�K�i�̐��@�ɌW��K�蓙��K�p���Ȃ����ƂƂ���B
�i���y��ʑ�b����߂��\�����@�̊T�v�j
| �K�i�̎�� |
�K�i�y��
��
�̗x��̕� |
�������̐��@ |
���ʂ̐��@ |
| ���s |
�� |
�������� |
| �i1�j���w�Z�ɂ����鎙���p�̂��� |
140cm�ȏ� |
16cm�ȉ� |
�@�����Ɏ肷���݂��A�K�i�̓��ʂ̕\�ʂ�e�ʂƂ��A���͊���ɂ���
�ޗ��Ŏd�グ���ꍇ�A
18cm�ȉ� |
26cm�ȏ� |
�ȉ��C�����Q�U�N�V���P�����������{�s����Ă��܂��B
�i�����j
�� ���y��ʏȍ����掵�S�㍆
���z��@�{�s�߁i���a��\�ܔN���ߑ�O�S�O�\�����j���\�O���l���̋K��Ɋ�Â��A�����ꍀ�̋K��ɓK������K�i�Ɠ����ȏ�ɏ��~�����S�ɍs�����Ƃ��ł���K�i�̍\�����@�����̂悤�ɒ�߂�B
������\�Z�N�Z����\����
���y��ʑ�b���c���G
���z��@�{�s�ߑ��\�O���ꍀ�̋K��ɓK������K�i�Ɠ����ȏ�ɏ��~�����S�ɍs�����Ƃ��ł���K�i�̍\�����@���߂錏
���@���z��@�{�s���i���ɂ����āu�߁v�Ƃ����B�j���\�O���l���ɋK�肷�铯���ꍀ�̋K��ɓK������K�i�Ɠ����ȏ�ɏ��~�����S�ɂł���K�i�̍\�����@���A���w�Z�ɂ����鎙���p�̊K�i�ł������A���̊e���Ɍf�����ɓK��������̂Ƃ����B
��@�K�i�y�т��̗x��̕����тɊK�i���������y�ѓ��ʂ̐��@���A���ꂼ��A�S�l�\�Z���`���[�g���ȏ�A�\���Z���`���[�g���ȉ��y�ѓ�\�Z�Z���`���[�g���ȏ�ł��邱�ƁB
��@�K�i���������A�肷���݂������̂ł��邱�ƁB
�O�@�K�i�����ʂ̕\�ʂ��A�e�ʂƂ��A���͊���ɂ����ޗ��Ŏd�グ�����̂ł��邱���B
���@�ߑ��\�O���̋K��͑���ꍆ�̓��ʂ̐��@�ɂ��āA�����O���̋K��͓����̊K�i�y�т��̗x��̕��ɂ��ď��p����B
����
���̍����́A������\�Z�N�����������{�s����B
�� 002-3�@2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����K�͌��z���͈̔͂̍�����
�u�ߑ�121�������v�@�i�u���y��ʏ�.htm�v��蔲���j
�ߘa2�N�S���P���{�s�̉������z��@�{�s��
2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����K�͌��z���͈̔͂̍�����
�ߑ�121���́u2�ȏ�̒��ʊK�i��݂���ꍇ�v�̐ݒu�
1�D�]������̐ݒu�
�y2�ȏ�̒��ʊK�i��݂���ꍇ�z
�ߑ�121���@���z���̔��K�ȊO�̊K�����̊e���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ɂ����ẮC���̊K������K���͒n��ɒʂ���2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�c�c�i�ȗ��j�c�c
�l�@�a�@�Ⴕ���͐f�Ï��̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ�����a���̏��ʐς̍��v���͎��������{�ݓ��̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ����鎙�������{�ݓ��̎傽��p�r�ɋ����鋏���̏��ʐς̍��v���C���ꂼ��50�u�������
�܁@�z�e���C���َႵ���͉��h�̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ�����h�����̏��ʐς̍��v�C�����Z��̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ����鋏���̏��ʐς̍��v���͊�h�ɂ̗p�r�ɋ�����K�ł��̊K�ɂ�����Q���̏��ʐς̍��v���C���ꂼ��100�u�������
�c�c�i�ȗ��j�c�c
2�@��v�\���������ω\���ł��邩�C���͕s�R�ޗ��ő����Ă��錚�z���ɂ��đO���̋K���K�p����ꍇ�ɂ́C�������u50�u�v�Ƃ���̂́u100�u�v�ƁC�u100�u�v�Ƃ���̂́u200�u�v�ƁC�u200�u�v�Ƃ���̂́u400�u�v�Ƃ���B
����j�D
�ߑ�121���P����l���C��2���ɂ��C�a�@�⎙�������{�ݓ��ɂ��ẮC��v�\���������ω\���ȏ�̐��\�Ƃ����ꍇ�ł��C���̊K�̕a���⋏���̏��ʐς̍��v��100�u�����2�ȏ�̒��ʊK�i��݂��Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��C�ߑ�121���2����K�p���Ȃ��ꍇ�C��P����܍��ɂ��C�z�e���⋤���Z��ɂ��ẮC���̊K�̏A�Q���̏��ʐς̍��v��100�u�����2�ȏ�̒��ʊK�i��݂���K�v������܂��B
2�D�V�݂��ꂽ�ݒu��̍�����
�ߑ�121���ɑ�S�����lj�����܂����B
4�@��P���i��l���y�ё�܍��i��2���̋K�肪�K�p�����ꍇ�ɂ����ẮC��l���j�ɌW�镔���Ɍ���B�j�̋K��́C�K����3�ȉ��ʼn��זʐς�200�u�����̌��z���̔��K�ȊO�̊K�i�ȉ����̍��ɂ����āu����K�v�Ƃ����B�j�i�K�i�̕����i���Y��������̂ݐl���o���肷�邱�Ƃ̂ł���֏��C���O�d�b�����̑������ɗނ�����̂��܂ށB�j�Ɠ��Y�K�i�̕����ȊO�̕����i���ڊO�C�ɊJ������Ă���L���C�o���R�j�[���̑������ɗނ��镔���������B�j�Ƃ��Ԏd�ؕǎႵ�������̊e���Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂�h�ΐݔ��ő�112���19����ɋK�肷��\���ł�����̂ŋ�悳��Ă��錚�z�����͓����15���̍��y��ʑ�b����߂錚�z���̓���K�Ɍ���B�j�ɂ��ẮC�K�p���Ȃ��B
���@����K���P����l���ɋK�肷��p�r�i���������{�ݓ��ɂ��Ă͓�������҂̐Q����������̂Ɍ���B�j�ɋ�����ꍇ
�@��2���㍆�̓ɋK�肷���h�ΐݔ��i���Y����K�����錚�z���̋����C�q�ɂ��̑������ɗނ��镔���ɃX�v�����N���[�ݔ����̑�����ɗނ�����̂�݂����ꍇ�ɂ����ẮC10���Ԗh�ΐݔ��j
���@����K�����������{�ݓ��i��������҂̐Q����������̂������B�j�̗p�r���͑�P����܍��ɋK�肷��p�r�ɋ�����ꍇ
�@���i�ӂ��܁C��q���̑������ɗނ�����̂������B�j
����j�D
�ߑ�121���S�����V�݂��ꂽ���Ƃ��C�a�@�⎙�������{�ݓ��C�z�e���⋤���Z��̂����C�K����3�ȉ��ʼn��זʐς�200�u�����̏��K�͂Ȍ��z���ɂ����C���ʊK�i�̕����Ƃ���ȊO�̕����Ƃ��C����K�i���K�ȊO�̊K�j�̗p�r�ɉ����C�Ԏd�ؕǖ��͖h�ΐݔ��i�@��2���㍆�̓��C���ɋK�肷��h�ΐݔ�����j�ɂ���悵���ꍇ���C2�ȏ�̒��ʊK�i�̐ݒu���K�v�Ȃ��Ȃ�܂����B
����K��a�@�⎙�������{�ݓ��i�Q����������́j�ɂ����ꍇ�ɗp����@��Q���㍆�̓ɋK�肷���h�ΐݔ��ɂ��ẮC�X�v�����N���[�ݔ���݂����10���Ԗh�ΐݔ��i�ߑ�112���12���Œ�`�j�ł悢���ƂɂȂ�܂��B
����K�����������{�ݓ��i�Q����������̈ȊO�j�C�z�e���⋤���Z��ɂ����ꍇ�ɗp�������ɂ��ẮC�Ў��̐ډ��ɂ���Ē����ɉΉ����ђʂ��邨����̂���ӂ��܁C��q�C���ʔK���X�C�����Rmm���x�̍����ő���ꂽ���̓��͏�����Ă��܂��B
�Ȃ��C�@��Q���㍆�̓ɋK�肷���h�ΐݔ��C10���Ԗh�ΐݔ��C���Ƃ��ߑ�112���12���E��13���̋K��ɂ�����K�͕a�@���E���K�͏A�Q���̏��G�����ɗp������h�ΐݔ��Ɠ��l�C�ߑ�112���19����ɋK�肷��Չ����\��L���铙�̍\���̂��̂Ɍ����܂��B
�ȉ��C�ߑ��ł��B�i�O�q�Ə����d�����܂��B�j
�����̔w�i
�E
�����{�݁i�V�l�z�[���C�f�C�T�[�r�X�Ȃǁj��f�Ï����́C���ʐς�50�u���̊K�i2�K�ȏ�j�̏ꍇ�C2�ȏ�̊K�i��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�E �ˌ��ďZ��̋Ɓi�ʏ�C�K�i��1�j�������̗p�r�ɕύX���Ċ��p���悤�Ƃ���ꍇ�C�{�K�����x��ƂȂ��Ă���B
�������e
�K�i���������u�h�Ό˕t���̊Ԏd��ǁv��݂����ꍇ�ɂ́C���S�����m�ۂ���Ă��邱�Ƃ���C�K�i��1�Ƃ��邱�Ƃ��\�Ƃ���i3�K���Ĉȉ����ؖʐ�200�u�����̌��z���j
�����O
3�K���Ĉȉ����זʐ�200�s�����̌ˌ��ďZ���V�l�z�[���ɗp�r�ύX����ꍇ
�����{�݂ւ̗p�r�ύX�̏ꍇ�C�K�i��2�K�v�ƂȂ�
�� �K�i��1�����Ȃ����߁C�p�r�ύX������
������
3�K���Ĉȉ����זʐ�200�u�����̌ˌ��ďZ���V�l�z�[���ɗp�r�ύX����ꍇ
�K�i�Ƃ̊Ԏd��ǂƂ��āu�h�Ό˕t���̊Ԏd����v��݂����ꍇ�C�K�i��1�Ƃ��邱�Ƃ��\�Ƃ���
�� �K�i��1�ł��C�p�r�ύX���\��
���̏ꍇ�C�e�K�ɂ͎����Ќx��ݔ����K�v�ƂȂ�B
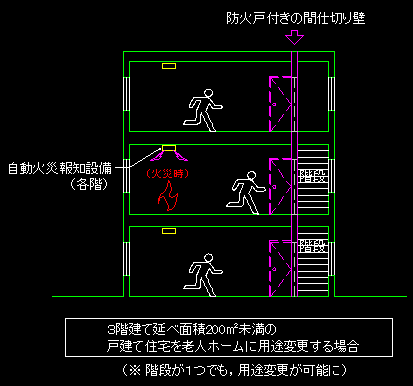
�� 003�@���O�ɐ݂��钼�ʊK�i��ؑ��Ƃ���ꍇ�̖h���[�u�̖��m���@�i2023W�j
2022�N�i�ߘa4�j
�ߘa3�N4���ɔ����q�s���ŋ����Z��̖ؑ����O�K�i���������C�l���S���Ȃ鎖�̂������������Ƃ��āC���z��@�ɂ�����u�ؑ��̉��O�K�i�v�̎戵�������i������Ă��܂��B
�i�Q�l �F��ʓI���C�ؑ�2�K���Ă̌ˌ��Z��i����̉����ȗߑΏۊO�j�ł���J���炵�ƂȂ鉮�O�K�i��ؑ��ɂ���̂͋H�ŁC�h������S��w�ǂ��S���ȏ�ł��傤�B�j
���O�K�i�C���ɂ����̂����炢
�i���O�K�i�̍\���j
�ߑ�121����2
�O2���̋K��ɂ�钼�ʊK�i�ʼn��O�ɐ݂�����̂��C�ؑ��i���ω\���̂����L���Ȗh���[�u���u�������̂������B�j�Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�u�O2���v�Ƃ��ߑ�120���y����121���ŁC���ꂼ��u���ʊK�i�v�Ɓu2�ȏ�̒��ʊK�i�v�Ƃ����C���W�K��̖@���ł��B
�ߑ�121����2�͑S�Ă̌��z���ɂ�����K���ł͂���܂���B���ʊK�i���s�v�Ȍ��z���͉��O�K�i��ؑ��ɂ��鎖���\�ł��B
���ʊK�i�́C�@��35���ɒ�߂��Ă��܂��B���K���������錚�z�������ʊK�i���K�v�ł��B�@����C�ȉ��ȊO�̌��z���͉��O�K�i��ؑ��ɂ��Ă��ǂ����ƂɂȂ��Ă��܂��B
���@��35���̋K���������錚�z��
�E �ʕ\��1(��)��(1������(4)���܂łɌf����p�r�ɋ�������ꌚ�z��
�E �K����3�ȏ�ł��錚�z��
�E ���߂Œ�߂鑋���̑��̊J������L���Ȃ�������L���錚�z���i���������j
�E ���זʐς�1,000�u�������錚�z��
120���C121���̋K��̓K�p�ɂ��ẮC�ȉ��ߑ�117���ɋL������Ă��܂��B
�y�K�p�͈̔��z
�ߑ�117���@���̐߂̋K��́A�@�ʕ\��1�i���j���i1�j������i4�j���܂łɌf����p�r�ɋ�������ꌚ�z���A�K����3�ȏ�ł��錚�z���A�O���1����ꍆ�ɊY�����鑋���̑��̊J������L���Ȃ�������L����K���͉��x�ʐς�1,000�u�������錚�z���Ɍ���K�p����B
�i�@�ʕ\��1 �� �@�ʕ\��1
�u�ωΌ��z�����͏��ωΌ��z���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����
... �v�j
2�@
���z�����J�����̂Ȃ��ω\���̏����͕ǂŋ�悳��Ă���ꍇ�ɂ����ẮA���̋�悳�ꂽ�����́A���̐߂̋K��̓K�p�ɂ��ẮA���ꂼ��ʂ̌��z���Ƃ݂Ȃ��B
�܂�C����@�����̑ΏۂƂȂ��Ă���u���O�K�i�v�͉��������Z��̊K�i�������ΏۂɂȂ�킯�ł͂���܂����B
��117���ɋL�ڂ̂Ȃ��p�r��K�͂̌��z���ɐݒu����鉮�O�K�i�ɂ��ẮC����̉����̑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƁB�Ⴆ�C��ʓI���ؑ�2�K���Ă̌ˌ��Z����2�K���Ă̒����Ƃ������p�r�ł�����ΏۊO�ɂȂ�܂��B
�i�Ȃ��n������Ƃ��āC����ʼn��O�K�i�ɉ��炩���K�����t�������ꍇ������܂��B�m�F����K�v�͂���܂��B�j
���O�K�i�Ƃ��i�����炢�j
��ʓI�ɂ́u���z���̖h�Δ��K��̉���v�ɏ��������ƂɂȂ�܂��B
�ȉ��C���O�K�i�Ɖ��O���K�i�̎戵���i���z���̖h�Δ��K��̉���j���
�K�i��2�ʈȏ��C���C�����̂����ނ�2����1�ȏオ�L���ɊO�C�ɊJ�����ꂽ�K�i�́C�ߑ�23���1�����������ɋK�肷�鉮�O�K�i�Ƃ��Ď�舵�����Ƃ��ł���B�Ȃ��C���Y�J�����������ǎ肷�����݂����Ă���ꍇ�ɂ����ẮC�肷��̏㕔������1.1���ȏ�L���ɊO�C�ɊJ������Ă���K�v������B
���O�K�i��ؑ��ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����z���ł��ȉ���2�̏��������Ζؑ��ł̌v�悪�\�ł��B��121����2�̃J�b�R�����i���ω\���̂����L���Ȗh���[�u���u�������̂������B�j�ł��B
�ȉ�2���ǂ���ɂ��K�������邱���B
�@ �K�i���������ω\���i���j�ɂ���
�A �L���Ȗh���������u��������
�Ƃ͂������̂́C�`���ŐG�ꂽ�����q�̊K�i�������̂�����܂ŁC�{�s��121����2�ɋK�肷��u�L���Ȗh���[�u���u�������́v�̔��f��͞B���ŁC���Ԃ̐R���@�ւɂ���Ă͂��ꎩ�̂�F�߂Ă��Ȃ����Ƃ�����悤�ȏł��B���炩���ߐ\����ɑ��k���̊m�F���K�v�ł��傤�B
�L���Ȗh���[�u�Ƃ́i��̓I�Ȏd�l�͖�����߂Ȃ��̂悤�ł����B�j
�ߘa4�N4���ɉ����ȗ߂��{�s����C�ؑ��̉��O�K�i�ɂ��Č��z�m�F�\�����ɕK�v�ȓY�t�}���̖��m���������ɔ����C�h���[�u�E�x�����@�̖��m����C�K�Ȉێ��Ǘ��̂��߁u�ؑ��̉��O�K�i���̖h���[�u���K�C�h���C���v�����y��ʏȂɂ��Ƃ�܂Ƃ߂��܂����B���C��͂�\����ւ̊m�F�͕K�v�ł��傤�B
�ȉ��C���ڂ͐�������Ă��܂��B�v��E�v���ɂ͈ȉ��̓_�ɔz�����܂��傤�B�i���R�̂��Ƃ���ł����B�j
�E
�ݒu���ւ̔z���i�������ؗ�����ꏊ�͔�����j
�E
�h�������iFRP��V�[�g�h���̊��p�j
�E
�ޗ��̑ϋv���m�ہi�����h�~�̖�����j
�E
�J������ɑ���[�u�i�������̐ݒu�j
�E
�����̑ؗ��h�~�[�u�i�r���⌋�I����j
�E
�_���̂��߂̑[�u�i�ڍ������̓_���֔z���j
�E
�x�����@�i�����������z���ւ̉d�C�ڍ����̌����j
���ߘa4�N4���NjL��
���K�C�h���C���̎Q�l�����Ƃ��āC�h���[�u���y�шێ��Ǘ��Ɋւ����̎���y�щ�����ȉ��Ɏ��܂Ƃ߂��܂����B
�u�ؑ��̉��O�K�i���̖h���[�u���K�C�h���C������W�v
���z�F�ؑ��̉��O�K�i���Ɋւ���K�Ȑv�C�H���ė��C�����y�шێ��ۑS���ɂ���-���y��ʏ�
���y��ʏȂ̃E�F�u�T�C�g�ł��B����C���\�����C���v���C�e��\���葱���Ɋւ�����Ȃǂ��f�ڂ��Ă��܂��B
���j�D���ω\���̊K�i�Ƃ��i�����炢�j
���ω\���ɂ��Ă͌��ݏ�������1358���i����12�N5��24���j�����m�F���������B�T�v�͈ȉ��̂����ꂩ�̏����ł��B
�E
�i�Ƃ�����x���錅�̖؍ނ̌�����6cm�ȏ�Ƃ���
�E
�؍ތ�����6���������̂��̂́C�p�{�[�h���œK�ɑωΔ핢��݂���
���̑��C��b�F����擾�����d�l�Ȃ獐���ɓK�����Ȃ��Ă��n�j�ł��B
����̍��������Ŗؑ��̉��O�K�i���̈ێ��Ǘ������i��������@�i2022�N�i�ߘa4�j�j
�@12���̒���������ɂ����āC�ؑ��̉��O�K�i���ɌW���u�K�i�e���̗y�ё����̏��v�̒������@�y�є������lj�����܂��B
�v��n�����ǂ������s�������C�@12���̒�������̑ΏۂƂ��ċ����Z����w�肵�Ă���ꍇ�i���j�ɂ͔z�����K�v�ł��B
���j�D�����Z�����̑ΏۂƂȂ��Ă��邩�́C���ǂ̓���s�������ƂɈقȂ�܂��̂ŁC�e�����̂�HP���ł��m�F���������B
�܂Ƃ�
��ނ��ؑ��ł̉��O�K�i���v�悷��ꍇ�ɂ́C�@�ߏ���C�Z�p�I�Ȉ��S�������\���K�v�ł��B
�E ���K�肪�����錚�z���͌����C�ؑ��̉��O�K�i�s��
�E �������C���ω\���Ƃ����h���[�u���u�������O�I���\
�E �h���[�u�������Ȃ̃K�C�h���C�����Q�����ׂ�
�i�Q�l �F�`���Ő\���グ�܂������C���O�K�i�͖h������S��S���ȏ�Ƃ���̂���{�ł��傤�B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u�ڎ��v�֖߂�