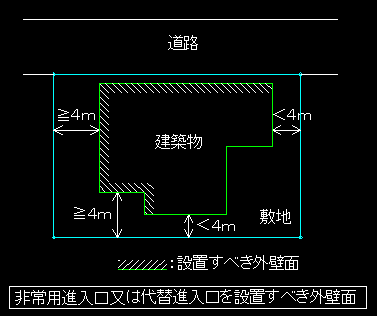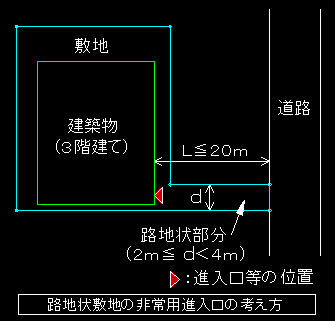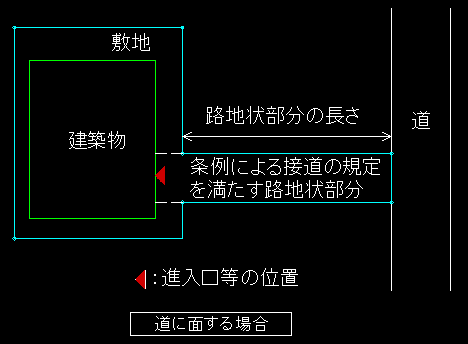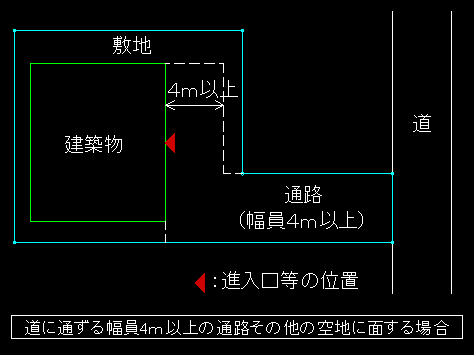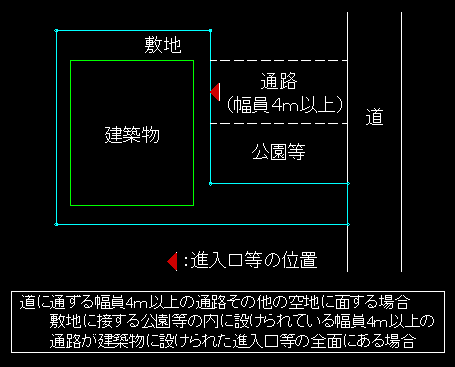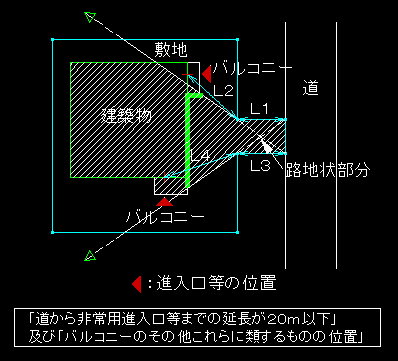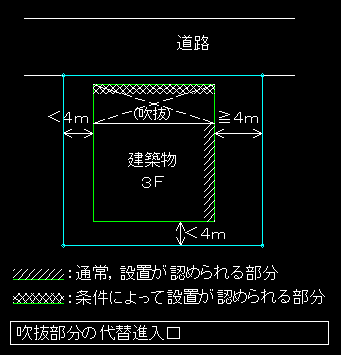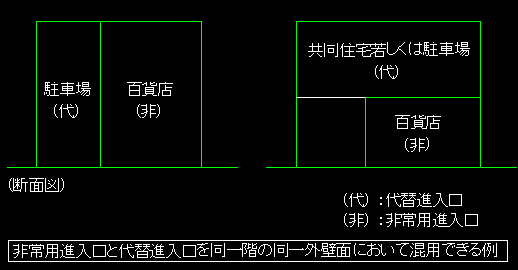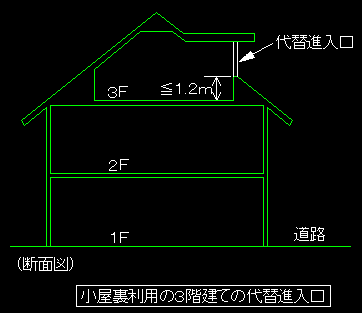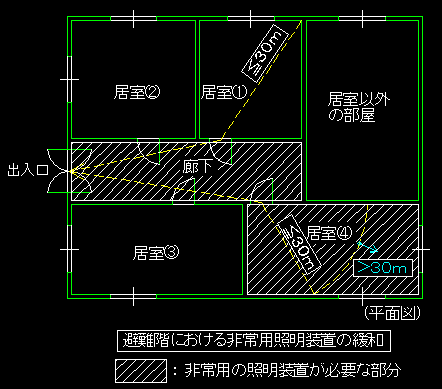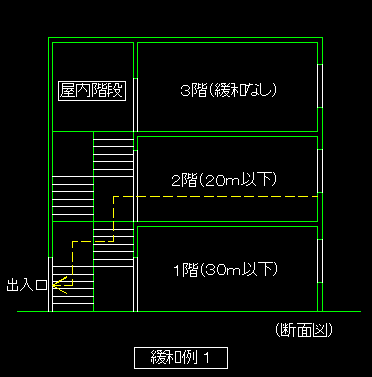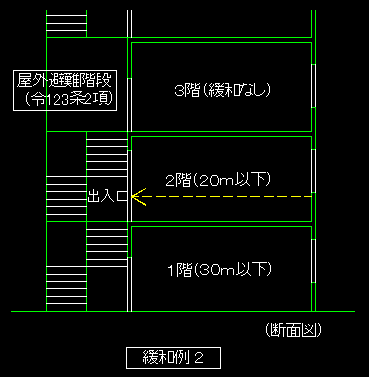「建築基準法及び関連法解説」
全ページ
→
遠山英雄都市建築設計事務所 - HOMEへ
__________________________________________________
非常用進入口・非常用照明
「 目 次
」
非常用進入口
■ shin_001 関連法令
【設置】第126条の6
【構造】第126条の7
※1
非常用進入口又は代替進入口を設置すべき外壁面
非常用進入口の緩和
参考1).横浜市建築基準法取扱基準集より
非常用の進入口について 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917)
参考2).横浜市建築基準法取扱基準集より
路地状敷地における一戸建ての住宅に関する進入口等の取扱い 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917)
吹抜部分の代替進入口
非常用の進入口の注意事項
非常用進入口と代替進入口を同一階の同一外壁面において混用できる例
壁のない3階部分の考え方(小屋裏利用の3階建て)
非常用照明
■ shyo_001 関連法令
【設置】第126条の4
【構造】第126条の5
告示による非常用の照明装置の緩和
(H12告示1411号)
避難階の直上階又は直下階の非常用照明装置の緩和例
居室の一部が避難経路を兼ねる場合の非常用の照明装置
非常用進入口
■ shin_001 関連法令
第5章 避難施設等 第5節
非常用の進入口(令第126条の6・令第126条の7)
【設置】
第126条の6 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
国土交通大臣が定め ⇒ 告平12年 1438号 「屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定め ... 」
一 第129条の13の3の規定に適合するエレべーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面(※1)に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごと(※2)に設けている場合
【構造】
第126条の7 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
二 進入口の間隔は、40m以下(※2)であること。
三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75㎝以上、1.2m以上及び80㎝以下であること。
四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
五 進入口には、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること。
六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
七
前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
国土交通大臣が定め ⇒
告昭45年 1831号
「非常用の進入口の機能を確保するために必要な構造の基
... 」
※
「令第126条の6第1項第二号」で無窓となった場合
非常用進入口の設置又は非常用エレベーターの設置が義務付けされる。
※
前条第126条の6第1項第二号は「代替進入口」です。
代替進入口は、非常用進入口に代わる窓のことで、災害時に消防隊が外部から進入するための開口部です。
※1
非常用進入口又は代替進入口を設置すべき外壁面 (2006H)
| 非常用進入口又は代替進入口を設置すべき外壁面
|
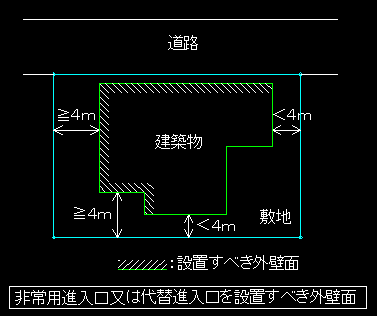
|
道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面
※道路又は空地と高低差がある場合やのり地等の場合も原則は必要
非常用進入口に替わる開口部
延焼のおそれのある部分の窓には,通常,網入りガラスを使用するが,この窓がFIXの場合,外部から破壊しての進入が困難となるので,網入ガラスの使用の場合は,開放できる窓構造としなければならない。その場合,両面ハンドルが必要となります。
消防法では網入りガラス等でない厚6mm以下の進入を妨げない構造の嵌め殺し窓は基準諸寸法を満たせば,全面破壊可能として有効開口部として認められています。
|
※2
進入口に代わる開口部は外壁面10m以内ごとに任意に設ければよく,開口部の中心間が10mを超えてもかまわない。
建築物の外壁端部から進入口の中心までの距離は20m以下とし,各進入口中心間の距離は40m以下とする。
非常用進入口の緩和 (2006H)
路地状敷地の非常用進入口の考え方
非常用進入口の緩和
路地状敷地の非常用進入口の考え方
|
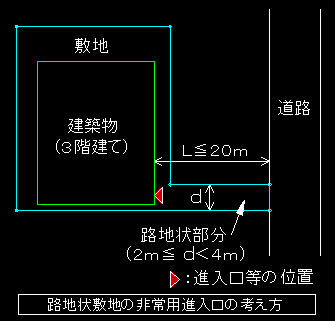
|
非常用進入口や代替進入口は,道または道に通ずる幅員4m以上の通路などに面することが条件となっている。このため4m以上の接道がない路地状敷地では消防隊の進入が困難となることも考えられる。よって,こういった路地状敷地については,以下の要件を満たすことにより,「道又は道に通ずる幅員4m以上の通路などに面する」ものとして整備が図られている(H5.12.13建設省事務連絡)。
①
道から非常用の進入口等までの延長距離(L)≦20m
②
路地状部分の幅員(d)≧2m
③
階数(地階を除き)=3
④
特殊建築物の用途でないこと
⑤
非常用の進入口等(当該非常用の進入口等に付随するバルコニーその他これらに類するものを含む。)が,道から直接確認できる位置に消火活動上有効に設置されていること。
注意).
この路地状敷地の扱いは,行政庁によっては運用していないところもあり,事前確認しておきたい。
|
参考1).横浜市建築基準法取扱基準集より
非常用の進入口について 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917)
令第126 条の6第2号及び第126
条の7第1号に規定する「道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する」とは、以下の各図に該当する場合と解するものとします。
非常用の進入口について 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917)
道に面する場合 |
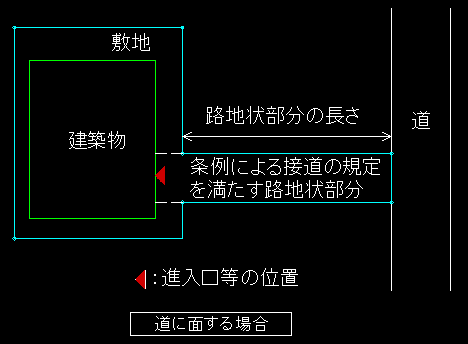
|
道から建築物に設けた進入口等が直視でき、かっ、道から進入口等の前面まで横浜市建築基準条例第4条本文の規定を満たす路地状部分が有効に確保されている場合 |
非常用の進入口について 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917)
道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する場合 |
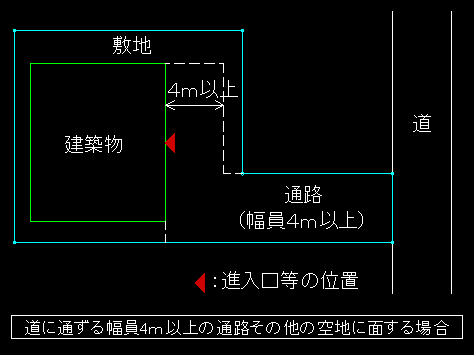 |
道から建築物に設けた進入口等の前面まで幅員4m以上の敷地内通路が確保されている場合 |
非常用の進入口について 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917)
道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する場合 |
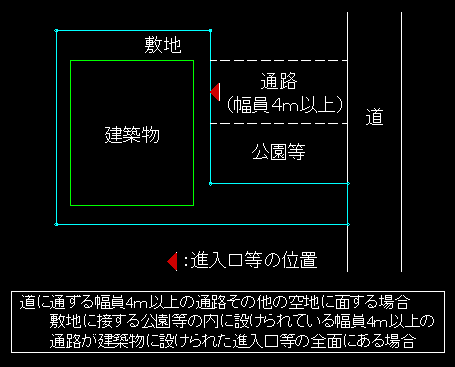 |
敷地に接する公園等の内に設けられている幅員4m以上の通路が建築物に設けられた進入口等の全面にある場合 |
参考2).横浜市建築基準法取扱基準集より
路地状敷地における一戸建ての住宅に関する進入口等の取扱い 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917)
一戸建ての住宅に限っては、次の各号に適合する場合についても、令第126
条の6及び第126 条の7の規定上、進入口等(2-4「非常用の進入口について」参照)が「道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する」ものと解することとします。
なお、本取扱いによっても「道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する」ものと解されない場合は、3階建て以上の建築物を建築することはできません。
1 進入口等から、各居室に容易に到達できる経路を有するもの
2 地階を除く階数が3であるもの
3
条例第4条の規定により路地状部分の長さに応じて必要となる幅員があるもの
路地状部分の長さが15m以下の場合は,路地状部分の幅員は2m以上必要
路地状部分の長さが15mを超える場合は,路地状部分の幅員は3m以上必要
4 道から進入口等までの延長が20m以下であるもの
5 進入口等(当該進入口等に付随するバルコニーその他これに類するものを含む。)が、道から直接確認できる位置に消防上有効に設置されており、進入口等までの通路幅員が2m以上確保されているもの
| 路地状敷地における一戸建ての住宅に関する進入口等の取扱い 横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月(1917) |
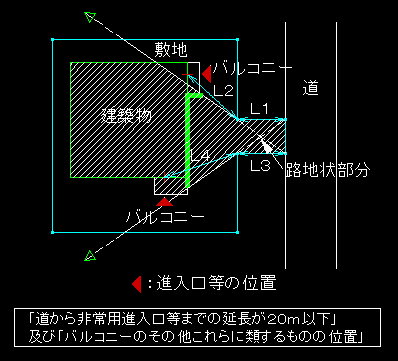 |
・ L1+L2≦20m又はL3+L4≦20mであること
・ バルコニーには非常用進入口等がある旨を表示する
図中太線部分(網掛部分も含む)は、非常用進入口等(バルコニーその他これらに類するものを含む)の設置が可能な部分です。
(建企指第1015 号 平成6年6月7日)
(まち建企第2287 号 平成20 年3月4日改正)
(建建企第811 号 平成22 年8月9日改正)
(建建企第1290 号 平成24 年9月3日改正)
なお、この取扱いは、下記についても注意が必要です。
【参考】
1 適用建築物について
本取扱いは、横浜市建築基準条例(以下「条例」という。)第4条の2第1項の規定により、一戸建ての住宅に限り適用できます。なお、階数3以上の一戸建て住宅以外の用途については条例第4条の2の規定により接道長さが4m以上必要となるので取扱い2-7
(「非常用の進入口について」平成2年5月17日 建企指第1006号)が適用されます。
2 路地状部分の幅員について
取扱い第3項中「路地状部分の幅員が2m以上」とあるのは、条例第4条の規定により路地状部分の長さが15mを超える場合には、路地状部分の幅員3m以上必要となります。
|
吹抜部分の代替進入口 (2007W)
| 吹抜部分の代替進入口
|
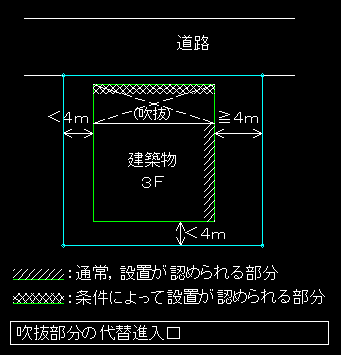 |
3階建で吹抜けのある建築物の場合,
通常道路に面する部分に進入口を設けても認められない。
但し,不燃材で造られた幅1m以上のキャットウォークを設けることにより,3階に進入可能であれば,
道路に面する部分に設けることができる。
|
非常用の進入口の注意事項 (2006H)
非常用の進入口の注意事項
非常用進入口と代替進入口を同一階の同一外壁面において混用できる例 |
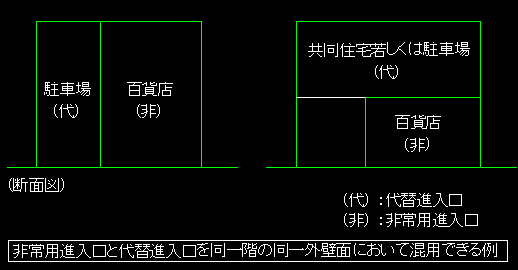
|
①
非常用進入口と代替進入口の混用
非常用進入口と代替進入口は,同一階の同一外壁面において混用してはならない。ただし,避難上及び消防活動上支障がなく,設置された部分の避難経路が用途ごとに異なる場合等は可能である。
②
アトリウムなど床のない場合の設置について
吹抜きなど床のない部分の外壁面で,当該階の避難上及び消防活動上支障のないものについては代替進入口の設置は不要とされている。しかし,前面道路等に大空問の吹抜き(アトリウム)が面する場合,非常用の進入口を設けづらい計画ではあるが,避難上及び消防活動上支障のないように3階以上の階へ連絡する進入口を設けるか,非常用の昇降機を設けなければならない。
Web参考).
3階建で吹抜けのある建築物の場合,不燃材で造られた幅1m以上
のキャットウォークを設けることにより,3階に進入可能であれば,
要設置部に設けることができる。
注意).
キャットウォーク等がない場合 (消防法による無窓階の取扱い)
吹き抜けの存する部分の床面積及び開口部の取扱いは,次によること。
ア 床面積の算定は,当該床が存する部分とする。
イ 開口部の面積の算定は,床が存する部分の外壁開口部の合計とする。
|
| ③
壁のない3階部分の考え方(小屋裏利用の3階建て) (2006H)
|
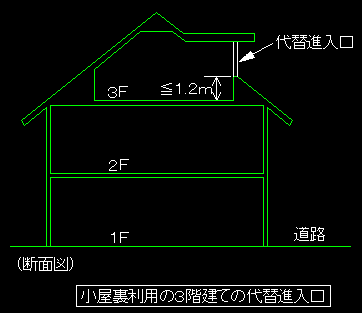 |
非常用進人口等は「各階の外壁面」に設けることとなっている。ただし,小屋裏利用の3階建て住宅等の形式的に「屋根面」とみなされる部分に設ける屋窓やドーマー等も,機能上は「外壁」に設けられる代替進入口となんらかわることがないため,以下の扱いがされている。
イ
屋根面を外壁面と見なした場合に,令126条の6第2号に適合する窓その他の開口部とすること
ロ
開口部(傾斜屋根に設けられたものにあっては,その下端)の床面からの高さが1.2m以下とすること
|
参考).「令126条の6,7」関係法令等 昭和46.1.29
住指発第44号
非常用照明
■ shyo_001 関連法令
第5章 避難施設等
第4節 非常用の照明装置(第126条の4・第126条の5)
【設置】
第126条の4 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室、第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
法別表第1 ⇒ 法別表第1
「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊
... 」
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二
病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
学校等 ⇒ 令第126条の2第1項第二号 「設置」
四
避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
国土交通大臣が定め ⇒
告平12年 1411号
「非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避
... 」
【構造】
第126条の5
前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ
照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であっても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
国土交通大臣が定め ⇒ 告昭45年
1830号 「非常用の照明装置の構造方法を定める件」
ハ 予備電源を設けること。
ニ
イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
国土交通大臣が定め ⇒
告昭45年 1830号 「非常用の照明装置の構造方法を定める件」
二
火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあっても床面において1lx以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
※ 非常用照明設備
詳細基準,他
「非常用の照明装置」とは非常灯,非常用照明などとも呼ばれているもので停電時にバッテリー等の予備電源(蓄電池や自家用発電機)により30分以上点灯しても,白熱灯で床面で1ルクス(蛍光灯又はLEDの場合2ルクス)以上の照度を保ち,避難を速やかに行うための照明器具です。1ルクス(lux)は「1平方メートルの面が1ルーメンの光束で照らされるときの照度」と定義されています。
参考).以下,「特殊建築物定期報告制度」(法第12条第1項及び第3項)における非常用照明設備検査の留意です。(左フレーム内INDEXの「その他の規制及び参考」の改正法「特殊建築物定期報告制度」より)
1).測定位置
非常照明の照度は全ての器具の直下で測定ではなく,非常照明器具の間で避難に当たり最も必要な点を中心に計測すればよい。出入口や壁際などの照度が不利になるような箇所で測定されていればよいのです。これは国交省監修の業務基準書に記載されています。大きな建物になると計測に時間がかかるので,必要な箇所のものだけで済ませて良いとされている。箇所数についての基準はないようです。
申請側,審査側のお互いの作業の軽減の配慮という背景があるようです。
参考).必要な箇所の例
: 病院の場合 →
廊下,EVホール,階段室,待合室,ナースステーションなど。
2).測定基準 照明方法および設計上の注意
非常用照明器具で要求される床面の照度は,直接照明による照度測定点の水平面照度が,30分間非常点灯後1ルクス(蛍光灯及びLEDの場合,周囲温度上昇による光束低下を見越して2ルクス)以上と規定されています。
3).試験方法
非常点灯の性能をチェックする時は,十分(誘導灯
24時間・ 非常用照明器具 48時間)充電したのち常用電源を遮断して非常点灯に切り替えて,誘導灯は20分・非常用照明器具は30分経過後,
非常点灯しているか再び確認する。
4).照度測定面の高さ
照度測定面の高さは,室内に机,作業台などの作業対象面がある場合は,その上面または上面から5cm以内の仮想面とします。特に指定のない場合は,床上80±5cm,和室の場合は畳上40±5cm,廊下,屋外の場合は,床面または地面上15cm以下とする。
※
他,非常用照明設設備については左フレーム内INDEXの「その他の規制及び参考」の改正法「特殊建築物定期報告制度」の以下を参照してください。
参考).非常用照明設備についての詳細
告示による非常用の照明装置の緩和
(H12告示1411号) (2006H)
| 告示による非常用の照明装置の緩和 |
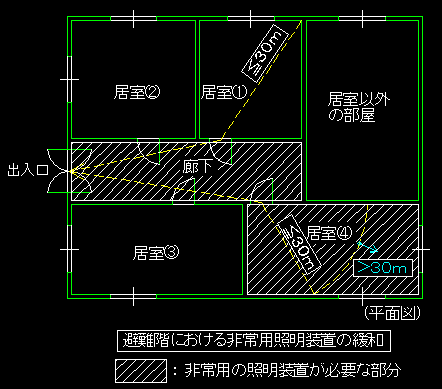
|
● 避難階の居室
避難階の屋外の出入口 :
歩行距離30m以下
● 避難階の直上階又は直下階の居室
避難階の屋外の出入口 :
歩行距離20m以下
屋外避難階段に通ずる出入口 :
歩行距離20m以下
注意).
・
採光上有効な開口部を有する(床面積の1/20以上)居室に限る
令116条の2第1項第一号
・
避難上支障がないこと
・ 居室①②③は緩和
・ 居室④は30mを超える部分があるため,超える部分を含めて居室内全てに非常用照明が必要
・
廊下は本告示では緩和されないため非常用照明が必要
|
避難階の直上階又は直下階の非常用照明装置の緩和例 (2006H)
| 避難階の直上階又は直下階の非常用照明装置の緩和例1,2 |
| ・
避難階の屋外の出口 : 20m以下 |
・
屋外避難階段に通ずる出口 : 20m以下 |
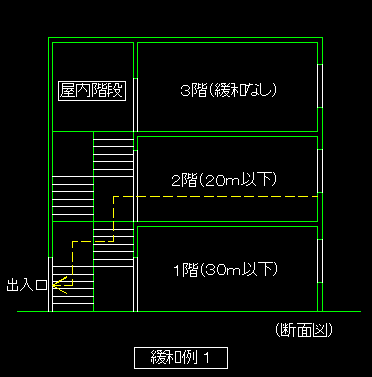
|
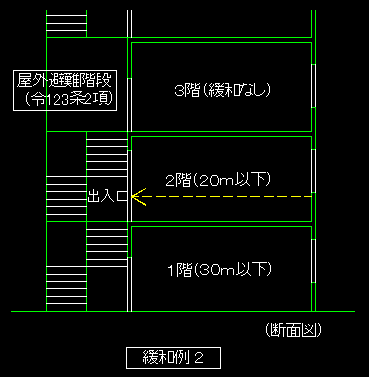
|
居室の一部が避難経路を兼ねる場合の非常用の照明装置 (2006H)
| 居室の一部が避難経路を兼ねる場合の非常用の照明装置 |

|
令126条の4において,採光上無窓の居室(令116条の2第1項第一号)から地上に通ずる廊下,階段その他の通路には非常用の照明装置の設置が必要とされている。よって,採光上無窓の居室から,避難経路として他の居室を経由する場合には,その居室が有効採光を確保していても,その避難経路に当たる部分には原則として非常用の照明装置の設置が必要となる。 |
「目次」へ戻る