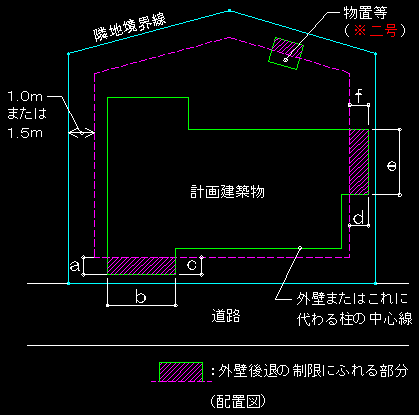
一号 :a+b+c+d+e+f≦3m
二号 : 軒の高さ≦2.3mかつ床面積の合計≦5㎡の物置等その他これらに類する用途に供されるもの(床面積は,複数ある場合は合計)
参考).横浜市建築基準法取扱基準集より
床面積に参入されない基準に合った出窓でも,一号の合計3m以下の取扱いとなる。
「建築基準法及び関連法解説」
全ページ
→
遠山英雄都市建築設計事務所 - HOMEへ
__________________________________________________
外壁後退・延焼のおそれのある部分・22条区域
「 目 次
」
外壁後退
■ gai_001 関連法令
法54条
令135条の20
■ gai_002 外壁後退の制限の緩和
外壁後退の制限を緩和される要件
(令135条の20)
二つの地域・区域にわたる場合
法54条以外の外壁後退規定
住宅等の地盤面下の掘り抜きの地下車庫 (2008横浜市pdfより)
外壁及び柱のないはね出しの庇等について(法54条第1項,令135条の20) (2009JCBAより )
外壁がない場合の壁長の算定について(法54条第1項,令135条の20) (2009JCBAより )
参考).外壁後退の緩和措置の解釈について
からぼり等の扱いについて (2008横浜市pdfより )
建物は,隣地境界線から50cm以上離さなければならないのか
以下を参照してください。特例・参考・現実論,…他,記してあります。
左のフレーム(INDEX)の「建築確認制度,他」
→ 「■ 011 民法234条の「建物を築造するには,境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」
について
延焼のおそれのある部分
■ en_000 主な取扱いについて 延焼のおそれのある部分(法第2条六号)
【用語の定義】
道路,隣地境界線,線路敷及び公共水路・緑道等の取扱い
線路敷及び公共水路・緑道等の取扱い
参考).(横浜市建築基準法取扱基準集 平成29年4月)
■ en_001 建築物相互間の中心線の設定方法
建築物相互間の中心線の設定方法
法第2条第六号ただし書きの「耐火構造の壁に面する部分」の取扱い
地階において延焼のおそれのある部分が生じる場合
(ドライエリアのある地階)
附属建築物の取扱いについて
建築物相互をつなぐ開放の渡り廊下と建築物の関係
■ en_002 『延焼ライン(延焼のおそれのあるライン)の緩和』について
[2019年改正] (Webサイトより抜粋)
22条区域
■ 22_001 適用除外を受ける建築物
(法第22条)
適用除外を受ける建築物
ポリカーボネート板の屋根材としての使用について
外壁後退
■ gai_001 関連法令
法54条
【第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離】
第54条
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては,建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は,当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては,政令で定める場合を除き,当該限度以上でなければならない。
政令 ⇒ 令第135条の20 「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内に
... 」
2
前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては,その限度は,1.5m又は1mとする。
後退距離の限度 ⇒ 都市計画法
第8条第3項第二号ロ 「地域地区」
令135条の20
【第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和】
第135条の20 法第54条第1項の規定により政令で定める場合は,当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかにに該当する場合とする。
一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
二 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であること。
(その他の関連法令 :法60条,68条第2項)
■ gai_002 外壁後退の制限の緩和
外壁後退の制限を緩和される要件(令135条の20) (2002K
)
| 壁後退の制限を緩和される要件(令135条の20) | |
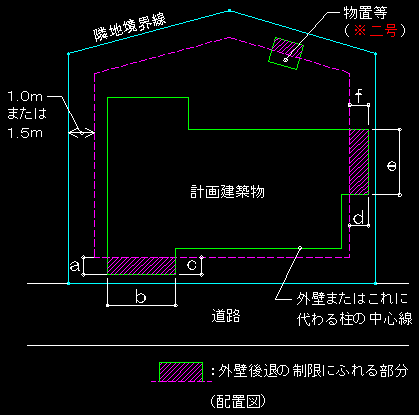 |
一号 :a+b+c+d+e+f≦3m 二号 : 軒の高さ≦2.3mかつ床面積の合計≦5㎡の物置等その他これらに類する用途に供されるもの(床面積は,複数ある場合は合計) 参考).横浜市建築基準法取扱基準集より 床面積に参入されない基準に合った出窓でも,一号の合計3m以下の取扱いとなる。 |
二つの地域・区域にわたる場合
都市計画で定められた第1・2種低層住居専用地域内における外壁後退については,敷地および建築物の部分が,その制限を受ける区域と,その他の区域にわたる場合は,その他の区域の敷地および建築物の部分は,この規定による制限を受けない。
したがって,適用される用途地域が第1・2種低層住居専用地域であっても,必ずしも外壁後退の規定が適用されるとは限らないので,各特定行政庁で制限がかかる区域を事前に調査する必要がある。
法54条以外の外壁後退規定
外壁後退の規定は,法54条以外に,法46条(壁面線の指定),法59条(高度利用地区)および法60条(特定街区)の壁面の位置の制限,法68条の2項にもとづく条例で規定する壁面の位置の制限,法69条(建築協定の目的)などがあり,ほかに都市計画法にもとづく風致地区内での外壁後退の制限がある(都計法58条,表1・2)。
住宅等の地盤面下の掘り抜きの地下車庫 (2008横浜市pdfより)
| 住宅等の地盤面下の掘り抜きの地下車庫 | |
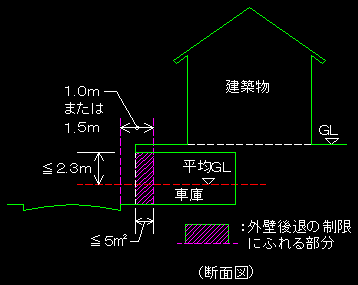 |
住宅等の地盤面下の掘り抜きの地下車庫も令135条の20第二号の「・・・その他これらに類する用途・・・(軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内)」に含まれ,外壁後退の制限が緩和される。 参考).横浜市建築基準法取扱基準集より 地下車庫についての取扱いは,地下車庫の屋根スラブの先端位置からの計算となる。 |
外壁及び柱のないはね出しの庇等について(法54条第1項,令135条の20) (2009JCBAより )
| 外壁及び柱のないはね出しの庇等 | |
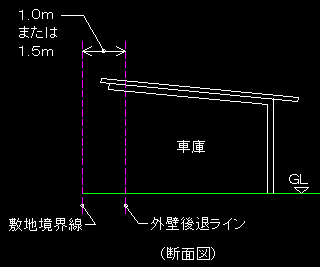 |
外壁及び柱のないはね出しの庇等については,外壁部分とみなさない。 |
外壁がない場合の壁長の算定について(法54条第1項,令135条の20) (2009JCBAより )
| 外壁がない場合の壁長の算定 | |
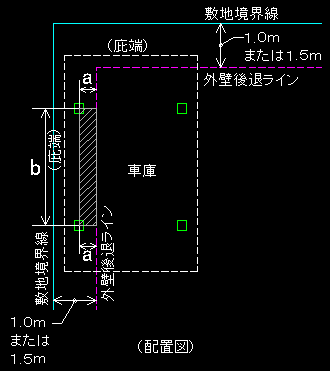 |
壁がなく,柱のみの場合は,2a+b(=a+b+a)を壁長とし,2a+b≦3m,又は軒高2.3m以下かつa×b≦5㎡として,令第135条の20を適用する。 緩和されるということ。 |
参考).外壁後退の緩和措置の解釈について (2007W)
外壁(またはこれに代わる柱の中心線)の長さの合計が3m以下であれば,後退距離を満たさなくてよいとする緩和措置があります。つまり建物の角が1辺1.5m以内の正三角形程度に後退ラインを出るのはOKなわけです。
からぼり等の扱いについて (2008横浜市pdfより )
| からぼり等の扱い | |
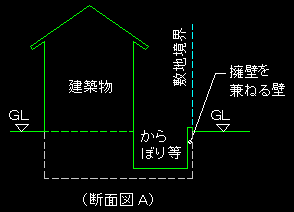 |
法54条 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内の外壁後退建築物と構造上連続する壁であっても,擁壁を兼ねるものである場合には,当該壁は「外壁又はこれに代わる柱の面」には該当しないものとして取扱います。 後退する必要がないということ。 |
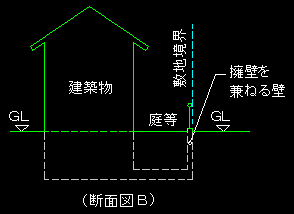 |
|
延焼のおそれのある部分
■ en_000 主な取扱いについて
延焼のおそれのある部分(法第2条六号)
【用語の定義】
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線,道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は,1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から,1階にあっては3m以下,2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし,防火上有効な公園,広場,川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く
※).
ただし書きの「耐火構造の壁に面する部分」の取扱いについては「法第2条第六号ただし書きの「耐火構造の壁に面する部分」の取扱い
」(同じウィンドウで移動) を参照してください。
■ en_001 建築物相互間の中心線の設定方法
建築物相互間の中心線の設定方法 (2006H)
| 建築物相互間の中心線の設定方法 同一敷地内の2以上の建築物の延べ面積の合計が500㎡以上の場合 建築物の分け方は任意でよいとのこと。 |
|
| 外壁面が平行で長さが異なる場合 | 外壁面が平行でない場合 |
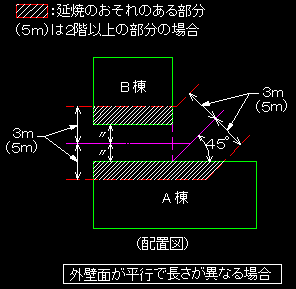
|

|
複数の建築物の延面積合計が500㎡以内であれば,それらの建築物は一つの建築物とみなされる。すなわち延焼ラインは生じないということ。
※).
附属建築物の取扱いについては以下を参照してください。
附属建築物の取扱いについて (同じウィンドウで移動)
法第2条第六号ただし書きの「耐火構造の壁に面する部分」の取扱い
| 外壁面が平行で長さが異なる場合 | 外壁面が平行でない場合 |
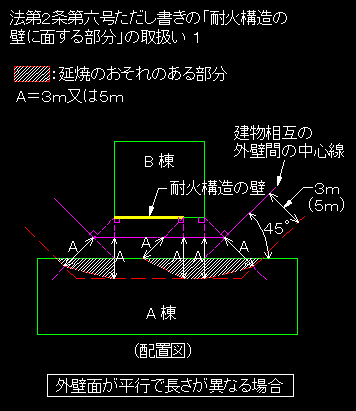 |
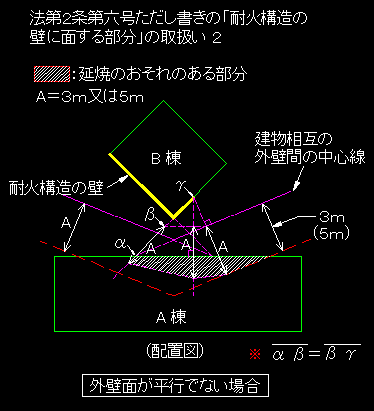 |
地階において延焼のおそれのある部分が生じる場合
(ドライエリアのある地階) (法第2条) (2006H)
| 地階において延焼のおそれのある部分が生じる場合 (ドライエリアのある地階) | |
| 延焼のおそれのある部分は地階については言及されていないが,地階は必ずしも完全に地中に埋もれたものばかりではない。地階であっても開口部が地上部分に面し,延焼の観点からすると1階と同様なものがある。したがって,下図に類する地階の形状の場合は,延焼防止上,地階を1階とみなし延焼の恐れのある部分を算定する。ただし,ドライエリアの壁等で防火上有効に遮られている部分は除く。 |
補足). 法規上は地階であっても,その天井高さの上部2/3までは地盤面から上にあるという地階が存在します。とうぜん,地盤面上の2/3部分には外壁があり,開口部を有する場合もあります。 日本建築行政会議は,「建築物の防火避難規定の解説」において,地階については延焼のおそれのある部分は規定上生じないとしたうえで,上記のように,地盤面上に地階の外壁・開口部等がある場合は,「延焼防止上,地階についても1階とみなし,延焼のおそれのある部分を算定する必要がある。」としている。 ただし,地盤面下でドライエリアになっており,そのドライエリアの壁等に対面して,防火上有効に遮られているとみなされる部分についてはこの取り扱いから除外され,延焼ラインの対象とはならない。 この取り扱いについては,ドライエリアをなす壁を地盤面上に立ち上げた場合や,逆に1階の床レベルが地盤面よりも下にあり,壁や開口部の一部がドライエリア内にある場合など,いろいろなケースが想定される。 これについては法文のただし書き「耐火構造の壁その他これらに類するもの」との関係も考えられるので,審査機関との打ち合わせが必要であろう。 |
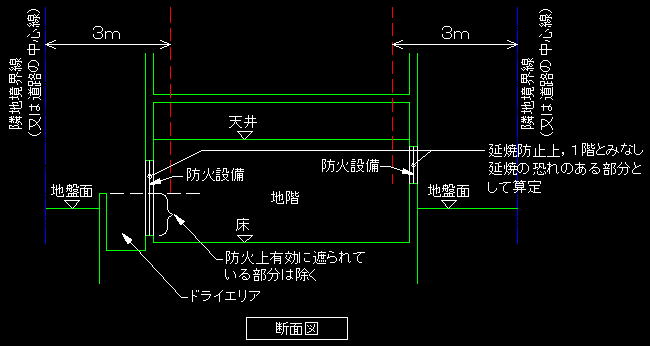 地階の定義・詳細については以下を参照。 左のフレームの「地盤面・階・建築物の高さ・天井の高さ」 → ■ 002 地階 → 令1条第2号に規定する用語「地階」の意義 …… 当該階の最も高い位置の床及び天井の1/3以上(h>H/3)とする。 …… |
|
| 附属建築物の取扱いについて | |
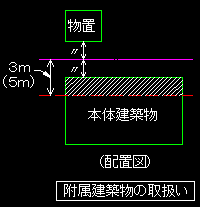
|
規模や用途によっては,そもそも2以上の建築物とみなさないような取扱いも規定されている。 以下,日本建築行政会議「建築物の防火避難規定の解説」から引用。 「附属建築物のうち自転車置場,平屋建の小規模な物置(ゴミ置場も含む。),受水槽上屋,屎尿浄化槽及び合併浄化槽の上屋,ポンプ室で主要構造部が不燃材料で造られたもの,その他の火災のおそれが著しく少ないものについては,法第2条ただし書の「その他これらに類するもの」として取り扱い,本体建築物においては延焼のおそれのある部分を生じないものとする。 なお,小規模な物置の開口部については,法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(両面20分の防火設備。以下同じ。)を設けること。」 ここであげられている用途については,それ自体が火災の発生のおそれが少ない用途であり,また,不燃材料で造られていることから,他の建築物からの類焼も想定されないことにより,防火上有効な公園,広場,川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁と同等のものとして取り扱うものである。 ただし,小規模な物置の具体的な規模については,本体建築物の用途・規模等によってそれぞれ判断されることであり,審査機関との調整が必要であるとされている。 また,不燃材料で造られた屋外階段・開放廊下・バルコニーの部分についても,法2条第6号ただし書きの「その他これらに類するもの」として取り扱い,同一敷地内の他の建築物においては延焼のおそれのある部分を生じないものとするという取扱いが示されている。 |
建築物相互をつなぐ開放の渡り廊下と建築物の関係 (2009JCBAより)
| 建築物相互をつなぐ開放の渡り廊下と建築物の関係 | |
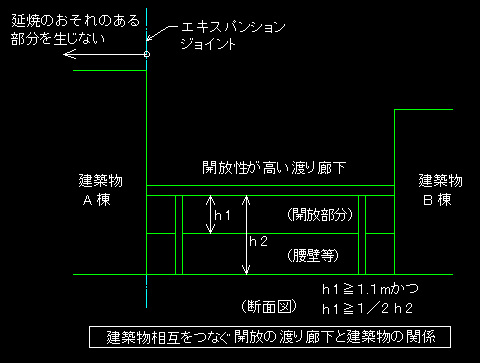 |
【内容】 外気に有効に開放されており,屋内的用途に供しない渡り廊下(接続される建築物と独立した構造であり,主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)と,エキスパンションジョイント等で接続されている建築物については,法第2条第6号ただし書きの「その他これらに類するもの」として取り扱う。 ・ この場合,当該渡り廊下と接続する建築物の間の関係において,延焼のおそれのある部分は生じない。 【解 説】 ・ 渡り廊下について,その主要構造部が不燃材料で造られたものであり,かつ外気に有効に開放され屋内的用途に供しないものについては,当該部分からの延焼によりエキスパンションジョイント等で接続する建築物に対する影響がないことから,接続する建築物に対して延焼のおそれのある部分を発生させない部分として取り扱うこととする。 ・ また,外気に有効に開放されている廊下かどうかを判断するにあたっては,『床面積の算定方法(昭和61年4月30日 建設省住指発第115号)』において掲げられている「吹きさらしの廊下」の条件である「外気に有効に開放されている部分の高さが,1.1m以上であり,かつ,天井の高さの1/2以上である廊下」に該当するかどうかを判断材料とする。 |
■ en_002 『延焼ライン(延焼のおそれのあるライン)の緩和』について
[2019年改正] (Webサイトより抜粋)
2019年より延焼ラインに新たな緩和規定が追加になりました。
利用できそうだが複雑でややっこしい計算式が登場します。
詳細については省略します。各Webサイトでイラスト入り解説が数々あります。数多く比較参照することで全容が理解できるでしょう。
以下,概要です。
以下,建築基準法第2条第1項第六号が改正されました。
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線,道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は,一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から,1階にあつては3メートル以下,2階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし,次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ 防火上有効な公園,広場,川その他の空地又は水面,耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて,当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
最新の法改正で追加になったのは赤文字部分です。
緩和の詳細内容は以下告示第197号に記載があります。ややっこしくて複雑です。詳細内容は省略します。
法第2条第六号ロの規定に基づく延焼ラインの緩和について
国土交通省告示第197号(令和2年2月27日付け公布,同日施行)
告示第197号の要点
緩和の使い道は2種類あります。建物相互間の延焼ラインについては条件付き。
1.距離の検討で緩和する計算について隣地境界線等に面するの考え方
2.高さの検討で緩和する計算についてS(建築物から隣地境界線等までの距離のうち最小のもの)の考え方
緩和できる延焼ライン(法文上の隣地境界線等)
① 距離で検討
隣地境界線の延焼ライン
道路中心線の延焼ライン
建物相互の間の延焼ライン※条件付き(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は,発生なし)
(3つ全て緩和可能)
② 高さで検討
建物相互の間の延焼ライン※条件付き(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は,発生なし)のみ緩和可能
※
大事なのは,緩和できる延焼ラインが異なるという点です。利用する場合のスタートの根本的な部分なので慎重に!
22条区域
■ 22_001 適用除外を受ける建築物
【屋根】
第22条
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は,通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし,茶室,あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置,納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については,この限りでない。
準防火地域 ⇒ 都市計画法 第9条第20項
政令 ⇒ 令第136条の2
「地階を除く階数が3である建築物の技術的基準」
2 準防火地域内にある木造建築物等は,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし,これに附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。
木造建築物等 ⇒ 法第23条
「外壁」
適用除外を受ける建築物
法第22条区域の屋根の構造の適用除外を受けるその他これらに類する建築物については以下
(2009JCBAより )
自転車置場(バイク置場を除く)/浄化槽ポンプ室
※
以下は該当しない
プロパン庫/危険物庫
【解説】
物置,納屋その他の建築物として想定されるのは,附属的な用途の建築物である。ただし,附属的な用途であっても,規定の趣旨を踏まえて防火的な観点から,多量の可燃物を有する附属建築物は,法第22条の適用除外を受ける建築物としては取り扱わず,適切に飛び火防止のための措置をとる必要がある。
ポリカーボネート板の屋根材としての使用について
(2006H)
法22条で指定されている屋根不燃区域や防火・準防火地域の屋根に求められている性能(H12年告示1365号)は,通常の火災による火の粉により,防火上有害な発炎をしない(転炎性)こと及び屋内に達する防火上有害な溶融,き裂等の損傷を生じない(燃え抜け性)ことが要求されている。
ただし,不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(H12年告示1434号)の場合は,防火上有害な発炎をしない(転炎性)ことのみ有することでよいことになっており,性能的にはH12年告示1365号の第1を満たせばよい。
ボリカーボネート板や強化プラスチック板(旧法における準難燃材料)等の多くは,「燃え抜けはするが,燃え広がりはしない」ものとして国土交通大臣認定を受けているため,不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途の屋根には使用が可能となる。
不燃性の物品を保管する倉庫に類するものとしては,次に掲げる用途が該当する。
1.スケート場,水泳場,スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
類する用途とは,テニスの練習場,ゲートボール場等,スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく,また,見通しが良く避難上の支障がないもの。
2.不燃性の物品を取り扱う荷捌き場,その他これと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途
同等以上のものとは,以下のもの。
・ 通路,アーケード,休憩所
・十分外気に開放された停留所,自動車車庫(30㎡以下),自転車置き場
・機械製作工場
3.畜舎,准肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場
「目次」へ戻る